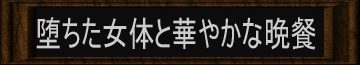
第五章
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
階下が騒がしく、不安を掻き立てられる。 亜希の部屋の窓から、暮れゆく西の陽が斜めに差し込んでいた。 結局、昨日の夜に衣類をすべて奪われてから、今も、何も着させてもらえない。電気の点いていない暗い部屋のなかで、千尋は、全裸で赤いロープに両手を縛られている。 今日から、世にも惨めな裸の生活が始まった。 午前中、亜希は学校のため、家にはおらず、加納はひとり、部屋の掃除や洗濯などをしていた。千尋をいじめ抜くことを快感としている加納だが、使用人としての仕事ぶりは、どこか家庭的な女の匂いを感じさせるほど、丁寧でひたむきだった。 昼過ぎに、千尋は一つの仕事を与えられた。 「お嬢さまのために、おまえの得意だというパスタを作っておけ」 加納にそう命じられ、千尋は裸のまま台所に立ち、鍋で麺を茹で、フライパンを振るった。千尋が中学生の頃、亜希にレシピや調理のこつを教えながら、一緒に作ったことのあるペペロンチーノ。 午後になり、亜希は一度帰宅したが、この部屋に戻ってくるなり、なにやらめかし込んで、またすぐに出かけていった。しばらくして、亜希は帰ってくると、愕然とさせられることに、友達を連れてきていた。 「おじゃましまぁーす」 鼻にかかった少女の声が、階下の玄関のほうから聞こえた瞬間、千尋は、全身の筋肉が収縮するような緊張を覚えた。 見世物にされるんだ、わたし……。千尋はそう思った。 いやだ、いやだ、いやだ。心の中で叫んでいた言葉は、いつしか悲痛な呟きに変わっていた。 「いやだ、いやだ、なんでそんなこと……。いやだ……」 だが、案に相違して、亜希とその友達は、この部屋には上がってこなかった。亜希たちは、加納と共に、一階のリビングで時間を過ごすことにしたらしく、やがて階下が賑わい始めた。 亜希の友達の前で見世物にされるという、千尋の最悪の想像は、現実には起こらないように思われた。高校生ならば、友達を招いたら、まず自分の部屋に通すのが普通だろう。亜希がそうしないのは、千尋の姿を友達の目に触れさせたくないからではないか。つまり、亜希も、女の子を裸にさせて縛っておくなどという、自分の悪趣味を知られるのは、望ましくないと認識しているということ。 二階の自室に千尋を監禁しておきながら、リビングでは、平然とした顔で友達とお喋りに興じているのだろう亜希の神経は、異常としか言い様がない。だが、それでも、亜希が千尋の存在を隠そうとしているなら、まだ救いがあるというものだ。 けれども、本当にそうなのだろうか。 階下が賑やかなのは、ひょっとすると、どのように千尋をもてあそぶかという案を、それぞれが出し合って盛り上がっているからなのではないか。そうして、今にも、亜希が友達を引き連れ、階段を上ってくるかもしれない……。 想像しているうちに、叫びだしたいほどの恐怖に襲われ、千尋は思考を中断した。体中の毛穴から、脂汗が滲んでいるような感じがした。 そんなことない、そんなことない。千尋は、半ば自分を鼓舞するように、心の中で繰り返した。 亜希は、千尋を見世物にするつもりなのか。それとも存在を隠しておきたいのか。この部屋へと、やって来るのか、来ないのか。一階のリビングから、耳障りな笑い声が響くたび、千尋は、暗い部屋のなかで、不安を煽られていたのだった。 西日が赤く差し込み、千尋の座っている周辺が、ぼんやりと照らされている。 もう一つ、嫌でも意識から切り離すことのできないものがあった。 ガラスの容器のトイレである。 その底には、数回分の小便が浅く溜まっている。しかし、それだけではない。黄色い液体の中には、悪臭を放つ茶褐色の塊が浮かんでいるのだった。 隙を見て家のトイレを勝手に使おうと、千尋は考えていた。しかし加納は、自分が見張っていられない間は、千尋の手を縛ってベッドに繋ぎ、決して行動の自由を与えなかった。 便意は、やがて耐え難い腹痛へと変わった。腹の中からは、ぎゅるぎゅると荒れ狂う音が鳴り、寒気に体を蝕まれた。もはや選択肢は、それだけしかなかったのだ。 約二時間前、亜希が外出している際に、千尋は、初めて大のほうをするために容器に跨った。その時の惨めさは、精神に異常を来しそうなほどだった。さらには、し終わったあとに何かで拭くこともできず、今でもおしりが、便の汚れでべた付いている始末だ。 ガラスの容器で小便に浸っている茶褐色の塊は、まさに、人間としての恥の極みである。 今朝方、容器に溜まった小便を見た亜希と加納が、堪らず耳を覆いたくなるほどの言葉を、ねちねちと浴びせてきた。だが、まだ、この大便は見られていない。これを二人が目にしたら、どんな言葉を吐くだろうかと、千尋は、ほとんど怯えに近い思いを抱いていた。 階下への意識が薄れている時だった。 とん、とん、とん、とひとりが階段を上がってくる足音が、耳に飛び込んできた。 ついにその時がやってきたのだ。意識が極限まで研ぎ澄まされる。亜希の友達、自分の汚物、亜希の友達、自分の汚物……。二つの恐怖が、千尋の肩にのし掛かってくる。 足音は、真っ直ぐにこの部屋に向かってきている。亜希か、加納か。 ドアが開けられた。間を置かずに電気が点けられ、部屋が明るくなる。 加納だった。壁に寄り掛かるようにして、入り口に立っている。フリルの付いた派手なブラウスを、加納は着ていた。その出で立ちには、いかにも何か愉しいことでもあるような印象を受ける。 両手を拘束された状態で、正座の姿勢を取っている千尋は、ただただ、そんな彼女の姿を見ていた。 加納が、おもむろにこちらに歩いてきた。その足が、ぴたりと止まる。 「千尋、あんた……」 加納は苦笑いのような表情を浮かべ、鼻をひくつかせた。 ガラスの容器から放たれる悪臭が、加納の鼻にも届いたらしい。恐ろしくひどい臭気だと、自分でも閉口しているものを、他人に嗅がれる恥ずかしさ。 加納は、つかつかと容器のそばまで来ると、嫌悪感と好奇心の入り交じった顔で、千尋の排泄物に目を留めた。 ふふっと、小さな笑い声が漏れる。その笑いは、痙攣のように続き、やがて加納は、口をばっくりと開けて大声で笑いだした。 「ははっ、ははははっはは……。はははぁ」 こんなはしたない笑い方をする加納を見るのは、初めてだった。日常生活の鬱積した感情が、爆発したかのようでもあった。 「安城家の娘であるおまえが、こんなところに糞を出すほど落ちぶれるとはねえ。まったく笑っちゃう。それにしても、ひどい臭い……。お嬢さまの大事なお部屋に、この臭いが染みつかないか、心配だわ」 自分の汚物の悪臭に包まれながら、千尋は、加納の毒々しい言葉責めを背中で受け止めていた。 ふと、そんな千尋の背中に、ぴしゃりと加納の手が宛がわれた。千尋は、体に電気を通されたかのようにびくりとし、体の筋肉が、一層こわばった。 加納は、低い笑い声を漏らしながら、千尋の背中を上下に撫でさすった。気色の悪い手つきで、ぞわぞわと悪寒が走る。 「千尋……。今夜はね、お嬢さまが、夕食会に、お友達の方を招待したんだよ。いらっしゃっている方は、瀬名川記念病院の院長の娘である、瀬名川朱美さま」 院長の娘……。その言葉を聞くと、ひどく不吉な予感を抱かずにはいられなかった。亜希と同じ、そして、以前の千尋とも同じ、資産家の令嬢が、今、この家の一階にいるというのだ。 わがまま。身勝手。人に尽くされるのが当たり前と思っている。そんなマイナスのイメージばかりが、脳裏に浮かんでしまう。 千尋の背中を撫でさすりながら、加納は続けた。 「光栄なことに、今夜、おまえは、お嬢さまと瀬名川朱美さまを、もてなす仕事を与えられたんだよ。しっかりと糞も出したことだし、これからリビングに下りて、お二人のために精一杯働きなさい」 加納と目が合う。加納は、にやりと唇を歪め、千尋の両手を縛っているロープを、ほどきに掛かった。 今、どうしても、訊かずにはいられないことがある。 「わたし、こっ……、この格好で、下りるんですか……?」 千尋は、泣き出しそうな声で言った。その令嬢の前でも、わたしは全裸でいなくてはならないのか。 すると、加納は鼻にしわを寄せ、くすぐったそうな笑みを見せた。 「そうだよ。服なんか着なくても、お客様をもてなす仕事はできるから、心配なんてしなくていいんだよ。……それとも、何? おまえ、恥ずかしいの? 見ず知らずの女の子に裸を見られることが、恥ずかしいの? ねえ? おまえにも、まだプライドが残ってたの?」 加納はもう立派な大人の年齢であろうに、喋り方が、千尋と同年代のように退行していた。つまり、この状況を、子供のように愉しんでいるのだ。 千尋は、歯を食いしばったまま、答えなかった。 薄々予期していたが、やはり亜希は、千尋という生きた玩具を見せる目的で、友達を呼んだらしい。だが、亜希の友達の子とは、一体全体、どういう人間なのか。同じ女を辱めて愉しむような、亜希や加納と同類の人間が、果たして他にもいるのだろうか。 もしかすると、亜希の目的はむしろ逆で、千尋に対して、より耐え難い苦痛を与えるための道具として、友達を用意したのかもしれない。考えれば考えるほど、そちらが実情に近い気がしてくる。 「千尋、立ちなさい、下りるよ」 立ち上がった加納が、薄笑いの表情で見下している。 恐怖と絶望によって、体のすべての細胞が狂い始めていた。目が霞み、顔の筋肉は引きつり、心臓は早鐘を打ち、四肢の至る所で痙攣が起きている。 立ち上がりたくない。いや、立てない。処刑台に連れていかれるかのような恐怖だった。 「立つんだよ、千尋っ」 ついに加納は、千尋の二の腕を引っつかんだ。 鈍い光沢を放つ金属製のドアが、目の前にある。ドアを隔てた向こうから、亜希と、もう一人の女の子の話し声、それに、スピーカーから流れる男性アイドルグループの曲が聞こえてきた。 「何をためらってるの、千尋……。早く、ご挨拶をしに入りなさい」 千尋のかたわらに立っている加納が、低く言った。 身体感覚が妙に頼りなく、片足を一歩踏み出すという動作に、どれだけの労力が要るのか、といったことが曖昧になっている。 まず、ドアを開けなくてはならない。そして、見ず知らずの少女の前に、全裸で進み出て、挨拶を述べるのだ。 手をドアの取っ手に掛けた瞬間、地から何かが這い上がってきたかのように足が竦んだ。麻痺を起こしたみたいに動けなくなった。 「あの……、これから、わたしは何をするんですか」 千尋は、引きつる唇を動かして尋ねた。わたしは何を『される』んですか、と本当は問いたかった。 「それは部屋に入ったら、お嬢さまが教えてくれるわよ。わたしの口から言えることは、おまえは、お嬢さまと、朱美さまを愉しませて差し上げる仕事をするってことだけ」 その物言いから、リビングにいる亜希の頭には、千尋を生贄とした夕食会の計画が、極めて具体的に思い描かれていることが窺い知れた。あの幼い顔に悪魔のごとき下卑た笑みを浮かべながら、千尋に何かを要求するのだろう。 このドアは、亜希の待つ地獄への扉なのだ、と千尋は再確認した。 そうすると、なぜか突然、奇妙な気持ちになった。すぐそばに立っている女は、まだ最後の一線で、人間の心というものを残しているのではないか。亜希よりかは、この女のほうが、ずっとましだ……。 千尋は、体の向けを変えて両手を伸ばし、加納のワンピースの肩に触れた。泣いている小さな子供が、心配する親に対して、何かを訴えかける時のように。そうして右手を滑らしていき、意外なほど、すべすべとした加納の腕を、そっとつかんだ。 さすがの加納も、意表を衝かれた顔をしている。 「加納さん……。わたし、ごめんなさい……。あの、前から、加納さんが丁寧な態度で接してくれてたのに、わたしは、素っ気ない態度とか、取ってたと思います。加納さんが怒るのも、無理ないと思ってます。わたし、こんな目に遭って、ようやく気づきました。いい気になってたんだって。ごめんなさい。もう、許してもらえませんか。お願いします……」 千尋は、加納の目を見つめた。加納のほうも、邪険に突っぱねるようなことはしない。 やがて、加納は小さな溜め息を吐いた。 「許す、ねえ……」 加納は、言いながら片手を上げ、千尋の唇に触れた。加納のほうもまた、実に奇妙な反応を返してくる。千尋は、加納の意図が読み取れず、されるがままになっていた。 加納の手が、千尋の唇をめくり返しながら下りていき、喉元を通って鎖骨を撫でた。さらに自然な手つきで、掌が胸の谷間へと移動する。その掌の滑り具合には湿り気が含まれており、千尋は、全身から汗が噴き出していることを自覚させられた。むろん、じめついた暑さのせいではない。 ごくっと、千尋は喉を鳴らした。 「お嬢さまのために尽くすのは、おまえに与えられた仕事でしょう。どんなにつらいことでも、我慢しないといけないわ。わたしが、千尋を好きとか嫌いとか、そんな問題じゃあないの」 反射的に呼吸が止まっていた。 加納が、胸の谷間から脇の下へと、乳房を押し潰しながら手を滑らせていったのだ。さらに今度は逆に、外側から内側へと、千尋の乳首をひん曲げながら乳房を撫でる。その往復の動作が繰り返された。 「うぅ……。いや……」 恐怖と混乱に陥った精神状態で、性的な刺激を与えられ続けるのは、気の狂うような責め苦だった。 やがて、加納はもう片方の手を上げると、両手を、千尋の双方の乳房に、ぴたりと宛がった。乳首が、指と指の間に挟まれる。加納の微妙な指使いによって、性感帯の突起はこすれたり、締めつけを受けたりする。 千尋は、身悶えするような恥辱に喘いだ。 明らかに加納は、自分にすがってきた千尋のことを、もてあそんでいた。千尋の頭の中には、もはや絶望しかなかった。どうしてわたしは、こんな女に情けを期待したのだろう。 「ひとつ言っておくわ、千尋……。もし今夜、おまえが、お嬢さまの命令を嫌がったために、夕食会の雰囲気が悪くなって、お友達の朱美さまが、不満を持ったりした場合、おまえは、ただじゃ済まないからね。その時は……」 加納は、意味ありげに言葉を切り、右手をすっと下ろした。その手は、いきなり、無防備な千尋の性器に食いついた。 「はあうっ」 衝撃の悲鳴を、千尋は発していた。 加納は、千尋の性器を揉みほぐすように手を動かした。貪欲なまでに五指を蠢かせて、柔らかな女の組織を探索し始める。太ももの付け根と大陰唇との溝を、性器の縁取りをするように指が行き来する。その内側では、陰唇が抓まれて揉みくちゃにされていた。 性器の組織が、その悪魔の手によって、ぐちゃぐちゃに溶かされていくような錯覚に襲われる。身を裂かれるような恥辱と嫌悪感に悶え、千尋の両足の踵は、ふくらはぎが攣ったように浮き上がりっぱなしだった。 恥部の裂け目の中に、中指が差し入れられる。加納は、千尋の耳元で、言葉の続きを囁きだした。 「けじめとして、処女の血を流して朱美さまに謝罪させるからね。そんなの悲しいでしょう。だったら、お嬢さまに言われたことは、どんなことでも従いなさい。お嬢さまと朱美さまに愉しんで頂くことだけを、考えるの……」 全身が凍りつくような脅しだった。脚の力が抜け、踵が床についた。 千尋の性器から、ゆっくりと手が離れる。加納は、その手を、千尋の顔にべったりとこすりつけてきた。 「うっうう……」 むせ返るほどの臭気の中、千尋は、言い様のない感情にうめき声を上げた。 「さあ、リビングに入りなさい」 有無を言わせぬ口調で、加納が言った。 もはや、逃げ道はどこにもなかった。千尋は、ドアノブを回し、おずおずとドアを押していった。極めてゆっくり、裸の体を見られる瞬間を、一秒でも先送りしたいというような気持ちで。 男性アイドルグループの歌声が、耳に飛び込んでくる。そして、二人の喋り声。リビングの中は廊下よりもずっと明るく、眩しいと感じた。 広大なリビングに、大小二台のテーブルが置かれていて、どちらにも白いテーブルクロスが掛けられている。大きいほうのテーブルにだけ、色とりどりの料理が載せられていた。それは、以前の千尋の感覚からしても、華やかな晩餐に映る。 奥にあるソファに、亜希たちが揃ってだらしなく腰掛けていた。 千尋は、二人のほうへと、そろそろと脚を送り出していく。後ろから、お目付役の加納が、一定の距離を置いて付いてきていた。 いよいよ対面である。 亜希が、千尋の姿を認めた。 「あっ。千尋ちゃあん。待ってたよー」 当然、もう一人の女の子も、千尋に目を向ける。 この瞬間。 赤の他人に、一糸まとわぬ体を見られる屈辱。加納に監視されているので、胸や性器を視線から守ることもできない。 朱美という子は、目鼻立ちがずいぶんとはっきりしており、そのためか、亜希よりずっと大人っぽく見えた。髪の毛は、肩下まで無造作な感じに下ろしている。髪を染めているわけでもなく、髪の量は、野暮ったい印象を受けるくらい多いため、ヘアスタイルには、それほど気を遣っていないようだった。 その朱美の大きな目が、千尋の裸の体を、何の憚りもなく無遠慮に観察しているのがわかる。そして、千尋の顔にも、じっと目を向ける。同じ十代の女の子の全裸を目の当たりにした朱美は、馬鹿にするでもなく、むしろ、怪訝そうな顔をしていた。このひとは、恥ずかしくないのかな、とでも言うような顔をしているのだ。たちまち、自分の顔が紅潮してしまうのを、千尋は感じた。 亜希が、リモコンを操作して、ステレオから流れるJポップを消して言う。 「こっちに来て、千尋ちゃん。朱美ちゃんも、ほら、立って」 亜希が朱美を促し、二人はテーブルの椅子に着いた。 だが、豪勢な料理の載っている大きいテーブルではなく、小さいほうだった。そのことに、千尋は、強い違和感を抱いた。なぜかは、自分でもわからない。恥辱に晒され続け、何事にも敏感になっている自分の意識が、漠然とした何かを捉えたのだ。 亜希と朱美の着いたテーブルのほうに、千尋は寄っていく。 そこで、亜希が、うきうきとした顔を、千尋と朱美の交互に向けながら、紹介を始めた。 「ねえ千尋ちゃん、この子は、アケミちゃんっていうの。わたしと同い年だよ。お父さんが、瀬名川記念病院っていう、すごい大きな病院の院長さんなんだよ。千尋ちゃんは、瀬名川記念病院って知ってる?」 「いえ……」 千尋は、力なく首を横に振った。 全裸で紹介されるだけでも耐えがたいことなのに、千尋のその苦痛に、スパイスを加えるような嫌味を、亜希は確信的に吐いている。千尋が失った、何不自由ない生活というものを、その子は、亜希と同様、持ち続けているということ。まず、その現実を、千尋に思い知らせようという意図が、亜希の口振りには、明らかに含まれていた。 「朱美っていいまーす」 朱美は、鼻にかかる声でぶっきらぼうに言った。 千尋は、朱美の素振りから、彼女が、この異常としか言い様のない状況を、どのように捉えているのかを推し量ろうとした。しかし、皆目見当が付かない。この子は、いったいどんなことを考えて、その席に着いているのだろう、と千尋は思う。 次に、亜希が千尋を紹介する。 「そんで、こっちは、千尋ちゃん。うちらより二つ年上。安城商会っていう会社の、社長さんの家の子なの」 亜希のその言葉に、朱美が少し反応した。 「へえー」 意外そうな声を出した朱美は、斜めに見上げるようにして、改めて千尋の顔に目を向ける。 どうも朱美は、千尋の境遇について、亜希からまったく聞かされていない様子である。つまり、この家で、千尋が慰み者の扱いを受けていることも、知らないのだろう。それで、目の前に立っている裸の女の子が、自分と同じく良家の娘だと教えられ、意外の感に打たれているのだ。 要するに亜希は、この夕食会で、千尋と朱美の両者を驚かせようとしているのだ。もちろん、その質と程度は、まるで異なってくるのだが。 加納がそっと近寄ってきて、千尋にだけ聞こえるような声で言う。 「千尋……。今度は、おまえが挨拶をする番でしょ。もっとテーブルのそばまで寄って、礼儀正しく自己紹介をしなさい」 またひとつ、自分の誇りを捨てなくてはならない。千尋は、奥歯を噛みしめて足を踏み出し、亜希と朱美の座っているテーブルとの距離を、縮めていった。 テーブルからは、二人の女の目が千尋に向けられている。いや、女のガキの目、というべきだ。どちらも、互いに真似しあったように、下手くそなアイメイクで黒々と目を縁取っており、くだらない背伸び感が滲み出ている。亜希などは、色白の幼い頬に、チークを塗りたくっていて、千尋には、もはや滑稽にしか見えなかった。 ふと、千尋の脳裏に、輝いていた頃の自分の姿が浮かぶ。以前のわたしだったら……。 きっと亜希は、千尋と幼なじみであることを自慢するかのように、千尋を朱美に紹介したことだろう。また、朱美も、それを羨ましがり、千尋と少しでも親しくなろうとしたはずだ。かりに、初対面特有の対抗意識から、朱美が、生意気な態度を取ったとしても、千尋のほうは、年上の度量の広さを見せつけ、軽くあしらってしまう。女として、朱美に負けているところなど、皆無と言っていいのだから、張り合う必要は、どこにもない。 そんなものなのだ、本当は……。 しかし、今、この状況はどうだ。 亜希は、嘲りの目つき、朱美は、奇異なものでも見る目つきで、千尋を眺めている。 こんなクソガキたちの前で、女としての誇りを蹂躙されている屈辱。 「ええっと……、あ、安城千尋といいます。え……、よろしくお願いします」 声は震えていた。言い終えると千尋は、朱美に向かって頭を軽く下げた。あまりに惨めで情けなかった。 わずかの間、対応に困るような顔をしていた朱美が、はあっと、ため息を吐いた。 「ねえー、ちょっと、亜希ちゃーん。わたしさあ、女体盛りっていうから、もっと、なんていうか、モデルみたいな、綺麗な人が出てくるのかと思ってたのにぃ」 耳を疑うような言葉に、千尋の意識は鈍く貫かれた。 にょたい、もり……。 「ええ? 朱美ちゃん、千尋ちゃんじゃあ、不満?」 亜希は、苦笑いを浮かべて訊く。 朱美は、拗ねるように唇を曲げた。 「不満っていうか……、そもそも、何なの、この人の髪型。あり得ないくらいダサいんだけど……。それに、なんか、おどおどしちゃってるし……。見た目とか態度とか、そういうの全部ひっくるめて、ダサい」 すでに朱美は、千尋の人権など眼中にないようだった。自分に仕える立場の人間に対しては、何を言っても許されると思っているのだろうか。しかし、今は、それに腹を立てている場合ではない。 「千尋ちゃんの髪型は、色々と事情があったのぉ。千尋ちゃんは、女体盛りやってくれるんだから、あんまりひどいこと言っちゃダメだよ。朱美ちゃんだって、女体盛りに興味あるって、言ったでしょう?」 亜希は、ふくれっ面のような表情で話している。 「たしかに言ったけどさ……」 朱美は、もう一度、納得のいかない顔で千尋を見やる。 「千尋ちゃん、ごめんね。千尋ちゃんに断らずに、こんな計画立てちゃって。でも、千尋ちゃんなら、きっと、やってくれると思ってたからぁ……」 語尾と共に、亜希の目つきに、底無しの悪意が宿っていくのが、千尋には見えた。 千尋は放心状態で、言葉を失っていた。 亜希や朱美や白いテーブルの入った視界が、霞んで見える。自分の裸体が、その白いテーブルの上に、仰向けに横たわっている光景を想像する。そして、豪勢な料理の数々が、乳房や腹部、太ももなどに載せられる。亜希と朱美が、そこに箸やホークを伸ばしていく……。 想像しているうちに、意識が遠のきそうになった。そんなこと、ぜったい、できない……。 その時、すっと隣に寄ってくる気配があった。脅すような低い声がし、それが加納だとわかった。 「やって差し上げられるでしょう? 千尋……」 その声には、さっき、廊下で与えた警告を憶えているわね、という響きが含まれていた。 千尋は、心臓を締めつけられるような思いで返事をした。 「はい……。やります……」 すると、わっと亜希が手を叩きだした。 「やっぱり! ありがとう、千尋ちゃんっ」 あどけなさを装ってはしゃぐ亜希の一方で、まだ朱美は、探るような目つきで千尋を眺めていた。 「そこでね、千尋ちゃん……。千尋ちゃんの女体盛りを記念して、千尋ちゃん本人のおしっこで、乾杯をするってことにしたの。粋なアイデアでしょっ?」 耳には入っているが、亜希の話す内容が、途方もなく現実味を欠いているせいで、千尋には、その状況が想像できなかった。 亜希が、何か得意気な様子で話を続けている。 「で、乾杯するだけで、まさか本当にそれを飲むなんてことはしないんだけど、一応、新鮮なのがいいわけよ。だからあ……、ガラスのトイレをここに持ってきてさ、……おしっこ、出してよ、千尋ちゃん」 亜希と朱美が、けばけばしいアイメイクを施した目で、千尋を凝視している。そして隣では、加納が目を光らせているのを、ひしひしと感じる。 ほどなく、亜希の話の内容が、実感として襲ってきて、千尋は戦慄した。 「へっ……へえぅ……」 千尋は、小さな嗚咽を漏らしていた。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.