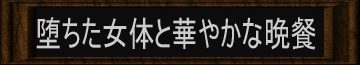
第七章
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
アスパラやレタス、アボガドなどの前菜が、乳房の谷間に載せられた。 テーブル上に、冷凍した魚のように横たわった千尋の裸体を、亜希と加納が眺めている。どこに何を配置するとよいか、見た目のバランスや利便性などを、それなりに考えているらしい。 「千尋ちゃん、ちょっと、気をつけして。動いちゃダメだよ」 亜希に命じられ、千尋は、両腕を胴体にぴったりと付けた。亜希は、千尋の腕に、チーズをサーモンで巻いた一口サイズのつまみを並べていく。 「千尋、太ももをぴったりと付けなさい」 加納は、両脚の太ももから足首にかけて、三種類のフランスパンを置いていった。千尋の脚は、真っ直ぐで綺麗な形状をしているため、パンの列も整然としていた。 そうして千尋は、ほぼ金縛りの状態にさせられ、動かせるのは首から上だけという有様だった。千尋の呼吸のリズムに合わせて、乳房に配された前菜が上下している。窮屈というより、息が詰まりそうだった。 だが、自分の体が、女体盛りなどという猟奇的なイベントの『器』として、利用されていることについては、どこか他人事のようにさえ思われた。まともな感覚だったら、裸の体に食べ物が盛られていく過程は、ほとんど拷問のように感じることだろう。 さっき、心のヒューズが飛んでしまったのは、よかったのかもしれない。千尋は、ぼんやりとそんなことを思った。それにしても、わたしのことを、よくもまあ、ここまで追い込んでくれたものだ……。 ひとり席に着いている朱美は、控えめな笑みを浮かべ、それを眺めていた。趣向を凝らしたこの持て成しに、そこそこ満足しているふうである。さながら、少女の前に、全裸の少女が、生け贄として差し出されているかのような様相を呈している。莫大な財力を誇る瀬名川家の令嬢だけに、朱美には、同年代の女の子たちにはないような経験が数々あるだろう。だが、これほど非日常的な光景を目の当たりにするのは、初めてに違いない。 腹部に、白身魚と貝のムニエルが載せられると、千尋は、その熱さに思わず悲鳴を上げ、体を動かしていた。腕に載っていたつまみが、ぼとぼととテーブルに落ちる。 加納が、じろりと睨めつけてくる。 「すいません……。あの、熱かったんで……。もう少し冷ましてから載せてもらえませんか?」 千尋は、これ以上ないほど丁寧な口調で言った。 「何を馬鹿なことを言ってるの、千尋。朱美さまに、お出しする料理なのよ。冷ませるわけないでしょうが。おまえ、お客さまをお持て成しするという自覚が、足りないんじゃない?」 加納は歯牙にもかけず、鼻で笑った。 その非情さに、千尋は言葉を失った。だが、頼みが聞き入れられない以上、耐えるしかない。 三人分の熱い白身魚が腹部に載せられる。やはり熱い。けれども、耐えられないこともないような気がする。火傷の跡も、そんなにひどくはならないだろう。 朱美が、まだ十五、六の小娘とはいえ、客人を招いた夕食会とあって、千尋の裸体に盛られた料理は、どれも高級なものばかりだった。庶民の感覚であれば、女体盛りにして食べるなどという粗末な食べ方は、とてもできないだろう。この夕食会は、まさに金持ちの悪趣味な道楽としか言い様がない。 「亜希ちゃーん。この辺り、ぽっかり空いてるんだけど、何か載せないのー?」 朱美は、千尋の体を指差している。今、白身魚と貝のムニエルが載せられた隣、へその周辺から陰毛の生えぎわにかけての部分だ。恥丘のそばということもあり、朱美の顔には苦笑いが浮かんでいた。 「はい。そこには、千尋自身の手料理を盛りつけます。パスタなんですが、その子の自慢の料理らしいので、是非、お味をお確かめになってください」 加納は、有能な社長秘書のように答える。 この日の昼間、加納に命じられて作ったペペロンチーノのことだ。わたしの体に、あれまで載せるつもりなのかと、千尋は、もはや自虐的な笑いすら浮かべそうになった。 間もなく、千尋お手製のパスタが、体の一番際どい部分に盛られた。 シャンデリアの輝きを、千尋は、見るともなしに見ている。意思を発することもできず、ただ呼吸を繰り返すだけの、わたし……。もう人間ではなくなってしまった気がする。 わたしは、人間の形をした『なまもの』みたいなもので、この部屋にいる女たちに、わたしの体に載っている食べ物と一緒に、わたしの肉体も貪り喰われてしまうのではないだろうか……。 亜希と加納が揃ってテーブルのかたわらに立ち、自分たちの創り上げた芸術品を満足そうに見下ろしていた。千尋の首から下は、乳房の先端や陰毛の茂みを除いて、色とりどりの料理で飾り付けられている。 朱美が、感嘆の声を上げた。 「あー、なんか、すごーい。こうして見ると、綺麗なもんだねえ」 「朱美さまに気に入って頂けて、とても嬉しいです」 「うん、わたしもー。今夜の『これ』は、朱美ちゃんのためにやったんだもん。さっ、乾杯しよ!」 三人とも席に着き、彼女たちはグラスを手にした。その中には、千尋が人間としての誇りを捨てて排泄した、尿が溜まっている。千尋を囲む三人の女の顔には、揃って、背徳感をくすぐられているような薄笑いがあった。 亜希が、おもむろに切り出した。 「えっと……。じゃあ、千尋ちゃんの女体盛りっていう、なんか特別な、愉しい晩餐に乾杯しまーす。はい、カンパーイ!」 加納と朱美も嬉々として乾杯を唱和し、三つのグラスが合わさった。 シャンデリアの輝きを背景に、かちかちと触れ合うグラスの中で、黄色い液体が揺れる。 千尋は目を見開き、その光景を凝視していた。 「よしっと……。まあ、千尋ちゃんのおしっこは、あくまで乾杯のためのものだから、はじっこにどけておきましょう」 亜希と加納のグラスが、テーブルの端に置かれる。だが朱美は、自分のグラスを、千尋の頬の横へと押しやった。 「女体、あんたの飲み物は、これだから」 朱美は、鼻に掛かった声でそう言った。『にょたい』という言葉が、千尋のことを指しているのは明らかだった。 「喉が渇いたら、女体は、これを飲みなさいね。今、飲む? 体を動かせないなら、わたしが飲ませてあげようか?」 朱美は、千尋を『女体』と呼ぶことにしたらしい。同じ人間として扱う気がないことを、如実に物語る呼び方だった。そして、ついに自ら、千尋への嫌がらせを始めたのである。亜希や加納と違い、これまでは、千尋に対して傍観者の姿勢だった朱美が。 それを見ていた亜希は、目を輝かせて笑った。朱美が、同じ快感を共有できる同志だとわかり、嬉しくて堪らない様子だった。 「千尋、朱美さまに訊かれてるんだから、黙ってないでちゃんと答えなさい」 加納も、得意げな様子で朱美を後押しする。 「いえ、飲みたくありません……」 千尋は、仕方なく答えた。 「あーそう……。客のわたしが勧めてんのに、飲まないって言うんだ? ねえ、試しに、一口飲んでみてよ」 ぴたりと頬にグラスを付けられる。自分の尿の臭いが、鼻孔に流れ込んでくる。 「すみません……。飲めません」 千尋は、蚊の泣くような声で言った。 「女体、仕事でしょーう? あんた、客の言うことが聞けないわけ?」 朱美は、ますます付け上がってきた。 「おねがいです……、朱美さま。やめてください」 すると朱美は、にたりと白い歯を覗かせ、グラスをテーブルの端にやった。おそらく、千尋に理不尽な嫌がらせをし、許しを乞われるという体験を、一度してみたくなったのだろう。 驚きはしない。やっぱりな、と千尋は思う。朱美に指先で頬を突かれた時から、こうなることは予想していた。 ちょっとした意地悪な気持ち。朱美の中にも、それが芽生えていたのだ。きっと、その小さな悪意は、この状況下で際限なく膨らんでいくだろう。惨めな裸の女が、目の前に横たわっている状況では。 元から、朱美は、どちらかといえば性格の悪い部類に入る少女だっただろうと、千尋は推測する。けれども、仮に朱美の席に座っているのが、他の誰かであったとしても、結果は同じだったのではないか。人間なんて、そんなものだと、今となっては思う。千尋に救いの手を差し伸べるような人間ならば、最初から、その席には座っていない。 亜希と朱美はフルーツサワー、加納はワインを飲んでいた。 旨そうにサワーのグラスを傾ける亜希を、千尋は横目で眺めた。これまでに、千尋の前で亜希がアルコールを口にしたことは、一度もなかった。だから、そのうち、この子に酒を教えてやろうなどと、わたしは考えていたっけ……。 三人の箸やフォークが、千尋の裸体に載った料理を取るために、肌をつつき始める。乳房、腕、腹部、太もも……。千尋は奥歯を噛みしめ、その嫌悪感に耐えていた。 「千尋ちゃんの作るパスタは、ホント、おいしい。ねえ、懐かしいよねえ、わたしたち二人で、色んな料理作ったじゃない。これから当分、千尋ちゃんは、この家にいるんだから、いつだって一緒に料理できるね……」 亜希は、パスタを口に含んで言った。そして、くすっと笑って付け加える。 「料理する時にも、千尋ちゃんには服を着せてあげないけど、また色々と教えてねっ」 「でも、女体盛りに、女体自身が作った料理を載せるって、なんかおもしろーい」 パスタを巻く朱美のフォークが、へその下の柔肌を容赦なく刺激する。 今の亜希の言葉が、千尋の胸に鈍く刺さっていた。亜希と二人、仲睦まじく料理作りに励んだ過去が、にわかによみがえってくる。 千尋の下腹部に盛られたペペロンチーノ。それも、亜希にレシピを教えながら一緒に作ったことのあるものだった。そういった思い出までも、亜希が、千尋に対する当てつけとして利用しているのは明白だった。 心の内に、一粒の涙がこぼれ落ちる。なんで、こんなことになっちゃったんだろう……。 しかし、そこで千尋は思考を止めた。考えないほうがいい、何も。 今は、感情が、薄い膜に包まれているかのように茫漠としている。さっき、心のヒューズが飛んでしまったためだ。もし今、その膜に亀裂が走ったら、感情が噴出し、自分でも、どうなってしまうかわからない。 亜希と朱美は、食事が始まって十五分もすると、表情や喋り方に酒の酔いが現れ始めていた。 「どう? 千尋ちゃんも何か食べたいでしょう? はい、あげる」 亜希は、前菜をつまんだ箸を、千尋の口もとへ突き出した。 食べる気になどなれない。千尋は口を閉じていたが、亜希は、唇の中へ強引に箸を突っ込んできた。吐き出してやりたかったが、反抗的な態度を見せても何にもならないと思い、それを噛み始めた。 「千尋ちゃん、おいしい? でも、ちょっと味が薄かったでしょ?」 亜希は、悪意のないような微笑みを浮かべ、千尋を見下ろしている。下手くそな化粧で、初めから赤らんでいた頬だが、アルコールで上気したせいで、余計に赤くなっていた。 「やっぱり、味が薄かったでしょう。やっぱり……。今、味付けしてあげるから、ちょっと待ってね、千尋ちゃん」 なぜか亜希は、ひとりで合点し、今度は、レタスとアボガドを指でつまんだ。 「えっ……、なにしてんの亜希ちゃん」 朱美が、顔をしかめた。 ぴくりと千尋の下半身が反応した。 今、亜希のつまんだレタスとアボガドが、食事中には決して触れられなかった部分に置かれているのだった。ペペロンチーノの盛られたすぐそばだったが、そこは、陰毛の茂る肉の丘だった。 「やだっ、ちょっと汚い……」 朱美が、微苦笑をして言った。しかし、言葉とは裏腹に、何かを期待しているふうでもあった。 「調味料、調味料……」 亜希は、ぶつぶつと呟きながら、突然、陰毛の中に埋めた前菜で、恥丘をごしごしとこすり始めた。前菜の汁気で、陰毛が皮膚にへばり付いていく。 「うっ……」 千尋は、その不快感に耐えきれず、がたりと脚を動かした。整然と並んでいたフランスパンが、テーブルに落ちていく。 「千尋! 食べ物が載ってるんだから、動くんじゃないよ!」 加納が一喝し、千尋の両膝をつかむと、テーブルに無理やり押しつけた。 心臓が早鐘を打っている。女体盛りとして、料理を載せる『器』に徹していれば、この時間を、なんとかやり過ごせると思っていた。しかし、亜希は、酒の酔いも手伝ってか、それだけでは物足りなく感じ始めたようだった。 ふふふ、と亜希が笑い声を漏らした。その直後、亜希の手にある前菜が、千尋の性器の割れ目へと入り込んできた。 総毛立つ思いだった。身をよじって逃れたくても、加納に両脚を強く固定されていて動けない。 「千尋ちゃーん。千尋ちゃーんのためにぃ、味つけしてあげるんだからぁ、ちょっとくらいガマンしてよーう」 亜希は、呂律の怪しい口調で言い、つまんでいるレタスとアボガドを、肉の割れ目に沿って上下に動かしていった。 「ああぁっ……」 不覚にも、千尋は、喉の奥から悲鳴に似た声を漏らしていた。断続的にクリ○リスがこすられ、その刺激が、電気のごとく千尋の肉体の芯を貫いていった。加納の手による圧力を押し返すように、片膝が立ち始める。おしりが何度か浮き上がり、魚類がのたうつようにテーブルを打った。 「やっだあ、女体が感じてるー! なんか、すんごい淫らな光景を見せられてる気分なんだけど!」 珍しく朱美が興奮した様子で、嬌声を上げた。 ふざけんな……! 好き勝手を言ってはしゃいでいる朱美を、怒鳴りつけてやりたい。 おしりを浮かせて亜希の反対側、朱美のほうへと曲がっていく千尋の腰を追うようにして、亜希は、執拗に性器を責め続けてくる。 「女体、気持ち悪いから、こっちに寄ってこないで!」 朱美が、千尋の肩を邪険に小突いた。 「千尋! じっとしてなさいって言ってんでしょうが……」 加納が、本腰を入れて千尋の下半身を押さえつけてきた。腰と太ももに、体重を掛けられる。千尋の裸体に載っていた料理なら、すでに大半が落ちてしまっているというのに。 腰と両脚を固定されてしまうと、その耐えがたい刺激が、何か鋭利さを増して肉体を襲ってくるように感じられた。 加納は、冷ややかな薄笑いを浮かべ、千尋の身悶える様を眺めていた。 「あふぅ……。ううっうっうっ」 忌まわしい刺激を少しでも軽減したいという無意識が、千尋を喘がせていた。しかし、苦痛とは裏腹に、生理的な反応として、生温かいものが膣口から滲み出していることにも、千尋は気づいていた。 かろうじて動かせる上半身を、必死に左右によじる。苛烈に責め苛まれている下腹部から、体の上半分だけでも分断して逃そうとするかのように。 「いやぁ……、あっ、あっ、もうやめてぇ、亜希ちゃん……」 あられもない声を発してしまう口もとを覆いながら、千尋は、消え入るような声で哀願した。 排泄した大便を見られ、放尿の瞬間を晒し、羞恥心や屈辱感といったものは、もう、とっくに消えていると思っていた。だが、今、千尋の心と体は、絶望的なまでの恥辱に焼かれていた。 いつしか、目には涙が滲んでいた。 亜希が、くすくすと笑いながら、ようやく手を止めた。 「千尋ちゃーん。なに、あーん、とかエッチな声出してんのぉ? 朱美ちゃんもいるんだから、やめてよぉ、恥ずかしいなあ」 亜希は、千尋の恥部に挟み込んでいたレタスとアボガドを、おもむろに抜き取り、それをじっと見つめる。そこで、加納も手を離した。 解放された安堵と共に、千尋は、自分が自分ではなくなっていくような虚脱感に襲われた。ぐったりとしたまま、亜希の挙動を、見るともなしに視界に捉えていた。 亜希の目つきは、酒のせいか、とろんとしている。 とても信じられなかった。亜希の手で、こんなことをされるなんて。 「えへっ、へっへっ……。野菜が、変な汁でぬるぬるしてるぅ……。はい、千尋ちゃん。味つけしてあげたんだから、これ食べて」 放心状態の千尋の唇の内側へと、それがねじ込まれた。 千尋は、口を動かすことすらできず、前菜の味とともに、奇妙な酸っぱさが口の中に広がっていくのを、ただ感じていた。 「どーう? おいしい? 自分のま○この汁で、たっぷり味つけした野菜は」 頬杖をした亜希が、にたにたと笑いながら訊いた。 千尋は、力無く首を横に振った。 「おいしいです、だって、千尋ちゃんったら……。ねえねえ、朱美ちゃんも、千尋ちゃんに、何か食べさせてあげたら? 自分のま○この調味料が、よっぽど気に入ったらしいからぁ」 地獄に落ちろ、この腐った小娘……。 「えっ……? へへっ……?」 戸惑ったのか、朱美は低く笑い、はにかむような表情を見せた。 三人が、視線を交わしているような間があった。 元から性格の悪そうな朱美のことだ。やめてください、と訴えたところで、聞き入れられるとは思わなかった。 案の定、朱美もまた、食べ物を指でつまんだ。チーズをサーモンで巻いた、一口サイズのつまみだ。そして身を乗り出し、ためらいがちな素振りを見せながらも、千尋の股を覗き込む。 「やっだあ、女体……。変な汁、こんなに垂らしてたんだあ。変態じゃーん、きもーい。あんた、仕事中でしょう?」 じゅくじゅくとした陰唇に、つまみが押しつけられる。太ももやふくらはぎの筋肉が、反射的に突っ張り、足の指をきつく折り込んでいた。 しかし、亜希とは違って、朱美は、やたらと性感帯を刺激するようなことはしなかった。愛液をすくい取るように、肉の割れ目を、つまみで何度か撫で上げる。 ところが、その代わり、性器の下の器官、つまり肛門にまで手を出してきた。 「女体が……、おしりをちゃんと拭いてなかったの、さっき、見ちゃったんだよねえ……」 朱美は、不潔さに対する嫌悪感に眉をしかめながらも、口もとは、薄笑いで歪んでいた。おしりの肉の奥にねじ込むようにして、窄まった穴に、食べ物をこすり付けてくる。 こいつ……。こいつも……、信じられないくらい腐ってる……。 固形チーズを、ぐりぐりと肛門に押し付けられる汚辱感に、千尋は、全身に鳥肌が立つ思いだった。 千尋の愛液と大便の残滓が付着したつまみを、朱美は、自分の顔の前に持ってきて、まじまじと眺めた。苦笑いの表情が、一層苦々しげになる。 「うっわ、きったなーい。チーズが変な色になってるし……。これ、どんな味がするんだろう……。はい、女体、味見して」 朱美は、当然のことのように、それを千尋の顔に突き出した。 千尋は、不快感を表すこともせず、無抵抗に口を開けた。まだ、亜希に入れられた前菜も残っている口の中に、それが押し込められる。 「ちゃんと飲み込みなさいよ。吐き出したりしたら、許さないからね」 朱美に言いつけられ、『味つけ』された前菜とつまみを、ゆっくりと噛み始めた。本来なら、決して味わうことのないものが、喉に流れ込んでくる。胃液が逆流しそうだったので、その味を、なるたけ意識しないようにした。 「女体、どーう? あんたの、いやらしい汁とうんちで、ミックスされた調味料の味は? おいしい?」 返す言葉も思い浮かばす、千尋は、黙って噛み続けた。 すると、朱美は舌打ちし、眉間に何本もの皺を刻んだ。いきなり千尋の顎をつかむと、頭部を揺すってきた。 「なんなのー、あんた、訊かれたら答えろよなー、それが、お客に対する態度かよー、なあー?」 どうやら、こっちのガキも、ずいぶんと酒が回っているようだ。 「へんな……、へんな味が……、します」 ふん、と朱美は鼻で笑い、今度は、頬をつかんできた。 「変な味かあ、ざーんねん……。おいしいんだったら、わたしたちも、女体特製の調味料を付けて、何か食べたかったのになあ……」 そう言いながら、頬に宛がった指を閉じたり開いたりし、千尋の顔立ちを崩して愉しんでいるようだった。焦点の合わない目で宙を見つめたまま、朱美の指で唇を窄められ、千尋は、間抜け面を晒していた。 亜希が、握った拳を口もとに当て、せせら笑っている。 そこでふと、朱美が、意外な発見をしたような表情をした。 「あっ……。ねえねえ亜希ちゃん……。女体ってさあ、よくよく見ると、結構美人かもしんない。ダサい髪型してるからブスだと思い込んでたけど、顔だけ見ると、かなり綺麗かも……」 「そうだよっ、千尋ちゃんは可愛いんだよー。あ、ちょっと待ってて……」 亜希は、得意げな様子で席を立った。 ソファに置いたバッグから携帯電話を取り、ばたばたと戻ってくる。なにやら携帯のボタンを操作し、液晶の画面を朱美に向けた。 「ほらっ、これ、何ヶ月か前までの千尋ちゃんだよ!」 朱美は、その画面をじっと見つめ、驚きの声を発した。 「うっそ、可愛いじゃーん、女体! この子がこの女体だなんて、ぜーんぜん思えなーい!」 「千尋ちゃんも見て、ほら……。わたしたち、仲良く写ってるでしょう?」 亜希は、千尋の眼前に携帯をかざした。 携帯の画面には、寄り添って笑う亜希と千尋の顔があった。亜希の髪が、今と同じオレンジ色に近い茶髪なので、きっと、最後に会った時のものだろう。そうだ。後ろの景色に見覚えがある。グランドホテルの高級ケーキ店に行き、そのまま最上階の展望台に上った時に、撮ったものだ。 栗色の髪の毛を、モデルのようにふわりと下ろした女の子が、千尋だ。純粋に笑っているというより、少しばかりいたずらっぽい目つきをし、色っぽく見せていた。 隣の亜希も、そんな表情を作ってはいるが、千尋の色気には到底及ばない。年の差もあるだろうが、そもそも、素質が違う。もちろん、今、亜希と似たり寄ったりの化粧で、背伸び感の滲み出る、朱美なんかとも。 亜希と朱美への憎しみもあって、千尋の脳裏には、そんな思いが渦巻いていた。 今、亜希の携帯を、加納が手に取って眺めていた。 加納は、どこか不愉快そうな表情だった。もしかすると、まだ十代の小娘である千尋を、丁重に扱わなくてはならなかった過去が、思い出されたのかもしれない。 加納は、携帯の画面と、無惨に裸で横たわる千尋とを交互に見て、にやりと笑った。ざまあみろ。その冷たい目は、そう語っていた。 「えーっ、でも、でも、わかんない……。なんで女体は、こんなふうになっちゃったわけ? 亜希ちゃんとも、すごい仲良さそうにしてるし……」 朱美が、当然の疑問を口にした。 「べつに、わたしは千尋ちゃんと、喧嘩とかしたわけじゃないよ……。これには事情があって、話すと長くなっちゃうからさっ」 亜希は、扇ぐように手をひらひらと振った。 「ふーん……」 まだ不思議そうな顔をしている朱美だが、それ以上は訊かなかった。 さすがの朱美も、亜希と千尋の間に起こった出来事の顛末を知れば、衝撃を受けるに違いない。そして、恐怖すら感じるだろう。亜希が、自分の快楽のためなら、平気で人を裏切るような人間だということに。 朱美に、もう少し頭の回転があれば、そこまで気づいたはずだ。だが、野暮ったい黒髪の少女は、ぼんやりと小首を傾げ、変わり果てた千尋の姿を眺めているだけだった。 「千尋ちゃんの家は、たいへんなことがあったんだよねえ……? だから、こうやって働くのは、しょうがないことなんだよねえ……?」 亜希は、うっとりとした顔で、囁きかけるように言った。 「千尋、おまえはもう、前みたいに遊んでいられる立場じゃあ、ないんだからね。ここでの仕事のことだけを、考えるんだよ。仕事ぶりが認められたら、家のトイレで排泄することぐらいは、許されるようになるかもしれないから、しっかりと頑張りなさい」 加納は、そう言いながら、千尋の太ももをつかんで揺すった。それに合わせ、前菜の汁気に濡れた陰毛が、藻のように揺れていた。 もどりたい……。もどりたい、輝いていたあの頃に。 亜希の携帯に写っていた自分の顔が、目に焼きついている。本当の自分の姿は、あれなのだという思い。 あの頃に戻りたいという、痛切な願望。 それは、感情を覆っていた一種の膜に、亀裂が入っていく前触れだった。身を裂かれるような恥辱の中で、期せずして自己を防衛していた、薄い膜に。 その時、まだ千尋の胸もとに載っていたアスパラを、朱美が箸でつまんだ。箸で乳房の柔肌をつつかれる嫌な感触。 動けず、ただ呼吸を繰り返すだけの自分の肉体を、強烈に意識する。女体盛りの『器』になっているという現実感が、今になって、ひしひしと涌き上がってくるようだった。 千尋は、震え上がる思いがした。自分の体の上や、落ちてテーブルにちらばっている、高級料理の数々。以前なら、このような華やかな晩餐の席に、客人として座っているのが普通だった。それを、当たり前のように、千尋は食べていたのだ。しかし、今はなぜか、それらの料理と共に、自分の裸の体までもがテーブルに載ってしまっている。 ありえない、ありえない、こんなの、ありえない……。 千尋は、頭の混乱を覚えたが、次に感じたのは、激しい怒りだった。 何より悔しいのは、これほどまでのことをしておきながら、亜希や朱美には、明るい明日があるということ。何の罰を受けることもない。学校の時間が終われば、同年代の少女たちより一段高いところから、輝かしい青春を謳歌する。 こんな理不尽があってよいのか。許せない、と千尋は思う。 堰を切ったように、悲しみや怒りや屈辱感が、ない交ぜになって噴出し始める。 亜希の携帯に写っていた、寄り添って笑う千尋と亜希。そもそも、なんで、あの二人の関係が、こんなことになってしまったのか……。 そうだった。わたしは堕ちたのだ。だから亜希は、わたしとの対等な関係を終わりにした。 今、亜希の向かいには、千尋が失った様々なものを、当然のように持ち続ける朱美が座っいる。そして、そんなお嬢様たちを悦ばせるために、千尋は、慰み者として、ここに乗せられている。今の千尋の価値からすると、彼女たちの前では、こうしているのが、お似合いだというわけだ。 言い様のない感情が、胸の内から溢れ出ていく。涙が一筋、頬を伝った。 くそ……、亜希のやつ……。あんなに仲良しだったのに。泣き虫だった亜希はよく泣いて、その度に、わたしは亜希の顔を胸に抱いてやったのに。なんで、わたしのことを、こんな見世物に……。 「あっれえ……、女体が、泣いてるぅ! どうしたの? 今になってさあ?」 朱美が、鼻に掛かった声で言い、千尋の肩を揺すった。 「おーい、千尋ちゃーん。もしかして、自分だけ、ご飯が食べられないのが悲しいの? それだったら、言ってくれれば、なんでも食べさせてあげるよ? ……ちゃんと、千尋ちゃん特製の調味料を、たっぷりと付けてねっ」 亜希は、はしゃいでいた。もう血も涙もなくしているようだ。 珍しく加納が、はっはっはっ、と豪快に笑う。 「千尋、まさかおまえ、前のような生活に戻りたい、なんて甘いこと考えてるんじゃ、ないだろうね。無理なんだよ! おまえは、ここで働き続ける以外にないの。ほらっ、仕事中だよ。お客さまの前で泣くような失礼な真似、するんじゃないよ!」 千尋は、慟哭していた。野太い泣き声を上げていた。両眼を手で覆い、顔をくしゃくしゃにしている様は、髪の毛が短いせいもあって、まるで猿の赤ん坊のようでもあった。亜希の携帯に写っていた、モデルのような美少女の面影は、もはや、どこにもなかった。 それから二十分ほど経っていた。 新しいテーブルクロスに替えられたテーブルの上に、さっきまでと同じように、千尋は、仰向けで横たわっていた。千尋の体の表面は、消毒液を染み込ませたタオルで、もう一度拭かれていた。涙と鼻水の跡も、綺麗に拭き取られた。 今は、ミルクのムースとフルーツが、双方の乳房を覆うように盛りつけられている。晩餐のデザートだった。 「加納さん、もし女体が耐えられなくって、デザートが食べられなくなったら、本当に女体は、責任を取ってくれるんですかあ?」 朱美が、わくわくした様子で訊いた。 「もちろんです。少々手荒いやり方になると思いますが、この子に、体から処女の血を流させたうえで、きっちりと、朱美さまに謝罪させます」 千尋を見下ろして立っている加納が、どこか誇らしげな口調で答える。今では、朱美も、すっかりサディスティックな行為を愉しむようになっている。だから、加納も、初めは控えようとしていた暴力的な発言を、もはや一つのサービスのように提供していた。 「わかりましたー。じゃあ、女体は、嫌がって暴れたりは、絶対にできないねえ……」 「じゃあ、そろそろ頂きますかっ。ね、朱美ちゃん」 亜希が、陽気に声を掛ける。 「うん、おいしそー」と朱美。 彼女たちは、スプーンもフォークも手にしていなかった。 もうすぐ、想像も付かないほどの、おぞましいことが始まろうとしている。千尋には、その現実を現実として認めることはできなかった。しかし、体は小刻みに震えっぱなしで、かちかちと歯が鳴っていた。 やめてください……、亜希ちゃん……。最後に、亜希の良心にそう訴えたかった。だが、喉の奥から出てくるのは、言葉にならない、微かなうめき声のようなものだけだった。 うっすらと口を開けた亜希の顔が、左の乳房に迫ってきた。その口が、ムースとフルーツの層の上辺を、そっと含めていった。 右の乳房に盛られているほうを、朱美が、同じようにしていく。 亜希は、ピンク色の舌をゆっくりと垂らした。悪夢のようだった。 乳房のなだらかな斜面に、その舌先が、べたりと張り付いた。その瞬間、全身にびっしりと鳥肌が立つのを、千尋は感じた。 亜希の舌が、柔らかい肉の丘を這うようにして、ムースとフルーツの層を削っていく。 千尋の喉の奥から、甲高く間延びした声が漏れた。上体が反り返り、背中がテーブルから浮き上がった。発狂しそうな嫌悪感に、千尋は、ぶるぶると身悶えた。 もう、あとどれだけ正気を保っていられるのかもわからない。 視界の隅に、立っている加納の姿があった。加納は腕を組み、せいせいするとでもいうような表情で、それを鑑賞していた。 白いムースと唾液に塗れ、てらてらとした左右の乳房を、それぞれ、亜希と朱美が舐め続けている。 亜希は、舌を押し付けたところが柔らかくひしゃげていく様と、苦悶する千尋の表情を見比べ、やたらと面白がっていた。 もう片方の乳房を、朱美が、べろで弾くようにして舐め上げる。白くなった柔らかい肉の丘、それ自体が、まるで一個のデザートででもあるかのように、ぷるりと揺れる。 亜希が、いたずらっぽい顔で朱美に目配せし、ふくらみの先端を指し示した。朱美も、それに応じてうなずく。 けばけばしい目をした、お嬢様たちの舌が乳首に触れた時、千尋は、奇声を発して目を見開き、天井を見上げていた。 シャンデリアの輝きは、眩しい。
|
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.