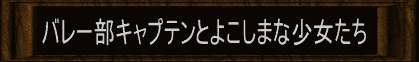
プロローグ〜狡猾な罠
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
放課後の体育館は、熱気でむんむんとしていた。部活動の女子高生たちが躍動し、汗を流している。女子校とはいえ、雄叫びのような勇ましいかけ声が、あちこちから上がる。 体育館のフロア全体は、真ん中で二つに分けられており、奥、つまりステージに近い半分をバスケ部が使用し、手前、出入り口側の半分がバレー部となっている。 今、バレー部のコート上では、二、三年生によるスパイクの練習が行われていた。白いTシャツに黒のスパッツ姿の部員たちが、次々にボールを叩き込んでいる。 トスが上がる。ボールが宙で弧を描く。 身長170センチ近くの立派な体躯の部員が、助走を踏んで大きく跳躍した。抜群のジャンプ力を見せる。伸びやかな肢体が、空中で弓なりに反り返る。その反動で、体重の乗った右腕がダイナミックに振り下ろされ、ボールを捉える。 ボールは、ネットの反対側へと鋭角に突き刺さり、豪快な音が鳴り響いた。 強烈なスパイクを打ち込んだ、この部員は、手応えを感じているかのように小さくガッツポーズをした。ここ五条橋女子高等学校バレー部キャプテン、三年の南涼子だ。 艶のある真っ直ぐな黒髪を、バレーに青春を捧げているかのように、飾り気のないショートカットに切り揃えてある。とても端整な顔立ちで、切れ長の澄んだ眼差しと高い鼻筋が際立っており、きりっと締まった印象を形作っている。小ざっぱりとした髪型が、凛々しい顔にすこぶる似合っており、清涼感のあるボーイッシュな雰囲気が、強く醸し出されていた。 そして、天性の恵まれた体を、日々、過酷な練習で鍛え抜いてきた、そのボディラインには、女性的な肉感と、アスリートとしての筋肉美とが、美しく調和して浮かび上がっていた。部活の運動着姿は、それを強調しているかのようだった。膨張色の白いTシャツの布地には、豊かな胸の盛り上がりによって、二つの山ができている。膝上丈の黒のスパッツは、筋肉質な太ももと大きなおしりで、はち切れんばかりの有様である。 また、屋外でのランニングも行っているため、顔や長い手脚は、ほんのりと小麦色に焼けており、そのため、極めて健康的で、より力強い風貌となっていた。 その威風堂々とした姿は、まさにオーラを放っている。彼女の揺るぎない意志や誇り高さといった内面の部分が、外に溢れ出ているかのように。この、かっこいいキャプテンに対して、バレー部員だけに留まらず、数多くの一、二年生が、憧れての気持ちを抱いているのであった。 「ラストぉ! 一本ずつ!」 南涼子は、声を張り上げた。低くてもよく通る声が、体育館に響き渡る。 オオーッ、と部員たちも大声で応える。 自分の番のトスが上がると、涼子は、再び全力でスパイクを打ち込み、エースアタッカーとしての力量を見せつけた。 焼けるように熱い息を吐き出し、両手を膝につく。Tシャツとスパッツは、汗でぐっしょりになっている。 「二、三年、サーブカットはじめて! 一年、ダッシュ五十本!」 涼子は、次に行う練習を指示した。一年生部員たちは、畏怖の混じった声で返事をする。 この高校のバレー部もご多分に漏れず、夏に三年生が引退するまでの間、ほとんどボールを触ることのできない一年生には、まず徹底的に基礎体力を付けさせる。むろん、涼子も、それを当然のことと考えていた。 体力や筋力がなかったり、声出しのできないような部員は、試合では使い物にならない。それが涼子の持論である。 「りょーちーん……。スパイクのぉ、調子ぃ、絶好調じゃーん」 ひとり紺色のジャージの上下を着込んだ部員が、いたずらっぽく笑いながら声を掛けてきた。バレー部のマネージャー、竹内明日香である。 相変わらず間延びした喋り方だなと思い、涼子は苦笑した。 「ええー、そうかなあ……」 涼子は、軽くとぼけて見せた。 「そうだよぉ……! だって、だって、スパイクの音、すっごいんだもん……。大会がたのしみぃ。あたしぃ、りょーちんが活躍するとこぉ、早く見たーい」 明日香は、『りょーちん』と涼子のことを呼ぶ。ちなみに、その愛称を使うのは、明日香だけだった。 その賞賛ぶりに、さすがの涼子もくすぐったくなっていた。 竹内明日香は、モデルのような美貌とスタイルを持った少女だった。ゆるいウェーブの掛かった、栗色のミディアムヘア。色白でほっそりとしており、どことなく小悪魔っぽい色気の印象を与える目鼻立ちをしている。その容姿は、まさにフランス人形のようという形容がぴったりである。 約一ヶ月前、明日香は、突然、面識もない涼子のもとに現れ、バレー部のマネージャーに興味があると言ったのだった。バレー経験もないという明日香の話を聞き、涼子は、つい首を傾げた。 まず何よりも、校則では禁止されている髪の染色とパーマだ。校則も守れないような子が、部活の雑用的な仕事など、出来るものなのだろうかと、懐疑的な思いを抱いた。それに、偏見かもしれないが、明日香のちゃらちゃらとした容姿や仕草などを見ていると、部活よりも、男の子と遊んでいるほうが、お似合いだという気がした。 ところが、二週間もしないうちに、そういった考えは完全に改められることとなった。 明日香は、見た目とは裏腹に、驚くほど献身的に尽くしてくれた。一年生部員に交じって球拾いをし、ボール磨きやフロアのモップ掛けも忘れない。さらには、練習後のマッサージまで買って出た。これは後輩に対しても行われ、一日に数人ずつ行われ、大好評だった。 涼子も、初めのうちこそ、そこまでしなくていいよ、と遠慮していたものの、今では、床にうつ伏せになると、明日香の手に、すっかり身を委ねてしまっている状態だった。練習でぱんぱんに張った肩やふくらはぎの筋肉を、優しい手つきで揉みほぐしてもらっていると、その気持ちよさに、つい、うとうとしてしまう。 キャプテンという立場上、涼子は、特に後輩の部員に対しては、厳しい態度で接することが多い。だが、明日香を叱るようなことは、一度もなかった。 涼子は、マネージャーとして、また仲間として明日香を受け入れた。もちろん、明日香は、他の部員たちの信頼も、しっかりと勝ち得ている。だが、後輩たちにとっては、それだけではなかった。 憧れである。 なにしろ、街を歩けば人が振り向くような美貌なのだから、当然かもしれない。 けれども、決してうぬぼれるわけではないが、涼子も、自分が、部員たちに憧れの眼差しで見られていることを、よく知っていた。自然な流れとして、涼子と明日香は、しばしば比較されているのだ。 後輩たちの言葉を借りると、『南先輩は厳しくてかっこいいお姉さんで、竹内先輩は優しくて可愛いお姉さん』なのだという。 涼子と明日香は、フロアの端っこに立ち、部員たちの練習を見守っていた。 「あっ、そうだ、りょーちぃん。あれっ、あれっ、さっき預けたやつ、もってきてくれるぅ? あたしぃ、今からぁ、職員室にぃ、届けてくるからぁ」 明日香が、思い出したように言った。 「ああ、オッケーィ。持ってくるから、ちょっと待ってて」 三年生にとって最後となる夏の大会の前に、合宿が行われる。マネージャーである明日香が、練習前に、その合宿費を部員全員から集金しておいたのだった。だが、明日香がバッグを教室に忘れてしまったということで、涼子が、代わりにそれを預かっていた。 涼子は、踵を返しかけたが、ふと足を止めた。 「一年生! 全然声が出てないよ! もっと声出して!」 そう怒鳴って両手を叩き、キャプテンとして厳しい態度を示す。 ダッシュを繰り返している一年生部員たちは、絞り出すように大声で返事をするものの、何人かは、もはや限界の表情を見せていた。 「りょーちん、こわーい」 その人形のような美貌をくしゃりと歪め、明日香が茶化してきた。 「しょーがないでしょう。甘やかすことは、できないのっ」 きっぱりと言って、涼子はフロアを出た。 一年生が新入部員として入部してきて、もうすぐ三ヶ月が経つ。すでに、その三分の一が、きつい練習に耐えられずに辞めていた。中には、バレー経験もなく、体力も根性も皆無に等しいのに、憧れの涼子と同じ部活に入りたいという理由だけで、入部する部員もいた。 楽しさも大事だが、涼子がキャプテンとして一番求めるのは、強いチームだ。それは、五条橋女子高等学校バレー部の伝統でもあった。 体育館内にある部室のドアを開ける。室内には、部員たちのバッグが乱雑に置かれていた。自分のバッグを見つけ、チャックを開ける。 あれ……。おかしい……。たしかに、ここに入れておいたはずなのに……。あるはずの封筒が無いのだ。 パニックに陥りそうになりながら、別のチャックも開け、終いには、バッグの中身をぶちまけても、現金の入った封筒は見つからなかった。 涼子は、呆然として床に散らばった私物を眺めていた。 無くした……。いや、盗まれたんだ、きっと……。でもいったい、誰が。あまり考えたくないことだが、可能性として高いのは、バレー部員のうちの誰かだ。しかし、涼子が代わりに合宿費を預かったことを知っているのは、明日香しかいない。その明日香だって、練習が始まってから、ずっとフロア内にいたのだ。 なぜ、あるはずの封筒が、忽然と消えてしまったのか。 明日香から合宿費を預かる時の会話を、ふと思い出す。 すぐにお金を職員室へ持っていったほうがいいと、涼子は勧めた。だが、明日香は、合宿費を納める際には、色々と面倒な手続きがあるから、練習が一段落する頃合いを見て持っていきたい、そして、バッグを教室に忘れてしまったので、少しの間だけ預かってほしい、と頼んできた。それについて、涼子は、断る理由も特になかったので、合宿費を預かり、自分のバッグにしまっておいた。 筋違いとわかっていても、明日香に対する腹立ちが、湧いてきてしまう。大金なんだから、すぐに職員室へ持っていくべきだったんだ。やっぱり、あの子は、見た目と同じで、だらしない……。 そこで頭を振った。やめよう。明日香を恨むのは間違っている。あっさりと引き受けた自分が、いけなかったのだ。 わたしは、四十万円以上もの大金を無くしてしまった……。 紛失した額の大きさに、頭が真っ白になるが、と同時に、これでは、合宿が中止になってしまうという不安を抱いた。夏の合宿は、高校最後の大会に向けて、コンディションやスキルを最終調整し、チームの結束を再確認する場である。いわば、涼子たち三年生にしてみれば、三年間の練習の締めくくりのようなものなのだ。 血と汗と涙の部活動生活が、あまりにも虚しい最後を迎えることになってしまうかもしれない。しかも、その原因は、キャプテンである涼子の不注意にあるのだ。 どうしてこんなことに……。なんとかしなくてはならない。なんとか。 すっかり途方に暮れている時、突然、部室のドアが開いた。びくりとして見やると、明日香だった。 「おーい、あんまり帰ってこないからぁ、心配してぇ、見にきたぞぉー。りょーちぃん、どーしたのぉ?」 何も知らない明日香は、明るく身振り手振りを加えて訊いた。 涼子は、答えることができず、ごくりと生唾を飲み込んだ。あれほどの大金を無くしたと言ったら、どのような反応をするだろうか。 「なんでぇ、バッグの中身がぁ、散らばってんのぉ? どーしたの?」 さすがの明日香も、異変に感づいたようだ。 「お金、……盗まれちゃったみたい」 消え入りそうな声で言った。目を合わせることができなかった。 明日香が息を呑む気配を感じる。 「でもっ、でもっ、盗まれたって言ってもさ、りょーちんのバッグに、合宿費が入ってたことを知ってるのは、あたしだけなんだよ?」 明日香の口調も、もはや、普段のような間延びした余裕はなくなった。 涼子は、小さく溜め息をついた。 たしかに言われたとおりだ。盗まれたといっても、状況的に考えれば、あり得ない話なのだ。最悪、自分が疑われても仕方がないかもしれない。集めた合宿費を、涼子が着服しようとしているのではないか、と。 そう思うと、涼子は、胸が締めつけられそうになった。 「信じて……」 かろうじて、その一言だけ口にすることができた。 「うーん」 明日香は、頬に人差し指を当てて唸った。 二人の間に、長い沈黙が降りる。 涼子には、この金縛りのような沈黙を破る言葉が見つからない。ひたすら、相手の出方を待つしかなかった。 その時、唐突に、明日香が早口で言い始めた。 「りょーちん、急いで荷物をバッグに詰めてっ。ここじゃあ、いつ誰が来るかわからないから、場所を変えよっ。お金が、全部無くなったことが、みんなに知れ渡ったら大変だから」 それを聞くと、涼子は、すがるような思いで、マネージャーであり友人でもある明日香の顔を見つめた。普段は、ひょうきんな表情ばかり浮かべる、その人形のような美貌が、今は、冷徹な大人の女性のように、涼子の目には映った。 涼子は、小さく頷くと、急かされるようにして、散らばっている自分のセーラー服や革靴、教科書、汗取りスプレー等をバッグに入れ直した。 ランニングシューズに履き替え、体育館を出た。何も言わずに明日香について行き、体育倉庫の前までやって来た。古びた扉を開けると、中には、体育の時間に使われる様々な運動用具が揃えられている。 放課後は、生徒が立ち寄らないという理由で、明日香は、この場を選んだのだろうが、そこまでする必要があるかと、涼子は思った。 入って中ほどまで進み、涼子が戸惑っていると、明日香は、さらに奥へと歩いていった。 「こっちこっち、りょーちん」 明日香が、地下へと下りる階段のそばに立ち、手招きしている。 さすがに、話を聞かれないようにするため、体育倉庫の地下にまで下りるというのは、大袈裟過ぎると感じた。だが、異議を唱えられる立場ではないことを、涼子自身、よくわかっていたので、素直に指示に従うことにした。 「りょーちん、先に行っててっ……。あたしも、すぐに行くから」 「えっ……。明日香は、どうするの?」 涼子は、まごついて訊いた。 「ちょっと、ひとつだけ、やることあるの。すぐに戻ってくるから、大丈夫だよ。……りょーちん、ちゃんと、下で待っててね」 明日香は、念を押すように言うと、涼子の肩にぴたりと触れた。 互いに見つめ合う時間が、数秒あった。 目の前の美少女は、にっこり笑い、くるりと身を翻して、早足で体育倉庫を出て行った。 その後ろ姿を見送ると、涼子は、合点のいかない思いと不安を抱えながら、一歩、また一歩と階段を下りていった。 明日香の態度が引っ掛かる。もしかすると、自分のことを疑っているのではないか、と勘ぐってしまう。たしかに、合宿費の無くなった状況を考えれば、疑われても仕方ないだろうが……。 涼子は、地下に降り立った。ここに来たのは初めてだ。 暗がりの中、壁に、電気のスイッチが見つかったので、それをパチンと押す。天井に並んだ蛍光灯が一斉に点灯し、意外なほど明るくなった。地下スペースは、想像していたよりずっと広かった。テニスコート一面分くらいの広さはあるだろうか。 明るく、広い。 だが、なぜか、ひどく陰気な場所に感じられてならない。 古びた灰色のコンクリートの壁には、あちこち、ひびが入っている。奥には、ほこりだらけの跳び箱やマットなどが、捨てられたように放置されている。空気はじめじめしており、汗まみれのTシャツやスパッツにまとわりついてくるようで、気持ちが悪い。 涼子は、力なく吐息を吐き、壁にもたれ掛かった。 いったい、誰が、わたしのバッグからお金を盗んでいったのだろう。返してよ……。合宿、このままじゃ中止になっちゃうかも……。そうなったら、みんなになんて言えばいいの……。 もはや、涼子には解決策が思い浮かばず、頼れるのは明日香だけだった。 |
次章へ
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.