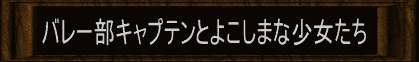
第二章〜憧憬と悪意
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
教壇に立っている三十半ばの女教師が、次の生徒を当てた。 「はい、ではそこから、南さん、お願いします」 「はい」 南涼子は、返事をして起立した。 「ザッティー、オヴ、グッドスムェル、イズサーヴドゥイン、フロントオブヒアー……」 吉永香織は、その、どことなく甘い響きを帯びたアルトヴォイスの朗読を、小気味よさに浸りながら聴いていた。常日頃から、香織は、涼子の発する声音には独特の魅力を感じていたのだが、今日は、根本的に別の意味があった。淀みなく、高校生にしては上出来すぎるほどに英単語を発音する涼子の声に、胸の奥をくすぐられるようで、気持ちがいいのだ。 胸の奥。そこには、嗜虐心があった。 今、涼子は、前のほうの席で、教科書を広げて立っている。香織の席は、一番後ろだった。流暢に英文を読み上げる涼子の背中を、香織は眺めている。 ついつい、にやけが零れてしまう。昨日、あんな目に遭わされたというのに、普段と変わらぬ堂々とした態度でいられるとは、まったくご立派なことだ。 さすがは、南涼子。それだけの女だからこそ、周到に計画を練り、リスクを冒してまで、無様な姿を拝んだ価値があるというもの。さらに、今日もまた、あの忘れられない快感を味わえることを思うと、身震いが起きそうだった。 今の香織にとって、涼子の朗読は、得も言われぬメロディであった。 約三ヶ月前の四月。 三年に進級し、二年時にクラスメイトだった明日香と別々になり、涼子と同じクラスになった。 前の年、つまり二年の時は、運が良かった。あの明日香と、早々に仲良くなれたのだから。 テレビに出演するモデルとも遜色のない容姿の明日香は、むろんクラスでは、ずば抜けた可愛さだった。真顔の時は人形のようで、少々、人間味が感じられないほどの、ひんやりとした美貌の顔に、しょっちゅう、おどけた笑顔を浮かべる。 校則違反に当たる、髪の染色とパーマについても、日本人離れした顔立ちにはぴったりで、生徒はもちろん、教師も注意を与えられなかった。きっと、美しく整ったものに文句を付ける行為は、自分の存在を卑小にするだけだという無意識が、教師たちのなかにもあったのだろう。だから、明日香の校則違反に関しては、目を逸らしていたのだ。 そんな明日香と友達になれたのなら、もう、クラスの上流グループに入れたも同然だった。 その年の一年間は、初めの二週間で、どのような仲間とグループ関係を作れるかで決まる。 自分には、特別な魅力もなく、これといった特技もない。そんなことは百も承知だったが、見栄っ張りな香織は、是が非でも上流グループに加わろうと奔走した。ブス、デブ、奇行者、根暗とは、決して口を利かない。 努力の甲斐あって、香織は、明日香と同じ輪に入り込むことができ、その一年を『明るく』過ごせたのだった。時には、下流グループを見下したり、わざと聞こえる声で嫌味を囁いたりしながら。 しかし、信頼や固い絆などといったものは、望むべくもなかった。 放課後には、連れ立って駅前や歓楽街に繰り出し、しばしば他校の男子生徒と交流を持ったが、彼らの目当てが明日香だけであることは、グループ内の誰もが承知していた。当然、嫉妬や劣等感の空気が常にグループを覆っていた。香織も、明日香が男たちの前で、容姿に対する自信に裏打ちされた、挑発的な振る舞いをする姿には、幾度もへどが出そうになっていた。 明日香が、取っかえ引っかえ男と遊んでいる間に、香織には、ひとりの彼氏もできなかったのだ。 それでも明日香と一緒につるんでいたのは、高校生活なんてそんなものだという、一種の諦めにも似た価値観を、香織が持っていたからだ。可愛くて派手な友人と共に行動し、なんとなく華やかな気分を味わっていれば、それでいいのではないか。 そんな中、香織たちと同様に、無為なのか充実しているのかも判然としないふうに、街でぶらついている一学年下のグループと、たびたび接触するようになった。 そこに、石野さゆりがいた。さゆりは、髪型もごく普通のストレートで、一見したところでは地味にすら映るのだが、よくよく見ると、かなり綺麗な顔立ちをしていた。そして、人と目が合う時には、いつも口元に、うっすらと微笑のようなものを滲ませているのだった。そんな表情と、どこか挙動不審にも思えるひょうきんな仕草とが相まって、さゆりには、ミステリアスな印象があった。 グループ内の中心人物でもなく、目立った発言もしないその後輩に、香織は、なぜか妙に惹かれるところがあって、自分から何気なく話しかけた。 そうして香織とさゆりは、ほどなくして、内心を吐露し合う間柄になっていった。要するに、主に、互いのグループの仲間に対する陰口を言い合っていたのだ。 さゆりは、香織の前で、忌憚なく友人たちをこき下ろした。あたし、早く帰りたいのに、無理矢理あの子たちに付き合わされてるんですよね、いい迷惑ですよ……。あんな顔して、かっこいい男からのナンパ待ってるんだから、笑っちゃいますね……。 そういった台詞は、さゆりの風貌に、似合っていないようで、とても似合っているように香織は感じた。 香織のほうも、さゆりに負けず劣らず仲間をけなした。その悪口のなかには、少なからず明日香のことも話題にのぼっていた。香織にとって、さゆりは理解者だった。 そんなこんなで一年が過ぎ、三年に上がった。 今年は受験もあるし、登校日数もだいぶ減るので、友達のレベルについては二年時ほど重要視していなかったが、一応、それなりに華やかな子とグループを組みたかった。いや、逆に、最後の年だからこそ、という思いもあったかもしれない。 香織は、例によってクラスメイトを物色し、値踏みしていった。 クラスのなかで最高の価値を誇ると思われる子を、すぐに発見した。 しかし、香織は、その子が、高校に入学した当初からずっと部活に励んできたという事実に、意外の感に打たれた。しかもキャプテンを努めていたのだ。 前々から香織は、部活動や生徒委員会といった類のものを、冷ややかな目で見てきた。高校生にもなって、汗水垂らして走り回ったり、なんの特にもならない会合に出たりする生徒の神経が、理解できなかった。 あの子は、あたしとは違う人種なんだ……。香織は、そう思った。たしかに、彼女は綺麗でプロポーションにも優れているが、よく見ると、いかにも運動部系という『いも臭い』雰囲気を漂わせているし、顔つきにも、なにか痛々しいほどの真面目さが表れているように感じた。 香織は、ちょっと興醒めさせられた気分になり、その子へのアプローチを考え直すことにした。けれども、ふとした時などに、横目で、その子のことを観察していた。 彼女の周りには、いつも人が集まっていた。いったい、彼女は、どのような生徒と交友関係を結んでいるのか。それを、香織は見極めようとした。 漫然と眺めていると、彼女は誰とでも仲良くしているように見えたが、実は、その仲間たちには、ある共通点があることに気づいた。学校内外を問わず、何かに打ち込んでいるという点だった。やはり運動系の部活の生徒が多かったが、そのほか、吹奏楽部や、ダンス教室に通っている生徒たちなどである。 時には、休み時間中は常に読書をしているような根暗で眼鏡の図書委員と、彼女が、読んだ本について熱く語っている場面も見受けられた。 詰まるところ、彼女が親しくするのは、目的も目標もなく学校生活を送っている香織とは、対極的な人種の生徒たちなのである。そのことを悟った香織は、彼女と友達になろうとする考えを捨てた。 しかし、ほんの些細な出来事が、香織の心を揺さぶった。 その日の朝、香織は、普段より二本早い電車に乗った。特に理由はなかった。学校に行く準備が整っていたので、たまには、早く登校するのもいいかと思っただけだ。 駅を降りると、香織を待っていたかのように、ちょうどバスが到着するところだった。そうして香織は、チャイムの三十分も前に、校舎に足を踏み入れていた。 どっか寄ってから来ればよかった、教室に誰もいなかったらどうしよう……。後悔の気持ちを抱えながら、ぼんやりと、教室のある三階へと階段を上っていた。 三階に行き着き、廊下の角を曲がったところで、香織の足は止まった。 水飲み機のペダルを踏み、噴き出した水に、今まさに、口を近づけようとしている生徒がいた。 その生徒は香織の存在に気づき、首を香織のほうへとわずかに巡らせた。 切れ長で黒目がちの双眸が、香織を捕捉していた。意識が吸い込まれそうだった。 目の前にいるのは、香織が、クラスのなかでベストだと密かに評していた、あの彼女なのだ。部活の朝練の後らしく、汗なのか水なのかわからないが、髪の毛が少し濡れているのが気になった。 彼女は、表情をまったく変えずに、唇だけを動かして声を発した。 「おはよー」 無機質な低い声だった。 香織も、咄嗟に挨拶を返した。 「あっ、おはよぅ……」 蚊の鳴くような声量しか出ていなかった。 ほんの二、三秒のやりとりだった。 その後、彼女は水を飲み始め、一方、香織は、逃げるようにそこを去り、教室に向かった。教室には、まだ誰もいなかった。無人の教室に入り、机にバッグを置くと、香織はパニックに陥りかけた。 当然、これから、彼女もここにやって来る。つまり、二人っきりになるのだ。気まずい……。というより、気恥ずかしい……。 香織は、瞬時の判断で、またも逃げるように教室を出て、トイレに駆け込んだ。 個室のドアに凭れかかると、心臓が異常なほど速く鼓動を打っているのがわかった。なにやってんだ、あたしは……。深い溜め息を吐き、しだいに頭の中が冷静になっていくと、香織は、今しがた、自分と彼女の間に起こったことを反芻した。 彼女は、水を飲みかけたところで香織の姿を目にし、声を掛けてきた。 『おはよー』だ。いや、『おはっ・よー』と若干節を付けて言っていたかもしれない。 つまり、香織がクラスメイトであることは、知っていたのだ。けれども、その声音は無機質で、なんの感情も含まれていなかった。ただ単に、同じクラスの生徒と顔を合わせたから挨拶しただけ、という感じだった。 それに対して香織は、どうだろう。 かろうじて言葉が出せたというような、消え入りそうな声で挨拶を返すと、逃げに逃げて、今はこんなところに立っている。 猛烈な自己嫌悪に、全身を襲われた。自分が、あの子と比べて、ちっぽけ過ぎる存在に思えてならない。 そして、もう一つ、認めなくてはならないことがあった。 悲しいほど情けないが、香織の取った一連の行動は、憧れの男子に偶然出くわしてしまった時の女子生徒のそれに、ぴったりだった。 香織は、言い様のない複雑な思いを抱えながら、心の中で呟いた。 南さん……。 その時から、南涼子に対する興味が、加速度的に膨れ上がっていった。 しかし、香織は断じて、それが、いわゆるレズビアン的なものであるとは認めなかった。女に恋をする女など、異常者以外の何物でもない。自分が、そんな人種の仲間入りをするなどと考えると、おぞましさに鳥肌が立ちそうだった。 それでも、暇さえあれば香織は、彼女について空想を巡らせていたのである。彼女のことをもっと知りたいという思いは、もう抑えの利かないほどに強くなっていた。 早朝の事件があった日から三日目の放課後、香織は、バレー部を率いている時の彼女の勇姿を、目で確かめに行くことに決めた。ただ、香織が単独で練習風景を眺めているのを、もしも彼女が見たら、少々変に思われる可能性がある。そこで、同じクラスの、仲良くなったばかりの友人をひとり、さり気ない口調で誘って一緒に行くことにした。 体育館の二階のギャラリーで、香織は、嵐のような衝撃を受けた。 部活用の運動着姿で仁王立ちしている彼女の肉体に、目が吸い付けられた。 シャツが汗に濡れて、かすかに肌が透けて見える上半身が、妙にエロティックに感じられた。さらに、スパッツに包まれた部分には、まるで爆弾でも入っているのではないかと思いたくなるような、大きな二つの丸みができている。 だが、香織の隣にいた友人は、なんとも間の抜けた言葉を口にした。 「あー、あれ、南さんでしょう。やっぱりすごいねえ、キャプテンって感じするよお」 友人の感受性の鈍さに、香織は呆れかえる思いだった。あの肢体を見ても、こいつは、そんな詰まらない感じ方しかできないのだろうか。 その時、香織たちから少し離れた場所にいる、一年生らしきグループ連れのなかから、切なげな声が発せられた。 「南先輩、かっこいー」 香織は、それに耳ざとく反応した。 連日、南涼子を目当てとした後輩たちが、バレー部の練習を見に来ており、本気でファンレターを渡した子もいるという。三年になってから、そういった噂は何度か聞いていたのだが、どうやら誇張ではなかったらしい。 ここみたいな女子高では、南涼子のような存在が、共学における憧れの異性的な役割を、自然と担っているのだ。テレビドラマや漫画のような話だな、と香織は思った。 あたしとあの子では、住む世界が違っているんだ……。その現実を認識させられた香織は、友人に声を掛け、帰ることにした。 香織は、もやもやとした、なんとなくやるせない気持ちを抱えながら、駅のホームのベンチに長いこと座っていた。 なんで、あたしは、こんな凡庸な容姿をしているんだろう。背も低いほうだし、自分の体には、まったく自信がない。顔立ちも平凡だが、大嫌いな吊り目のせいで、容姿がワンランク落ちている。 それに比べ、あの子の、なんとも凛々しく躍動的なこと。 また、ルックスだけではなく、彼女の自由に突っ走るような生き方も、香織と大きく異なっている点だ。 学校では常に周囲の目を気にし、あくせくと仲間の輪に加わっている香織に対し、彼女は、有りのままの自分を振る舞うことで、多くの友人たちに溶け込んでいる。それに彼女の場合は、たとえ、ひとりで行動していようと、その姿が惨めに映ったりはしないのだ。 揺らぐことのないアイデンティティーを基盤に、頭脳明晰、運動神経抜群ときている。 彼女の高校後の進路は、どのような方向へ向かうのだろう。はっきりしているのは、彼女が歩む道ならば、そこは輝きに包まれているということ。 髪を、もう少し伸ばすかもしれない。ぐっと女らしくなって、さぞかし周りの人間を魅了するに違いない。 彼女のポテンシャルを存分に発揮すれば、どんな高い目標にだって到達してしまうだろう。 さながら美獣のようだ、と香織は思う。大地を思いのままに駆ける美獣は、輝きに満ちた未来へと、今、飛翔しようとしているところなのだ。 人生など、がんじがらめにされているも同然であり、他人なんて、どろどろとした汚いものであるといった本当の現実を、彼女は知らないのだ……。 それはほとんど天啓に思えた。あたしが、その現実を教えてやればいいのでは。 実は、周囲の人間なんて信用ならない者ばかりで、あんまり調子に乗っていると、とんでもなく痛い目に遭って、人生の歯車が狂ってしまうことも有り得るのだと、あたしが思い知らせてやればいいのではないか。 ふいに、武者震いのようなものが起こった。やってやる……。香織は、深く決意した。 こういうのを、可愛さ余って憎さ百倍、というのだろうか。ちょっと違うか。 問題は、気高い美獣のごとき大物に、なんの力も持たない自分が、どう攻めていくかという点である。 香織の出した結論は、徒党と、周到な計画だった。まずは、良き理解者である後輩のさゆりを、この策略に参加させようと決めた。だが、そこから先が、見えてこない。二人だけでは心許ないし、肝要の計画については、大筋さえ見当が付かなかった。 しかし、思わぬことに、当の南涼子が、その答えをもたらしてくれたのだった。 高校最後の大会に向けて、ゲームのスコアを付けたりユニフォームの管理をしたりといった仕事を担ってくれるマネージャーを探している……。涼子は、友人たちに、そんなことを話していたらしい。その情報が、噂として香織の耳にも届いたのだった。 香織は、これを利用しない手はない、と確信した。涼子と密接な関わり合いを持つことができれば、付け入る材料の一つや二つ、おのずと発見できるだろう。 これはラッキーだと思いながらも、香織は、心の内で悪態をついたのだった。馬鹿が……。周りの子たちが、みんな自分に好意的だと思い込んでるんだね。そのおめでたい思考のせいで、近いうち、あんたは痛い目を見ることになるんだから。 けれども、香織はマネージャーという柄ではない。 そこで、二年時に同じクラスだった明日香の姿が、頭に浮かんだ。あの茶髪とパーマがネックだが、明日香の美貌ならば、バレー部の後輩たちにも慕われるのではないか。女は、女の世界でも容姿がものをいう。 それと明日香は、自分が愛嬌を振りまけば、誰にでも好かれるし、どんな落ち度も許してもらえると思っている節がある。だから、右も左もわからない部活動であろうと、物怖じすることはないはずだ。 その後、さっそく香織は、放課後に、さゆりと明日香を引き連れ、体育館へと赴いた。ターゲットを確認させてから、二人に計画を話したのだ。 南涼子は、声を張り上げ、部員たちに何かを指示しているところだった。 あっさりと、さゆりは与してくれた。涼子に対して、特に興味も不快感も持っていないが、年上の女子生徒を陥れるという計略に、なにか新鮮な刺激を受けた様子だった。 だが、より重要なのは、明日香が首を縦に振るかということである。明日香には、バレー部に加入して、マネージャーとしての役割をこなしてもらわなければいけない。非常にしんどく、途方もない任務なのだ。 香織の話を聞いた明日香は、ぽかんと口を半開きにした顔で、標的と教えられた女の姿を、ぼんやりと目で追っていた。曖昧な態度の明日香に、香織は、ほとんど懇願の口調で頼み込んだ。 すると、ふいに明日香は含み笑いを見せ、静かにこう言ったのだった。 「しかたないなあ、やってあげるよ……」 なぜか香織は、その返事を聞いた時、嬉しいという思いより、奇妙な印象のほうが強かった。香織に根負けした、という感じではなかったのだ。 実は今でも香織は、あの時の明日香が、腹に何を抱いたのか、よくわかっていない。もしかすると、単に、後輩たちのアイドル的な存在の涼子が、自分より上に思えて不愉快になったとか、そんな理由から引き受けたのかもしれない。 だが、それは香織の憶測に過ぎなくて、明日香の真意は、未だにはっきりしていないのだ。それでも、あの時の明日香からは、彼女らしくない、冷たく深い決意が伝わってきた。 改めて、香織たち三人は、エネルギッシュなバレー部のキャプテンを、標的として見据えた。互いに信頼し合っているとは言い難いが、南涼子を計略に掛けるという点においては一枚岩となったチームが、生まれた瞬間だった。 やはり最初、明日香は、くそ真面目な涼子に苦戦した。 マネージャーとして貢献したいと善意を示す明日香を、涼子は、あまり歓迎してくれなかったらしい。理由は、当然、明日香の身だしなみにあった。 しかし、その状況を見事に打開したのは、さすがは明日香としか言い様がない。 明日香は、風貌にそぐわない献身ぶりを披露して、部員たちに意外性を与えながら、そこに織り交ぜるような形で、自分の魅力をアピールしていった。まさに魔性の虜になるがごとく、まず後輩部員たちが明日香に惹かれていき、二週間も経つ頃には、明日香は、すっかりとバレー部に溶け込んでいた。 校則を重んじる、規範意識の高い涼子ですら、明日香を受け入れたのだ。それについては、明日香のほうが一枚上手だったと言うべきか、あるいは、涼子の、順風満帆すぎた人生に起因する、人をすぐ信用してしまう甘さが出たと捉えるべきだろうか。 明日香は、標的を欺くことに成功した後も、油断せず、部活に尽くし続けた。 しんどい任務に当たっている明日香を、ほったらかしにして帰るわけにもいかないので、香織とさゆりは、毎日、バレー部の練習が終わるまで、駅の近辺で時間を潰した。 たいてい、ファーストフード店で明日香と落ち合った。その日の出来事、特に、南涼子に関する情報を、明日香から聞かせてもらうのだ。 「あたしの青春があぁー、ああー、南さんに削られてくよおぅ。もうあんな汗臭いところなんか、行きたくないよおぅ」 決まって明日香は、開口一番、大袈裟に嘆いてみせるのだった。明日香は、本人の前では『りょーちん』なんて気色の悪い呼び方をしているが、普段は『南さん』で、語気が荒くなると『南』と呼び捨てにすることもしばしばだ。 だが、香織は、明日香がバレー部のマネージャーという立場に、まんざらでもなさそうなのを、彼女の話口調から感じ取っていた。たぶん、涼子との双璧となって、後輩のバレー部員から憧れの目で見られるのは、悪くない経験だったのだろう。 それにしても、と香織は思った。忍耐や根性といった言葉とは無縁の明日香が、感心させられるほど、苦労に耐えてくれている。明日香が音を上げたら、この計画も立ち消えになってしまうので、彼女の頑張りは、香織にとって嬉しい限りなのだが、不思議に思わずにはいられない。 明日香を衝き動かしていたものは、いったい、なんだったのか。 「あっあー、くっそおぅ、あたしが下手に出てやりゃあ、南のやつ、なんでもかんでも押しつけやがってえー。今に見てろよなあ……」 目先の欲望にしか興味のない高校生活をしてきた明日香が、虎視眈々と、涼子の弱みになりそうな材料を探している。違和感を感じるが、頼もしくもある雰囲気だった。 ついに、待ちわびていた朗報が訪れた。合宿費の件だ。 明日香が持ち帰ってきた話を基に、香織が、一晩かけて策略を組み立てた。あらゆるアクシデントを想定し、何段構えにも策を強化していくと、失敗の要因は、ほぼ消し去ることができた。 次に三人で相談しなければならないのは、罠に掛けた南涼子を、どうするのかという点である。肝心なことなのに、それが決まったのは、実行日のわずか五日前だった。 いつものファーストフード店。 土下座、往復ビンタ、断髪などの案が上がっていた。いずれも、さゆりと明日香の口から出たものだった。 その席で、香織は、もどかしい不満が募るばかりだった。さゆりも明日香も、なに惚けてんのよ……。てっきり、席に着いた直後には、異口同音に、『あれ』が提案されて、即決、となると予想していたのに。 やむなく、香織はおもむろに切り出した。 「ねえ……、脱がしてやろうよ」 さゆりが、虚を衝かれたような表情をして、訊いてくる。 「えっ。服を……? 全部、ですか?」 愚問だった。 「当たり前じゃない。そんくらいしないと、明日香だって、腹の虫が治まらないでしょう?」 香織は、ちょっと苛立ったように言った。 話を振られた明日香は、小首を傾げ、やんわりと口元を緩めた。 「うーん、うん、うん……」 頷いてはいるものの、どこか煮え切らない態度だった。 結局、最後には、香織の案でいこうと決まったが、さゆりと明日香は、勢い込んで乗ってきたというより、ただ賛成の意を示したといった感じだった。 香織は、拍子抜けさせられた気分で、帰路についた。がっかりだ……。今日はもっと盛り上がると期待していたのに。さゆりと明日香の念頭には、香織の案のような考えは、まったくなかったのか。いや、そんなわけがない。きっと、誰かが言い出すのを待っていただけなのだ。まったく、こんな時に誤魔化し合ったってしょうがないじゃない……。 その時、香織は悟ったのだった。あたしがリーダーシップを取って、あの二人を引っ張ってやらないと、お話にならない。 香織にとって、この十七年の人生のなかで最大と言っても過言でないイベントは、恐いくらいの大成功を遂げた。 体育倉庫の地下に降り立った瞬間。 大金を無くし、困り果てている顔色をした涼子は、もはや美獣ではなくなっていた。牙が、すっかり抜けていたのだ。あれは牝鹿だった。牝鹿ならば、香織でも、容易に手なずけることができる。 「さて、南さん」と自信に満ちた声で涼子の名を呼んで、口火を切った。 香織は、涼子を相手にイニシアティブを握る自分の話術に、半ば酔いしれていた。自分の隠れた才能を、発見した思いでもあった。 涼子をじわじわと追い込んでいくのは、この上なく愉しいことだった。いや、快感という言葉以外、当てはまらないのかもしれない。なにしろ、涼子のそばに立ち、運動後の汗の臭いを仄かに嗅いだだけで、香織は、体の芯がじーんと熱くなるのを感じていたのだ。 汗を吸った涼子のシャツやスパッツを手に持った時には、随喜の声を上げそうになった。終盤になり、全裸になった涼子の、こわばった表情を拝む頃には、すでに、香織の下着はべとべとになっていた。 香織たちは、レストランで成功を祝した。 四十二万八千円。涼子のバッグから盗んだ合宿費が、香織の手元にあった。そこから慰安費として、明日香に十五万円渡した。これまでの明日香の苦労を鑑みれば、少ない金額だったかもしれない。だが、それ以上は、資金を割くわけにはいかなかった。残りの金は、南涼子を縛り付けておく計画のために必要なものなのだった。 けれども、明日香は、うっぷんなら充分に晴らせたというように上機嫌で、ほとんど金には興味がない様子だった。 取りあえず、めでたい今日だけはと資金を削って、香織たちは、ちょっとだけ贅沢に飲み食いを愉しんだ。 その夜、香織は、体育倉庫の地下での出来事を思い起こしながら、オナニーに耽っていた。 涼子のブラジャーを強引に剥ぎ取った時、濃密なボリュームの乳房が驚くほど柔らかく潰れた、あの感触が手に残っている。全裸で香織たちに背中を向けた、涼子の巨大な生尻は、瞼の裏に焼き付いていた。 香織は、手で性器を包み込むようにし、全体を満遍なく圧迫していった。直接クリ○リスや膣を刺激するより没頭できるので、香織は、このやり方を好んでいた。 あたしは、南涼子の裸に興奮しているわけではない。つまり、今、レズビアンとして性的な快感を得ているわけではないのだ。断じて……。 最大にして唯一のポイントは、涼子が嫌がっているという点である。すなわち、あたしはサディスティックな性癖を持っている。 この性癖は、自分の捻くれた性格に起因していると思うのだ。昔っから、弱い者いじめや仲間外しといった類のことが大好きだったし、可愛い子が幸せそうな顔をしているのを見ると、しばしば不幸に陥れてやりたい欲求を抱いたものだ。 この性格の悪さには、自分でも苦笑してしまうのだが、それが高じて、性的な面にまで影響を及ぼすようになっていた。 体育倉庫の地下で、その事実に気づくことになった。なにせ、体が反応していたのだから。 ベッドの上で、香織は多少の戸惑いを感じながらも、悦びに打ち震えていた。 この快楽をもっと早く知りたかった、とも思う。例えば、二年の時に、あの明日香を標的にしたってよかったのだ。明日香に関しては、香織自身が身近にいたのだし、グループ内の誰もが多かれ少なかれ嫉妬を抱いていたのだから、涼子を嵌めるより、遙かにたやすかったはずだ。 素っ裸にされたら、明日香は、泣きじゃくっただろうか。土下座しながら、あの綺麗な顔を涙と鼻水で醜く崩して、必死に許しを乞うたかもしれない。想像するだけで、ぞくぞくしてくる。 けれども、もういいのだ。南涼子という、文句なしの大物を手中に収めたのだから。それに、『やりがい』や『達成感』は、明日香が相手だと、涼子ほど絶大にはならなかっただろう。 今後、南涼子は、香織の欲望を満足させるための対象として、生きていくのだ。 同じ女に苦痛を与えて性的に興奮してしまうのだから、自分が、倒錯した性癖を持っていることは、認めざるを得ないし、受け入れるべきだ。しかし、自分はサドではあってもレズではない。この論理に、矛盾は一切介在していない。 快感の法則は、至ってシンプルだ。対象が、嫌がれば嫌がるほど、香織の興奮は増す。だから、南涼子が耐えがたい苦痛を感じるようなことを案出し、それを実行すればいいのだ。 するとおのずとああいった仕打ちになる……。 香織は、自慰行為に没入するため、タオルケットを口元に巻き付けた。 ……あの朝、廊下でばったり会って挨拶し合ったこと、あたしはずっと胸に残ってたよ、南さん。でも、南さんにとっては、ちっぽけなことで、もうとっくに忘れちゃってるよね。そんなだから、あんたは、こっぴどい目に遭ったんだよ。もう絶対に逃がさないし、許さない。明日っから、あんたの気が触れそうになるくらい、いじめ続けてあげるからね、南さん……。 低酸素状態で、めくるめく快感に呑まれていき、香織は、本当に失神しかけていた。 チャイムが鳴り響いていた。 今日の最後の時限である、英語の授業が終わったのだった。 いけない、いけない。今年は受験なのだから、授業中は集中しなければ。 ふと、香織は、前のほうの席に目を向けた。 涼子は、普段と変わらぬ様子で、隣の席の子と談笑していた。だが、その横顔には、悲しみや不安の暗い影が滲んでいるようにも見えなくもない。 昨日の一件で、涼子が、精神的に多大なショックを受けているのは、間違いない。そして、今日も部活後には受難が待ち受けていることを思い、心底不安になっているはずなのだ。それでも、友達には、そんな素振りは見せまいと努めている。 香織は、涼子のいたいけな姿に、またしても胸の奥をくすぐられていた。 帰りのホームルーム終了後、香織は、二階の待ち合わせ場所に向かった。 すでに、さゆりは待っていた。香織を目にすると、意味深とも無意味とも取れる微笑を浮かべる。 まったく不思議な後輩だ、と思いながら、香織は挨拶代わりに、さゆりの肩をとんと押した。 するとさゆりは、今度は、口元の両端をはっきりと吊り上げた。意味ありげな笑いだった。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.