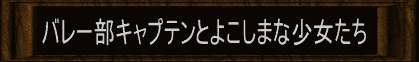
第七章〜放課後の教室
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
「リョーコー、じゃあねーっ」 「じゃーねえー」 二人のクラスメイトの爽やかな声に、南涼子は、はっと顔を上げた。 屈託のない表情をした二人の女子生徒が、ぼんやりと席に突っ立っている涼子に、小さく手を振っていた。 涼子は、とっさに、明るく快活な表情を作った。 「じゃっねえー。また明日」 そう返しながら、彼女たちと同じように右手を伸ばし、ひらひらとさせた。 二人が教室を出ていくと、涼子は席に腰を落とし、やるせない溜め息をついた。 今のわたしは、意識してほっぺたを持ち上げないと、笑顔を表すことすらできない。あの子たちに声を掛けられる寸前まで、わたしはいったい、どんな顔つきをしていただろう。以前と変わらぬ自分を振る舞うのが、とても疲れる。 だが、クラスメイトたちに、暗く落ち込んでいるような素振りを見せるのは、なんとしてでも避けたかった。 体育倉庫の地下で起こった出来事は、片時も忘れることができないが、そのせいで、高校生活の友人関係にまで影響が出てくるという事態を考えると、なんとも言い様のない悲しみを覚えるのだ。 それともう一つ、理由がある。同じクラスの、香織の目だ。授業中、移動教室、昼食の間、休み時間。四六時中、涼子を視界に捉え、涼子の一挙一動をねちっこく観察しているのであろう、香織の存在。涼子の変調に感づいた友人が、親切にも心配の言葉を掛けてくれる場面などを、もし、香織が目に留めたとしたら、さぞかし内心で抱腹絶倒することだろう。これ以上、香織をいい気にさせる必要はない。 教室の窓から、日中に比べてやや弱まった陽の光が射し込んでいる。帰りのホームルームが終わって、十数分ほど過ぎていた。女子しかいない教室では、終業と同時に、ほとんどの生徒が、もはや何の用もなしとばかりに、ぞろぞろと退出していく。今は、数えるほどしか残っていなかった。 香織の姿もない。きっと、どこかで時間を潰しているのだ。 体育倉庫の地下には、二度、連れて行かれた。二度目のあの日から、今日で三日目。間の二日間は、どこかに連れ込まれるようなことはなかった。 しかし、昨夕、呼び出しのメッセージが、思いもよらぬ形で飛んできた。あの時のことは、苦い感情と共に、克明に憶えている。 放課後、部活の始まる前のことだった。涼子は、運動着に着替えるために、体育館内にある部室に入ろうとしていた。ふいに、一年生らしき生徒が走り寄ってきた。バレー部員ではなかった。 小柄で、頬のふっくらした幼い顔立ち。神経質なストレートヘア信仰を感じさせる、全体的にぺったりとした髪の毛を、どことなく遠慮がちに肩まで下ろしていた。まだ中学生にしか見えない風貌である。 見覚えがあった。涼子が記憶をたぐろうとした時には、その子が話し始めていた。 「南先輩、すいません……」 頬を赤らめながら、開口一番、畏敬の念や恥ずかしさのこもった謝りの言葉を述べ、慌ただしく頭を下げる。 「あ、あの、あたし、竹内先輩から南先輩に伝えるように頼まれたんです。あの、あたし、よくわからなかったんですけど……。明日、帰りのホームルームが終わって一時間後、E組の教室に『四人で』集合するから、絶対に待っててってことらしいです……。そう言われました」 その子は、一刻も早く用を済ませて逃げ出したいかのように、早口でそう告げた。 思い出しかけていた目の前の生徒に関する記憶は、すっかり消し飛ばされていた。 あの三人から送られてきた、紛れもない命令。心臓が早鐘のように打ち始め、体の体温が急激に下がっていく感覚があった。 涼子は押し黙り、立ち尽くしていた。幼げな後輩の、ぱっちりとした可憐な眼差しが、機嫌を窺うように、じっと涼子を見つめている。涼子は、ふうと息を吐き出し、なんとか口元を曲げて笑顔を作った。 「うん、わかった……。教えてくれて、ありがとね」 涼子がねぎらうと、その生徒は、再度ぺこりと頭を下げ、早足に去っていった。 後輩への態度とは裏腹に、胸の内では、真っ赤な憎しみの炎が燃えていた。あの三人を焼き尽くす怒り。特に、明日香に対しては、炎が躍り上がっていた。 この前日のことだ。 ふてぶてしくも、何食わぬ顔をして部活の練習に参加しようとした明日香を、涼子は呼び止めたのだ。そのちゃらちゃらとした美貌の顔面を、渾身の力で殴ってやりたい衝動を抑え、「出ていってよ。もう二度とここには来ないで」と、涼子は、言葉少なに言い放った。 すでにジャージに着替え終えていた明日香は、きょとんとした顔になり、何も言わず黙っていたが、やがて、ふて腐れた態度で立ち去っていった。 おそらく、明日香の悪意に油を注ぐことになっただろうが、明日香が、この場所に足を踏み入れることだけは、金輪際ないと思われた。 また、涼子は、携帯電話を持っていなかった。私立であるこの高校は、公立に比べて校則が厳しく、学校への携帯の持ち込みは禁止されていた。それを遵守しているというのもある。むろん、今時、そんな規則を律儀に守っているのは、天然記念物さながらの少数派であることも知っていた。教師たちでさえ、ほぼ公然の秘密として扱っている。 けれども、涼子にとっては、校則だけが理由の全てではなかった。来たる夏の大会に向けての部活動に忙殺される毎日で、友達と遊ぶような時間も満足に作れない。それに、メールのやり取りなどしなくても、本物の友情は、実際に顔を合わせれば確かめられる。要するに、携帯を必需品だとは感じなかったのだ。 しかし、そういった現状が重なったせいで、香織たちが、卑怯千万にも、無関係な後輩を使った伝言という手段を取ったのかもしれなかった。 涼子は、あまりの不快感に歯噛みした。どこまでも陰険で卑劣な、あの三人……。 体育倉庫の地下を思い出す。あそこには、涼子の味わった、到底言葉にはできない汚辱が詰まっている。 それでも涼子は、香織たちが望むのであれば、もう一度、あそこに出向いてやろうと思っていた。もう一度だけだ。逃げるのではなく、あいつらと対峙し、片をつけるのだ。二度と言いなりにはならないし、服を脱ぐような馬鹿げたことも絶対にしない。その時には、自分の最大の武器である膂力を行使する公算が高いだろうとも踏んでいた。 体育倉庫の地下で、香織と明日香とさゆりの悪意によって生じた汚辱は、同じ場所で、同じ人間を相手にして、自分ひとりできっちりと清算する。あの場所で起こった惨劇を、友達や教師、あるいは親などに打ち明けて助けを求めるという選択肢は、毛頭ない。それは、まさに涼子のプライドだった。 だが、あの三人が、無関係な後輩を伝言役として送ってきたことが、涼子をひどく動揺させていた。そして、メッセージのE組とは、涼子と香織の教室である。 涼子の脳裏で、禍々しいイメージが動き出していた。体育倉庫の地下に封じ込め、滅却するつもりだった、涼子の汚辱を象徴する黒い染みが、あの建物から漏れ出しているのだ。身の毛もよだつほどおぞましい黒い染みは、生き物のようにその範囲をどんどん広げていき、校舎や体育館までも覆いだし、また、ほかの生徒たちの体にも付着していく。 気づかぬうちに、得体の知れない包囲網が広範囲にわたって敷かれ、その中には、なぜか涼子の姿を見て嘲り笑う生徒たちが、そこかしこに立っている……。そう、香織たちと同類のような。 涼子はそこで、際限なく膨らんでいく被害妄想のイメージを追い払った。涼子は、自覚していた。自分がもっとも怖れているのは、波及であるということを。体育倉庫の地下以外の場所や、第三者への波及。 涼子は、伝言役の後輩の来訪により、不意打ちを喰らい、恐慌をきたしかけた頭の中を、どうにか鎮めようと努める。なんのことはない。戦いの舞台が教室に変わっただけだ。状況的には、何も変化していない。 そうして、これから始まる部活の練習へと、なんとか気持ちを切りかえる。不安や焦燥は、心にも体にも、こびり付いていて離れないが、鍛え抜いた精神力をもってして、キャプテンとしての自分を貫き通すのだ。 部室のドアを開けて、空いているスペースにバッグを置いた。運動着に着替え始めると、ふと、さっきの後輩の顔が脳裏に浮かんだ。 記憶が蘇ってくる。まったくの無関係ではない生徒だった。 あの後輩は、涼子にファンレターを手渡してきたことがあったのだ。それも、わりと最近のことだったと思う。 涼子は、こめかみの片側に指を当て、記憶を探った。 たしか、手紙の文章も、あの子供っぽい風貌によく結びつくような、稚拙で支離滅裂な感じのものだった。薄いピンク色の便箋。その一番下に、丸っこい文字で、クラスと名前が書かれていた。 そうだ。一年C組。名前は、『足立舞』。 よく、ここまで思い起こせたなと、我ながら感じる。涼子の胸の内に、それほど深く刻まれた出来事ではなかった。過去には、両手では数え切れないほど、足立舞と同様の生徒、特に後輩が、涼子のもとへやって来たからだ。 二年の後期、キャプテンに選任され、部活の中心として動き始めた頃から、妙にモテるようになった。当初は、さすがに戸惑いを覚えた。 運動系の部活の『キャプテン』。しばしば威厳めいた印象を人に与える、その言葉が、自分のボーイッシュな外見や、男勝りな気質、伸びやかな体躯などの要素と合わさって、同性の女の子たちを惹きつける何かを、生みだしているのだろうか。 夜、自分の部屋で、机に頬杖をつき、真剣にそんなことを考えた日もあった。同性とはいえ、涼子のことを魅力的だと思ってくれる生徒が数多くいる事実なのだから、もちろん悪い気はしなかった。けれども、不思議に思う気持ちのほうが強かったのだ。 わたしって、みんなが思っているような、かっこいい女なんかじゃないのに……。涼子は、しょっちゅう内心でそう呟いては、苦笑していた。 しかしながら、リーダーとしての厳しい責を背負い、遮二無二、部員たちを引っ張って、それまで以上に部活動に没頭するようになると、ファンレターを渡されても、もはや、心を揺れ動かされることはなくなった。涼子目当てに、体育館の二階のギャラリーに集まる生徒たちの存在に至っては、眼中にも入らない。 頭の中が、自身に課した厳しいハードル、部活全体の統率への熱意などで一杯になり、感慨を覚えているゆとりすらも消えていったのだ。 もらった手紙には、一応、目を通してきたのだが、時たま、いささか困らされるケースがあった。返事を期待しているような文面である。 むろん、その子たちの複雑極まりない思いに応えることなど不可能だったし、頭を悩ませている余裕もなかった。そういった場合、どのように対応しようとも、彼女たちの繊細に入り組んだ心を傷つけてしまうのは目に見えていたので、涼子は、徹底して知らぬ振りをすることに決めていた。それが、自分にとっても相手にとっても最善だと思われた。 たとえ、手紙を寄越した生徒が、後日、期待と不安の面持ちで涼子を見つめているのに気づいても、黙殺した。 そういえば、足立舞も、その困らされるケースだったと思い出す。きっと、彼女は、その後も度々、体育館のギャラリーをうろうろとしていたに違いない。そのせいで、なんとも運の悪いことに、伝言役として利用する生徒を物色中だった香織たちに、目を付けられてしまったのだろう。 かわいそうに……。そして、なんだか申し訳なかった。 たぶん、あの子は、年上の生徒の身勝手な依頼に、さぞ狼狽したであろう。赤裸々な気持ちを綴った手紙の相手である、涼子のところに、訳のわからない言伝を言いに来るのは、どれほど恥ずかしい思いだったか。 さっき、足立舞が見せた、赤らんだ頬やおどおどした態度が、脳裏に浮かぶ。 「くそっ……」 涼子は、つい、そう呟いていた。自分が舐められているせいで、高校に上がって間もない生徒に、迷惑がかかってしまったという不甲斐なさ。やり切れない屈辱感。燃えたぎる怒り。 下唇を噛みしめる。暴力的な衝動を帯びた力が、四肢に広がっていく。 でも、今は、どうすることもできない。この感情は、明日、あの三人にぶつけてやればいい。 そう結論を下し、涼子は、体育館フロアへ向かおうと、ようやくドアノブを握った。その時、ふいに、違和感に似た引っ掛かりを覚えた。気づくべき何かが、意識上からこぼれ落ちてしまっている、というような感じだった。 よくよく考えたら、なぜ、それほど印象的でもないのに、足立舞に関する事柄を次々と思い出せたのか。彼女の顔の見覚えを糸口に、手紙の文面や名前にまで記憶がつながったのだ。 彼女に手紙をもらったのが、比較的、最近のことだったからか。 あっ、と涼子は思わず声を出していた。いや……。正確には、涼子が、最後に手紙をもらったのが、彼女だったのだ。 その事実に思い至ると、やおら直感が、不穏なものを捉えた。間を置いて、次に思考が、急速に悪い方向へと流れだす。 足立舞と接触したのは、まず間違いなく、この一ヶ月以内の出来事だった。 ドアノブを握っている手の力が抜けていき、滑り落ちる。すでに、涼子の胸中には、重苦しい黒雲が漂い始めていた。 放課後の教室へと、意識が舞い戻ってきた時、涼子は、バッグの中の荷物を意味もなくまさぐる動作を繰り返していた。いつの間にか、教室に残っているのは、数人だけとなっていた。 Tシャツの生地に指が触れると、それをぐっとつかんだ。ふざけた呼び出しのために、キャプテンの自分が部活の練習に不在という、やり切れない思い。隣のクラスの副キャプテンの生徒に、『やらなければいけない用事』で遅れてしまうという旨を伝えてあった。なるべく短時間で決着をつけて、その後は、体育館に向かいたい。 伝言で指定された時間まで、残り三十分強。この数日間続いた、おぞましい悪夢を、完全に断ち切るのだ。 決着。三対一の対峙。それらを強く意識したとたん、コントロールしていた不安が、どっと心身を覆った。 腹部に、鈍痛と不快感が現れる。涼子は、小さな舌打ちを漏らして席を立ち、教室を出た。 トイレの個室に入ると、苦々しい思いで便座に座る。今日、腹痛でトイレに駆け込んだのは、これで四度目になる。神経性の下痢に悩まされるのは、いつ以来だろうか。 おしりの下で鳴っている品のない音に、なんとも惨めな気持ちにさせられる。溜め息をつき、一度レバーを倒して水を流した。 脳裏に、香織の顔がちらついて仕方がない。すでに涼子は、あの三人による奸計の首謀者が、香織であると見抜いていた。 それにしても薄気味の悪い話だと感じる。なんの変哲もない、ごく普通の女子生徒にしか見えなかった香織に、なぜ、あんな正気の沙汰とは思えない悪意が宿ったのか。現に香織は、教室では以前となんら変わらず、友人たちとお喋りに興じ、携帯の液晶画面を見せ合い、女子高生に通有の親切心を示したりもしている。 わたしは知らず知らずのうちに、香織の胸に底無しの悪意を抱かせるような言動を取っていたのだろうか。同じクラスになってから、たったの数ヶ月。接する機会もなかったし、言葉を交わした記憶もない。恨まれる原因など、見当も付かない。 だが、涼子に対する嫌がらせとして、香織の選んだ手段や、あの愉快そうな態度などを勘案すると、怨恨という動機は、どうもしっくりこない。 だとすれば、あれは、考えうる限りもっとも悪質な類の、『いじめ』だったのか。性的ないじめ。自分がこの身に受けたとは、とても信じられないし、認めたくもないけれども、いじめであったならば、その言葉を措いて的確なものはない。 ターゲットは、誰でも構わなかったのか。この高校の門を通る、あまたの女子生徒の中で、偶然、わたしが、不幸な標的にされたのか。 でも、わたしは、いじめの餌食になるような弱者ではない。そのことには確信が持てる。性格にしろ活力にしろ友達関係にしろ、強く柔軟で、ほかの子たちより、ずっと恵まれていたと自負している。実際、中学校、小学校と時代を振り返ってみても、大きな悩みとなるような『いじめ』に遭った憶えは、一度たりともない。 それでは、香織の悪意の源泉は、なんなのか。悪意は悪意であり、鬼畜は鬼畜であるという事実だけで充分であって、そこに意味を求めること自体、馬鹿馬鹿しい気もするが。 ただ、涼子の意識の隅には、香織の動機を考える上での、もう一つの可能性と成りうる想念が明滅しているのだった。だが、それだけはないと否定する。ありえない。あってはならない。死ぬほどおぞましく、もっとも救いのない説だった。考えるだけでも総毛立つほど怖ろしいため、意識の隅に追いやった。 ようやく腹の不快感も治まってきたので、出ることにした。手洗い台の前に立って、蛇口をひねる。流れ落ちる水の中で両手を擦り合わせていると、ふと、思い付くことがあった。 水で濡らしたトイレットペーパー。それで性器と肛門を拭って、少しでも綺麗な状態にしておこうかという考えだった。にわかに、これから実行したい思いに駆られる。 何気なしに横目で鏡を見やると、怯えに歪んだ自分の顔が映っていた。唖然とする。こんなの、わたしの顔じゃない……。 涼子は、鏡の正面に顔を向け、自分自身を睨みつけた。今、一瞬でも愚行に走りかけた自分が、腹立たしくてならなかった。のっけから脱がされるものと諦めた、とんでもなく卑小で惨めな行為だというのに。 馬鹿……。情けない。なぜ、敗北や服従を考えているんだ。 自分の気持ちを立て直そうとするが、たった今、弱気によって脆くなった心の部分から、凍てつくような冷気が忍び込む。それは、裸足で立つコンクリートの冷たさにつながった。 ひとり全裸になり、三人の好奇の目に恥部を晒した、あの瞬間の感覚が、みるみると心身に蘇ってきた。目眩がし、視界の色が失せたようになり、心と体に襲ってくる猛烈な屈辱感。立っていることすら忘れそうな、おぼつかない肉体。 突然、胃から逆流してくるものを感じ、涼子は、手洗い台に両手をついた。呻き声を漏らしながら、胃液の混じった唾液を何度も吐いた。 最後の唾を吐き捨てると、深く深呼吸しながら、自分に言い聞かせる。だいじょうぶ、もう絶対に、二度と絶対に、あんな辛酸を嘗めることはない。わたしは、あいつらを打ち負かすのだから。 教室のドアを引くと、窓際のほうの席に、ひとりだけ残っていた。彼女は、机の上にバッグと参考書らしきものを載せ、気だるげに頬杖をついていた。ドアの開く音で、こっちにちらりと目を向けたが、さして関心のない様子で、視線を机上に戻した。 滝沢秋菜だった。定期試験や全国模試などの成績において、うちのクラス内に限れば、比類なく優秀だと囁かれている生徒である。とはいえ、能ある鷹は爪を隠すというのか、そんなふうには、あまり見えない。授業に対するスタンスにしても、積極的に発言する涼子とは正反対で、黙々と問題に取り組み、当てられたらそつなく答えるといったタイプである。 そして、才色兼備の言葉がぴたりと当て嵌まる。端正さに対しても、細部まで抜かりなく気を配っているような風貌だった。 滝沢秋菜が、教科の疑問点などを解消するために、放課後、しばしば担当の教師のところを訪れているのは、以前から涼子も知っていた。たぶん、そのような事情があって、今、教室に残っているのだろう。 涼子は、声を掛けてみることにした。念のため、口臭止めのタブレットを口に放る。自分の体とは思えないほど体調は悪く、まもなくこの場で火蓋が切られる戦いを前にして、安穏な気分ではいられない。それでも二人して黙っているのも気まずいし、また、この機にちゃんと話してみたい相手でもあった。 というのは、涼子にしてみれば珍しく、滝沢秋菜は、なんとなく相性の合わない思いのする生徒なのだった。気に障ることを言われたり、不快な態度を取られたり、という類ではない。 滝沢秋菜は、わりと賑やかな子たちと行動を共にすることが多いため、涼子もその輪に加わる機会が多いのだが、涼子が入ったとたん、口数が減るか、あるいは、ひとり離れていく場面が、度々印象に残っている。それに、話しかけても、態度が妙によそよそしい。 理由については知る由もないが、もしかすると、涼子のことを苦手に思っているか、最悪、嫌いな対象として見られている可能性もある。 疑念は、打ち消すか、確信に変えるかのどちらかだ。それが、涼子の、友人たちとの付き合い方だった。 秋菜が、参考書をバッグにしまい、帰り支度を始めていたので、涼子は窓際に歩いていった。 「ねえ、もうカーテン閉めちゃっていい?」 重い気持ちを押し殺して、とびっきりの笑顔を秋菜に向ける。 秋菜が涼子のほうに顔を巡らすと、胸元まで垂らしている洒落た髪型が一瞬崩れ、バネのように再び元に戻る。 「あっ……。ありがとう」と、秋菜のしっとりとした声が返された。 「もう、どこの大学受けるか、だいたい決めてるんでしょ?」 涼子は、カーテンを引きながら訊くと、秋菜のそばの机に腰掛けた。 「うん? あんまり……、まだ、よくわかんない」 相手とのテンションには、滑稽なくらいの差があった。 秋菜は、視線を落とし、曖昧な笑いを口元に滲ませている。 あらためて見ていると、彼女の特質は、生活態度からは窺えなくとも、その表情や仕草には、隠しようがない感じに表れている気がした。 顔立ち自体も、高校生にしては、たいぶ大人びているが、彼女の醸す雰囲気には、たしかに知性の深淵を感じさせるものがあったのだ。特に、その眼差しには、知力による自信を映し出しているかのような、涼しげな余裕とでもいうべき光が宿っていた。 ふと、涼子は、なぜか自分のほうこそ、滝沢秋菜に対する苦手意識が芽生えるような思いにとらわれた。だが、それを心に根づかせまいとするように、少々無理に話を続ける。 「あのさあ……。わたし、ずっとスポーツ推薦考えてたんだけど、最近になって、ほかに勉強したいことも見つかって……。それで、今、進路のこと、すごい迷ってるんだよね。滝沢さんは、推薦とか考えてないの?」 「まだ決めてないから……。でも、色々と悩むよね」 秋菜は、微苦笑すると、つと壁の時計を見やった。 「あっ、そろそろ帰らなくちゃ……。鍵……。日直から鍵、預かったんだけど、南さん、まだ残ってるなら、お願いしていいかな」 秋菜は、やはりどこか大人っぽい仕草で前髪を掻き上げると、席を立った。指に挟んだ教室の鍵を、控え目に示している。 涼子が二つ返事で受け取ると、秋菜は、バッグを肩にし、うっすらと微笑んだ。 「じゃあ、また明日。南さん、部活頑張って」 「ああ、あ、うん……。滝沢さんも、頑張って」 涼子も明るい声で言って、にこりと笑みを返す。 教室のドアへ歩いていく秋菜の、割合にプロポーションの整った後ろ姿を眺めながら、彼女が勉強だけではなく、体育の授業で行われるスポーツなどでも、なかなかの実力を見せていた光景を思い出す。 なんでもできる子……、か。涼子は、半ば無意識にそう呟いていた。むろん、自分だって彼女に引けを取らないという自負はあるが。 結局、滝沢秋菜への疑念は、疑念のままだった。だが、その疑念は、高校生活の最後まで解消されない予感がした。それならそれでいい、と思った。相性の合わないクラスメイトの一人や二人、いて当たり前なのだ。 そして、現実的には、そんな悠長な思考を巡らしている状況ではない。滝沢秋菜に話しかけたのは、気を紛らすための、一種の逃避だったのかもしれないと思う。たったひとり残された教室。もうすぐ、香織たちがやって来るはずだ。 緊張と不安、そして怒りが、涼子の精神と肉体を急速に支配しだした。 むだ毛の処理は禁止だからね、だって。ふざけんなよ……。もちろん、あんな馬鹿げた命令に従うわけがない。 思えば、あの三人には、三者三様の忌まわしさがあった。 吉永香織。計略の首謀者だと思われる、なにより憎き女。涼子に対する嫌がらせのさなか、三人の中でも、ひときわ悪意が強く、また、にやにやと下卑た顔つきで、涼子の恥辱を愉快そうに観察するのだった。 竹内明日香。涼子以下、バレー部員たちを欺いて、神聖なる部活動に入り込んだこと、絶対に許さない。いきなり抱きついてきたりと、変態的で気色悪く、何をしてくるかわからない不気味さもあった。 石野さゆり。性悪な年下ということで、ある意味、もっとも屈辱感を感じさせられる存在かもしれない。 あいつらに、人間としての真っ当な心はない。わたしは、これから、三人の悪魔と向かい合うのだ。 指定された時間まで、十分を切っている。両脚の底のほうから、寒さが急激に這い上ってきたのを感じた。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.