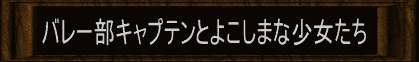
第十五章〜クラスメイト
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
もう二度と、滝沢秋菜に話しかけることはできない。いや、それどころか、あまりに後ろめたくて、今後、彼女の顔は、まともに見られないかもしれない。南涼子は、そんなふうに思っていた。 帰りのホームルームが終わるまでに、ハプニングは起こっていない。つまり、滝沢秋菜が、何らかの異変に気づいた様子はなかった。まるで恋の対象のように、彼女の一挙一動を目で追っていた涼子には、確信が持てる。封筒から一枚の写真を、同じクラスの生徒が抜き取っているなどとは、夢にも思っていないはずだ。 ごめんね、滝沢さん……。もう百回以上、心の中で謝り続けているような気がする。だんだん、それにも疲れてきた。 写真の受け渡し場所である、さっきのトイレへと、涼子は向かっていた。肩に提げたバッグの中には、あの写真が入っている。最後の葛藤が生じていた。盗んだ写真を本人に返すのは無理だが、あの三人に手渡すのは止めるという選択肢がある。黙って家に持ち帰り、処分してしまえばいい。そして、腹をくくる。これから先、何が起ころうとも、自分ひとりが犠牲になることで、すべてが終わる……、と。 しかし、そんな悲劇のヒロインめいた思考は、ふわふわと霧消していった。もう、身も心も疲れきっていて、感覚が麻痺していた。なにやってんだろう、わたし……。ふふっ。こんな女に、部活で、一、二年生の子たちを叱ったりする資格は、ないよなあ。やめちゃったほうがいいのかも……、キャプテン。 涼子は、半ば夢うつつの状態で、薄暗い廊下を歩き、トイレのドアを押した。しかし、その後、想像だにしない事態に直面し、涼子の意識は、叩き起こされることになるのだが……。 「へえー、ちゃんと盗ってきたんだ?」 写真を受け取った吉永香織は、ぎらりと目を光らせた。その口もとから、くっくっくっと小さな笑いが漏れる。 「まさか、あの、真面目で正義感の強い南さんが、本当に、写真を盗んでくるとはねえ……」 香織は、高らかに笑った。そして、意味ありげなことを言いだした。 「これで、南さんが、自分のことしか考えない人間だってことが、証明されたよね。南さんの化けの皮が、剥がれたって感じ……」 要するに、涼子が自己保身に走って、悪事に手を染めたことを、香織は面白がっているのだ。今さらながら、涼子は、自分のしたことが恥ずかしくなり、肩に提げたバッグをいじったり、髪の毛を押さえたりと、無意味な動作を繰り返した。 「もう、南せんぱい、自分が助かるためなら、なんだってするつもりなんでしょうね。こういう時に、ずるい本性が現れるって、なんか、サイテー」 石野さゆりが、汚物を見るような目を涼子に向ける。 「りょーちん、ちょっと幻滅したぁ……。あたしぃ、ホントはぁ、りょーちんなら、自分を犠牲にしてぇ、滝沢さんのこと、守ると思ってたのにぃ」 竹内明日香が、わざと悲しげな眼差しをして言い、彼女たちは、揃ってくすくすと笑った。 頬が紅潮していくのを、涼子は感じた。本当の『恥』というものを知った気がする。これまで、彼女たちには、服を脱がされ、あるまじきことには、性器や肛門までも見られ、文字通り恥を晒し続けてきた。だが、それでも涼子の中には、自分は、恥ずべきことは何もやっていないという、矜持が残っていた。恥ずかしく、見苦しく、醜悪極まりないのは、むしろ、この女たちなのだと。しかし、今回ばかりは違う。醜い自己保身を、人にあざ笑われるのが、こんなにも恥ずかしいものだとは……。ある意味、究極の恥なのではないかとすら、思われてくる。 「ごめんごめん、南さん。ちょっと意地悪な言い方しちゃったね。写真頼んだのは、あたしたちだもんね。気を取り直してよ。まあ……、これで、南さんも、あたしたちと同類……、いや、あたしたちの、仲間入りって感じかな?」 香織は、嬉しくて堪らない様子で喋る。だが、手に持ったその写真をまじまじと眺めると、その表情が一変し、しかめっ面になった。 「あー、なんかムカつく。滝沢さんが愉しそうにしてる顔を見てると、胸がムカムカしてくる。ぶっちゃけ、南さんも、ちょっとはそう思うでしょ? ねえ、そうでしょ?」 どうやら香織は、程度の差こそあれ、涼子も、本心では滝沢秋菜のことを嫌っていると、睨んでいるらしい。苦手イコール嫌い、と短絡的に考えているのだ。 涼子は、黙って首を横に振った。わたしは、おまえみたいに、ひねっくれてないんだよ……。 「この、青い服着てる人が、滝沢先輩ですよね? やっぱり、プライドが高そう……。でも、こういう人のほうが、やりがいがあって面白いかも……」 さゆりは、写真を覗き込み、薄笑いを浮かべた口もとを、手で押さえた。 その言葉を聞いて、涼子は、背筋の寒くなる思いがした。なんという陰湿さだろう。もうすでに、その後輩の頭の中には、上品で頭脳明晰な年上の生徒が、年下の自分に服従するという、そんな薄汚い青写真が描かれているのかもしれない。 「まあいいや……。じゃあさっそく、南さんが盗ってきてくれた、この写真を、使わせてもらおうか。この写真ねえ、滝沢さんに向けた、メッセージを作るのに必要だったの……。メッセージ。そんで、南さんには悪いけど、また協力してもらいたいんだよね」 メッセージ……? その写真にマジックで書き込まれた、滝沢秋菜への誹謗中傷、あるいは脅し文句のようなものが、脳裏に思い浮かぶ。涼子は、心臓の鼓動が、急激に大きくなっていくのを感じた。 香織は、つり上がり気味の目を見開き、話を続けた。 「驚かないでよ? 実は今さあ……、滝沢さん、帰らないで、教室に残ってるはずなんだよね。話があるから、放課後、教室で待っててって、さっき、あたしが言っておいたの。その滝沢さんに、あたしたちの作ったメッセージを、渡してほしいんだよね……」 香織の話を理解しようとすればするほど、涼子の頭は混乱した。 「えっ、ちょっと、待って、ちょっと、なに? その写真を使ったメッセージを、わたしが、これから、滝沢さんに渡しに行くって……、それって、写真を盗ったのが、わたしだってことを、滝沢さんに、教えに行くようなものじゃない? できない、そんなの」 涼子は、へどもどしながらも、慌てて抗議した。冗談じゃない。盗んだものを、どうして本人に届けることなどできようか。 だが、香織は、まあまあ、というふうに右手を挙げた。 「だいじょーぶ。南さんは、偶然どこかで、そのメッセージを見つけて拾ったっていう設定で、いいから。第三者ってことなの。意味、わかる? それと、あたしも、付いていくから。つまり、南さんとあたしの二人が、たまたま拾ったメッセージを、同じクラスの滝沢さんに届ける、っていうシチュエーションになるかな」 香織は、人差し指を振りながら説明する。 「なんで、南さんとあたしの二人かって言うとね、明日香やさゆりを連れて行くと、同じクラスでもないから、さすがに怪しまれるだろうし、後々のことを考えると、あたしたち三人が、知り合いだってことを、滝沢さんに知られてないほうが、都合がよくてね。……だから、協力してよ、南さん」 聞いた情報を、頭の中でなんとか整理する。その筋書きの全体像が、少しずつ見え始めてきた。要するに、滝沢秋菜を騙せということか。そのメッセージとやらは、香織たちの手によるものと知りながら、拾ったなどと嘘をつくのだから。 そんなことはできない。そもそも、今は、滝沢秋菜と顔を合わせるのすら、気まずい心境だというのに……。 「待って……。そのメッセージって、べつに、滝沢さんに、直接渡さなくても、いいんじゃ……? あとで、机の中に、入れておくとか……」 性根のねじ曲がった発言だということは、涼子も承知している。本来であれば、クラスメイトへの陰湿な嫌がらせ自体を、止めさせるべきところなのに。しかし、今の涼子に、そんな気持ちのゆとりは、残っていないのだった。 「ダメダメ。あたしは、メッセージを見た滝沢さんの反応を、この目で確かめたいの。あたしたち三人を代表して、あたしが確かめてくるの。そういうわけで、これから、渡しに行ってくれるよね? 南さんは、あたしたちの協力者だもんね?」 涼子と香織の水掛け論で、香織が引いたためしはない。自分ひとりでやってよ、と訴えたところで、この香織が首を縦に振るとは、とても思えなかった。 どうしよう……、と涼子は途方に暮れた。このままでは、それを実行させられる羽目になる。元から少し苦手意識のある、滝沢秋菜を前にし、第三者を演じ、何も知らないフリをして、自分の盗んだ写真が使われたメッセージを手渡す……。その精神的なハードルの高さに、涼子は、想像するだけで、くらくらと目まいを起こした。 「そんな……、やっぱり、わたし、できない……。滝沢さんを騙すなんて……」 涼子は、ぽつりぽつりと言った。 すると香織は、鼻で笑って馬鹿にした。 「今さら、なに、いい子ぶってんの? 南さんは、写真を盗んできた時点で、もう、滝沢さんを裏切ってるわけでしょ? つまり、あたしたちの側に付いてるってことなの。今になって、『滝沢さんを騙すのは、いや』なんて言うのは、虫が良すぎるよ」 その『あたしたちの側』という言葉には、強い違和感を覚えたが、香織の発言は、あながち的外れでもないような気がした。たしかに、自分はすでに、香織たちに荷担してしまっている。しかし、今度は、こっそりとものを盗むのとは違い、滝沢秋菜本人に対し、直接、行動を起こすのだ。良心の呵責というより、なにか生理的ともいえる抵抗を感じてならない。 せっぱ詰まった涼子は、とつとつと本音を吐露していった。 「あの……、待って。罪悪感とか、そういうのじゃなくって、わたし……、滝沢さんの前で、うまく喋れない気がするの……。わたし、そんな器用じゃないから。言葉に詰まっちゃうだろうし、そうしたら……、滝沢さんにも、絶対、怪しまれると思う……」 情けなくも、最後のほうは、蚊の鳴くような声量しか出ていなかった。 「だいじょーぶ。南さんなら、絶対にできるから。やってみないうちから、やれないとか、泣き言を言う人って、あたし、嫌いなの。滝沢さんと会う前に、ちゃんとセリフを考えておけば、失敗するわけ、ないって」 香織は、取り付く島もない。 とはいえ、涼子にしてみれば、知らない歌を全校生徒の前で独唱しろと言われているのと同じくらい、それは困難に感じられて仕方がないのだ。 「でも……、わたし、滝沢さんの前で……、頭が混乱して、変なこと言っちゃうかもしれないし……、それに……」 「あんまり怒らせないでよー、南さーん」 すがりつくような涼子の言葉を、香織は、にべもなくさえぎった。 「あたしたちの協力者として、もう、最後までやるしかないって、なんでわからないの? あたしたちの信頼を裏切って、ここで投げ出すつもり? そんなこと、許さないからね、絶対に。もし、そんなことしたら……、教室に、いられなくしてやるから」 香織は、涼子の顔を斜めに見上げながら、にやりと笑った。 へなへなと両脚から力が抜けていきそうだった。涼子の人生に致命的なダメージを与えるであろう、あの伝家の宝刀が、香織の手には握られているのだ。だめだ……。とても逆らえない。 やるしかないのか……。だが、メッセージの内容によっては、それを手渡した涼子が、結果的に、滝沢秋菜を地獄へと引きずり込むことになるかもしれないのだ。たとえば、日時を指定し、どこか特定の場所へと、彼女をいざなうような文面だった場合には……。それだけは忍びなかった。 「あの……、ねえ……、その、メッセージって、写真に、なんて書くの……?」 そう尋ねた時点で、渡しに行くと言っているようなものだった。ただの幼稚な悪口の類だったら、まだいいけど……、と涼子は思わざるをえない。 「うん? 写真に何かを書き込むなんて、あたし、一言も言ってないけど?」 香織は、とぼけるように言った。 意外な答えだった。 「えっ……? それじゃあ、メッセージって……、けっきょく、なんなの……?」 涼子が問うと、香織は、腹の底から込み上げる笑いを、堪えるような表情を見せた。 「メッセージが何かってこと? いい質問だね。……と、その前に、はっきりしておきたいんだけど、南さんは、ちゃんと、滝沢さんにメッセージを渡すってことで、いいんだね?」 今一度、念を押される。 もう、これ以上ためらっていても、香織から、くどくどと脅迫の言葉を聞かされるだけだと、わかっている。涼子は、口もとを結び、わずかに顎を引いた。頷いて見せたつもりだった。 曖昧な意思表示だったが、香織は、それで満足したらしく、再び話し始める。 「うんうん……。それじゃあ、これから、滝沢さんに向けたメッセージを作るから、南さんは、ちょっと、そこで待ってて。すぐに終わるから」 香織は、自分のバッグを手洗い台に載せると、チャックを開け、なにやら、一冊の教科書を取り出した。『保健』の教科書だった。 「これ、実は、滝沢さんのものなの……。ほらっ……。ねっ?」 香織は、裏表紙をこちらに向け、突き出した。驚くことに、その言葉どおり、名前の欄には、『滝沢秋菜』と手書きで書かれている。 涼子は、目をしばたたいた。 「ロッカーから盗んでおいたの。一昨日、こっそりとね」 涼子の疑問を先回りし、香織は言った。 では、滝沢秋菜は、涼子と香織によって、二つのものを盗まれたことになるのか。いや、それと、体操着も。全部で、三つもだ。 「なっ、なんで……?」 自分も同じことをやっているせいか、感覚が麻痺していて、盗みに対する義憤は、不思議なほど感じない自分がいた。 「うん、あのね、簡単に言っちゃうと、この教科書が、メッセージの本体なの。南さんには、これを、どこかで拾ったことにして、滝沢さんに渡してほしいの。滝沢さんの写真は、なんて言うか……、付属品みたいなものかな」 香織の話は、涼子にはさっぱり理解できない。 「まあ、見てればわかるよ。……さゆりっ。ハサミとノリと……、あと、マジック、出して」 「はーいはいっ」 指示された後輩は、香織と同じように、もう一つの手洗い台にバッグを置くと、うきうきとした様子で文房具を出し始める。 涼子は、呆然とそれを眺めていた。いったい、こいつらは、何を始めるつもりなんだろう……。 「南さん、ごめんね。実を言うと、もう一枚、使う写真があるんだよね……。『これ』は、決して変な意味じゃなくって……、ネットとかで、ほかに、いい写真があったらよかったんだけど……、まあ、探すのが、面倒臭くってさ」 そう言って、香織は、バッグから一枚の葉書サイズの写真を取り出した。 涼子は、それを見て震え上がった。想像だにしない展開だった。そこに写っているのは、全裸の涼子なのだ。体育倉庫の地下で、いつだったか、『犯罪者みたいに』と両手を頭の後ろで組まされ、その屈辱極まる姿を、正面から撮られたことがあった。その時のものだ。 問題は、なぜ、このタイミングで、香織がそれを出してきたか、だ。 「ねっ、ねえ……、なんで……、それ、なんで……、どうするの……?」 脈絡なく襲いかかった恐怖に、涼子の声は、今にも泣きだしそうなものになっていた。全裸の涼子の写真と、滝沢秋菜の教科書、それに、ハサミとノリと油性マジック。その組み合わせからは、息苦しいほど、不吉なものを感じてならない。 さゆりと明日香は、そんな涼子の反応を面白がって、くつくつとせせら笑っている。が、香織だけは、嫌みたらしい笑みを浮かべるでもなく、取り澄ました表情で、こちらを眺めていた。 「なんで、ひとりで勝手に怯えてるわけ? 変な意味じゃないって、あたし今、南さんに言ったでしょ?」 香織が手に持ち、ひらひらとさせているその写真に、視線が吸い寄せられてしまう。本当なら、目を背けたいところなのに。写真の中の涼子は、両腕を上げさせられているので、乳首はおろか、逆三角状に茂った陰毛までも見せている。写っているのが自分とは認めたくないほど、ショッキングな光景である。そんな写真が、クラスメイトへのメッセージに使われようとしているのだ。落ち着いていられるわけがない。 「南さんが『思ってるようなこと』には、ならないから安心して。だから、あたしたちが、メッセージを作り終わるまで、口を挟まないで、黙ってて」 いっさい抗議は受け付けないというふうに、香織はぴしゃりと言った。 「さっ、始めよっ、さゆり」 「はーい」 香織とさゆりが、涼子などお構いなしに、ごそごそと作業を開始する。 そんな……。わたしの裸の写真なんて……、いったい、どうするのよ……。涼子は、気が気でなく、おろおろしながら、彼女たちの手の動きを見張っていた。 手の空いている明日香は、うろたえる涼子に向かって、どこか優しげに微笑みかけていた。 そして間もなく、香織が何をやろうとしているのか、はっきりと理解した。たしかに、涼子の『思っているようなこと』とは少し違っていた。とはいえ、それも、到底、黙っていられることではなかった。 うそ……。なに考えてんの、こいつら……。 綺麗とはいえないトイレの床に、涼子は、バッグを取り落とした。吐き出す息が、震えた。 「やっ……、やめてえぇ!」 涼子は、割れんばかりに叫び、大股で香織に近づくと、思わずその肩をつかんだ。力を入れたら砕けそうなほど、華奢な肩だった。 突然のことに、香織は、すっかりすくみ上がり、ヒステリックに喚きだした。 「やだっ! やだ! 離してよっ! やめて! 触らないでっ!」 「やめてほしいのは、こっちのほうよ! ふざけるのも、いい加減にしてよ!」 涼子は半狂乱に怒鳴り、香織の小柄な体を激しく揺すった。 香織の顔は、恐怖に引きつっている。 「りょーちんっ! ボウリョクはやめなよっ!」 怖いもの知らずの明日香が、抱きつくようにして涼子の体を押さえてきた。 平静を失っていた涼子は、明日香の細い腕を振りほどこうとして暴れかかったが、すんでのところで思い止まった。前にそれをやって、身勝手な彼女が、烈火のごとく怒りだしたのを、憶えているからだ。 涼子の勢いが止まった隙に、香織は逃げるようにして離れていった。怯えたその顔が、安全圏に抜け出したとたん、怒りと不快感を露わにする。 性悪な後輩は、自分は無関係です、とでも言うように、そっぽを向いて固まっていたが、結局、涼子が手を出せないと見るや、悪辣ぶりを発揮した。 「なにやってんですかあ!?」 反撃のつもりなのか、さゆりは、邪険に涼子の後ろ髪をつかんだのだった。 がくっと頭部を後ろに引かれた涼子は、脳裏で、真っ赤な閃光が弾けるのを見た。 「やめろよっ!」 不良少女も黙るような野太い怒号を、後輩に浴びせる。 さゆりは、大音声に顔をしかめ、肩をすくめた。そして、視線を落とし、こわっ……、と小さく声を漏らした。その口もとには、相変わらず、嫌な薄笑いを滲ませているのだけれども。 「うっせぇーんだよぉ……。この写真はぁ、変な意味じゃあ、ねえって、言ってんだろーがよぉ」 明日香は、眉間にしわを寄せ、荒っぽく涼子を突き放した。 自分の荒い息遣いを、涼子は聞いていた。ふざけないで……。滝沢秋菜へのメッセージとして作りかけられている『もの』に、目をやる。実力行使に出たいと、今ほど思ったことはない。しかし、悲しいかな、それを許されない涼子は、泣き落としに頭を切り替えるほかなかった。 なりふり構わず、自分のプライドが、ぐにゃぐにゃになっても。 「ごめん……、乱暴しちゃって、ごめんね。許して。でも……、お願い。そんなの、わたし、滝沢さんに、ぜったい渡せない!」 涼子は、両手をこすり合わせたり、胸に手を当てたりと、派手にジェスチャーまで加えてみせた。 けれども、当然、彼女たちの怒りの表情は、そう簡単に消えない。 涼子は、トイレの床に両手をつこうかとまで考えたが、あるかなきかの最後の誇りが、それを押し止めた。 香織が、つかつかと歩いて来る。こめかみに青筋を立てたような顔をして。 「ふざけんなよ、おまえ……」 勢いよく振られた右手の平が、涼子の頬を直撃し、乾いた音が鳴った。予想通りだと思った。張られたところが熱くなるが、痛みを感じている場合ではない。立て続けにもう一発、同じところを叩かれる。 「ごめんっ、ごめんっ……。好きなだけ殴っていいから、『あれ』はやめて……」 手洗い台に載っている、滝沢秋菜へのメッセージ。今の涼子は、そのこと以外、もはや眼中になかった。 どさくさに紛れ、後輩が、怒鳴られた仕返しとばかりに、後ろから涼子のおしりへと、膝蹴りを入れてきた。不意を打たれ、息むような無様なうめき声を、涼子は漏らしていた。 血なまぐさい修羅場のような様相を呈していた。 「どうして、つかみかかってくるわけ? あんた、暴力ふるったからには、それなりの覚悟が、できてんだろうね? もしかして、もう、高校には未練がなくなって、辞める前に、あたしたちをボコボコにしようとか、そんなこと考えたの?」 香織は、腰に手を当て、下から顔を覗き込むようにしてくる。つい今しがた、涼子に怯えて逃げ出したのと比べると、ほとんど二重人格の変わりぶりである。 「ごめんね……、吉永さん。わたし、ちょっと、頭が……、なんていうか、パニックみたいになっちゃって、乱暴するつもりなんて、全然なかったのに……。ごめんなさい」 涼子は、必要以上にもぞもぞと体を動かしながら言い、頭を下げた。 「その謝り方、気持ち悪いんだよ……」 香織は、揃えた三本の指で、涼子の額を突いてきた。衝撃に首が反り返る。 「ごめんなさい、ごめんなさい……」 重大な罪を犯してしまったかのように、涼子は、ひたすら謝り続ける。 香織の表情にあった怒気が、だんだんと侮蔑の薄笑いに変わっていった。 「それじゃあ、学校から追い出すようなことするのだけは、止めてあげる。あたしって、優しいでしょ? その代わり、ちゃんと滝沢さんに、『あれ』を届けに行って。嫌とは、言わせないからね」 結局、振り出しに戻ったということか。最悪の事態だけは免れたとはいえ、それでも、一点、どうしても譲れないものがあった。 「許してくれて、ありがとぅ……。でも……、待って。滝沢さんに渡すことはするから、あの写真だけは使わないで……。お願い。ほかになにか、やり方があるでしょう?」 涼子は、少し涙ぐんだ眼差しで、じっと香織を見つめた。 「ダーメ。『あれ』を見た滝沢さんが、どんな反応をするか、この目で確かめたいの。いつまでもぐちぐち言ってると、本当に怒るよ。……さゆりっ、作ろっ」 もはや香織は、これ以上、何も聞き入れそうになかった。しかし、だからといって、このまま口をつぐむわけにはいかない。 「ねえ待って……。吉永さん、もうちょっと話を聞いて……」 そう言いかけたところで、涼子は、いきなり後頭部をはたかれた。またしても、性悪な後輩が、手を出してきたのだ。 「なに、いつまでも、往生際の悪いこと、言ってるんですかあ?」 涼子は、込み上げる怒りを、今度はぐっと呑み込んだ。 香織とさゆりが、メッセージを作る作業に戻る。 「あっ、そうだ……。滝沢さんにメッセージを渡して、はい、さよなら、っていうんじゃ、つまらないからさ、南さんに、いくつか、言ってもらいたいセリフがあるんだよね。聞いた滝沢さんが、怖がるような……」 香織は、妙なことを言い始めた。 「まず、そうだなあ……、これ……」 香織は、にたにたと笑いながら、十秒ほどの長さのセリフを口にした。 それを聞くと、涼子は、目の前が真っ暗になった。 「いや……、言えない……。そんなこと、わたし、滝沢さんに言えない……。それに、その写真も、本当にやめて。使わないで……」 「ダメ。言ってもらう。もちろん、写真も使う。……忠告しておくけど、これ以上、文句を言うようだったら、暴力ふるったこと、反省してないものと見なすからね」 「ねえ、お願い……。吉永さん、お願いだから、ねえ……」 涼子は、涙声になっていた。 だが、香織はもう、涼子の声には耳を貸さなかった。 頭を抱え、宙を仰ぐ涼子を尻目に、香織とさゆりは、胸躍るような顔をして、ハサミやノリなどを持った手を、動かし続けるのだった。 教室が近づいている。そこでは、滝沢秋菜が待っているという。同じクラスになって数ヶ月。珍しく、涼子が苦手意識を抱くクラスメイトだ。涼子に接した時の彼女の言動、ちょっとした仕草などが、走馬灯のように脳裏によみがえる。 そして、自分の体液で汚れた、彼女の体操着。この数日は、そのことが頭にこびり付き、後ろめたさと申し訳ない思いで、彼女の前に立つことさえできなかった。 その彼女に対し、これから、自分がやろうとしていること……。 自分と彼女との間に、まさか、こんな日がやって来るとは思わなかった。 夢の中の世界にいるかのように、体の感覚が頼りない。脚は、陶器のように冷たくなっている。何もかも捨て去って逃げ出したい。今となっては、彼女と顔を合わせること自体が、怖ろしい……。 涼子は、前を行く三人に付き従うように廊下を歩いていた。香織たちの作ったメッセージ、つまり滝沢秋菜の『保健』の教科書は、今は、涼子のバッグの中に入っていた。 香織が、振り返って嬉しそうに言った。 「ねえねえ……。滝沢さん、そのメッセージを見たら、すごいショック受けると思わない? 放心状態になったり、するかな?」 ショック……、か。それはもう、ショックを受けるだろう。こんなものを見せられては。涼子とは違い、滝沢秋菜は、まだ普通の高校生活を送っているのだ。さぞかし悲しみに暮れるに違いない。 だが、涼子の思いは、一つだった。滝沢さんより、わたしのほうが、つらいような……。 「あー……、それと、滝沢さんに言うセリフ、ちゃんと全部、憶えたんだろうね? 一個でも言い忘れたら、あたし、許さないからね」 香織に釘を刺される。 メッセージを渡すだけではなく、香織の用意した、いくつかのセリフを、涼子の口から、滝沢秋菜に聞かせなくてはならないのだ。メッセージを受け取った彼女に、より一層の恐怖を与えるためだと、香織は言うが……。 涼子は、そのセリフを頭の中で繰り返し暗唱し、思うのだった。滝沢さんがどうのというより、むしろ、それを言うわたしのほうが……。 と、そこで、涼子は、漠然とした違和感を覚えた。理屈ではない。直感に引っかかるものがあるのだ。何かが違っているという感じがある。その感覚は、加速度的に強まっていった。いや、今回が初めてでは、ない気がする。なぜかはわからないが、なんとなく、今日この日に起こった出来事のすべてが、根本的に噛み合っていないような……。あるいはまた、正面にある恐怖だけに気を取られていると、別の方向から迫ってくる怖ろしいものに、まったく対処できなくなりそうな、そんな得体の知れない、不気味な感覚だった。 直感が、訴えていた。ここで判断を間違えたら、致命的だ……、と。 しかし、今の涼子には、物事を冷静に吟味することなど、土台無理な話だった。眼前に差し迫った恐怖に、押し潰されそうになっているのだから。 「じゃあ、終わったら、携帯に電話するから」 「あー、あたしも、南せんぱいと滝沢せんぱいのやりとりを、見に行きたかったなあ。香織先輩、どんなふうだったか、後で教えて下さいね」 さゆりと明日香の二人は、教室には同行しないのだった。滝沢秋菜に怪しまれるからという理由らしい。 香織に付いて、涼子は、最後の角を曲がった。もう、遠くに自分の教室が見えている。そこに足を踏み入れ、一歩間違えれば、何かの仕掛けによって、自分の体がばらばらに切り裂かれてしまう。そんな場所に向かっているような恐怖感だった。今日は、無事に家に帰れるだろうかと、不安になる。家に帰り、風呂の湯船に浸かっている自分の姿が、想像できないくらいだった。 滝沢秋菜が、机に腰掛けて待っている姿が、眼前に思い浮かぶ。その彼女に、これから、自分がやろうとしていること……。 ふいに、胃液が逆流してきて、涼子は思わず口もとを押さえ、背中を丸めた。口の中は、胃酸の酸っぱさで一杯になる。 「ねえ……、吉永さん。わたし、やっぱり駄目だよぉ。……怖いのぉ」 涼子は、低く震える声で、本音を口にした。 だが無情にも、香織は、苛々した様子で、こっちへ来い、と手を振っている。声を上げないのは、教室にいる滝沢秋菜の耳を気にしているからなのか。 それでも涼子が立ち止まっていると、背後に足音が迫ってきて、背中を押された。ぎょっとして見やると、それは明日香だった。 「トトトトトトトトト……、っと」 明日香は、奇妙なかけ声と共に、両手で涼子の体を前に押しやる。直前になって、涼子が怖じ気づくことなど、最初からわかっていたふうである。 そうして前に進まされると、苛立った香織が、二の腕を引っつかんできた。小柄なわりに、びっくりするほどの握力を感じる。その手にぐいっと体を引っ張られ、涼子は、泣き声を上げそうになった。 「早く、来なさいよ……」と、香織は声をひそめて言う。 「りょーちん、頑張ってねぇーん」 明日香が、涼子の背中へ、小声でそう投げかけた。 もう、覚悟を決めなくてはならない。やるしかなかった。やるとなったら、自分に誓わなくてはいけないことがある。何があっても、『滝沢秋菜に謝ること』だけはしない……、と。 自分の教室のドアの前まで来た。それでも、やはり、完全に覚悟を決めることはできなかった。涼子は、最後の可能性に思いを託していた。彼女は、香織との約束をすっぽかして、すでに帰っているかもしれないのだ。そうだ。二人は、仲が良いわけでもないのに、放課後、教室でたったひとり、待っているなんてことが、本当にあるのだろうか……。 ドアを押して開けると、本当に、滝沢秋菜の姿はあった。自分の席に着いて、退屈していた様子で、携帯電話をいじっていた。 涼子が最初に感じたのは、失望だった。そして、彼女と目が合うと、心の準備はできていたとはいえ、どきりとさせられた。怯んじゃだめ。もう、やるしかないの……。 「あっ……。滝沢さんっ。あのっ……、吉永さんから、言われてたんだよね?」 どうしても、声がうわずってしまう。 「うん、そうなんだけど……、南さんも、わたしに、何か話があるの? わたし、吉永さんだけだと思ってたから……」 秋菜のしっとりした声は、いつ聞いても、大人のお姉さんじみた印象を受ける。 そこで、香織が口を開いた。 「驚かせちゃって、ごめんね、滝沢さん。話っていうのは、あたしと南さんが、掃除の時間に、滝沢さんの教科書を見つけたんだけど、そのことについて、ちょっと……。最初は、あたしひとりで話すつもりだったんだけど、やっぱり、南さんも来てくれるって言うから……」 嘘八百を並べ立て、香織は、こちらに目配せした。続きは、自分で話せ、ということらしい。 これから、自分も、虚言の渦に落ちるのだ。涼子は、すうっと息を吸い込んだ。心の内で、秋菜に対して両手を合わせる。そして、考えていたセリフを吐き出した。 「うん、そう……。掃除の時に、視聴覚室で、『保健』の教科書を見つけたのね。裏には、滝沢さんの名前が書いてあった。それで……、ひどいものが、貼りつけてあって……。見せるべきか、迷ったんだけど……」 太ももを生温かいものが流れそうなほどの恐怖で、もはや、嘘を口にする罪悪感すら、麻痺し始める。 「視聴覚室で……? えっ……、それで、ひどいものって、なに……?」 秋菜は、不安そうな面持ちで、下唇に人差し指を当てている。 涼子は、自分の心に鞭打って、脚を踏み出し、秋菜の前の席の椅子を引いた。椅子の向きを変え、秋菜の机を挟んで、彼女と向かい合う形で、そこに腰を下ろす。 こうして、すぐ目の前に秋菜がいるということ自体、非現実的だった。体操着を汚してしまった後ろめたさで、この数日間は、秋菜の横顔すら、まともに見られないほどだったというのに。まさに急接近である。それを意識するだけで、涼子はくらくらとしてくる。 その秋菜に、これを見せ……。心臓の鼓動が、地鳴りのように激しくなっている気がした。バッグのチャックを開け、秋菜の『保健』の教科書を取り出す。 「これ……、滝沢さんのものでしょう……?」 からからに乾いた口を動かして言い、裏表紙を見せた。 秋菜は、自分の字で名前が書いてあるのを確認すると、一層不安げな表情になり、そして、小さく頷いた。 「うん。わたしの……」 秋菜の涼しげな眼差しが、今は、少しばかり暗い色を帯びて、涼子に向けられている。 いよいよ、その瞬間がやって来る。 「視聴覚室の……、教壇に、こうやって開かれて……、置いてあったの……」 涼子は、表紙を捲った。すっかり折り目が付いていて、手を離しても、閉じることはない。 秋菜の眉間に、しわが刻まれた。 ぼっと顔中が熱くなるのを、涼子は感じた。この場だけ、時間の流れが停滞したかのようだった。 秋菜は、そっと手を伸ばし、開かれた教科書の向きを、静かに自分のほうへ変えた。 表紙の裏に、葉書サイズの写真が、ノリで貼りつけられている。写っているのは、涼子の全裸だった。囚人のように、両手を頭の後ろで組まされたポーズ。赤紫色の乳首や、逆三角状に茂った陰毛までもが、目に飛び込む。 だが、被写体は、涼子とは特定できない。頭部が、ハサミで丸く切り取られているからだ。その、ぽっかり空いた部分には、代わりに、秋菜の顔が貼られているのだった。素材は、今日、涼子が盗んだ写真で、秋菜は、少しいたずらっぽく微笑み、Vサインをしていたが、その肩から上の部分が使用された。 顔のすげ替え。いわゆるアイコラみたいなものである。あたかも、秋菜が、無様にヘアヌードを晒しているかのような。 そして、その上には、黒いマジックで、大きく『滝沢 おまえも、こうなる!!』と書き殴ってあった。 これが、香織たちによる、秋菜への『メッセージ』だった。関係のない第三者が見たら、失笑ものの、滑稽極まりない代物であるが。 「やだ……、なに、これ……」 どことなくひんやりとした目鼻立ちの秋菜だが、今は、その目が、わずかに見開かれていた。ゆったりとしたストレートヘアを胸もとまで垂らし、その毛先だけ、自然に内側にはねさせた、お洒落な髪型。その髪から、ふんわりといい香りがする。 こんな上品なクラスメイトの目と鼻の先に、まるで、臭いでも立ち上ってきそうな、生々しい自分の裸の写真があるのだ。顔の部分は切り取られているとはいえ、涼子は、猛烈な羞恥を感じずにはいられない。 「最悪……。誰が、こんなこと……」 秋菜は、虚ろな表情で呟き、寒気を感じたように肩を抱いた。その眼差しが、こちらに向けられる。 とてもじゃないが、涼子は、目を合わせられなかった。体が小刻みに震えていた。落ち着いて、と自分に言い聞かせる。ここでは、決して恥ずかしそうな素振りを見せてはいけない。ことに、相手が、頭のいい秋菜とあっては。 「あっ……、あの、これ、見せるべきか、迷ったんだけど……、表紙だから、破って捨てるわけにも、いかなくって……」 ごめんね、と言いそうになるが、涼子の胸には、自分に誓ったことがあった。秋菜に謝ることだけは、絶対にしない、と。なぜなら涼子は、無関係な第三者として、ここに座っているのだから。謝る道理など、どこにもないはずだ。 「ううん……。教えてくれて、ありがとう、南さん」 涼子が、どこか申し訳なさそうにしているのを察したのか、秋菜は、取りなすように言った。そして、なにやら、次の言葉をためらうような仕草を見せる。 「あの……、これって……、知ってるのは、南さんと吉永さんだけ? ほかに、誰か……、見た人はいる?」 その問いが、秋菜のプライドの問題であることに、涼子は、すぐに気づいた。こんな、気持ちの悪い嫌がらせを受けたということは、人に知られたくないのだ。涼子自身、初めて服をすべて脱がされた時、真っ先にそれを思った。だから、その気持ちはよくわかる。 「いや、わたしと、吉永さん以外は……」 涼子の言葉を、香織がさえぎる。 「それを、視聴覚室で発見した時は、あたしたち二人のほかに、人はいなかったよ。いつから、あそこにあったのか、わからないから、はっきりとは言えないけど……、たぶん、それを作った犯人以外だと、知ってるのは、あたしたちだけだと思うよ……」 香織は、そう言いながら歩いて来て、そばの席の椅子を引き、ようやく腰を下ろした。 「そっか……」 秋菜は、幾分ほっとしたように、二度、軽く頷いた。 「南さん、吉永さん。このことは……、誰にも言わないで……。わたし、ほかの子から同情とか心配とか、されたくないから」 秋菜の真剣な眼差しに、涼子は、わかった、と小さく答えた。香織も、そう言う。 なんとなく、秋菜のプライドの高さをかいま見た気がした。秋菜が、今、一番気がかりなのは、周囲の生徒たちへの波及なのだ。その心情は、まさに涼子と同じである。 会話の流れが途切れ、沈黙が下りた。 その時、香織が、わざとらしい咳をした。横から、香織の強い視線を、ひしひしと感じる。そろそろ言え、と急かす視線だった。 そう。今から涼子は、香織の考えたいくつかのセリフを、秋菜にぶつけなくてはいけないのだった。 滝沢さん、ごめんね……。今一度、心の内で両手を合わせ、涼子は口火を切った。 「あの……、滝沢さん。ほかには、嫌がらせみたいなこと、された覚えはない? 何か、思い当たるようなことがあったら、正直に話してほしいんだけど……」 何気ない質問のようで、ちゃんと意味はあった。秋菜にとって、被害は、この件だけではないことを、涼子と香織は知っている。秋菜は、何者かに体操着が盗まれたことを、忘れてはいないはずだ。 秋菜の視線が、わずかに揺れて落ちた。ためらうように下唇を軽く噛んでいる。 「とくに、ほかには、何も……。うん、何も、ない」 秋菜は、やや力の入った声で、そう答えた。 思ったとおりだった。やはり、涼子に話そうとはしない。涼子を信用していないというのではなく、彼女のプライドが、そうさせたのだろう。涼子が秋菜に対して抱くように、秋菜もまた、涼子への苦手意識を持っているかもしれないのだ。だとしたら、そんな相手に、これ以上、弱いところを晒すのは、屈辱以外の何物でもないはずだ。 「南さん。わたし、これを見た瞬間は、うわっ、て思ったけど……、こんなの、なんでもないよ。どっかの頭のおかしい人が、たまたま、わたしの教科書と写真を手に入れたから、こんなもの、作ったってだけ。怖くもなんともない。だから、南さんも、これを見たことは、忘れてね」 秋菜は、わずかに首を傾け、口もとで微笑して見せた。涼子に対して強がる姿が、なんだか痛々しくもある。 つと、横に視線を向けると、香織は、面白くて仕方がないのか、にやついているのをごまかすように、顔を俯けていた。 だが、次に涼子が口にするのは、そんな秋菜を、恐怖のどん底に突き落とすようなセリフだ。同時に、それを言う涼子のほうは、もう、狂気の一言だった。 「あの、怖がらせるようで、ちょっと言いにくいんだけど……、でも、滝沢さんのことが心配だから、言うね……。この写真、後ろに、マットとか飛び箱とか、写ってるでしょ? この光景、わたし、見覚えがあるの。これ……、きっと、この学校で撮られたものだよ……」 いったい自分は、どんな顔をして、こんなことを喋っているのだろう、と涼子は思う。すうっと気が遠のき、今にも、自分の体が、椅子から落ちてしまうのではないかと、不安になるような感覚だった。 写真の背景は、灰色のコンクリートの壁で、その壁際に、ほこり被った運動用具が、小さく写っている。 「えっ……、うちの学校……? これ、学校の、どこなの……?」 秋菜の顔から、余裕が消えていた。 「たぶん、体育倉庫の、地下……。わたし、一度、あそこに下りたこと、あるから……」 あの、じめじめとした、陰鬱な空間。涼子にとっては、監獄を連想するような場所である。 「それって、要するに……」 秋菜は、言い淀んだ。言葉にするのを、怖がっているようでもある。その喉もとが、ごくりと波打つ。そして、寒気を感じさせるような低い声で言った。 「ここに写ってる裸の体は、『うちの学校の生徒』である可能性が、高いっていうこと?」 やはり秋菜は、鈍感ではない。 「……そう。たぶん、だけど」 涼子は、ぽつりと言った。世の中に、こんなにも惨めなことが、あるだろうか。 秋菜は、青ざめた顔をして、写真に目を落とした。『うちの学校の生徒』だということを意識して、写真の中の裸体を凝視している。これまでとは、まったく別物に見えてくるに違いない。 当然ながら、涼子の気持ちを、秋菜は知らないのだ。そうやって、まじまじと全裸の写真を見られるのが、どれほど生理的に耐え難いかということを。 そこで、秋菜が口にしたのは、彼女にしては、驚くほど間抜けな言葉だった。 「この、裸になってる人って……、自分で、やりたくて、こんなことやってるんじゃ、ないよねえ?」 そんなわけないでしょう……! 「こんなことして、喜ぶ人なんて、いるはずないじゃん」 涼子は、つい、語気に不快感を込めてしまった。何も知らない秋菜の言葉に腹を立てるなど、筋違いだと、わかってはいるものの。 「そうだよねえ……。てことは……、うちの学校に、こんな目に遭わされた子が、いるってことなんだよね。信じられない……」 秋菜の片側の頬は引きつっていて、目の下がぴくぴくと痙攣するのが見えた。そんな秋菜の顔は珍しく、新鮮ですらあった。 「だから……、滝沢さんも、気をつけて。わたし、ただのいたずらだとは、思えなくて……」 全裸の女の写真は、ネット上のどこかにあったのを、ダウンロードして印刷したものだと、秋菜は最初、思っただろう。それならば、気持ちの悪い嫌がらせを受けたということで、大きなショックは受けるだろうが、後は、心の傷が癒えるのを待つだけである。だが、それが、実際にこの学校で起こった出来事となれば、話は、まったく異なってくる。なにせ、『前例』が示されているのだ。その、『滝沢 おまえも、こうなる!!』の言葉も、リアリティを伴って迫ってくるはずだった。 今、秋菜は、恐怖におののいている。本気で自分を狙っている人間が、この学校には、いるのかもしれない、と。気を付けないと、今度は、顔のすげ替えなどではなく、自分自身が、この被写体のようになってしまいかねない、と。 そして、今では、口を閉じ、ただの付添人のような風情の香織だが、そんな秋菜の反応を観察し、内心、満足げな笑みを浮かべているに違いなかった。 「やっだ……、何考えてんだろう、気持ち悪い。わたし、絶対に関わりたくない」 秋菜は、しっとりした声に激しい嫌悪感を込めて言い、腕をさすった。 気持ち悪い、という言葉が、半分は、被害者である全裸の被写体にも向けられている気がして、涼子は、胸が苦しくなった。まだ今は、涼子と秋菜の間に、立ち位置の『落差』がある。つまり、秋菜は、『普通の』高校生活を送る女子高生なのだ。その秋菜にしてみれば、惨めにも、人前で全裸にさせられ、それを写真に撮られた生徒など、悪気はなくとも、見下してしまうものなのかもしれなかった。 「あっ、でも……、南さん、これ、本当に、うちの学校の子かな……?」 秋菜は、含みのある言い方をした。 「えっ……、どうゆうこと……?」 涼子は、なんとなく嫌な予感を覚えていた。 秋菜の唇の端が、苦笑いでもするように、微妙につり上がった。 「これ……、大人っぽくない……? なんていうかさ、ほら……」 何を言いたいのか、すぐに感づいた。写真の中の裸体の、身体的特徴のことだ。 乳房や腰回りの艶めかしい曲線は、成熟した女性であることを示している。燃えさかるように広範囲に茂った陰毛も。また、肩や上腕、太ももなどに浮かび上がった筋肉は、どこか女子高生離れしていた。そういったものを総合して、秋菜は、直感的に『大人』を連想したのだろう。 みるみると顔に血が上っていくのがわかる。涼子は、恥ずかしくて仕方がなく、両手で顔を覆いたいほどだった。やだ……。そんなこと、言わないでよ……。 その時、息の止まるようなタイミングで、秋菜と目が合った。秋菜の涼しげな眼差しが、涼子の火照った顔を、真っ直ぐに捉えている。その瞬間が、涼子には、何秒間という長さに引き延ばされて感じられた。 えっ、なに……。 涼子は、思わず顔を背けていた。直後、自分のリアクションは、痛恨のミスだということに気づく。なにやってんの、ばか……。 「……あっ、南さん?」 秋菜が、訝しげに声を掛けてくる。 そうされると、涼子は、いよいよ恐慌をきたしてしまった。落ち着いて、大丈夫だから、落ち着いて、と必死に自分に言い聞かせるも、気持ちは静まるばかりか、動揺の炎に油を注ぐだけだった。 今、自分は、熱い湯船に浸かりすぎ、のぼせ上がった時のように、真っ赤な顔を晒していることだろう。頭の切れる秋菜が、不審に思わないわけがない。バレちゃう。この写真の裸の女が、わたしだってことが、バレちゃう……。もう、怪しまれてるかも……。 生きた心地がしなかった。なんだか、世の中のすべての事象が、がたがたと崩れていく様を、眼前に見ているような気分だった。 どのくらい、赤面した顔を、そうして伏せていただろう。一秒一秒が、拷問のようだった。 「ごめんっ! なんでもないっ! こんな写真見てたら……、なんか、わたし、悲しくなってきちゃって……」 涼子は、やっとの思いでそれだけ言い、ちらりと目をやる。 秋菜は、もの問いたげに小首を傾げ、じっとこちらを見つめていた。 「悲しく……、ねえ」 その生返事には、彼女の疑念が込められている気がしてならなかった。 もはや、恐怖と絶望で、頭の中がめちゃくちゃになっていた。涼子は、この場で叫び声を上げてしまいそうだった。もうだめ……。絶対に疑われてる。何もかも終わりだ。一刻も早く、この子の前から立ち去りたい……。 腰を浮かしかけたが、まだ、香織に与えられたセリフが、一つ残っていた。それを言わずに終わらせては、香織の怒りを買ってしまい、ここまで、気の狂いそうな思いで演技を続けてきたのは、なんだったのかということになる。 「あの、滝沢さん……。もしもだよ? もし、滝沢さんが、この写真の人みたいな目に遭わされたとしたら、どうする……?」 唐突で不自然な質問になったが、涼子は、早く終わらせたい一心で、最後のセリフを吐き出した。もう、半分、やけくそになっている自分がいた。 「えっ……。なに? わたしが、こんな格好、させられたら、ってこと……?」 秋菜は、苦いものでも噛んだような表情で、写真の裸体を指差した。 「うん、そう……」 涼子は、こわごわと頷いた。 気まずくも、少しの間、視線が交わっていた。 すると秋菜は、背もたれに体を預け、うっすらと微笑んだ。 「ありえない。人前で服を脱いで裸になるなんて、そんな間抜けで気持ち悪いこと、わたし、まかり間違っても、しない。だから、ちょっと、答えられない、かな」 間抜けで気持ち悪い……。涼子の胸に、ぐさっと刺さる言葉だった。とはいえ、その、秋菜の強気な宣言は、妙に説得力があった。たしかに、この上品で頭脳明晰な秋菜が、写真の中の涼子のように、不潔たらしい、無様な姿を晒しているところなど、涼子にも、まるで想像できない。なんというか、大した根拠はないが、この子だけは助かりそう、という気がしてくるのだった。 だが、今の発言は、さぞかし香織の悪意を刺激することとなっただろう。香織は、今、思っているはずだ。ならば、その、『ありえない』ことを、おまえに味わわせてやる……、と。 もう、憶えさせられたセリフは、すべて言った。 「そっか、そうだよね……。滝沢さんだったら、大丈夫だよね。あのっ……、わたし、もう、だいぶ部活に遅れちゃってるから、そろそろ行くね。なんにも力になってあげられなかったけど。じゃあ……、おつかれ」 涼子は、一方的に話を切り上げると、バッグを持って慌ただしく席を立った。これ以上、秋菜の前に座っていると、頭がおかしくなってしまいそうだった。 「あっ、うん……」 秋菜は、突然、涼子の態度が素っ気なくなったことに、少し面食らった様子である。 しかし、涼子は、それも気にしていられなかった。去り際に、こんなことをやらせて、自分と秋菜の二人をもてあそんだ香織に、横目で憎悪の視線を送る。 香織は、口笛でも吹くような顔で、ちらりと涼子を一瞥しただけだった。 あんただけは、絶対に許さないから……。いつか、わたしと滝沢さんで、あんたを追いつめて、泣かせてやるから……。 そうして涼子は、逃げるように、どたどたと教室のドアまで向かった。 「南さん!」と秋菜に呼ばれた。 涼子は、立ち止まって振り返った。 「あの……、わざわざ、わたしのために時間を作って、教科書を届けてくれて、ありがとう。それなのに、わたし……、動揺してたせいもあって、なんか、南さんに、失礼な態度を取っちゃって、ごめんね」 秋菜は、しおらしく言った。 「……ううん。ぜんぜん、そんなこと、ないよ」 謝るべきは、涼子のほうである。なにせ、すべて演技だったのだから。 「部活、頑張ってね」 秋菜は、軽く右手を挙げた。 「ああっ、うん」 涼子も手を伸ばし、掌を向ける。 教室を出て、後ろ手にドアを閉めた。 どうしよう……。あの子に、疑われているだろうか……。 今、涼子の頭の中を占めているのは、その恐怖感だけだった。秋菜を騙していたという罪悪感すら、ほとんど感じないほどに。わたしは、自分のことしか考えられないのか、と自分自身に少なからず呆れるが、もう、どうしようもなかった。 最後の秋菜の様子からすると、涼子に対し、何らかの疑念を抱いているふうには、見えなかった。だが、むろん、頭のいい彼女のことだから、そう装っていただけという気もする。 写真に写っている裸体は、実は、涼子の体なのではないかと、秋菜が、疑っているか、どうか。 涼子は、額を押さえ、冷静に思考を巡らせた。自分は、いたずらに物事を悲観する性分ではない。かといって、楽天家でもない。 ほどなく、結論が出た。可能性は、だいたい五分五分だろう、と推測する。秋菜が涼子を怪しんでいる場合は、家に帰って、あの写真の裸体を、徹底的に調べるはずだ。体のどこかに、南涼子であることを指し示す証拠が、写っていないかと……。 激しい生理的嫌悪感と恐怖に襲われ、涼子は、髪や胸を掻きむしりそうになった。いやだ……。そんなのって、そんなのって。 すると、またぞろ、あの、よこしまな思いが脳裏に浮かんだ。 あの子も、早く、わたしのところまで、落ちてきてくれればいいのに……。わたしと同じように、なってよ……。 もし、秋菜が、香織たちの陰謀に絡め取られ、涼子と同様の立場になったとしたら、どうなるか。そうなった時、秋菜は当然、涼子が、陰謀に荷担していたことを知るはずだ。涼子に対する秋菜の恨みは、どれほどのものになるだろう。涼子は、今から、修羅場を覚悟しておく必要があった。秋菜から、どこかに呼び出され、何発も頬を叩かれるような事態も、充分に考えられるからだ。だが、それでも、自分より『一段高いところ』にいる秋菜に、毎日、疑惑の目で見られ続けるのと比べたら、遙かにマシ、と思わざるをえないのだった。 むろん、それが、身勝手極まりなく、人間として卑しい考えだということは、百も承知である。秋菜からしたら、涼子が、そんなふうに考えること自体、不愉快な話のはずだ。けれども、こんな時、自分の身を一番大事に思うことは、果たして、罪なのだろうか……。 延々と続きそうな思考を、涼子は、そこで、なんとか打ち切った。もう、これ以上、ぐじぐじと思い悩んでいても仕方がない。たとえ、秋菜に疑われているとしても、疑惑は、しょせん疑惑でしかない。頭部が切り抜かれている写真から、決定的証拠は、見つからない……、はず。 そう結論付けてしまえば、涼子には、顔を上げて前に進むだけの、強靱な精神力が備わっていた。まだ、教室から、香織が出てきた気配がないことが、少し気になったが、もう、それすらも、どうでもいいと吹っ切る。 今、やるべきことだけを考える。すでに、部活の練習に、一時間以上の遅刻だった。まずは、みんなのところに、行かなくっちゃ……。わたしは、キャプテンなんだから。こんなことで負けてなんて、いられない……! 涼子は、自分を奮い立たせ、体育館へと向かった。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.