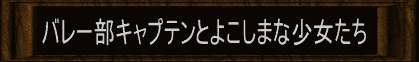
第十六章〜二年前
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
今日はどんな一日になるだろう。愉しみだ。吉永香織は、電車のつり革につかまっている時から、むずむずとしていた。 頭の中は、南涼子のことで一杯だった。ほんの一ヶ月ほど前までは、香織が憧れの思いを抱いていた相手。かっこいい、なんとかして友達になりたい、あの子が、バレー部で活躍している勇姿を、一目見たい……、と。だが、今では、天地がひっくり返ったかのように、香織の目から見て、世の中で一番惨めな人間に成り果てた女。 目を閉じた次の瞬間には、その涼子の姿が、まぶたの裏にはっきりと描かれる。いかにも部活少女らしい、飾り気のないショートカット。切れ長の澄んだ眼差しは、まるで、人間の汚い面を知らずに生きてきたかのようで、高い鼻筋は、同性として羨ましい。りんとして、よく整った顔立ちだ。だが、それでも、トップモデルのような美貌というほどではない。頬のあたりには、平凡な丸みがあるし、顔全体からは、都会の似合わなそうな、素朴で垢抜けない雰囲気も滲み出ている。今では、涼子のそんなところが、香織は大好きだったし、同時に、付け入る『隙』でもあったという気がしている。どこにも隙のないような完璧な美少女だったら、香織も、恐れ多くて、何かしてやろうなどとは考えなかったはずだ。そして、健康そうな小麦色の肌、Tシャツにスパッツ姿がぴったりの、肉感的で伸びやかな体つき。あの、女子アスリートにありがちな低い声も、耳によみがえってくる。 はやく会いたい。惨めなあいつの顔が、見たい。また色々とやってやるからね……。 ふと思うことがある。なぜ自分は、南涼子というクラスメイトに対してだけは、ここまで悪意をかき立てられるのだろうか。なぜだろう。正直、自分でもわからなかった。あたしは、悪魔なんかじゃないのに。ごく普通の、どこにでもいる女子高生なのに。 電車内では人に席を譲るし、誰かに道を尋ねられれば、微妙に愛想笑いを浮かべながら説明する。そんな時は、それなりに気持ちがいい。イヤホンを耳に当て、好きなミュージシャンが、歌詞の中で人類の愛や平和を訴えているのを聴くと、香織は、それに共感したりもする。そうだよ。なんで人は、争い続けるんだろう。おかしいよ。 博愛の精神みたいなものに感化されている時は、しばしば、涼子に対する申し訳ない思いで、胸がうずく。今までひどいことしちゃって、ごめんね、と言って謝ったら、涼子は、許してくれるだろうか……。土下座するのは無理だが、頭を下げるくらいなら、やってあげてもいい。それだけのことをしたのだから。涼子から、嫌な思いをさせられたわけでもないのに。なんでだろう。なんで、あんなひどいことを。もう、やめてあげようかな……。 ごめんね、南さん。 そうして、軽く目を閉じてみる。まぶたの裏には、すぐに涼子が現れる……。すると、どうだろう。まるで条件反射のように、めらめらと悪意が燃え上がるのを抑えられない。やだやだ。まだ全然、物足りない。もっともっと、涼子の苦痛に歪んだ顔が見たい。そういえば、涼子が、自分たちの前で泣いたことは、一度もないではないか。……強いじゃん。でも、いつか絶対に、泣き顔も拝ませてもらうからね。 悪いことだと自覚していながらも、やめられない。もはや、香織にとって、涼子を対象にした加虐の欲望は、食べたい、寝たい、といった生理的欲求に等しかった。ダイエットをしないと、と思っていても、甘いものを食べてしまう。それと一緒だ。そんなものだから、やめるのは至難の業なのだ。 駅のバス停で、香織は、学校行きのバスを待っていた。列ができていて、香織の前も後ろも、自分と同じ制服を着た三、四人のグループだった。 香織は、彼女たちのお喋りが、耳障りで仕方がなかった。自分が独りでいる時に、周りが賑やかだと、決まっていらいらとする。突然、きゃはは、という甲高い笑い声が上がると、自分が笑われたのではないかと、びくりとしてしまう。こういう時に限って、バスの到着時刻まで、だいぶ時間がある。 ああ、うるせーな……。香織は、意味もなくスマートフォンをいじりながら、周りに聞こえないように溜め息をついた。 その時、ふと思った。こうして、朝っぱらから気分が悪くなったのは、南涼子のせいじゃないか……。涼子のことを色々と考えていたせいで、足取りが遅くなり、知っている子が誰もいないバス停に、並ぶ羽目になってしまった。もう少し早く歩いていれば、今頃はバスに乗っていて、知り合いの子と、たわいない会話を交わしていたかもしれない。きっとそうだ……。だんだんムカついてきた。それだけじゃない。クラスの友人に冷たい態度を取られたり、体育のバスケで、同じチームの五人中、自分だけ点を入れられなかったりするのも、何もかも、涼子のせいだ。許せない。だから、日常のストレスのすべてを、涼子にぶつけてやる。 そんなふうにして、香織は、良いことも悪いことも、世の中のあらゆる物事を、南涼子という人間に結びつけ、集約していく思考のくせが付き始めていた。 たとえば、授業中、教師に当てられて、答えられない問題があったとする。そんな時、まず頭に思い浮かぶのは、涼子なら、わかるのだろうか、という疑問なのだ。 あるいはまた、クラスメイトの一人ひとりを分析する時、香織自身との関係性は、むろん重要だが、それと同じくらい、涼子と、どのような間柄なのかという情報が、欠かせない。香織というX軸と、涼子というY軸において、その生徒が、どこに位置する点なのかを、じっくりと見極めるのだ。涼子と話したことがあるのか。涼子と相性が良いのか、悪いのか。涼子との共通の趣味は……。 そう。滝沢秋菜という生徒は、そうした意味で、特殊な存在だった。彼女の座標は特異で、他のクラスメイトたちとは、大きく離れたところに位置していた。香織は、そこに目を引かれたのだった。 そんなストーカーじみた香織に、天は『味方』してくれた。味方したのは、天上の神ではなく、悪魔なのかもしれないが。逆にいえば、涼子は、とことん運から見放されていた。涼子の背中を、指差して笑ってやりたくなる。香織は、そのことが、涙が出るほど嬉しかったのだ。 もう止まらない……。あたしは、おまえのことだけを考えてるんだからね……。 涼子の体から流れ出したものが、滝沢秋菜の体操着に染み込んだ。その汚れた体操着と、犯人が涼子であることを示す写真。その二点のセットを『切り札』として持つことで、香織たちは、涼子に対する無限の権力を手に入れた。 あの日から四日後。 昼休みの時間、香織たちは、ひと気のないトイレに涼子を呼び出した。滝沢秋菜が写っている写真を、彼女のバッグから盗んでこさせるために。 もし、盗んでこなかったら、放課後、『検尿』を受けさせる。香織は、そう脅迫した。検尿という名の、公開の放尿の強制。さすがの涼子も、決断までに時間が掛かった。しかし涼子は、首を横に振った。人のものを盗むことは、できない、と。 涼子に対する脅しは、第二段階に移行した。検尿に加え、『ギョウ虫検査』も受けさせる、と脅迫。香織たちオリジナルのギョウ虫検査は、涼子の体のその部分に、香織たちが、じかにセロテープを貼りつけるという方法だった。涼子の気持ちが、激しく揺れ動いているのが見て取れた。だが、それでも盗むことを拒絶した。 脅しは、最終段階に入った。例の『切り札』の出番だった。あの二点のセットを、滝沢秋菜本人に送りつける、という脅迫だ。それにより、涼子が貫き通そうとしていた正義は、見事に砕け散った。 ついに涼子は、盗みを引き受けたのだった。 検尿、ギョウ虫検査、などと遠回りなことをせず、最初から涼子に『切り札』を突きつけてやれば、それで話は終わったのだろうが、そうしなかったのには、理由がある。香織たちは、あえて、『段階的に』脅したのだ。なにせ、あのトイレで香織たちが行ったのは、涼子に対する一種の『テスト』だったのだから。 そして本当に、涼子は、滝沢秋菜の写真を盗んできた。その事実は、重大な意味を持っていた。人にも自分にも厳しい、バレー部のキャプテン、南涼子が、保身を優先し、クラスメイトのものに手を付けたのだ。一度道を踏み外した涼子は、その後、転がり落ちていった。再起不能なまでに。 その日、放課後の教室には、涼子と香織と、そして滝沢秋菜の三人が残っていた。普段は、それぞれ会話を交わすこともないような三人が。 秋菜の机の上に、保健の教科書が開いて載せられた。表紙の裏には、涼子の裸体と、秋菜の顔という、アイコラ的な組み合わせの写真が貼りつけてあり、黒いマジックで『滝沢 おまえも、こうなる!!』と書き殴ってあった。秋菜へのメッセージだ。 そこで涼子は、秋菜に対し、嘘を口にした。この教科書が、視聴覚室の教壇に置かれていて、掃除の時間に、自分たちが発見したのだ、と。あの南涼子が、秋菜のものを盗んだ挙げ句、秋菜をあざむくために、嘘までついたのだ。香織は、それが可笑しくて堪らなかった。 そして……。 涼子の顔は、氷で冷やすべきだと思うくらい、真っ赤になっていた。なぜか。メッセージの写真の、全裸の女の体を、秋菜が、意味ありげに『大人っぽい』と表現したからだ。その発言は、涼子の羞恥の炎を、猛烈な勢いで煽り立てたらしかった。 だから涼子は、香織に与えられたセリフをすべて言い終えると、別れの挨拶もそこそこに、慌ただしく立ち上がった。そうして、逃げるように教室を出て行った。 みっともないったら、ありゃしない。香織は、涼子を追いかけようかと迷ったが、その場に残ることにした。 秋菜と二人きりになる。わずかの間、沈黙が流れた。まるで、熱気を発する涼子がいなくなったことで、この場の温度が、五度くらい下がったかのように感じる。 秋菜は、無表情でちらりと香織を見たが、すぐにまた、机の上の卑猥な写真に目を戻した。そして、ぼそりと呟いた。 「やだ……、汚らしい……」 香織は、どきどきと胸が高鳴るのを感じていた。 滝沢秋菜を初めて見たのは、高校に入学して、すぐのことだった。クラスは違った。一年の時、香織はC組で、秋菜はD組だ。 入学時に、芸術の選択科目、美術、音楽、書道の三つの中から、一つを選択する。香織は、美術を選んだ。授業は、美術室への移動教室となる。その時、秋菜と同じだったのだ。 美術室には、六人掛けの大きな机が、六台並んでおり、最初の授業で、生徒たちの席が割り当てられる。それぞれの机が、一つの班となる。香織の班は、C組から二人、D組から四人という構成だった。そして、香織の向かいの席に、D組の秋菜がいた。秋菜と同じ班だったのだ。 あの当時の秋菜の印象を一言で言うなら、凶暴、だった。外見からして、今とはだいぶ違い、ぼさぼさとした髪を、いくつかのピンでオールバック気味にしていて、顔が、もっと、むくんだように膨れていた。目つきも、常に気だるげで、いかにも攻撃的な雰囲気が漂っていた。 その風貌通りというべきか、美術の授業で、香織は、秋菜の攻撃性を、しばしば目の当たりにすることとなったのだ。 一番初めの授業で、それぞれの班の、班長を決めなくてはならない時のことだ。班長というものは、言ってしまえば、面倒な雑用係である。そんなものを進んで引き受けるような、奇特な生徒は、まず現れない。どの班も、ジャンケンとか、その類の方法で決められる。 それが香織たちの班だけ、決まっていないという状況だった。 四十前後の、眼鏡を掛けた男の教師が、首を伸ばして言った。 「おーい、四班の班長は、誰になったんだー?」 その時、香織の向かいにいる秋菜が、いきなり口を開いた。 「シバタさーん。ありがとう、引き受けてくれて。じゃあ、よろしくね」 彼女のしっとりとした声には、やゆが込められていた。 「芝田? 芝田、ちょっと手を挙げてくれないか」 美術教師は、秋菜の発言を真に受けたのか、そう言った。まだ名前と顔が一致しないのだ。 芝田と呼ばれたのは、こちらから見て、秋菜の左隣に座っている生徒だった。癖毛の目立つ、気の弱そうな外見の彼女が、おずおずと右手を挙げる。 「芝田、おまえが、そこの班長なのか?」 その問いに、芝田さんは、黙って首を横に振り、否定した。 それを見た秋菜は、おどけたような低い声で言うのだった。 「シーッバッタッさぁーん……」 芝田さんは、明らかに嫌そうな顔をしていた。 「班長やりたいって、言ったでしょーう? わたし、恥かいちゃったじゃなーい」 よその班から、失笑の声が上がった。むろん、芝田さんに対してだ。 「えっ……、班長やるなんて……、言ってないよ」 芝田さんは、秋菜を無視する勇気すらないようで、蚊の鳴くような声で答える。 すると、秋菜の右隣にいる、前髪の重い生徒が挙手し、ひどいがらがら声で言った。 「それじゃあ、あたし、芝田さんを、班長に推薦しまーす」 彼女の名前は、辻川といった。友人たちからは、『ミオ』と名前で呼ばれている。秋菜に負けず劣らず、柄の悪い生徒だった。 芝田さんは、悲しげに俯いてしまった。秋菜と未央の二人は、その様子を見て、にやにやと笑っている。 こうは、なりたくない。香織は、芝田さんのことを、そう思う。哀れだ。秋菜、未央と同じD組だから、普段の教室でも、この二人からは、こうして嫌がらせを受けているのかもしれない。 しかし香織は、一抹の不安を抱いていた。この性格の悪そうな二人、あたしには、何もしてこなければいいんだけど……。 結局、班長は、公平にジャンケンで決めることになった。負けたのは、香織と同じ、C組の生徒だった。芝田さんは、班長を押しつけられることは、免れたとはいえ、その表情は、授業中、ずっと沈んでいた。 その日以降も、秋菜と未央、とくに秋菜は、芝田さんに対し、度々、からかいの言葉を口にしたり、横暴な態度で接したりしていた。 「シーッバッタッさぁーん……」 秋菜からそう呼ばれるたび、芝田さんの体が、ぎゅっと萎縮する。芝田さんは、怯えていた。この班なら、誰でも知っていることだ。しかしそれでも、秋菜たちを注意する声は、一度として聞かれなかった。 秋菜や未央とは、とにかく関わりたくない。それが、香織の本音だった。彼女たちのせいで、美術の授業が憂鬱になったほどだ。同じ班の、香織の両隣にいる二人の生徒も、似たような思いを抱いていたに違いない。 そして、秋菜について考える時、必ず思い出す出来事がある。あれは、高校入学後、初めての中間試験が、そろそろ始まろうかという時期だった。 同じく美術の授業で、教室は、騒がしかった。それぞれの机には、マグカップやワイングラス、フォーク、スプーンなど、いくつかの食器類が置かれていた。生徒たちは、それらを鉛筆でスケッチブックにスケッチしていた。その日は、芝田さんが欠席だった。 「ああー、なんか飽きてきちゃった……」 秋菜は、ぐたっと机に突っ伏した。ややあって、その手が、おもむろに動きだした。机の端に寄せられた、持ち主不在のスケッチブックをつかむ。芝田さんのものだ。 スケッチブックは、サイズが大きいこともあって、生徒たちは持ち帰らず、普段は、美術室の棚に、班ごとに分けて置かれている。授業が始まる前に、班長が、自分の班のものをすべて、机に持っていく。そのため、欠席の芝田さんのスケッチブックも、机にあるのだった。 秋菜は、体を起こすと、気分転換なのか、それをぱらぱらとめくり始めた。隣の未央も、興味ありげに覗き込む。 「可もなく不可もなく……、ってところかな」 秋菜が、無機質な声で呟いた。 「あれ? でも、この『花』……、なんか、変」と未央。 「あっ……。わかった。色々と、自分でアレンジして描いてるんだ……」 「はあ、なるほど。……ホントだ。この『胸像』の絵も、マフラーみたいなのを、付け加えてるし……」 「わたしには、芸術のセンスがあるから、それを先生に見てもらおう……、みたいに、勘違いしてんのかな?」 「ありえる、ありえる」 秋菜は、スケッチブックを膝にのせて開いているので、彼女たちが、どの絵を見ているのかは、こちら側からは確認できない。 「そうだ。そんなにアレンジしたいんだったら……」 秋菜は、そう言って鉛筆を持ち、あろうことか、そのスケッチブックに、何かを書き込み始めたのだった。 「こんなふうに……。やっぱり、胸像の『目』も、ちゃんと細かく描いてあげないと……。可愛らしく、くりくりくり……、っと」 それを見て、未央が、吹き出しそうになる。 秋菜の言っていることからすると、どうも、芝田さんの描いた、石膏の胸像の絵に、いたずら書きを始めたらしい。 うわぁ……、引く……。さすがの香織も、そう思った。(高三になって涼子と同じクラスになるまでは、香織は、人に重大な危害を加えるような人間ではなかった。) けれども、教室は、がやがやとしていて、教師も、よその班の生徒も、秋菜たちの言動に注目したりはしない。 「髪型も、アレンジ。こう……、芝田さんっぽい髪型に……」 秋菜は、鉛筆を動かし続ける。その口もとには、背筋の寒くなるような、サディスティックな薄笑いを浮かべて。 「ああっ、なんか、だんだん、芝田さんに似てきてない!?」と未央がはしゃぐ。 香織の両隣にいる二人の生徒は、むろん、その、悪ふざけの域を超えた行為に、気づいているはずだった。だが、香織と同様、秋菜のことは、まるで見えていないかのように振る舞い、目の前にある食器のスケッチに、集中しているフリをしていた。 「あっ……、ちょっと失敗しちゃった。ダメだわ、これ」 秋菜が独りごち、舌打ちした。 次の瞬間、聞こえてきた音に、香織はぎょっとした。びりびりと紙を破る音。 愕然とすることに、秋菜は、今度は、落書きを加えていたページを、勝手に破り取ったのだ。何食わぬ顔をして。そして、それをくしゃりと潰し、両手で丸めると、体の向きを変え、ゴミ箱へぽーんと放った。紙屑は、壁に当たってゴミ箱の中に落ちた。 「よし、次いこう、次……」 秋菜には、罪の意識というものがないのか、再びページをめくりだす。未央は、くくくっと笑っている。 一線を越えてる……。香織の頭に、そんな言葉すら思い浮かぶ。なんて、性格が悪いんだろう……。(高三になって、香織が涼子に対してやったことに比べれば、この時の秋菜も、可愛いものかもしれないが。) 香織の両隣の二人からも、息を呑むような緊張の気配が伝わってくる。 結局、秋菜は、次に落書きしていたページも気に入らなくなり、破って捨てた。三枚目で、そこそこ愉快な仕上がりになったらしく、芝田さんのスケッチブックを、ようやく閉じた。 滝沢秋菜。人のスケッチブックの絵を、平気で破るような女。香織は、彼女の冷酷さに、恐怖すら覚えた。 この時の出来事は、三年になった今でも、秋菜のことを考える時には、決まってフラッシュバックする。 そして、香織は、秋菜と未央、この二人と同じ班であることが、心の底から嫌になった。自分自身は、性格の悪い人間だが、自分の周りに、自分以上の悪人には、いてほしくない。それが、香織の考え方だった。 ところが、少々意外なことに、秋菜の攻撃性は、日が経つに連れて、しだいに目立たなくなっていった。とにかく、芝田さんへの攻撃が減った。ついに教師から注意を受けた、あるいは、いたずら書きなどの悪事がバレて、こっぴどく叱られた、というわけではなさそうだった。それでもなぜか、一学期の終わり頃には、もう、秋菜が、芝田さんを馬鹿にするような場面は、ほとんど見受けられなくなった。 二学期に入ると、秋菜は、オールバック気味だった髪を、自然な形に下ろしていた。それだけで、刺々しい印象が、ずいぶん薄らいだ。外見の変わりぶりと同様、その言動も、さらに丸くなった。芝田さんに対する接し方で、それがわかった。体がぶつかったら、一応は謝るようになったし、芝田さんのスケッチブックが、自分の近くにあれば、それを取ってやったりもしていた。当然といえば当然なのだが……。 芝田さんの表情も、一学期の頃に比べると、心なしか明るくなったように見えた。 そして香織は、秋菜が、極めて学業優秀な生徒であることを知った。彼女のことは不良だと思っていたが、どうも、少し違うようだ、と香織は感じ始めた。というより、もう、生活態度は普通の生徒だった。 では、入学して間もない頃の秋菜は、何だったのか。香織は、予想する。あれは、いわゆる『高校デビュー』のようなものだったのではないだろうか。あの、気性の激しそうな髪型も。気の弱そうな芝田さんを攻撃していたのも。悪意を前面に出すことで、彼女は、高校生活における人間関係で、少しでも優位に立とうとした。きっと、そんなところだ。 だが、それは短い期間で終わった。その理由は、彼女にしかわからない。単に、そういうことに飽きたから。自分が、子供じみている気がしてきて、恥ずかしくなったから。あるいは、怖い、性格が悪い、と周囲から見られるデメリットに、気づいたのかもしれない。要するに、思春期の少女の、気まぐれである。 しかし、表面上は普通の生徒に落ち着いたからといって、秋菜から毒気が消えたわけではない。その毒が、剥き出しにならなくなっただけのことだ。香織は、確信していた。秋菜の本質は、あの、人のスケッチブックの絵を、平気で破った姿なのだと。 結局、同じ班とはいえ、班として何かに取り組む機会はなかったので、秋菜との会話は、必要最低限にとどまり、一年が終わった。二年も美術の授業で一緒だったが、クラス替えに伴って、座席も班も変わり、秋菜とは離れた。二年時の彼女について思い起こすことは、特にない。強いて挙げれば、彼女の、むくんだように少し膨れていた顔が、余分な脂肪がだいぶ落ちて、すっきりしたと感じたことくらいだ。 そして三年に上がり、秋菜と同じクラスになった。 こんなに綺麗だったっけ……? 香織は、秋菜を見て意外の感に打たれた。中分けにしたストレートヘアを、ふわりと胸もとまで垂らし、毛先だけ、自然に内側にはねさせた髪型は、エレガントだった。髪型がお洒落になり、顔の輪郭がすっきりしたことで、以前は、気だるそうな印象しか受けなかった眼差しが、クールという形容がぴったりの雰囲気を、発するようになっていた。 学業優秀というイメージもあるためか、秋菜は、全体的にお姉さんっぽく見えた。一年の頃、芝田さんを小馬鹿にして遊んでいたのが、嘘のようだ。もちろん、三年のクラスで、秋菜が、表立って誰かを攻撃しているところなど、目にしたことがない。それどころか、口数自体、ずいぶん減っていた。 大人しくなっちゃって……。香織は、秋菜の横顔を見ながら、くすっと笑いたくなった。しかし忘れてはいけない。騙されてはいけない。この子には、毒がある。それも猛毒だ。下手に刺激すると、その猛毒の牙を剥き出しにするかもしれない。 三年になった当初、香織は、そんな秋菜に関心を持っていた。しかし、その思いは、一週間ほどで消し飛んだ。もはや秋菜など、どうでもよくなった。 色々な意味で、それよりはるかに興味を惹かれる人物に、出会ったのだから。南涼子、その人だ。 香織は、暇さえあれば、涼子のことを考えるようになった。そして、友達になりたい、と痛切に願った。まずは、アプローチをする前に、涼子が、どんな子と親しくしているのかを、知りたいと思った。香織にとって、もはやクラスメイトとは、涼子という巨星の周りを公転する、ちっぽけな暗い惑星に過ぎなかった。涼子がいることで初めて光が当たり、意味を持つ。 移動教室へ向かう途中、体育やパソコンの授業、昼休み……。クラスメイトが流動する状況の時に、香織は、涼子とその周辺の生徒を、さりげなく、しかし事細かに観察した。涼子は、バレー部以外では、誰とよく喋っているか。最近、誰と仲良くなったか。やりとりの内容は……。我ながら気持ち悪いな、と独りで苦笑しながらも、それを続けた。 そんな中で、おやっ、と香織は思った。香織の目を引いたのは、あの、滝沢秋菜だった。涼子が現れてからというもの、秋菜の存在は、香織の意識から、すっかり抜け落ちていたのだが……。 南涼子と滝沢秋菜。この二人は、基本的には違うグループに属していた。けれども、社交性の高い涼子は、しばしば、秋菜のいるグループにも加わり、そこでも自然にとけ込んでいるように見えた。 だが、香織は、奇妙な出来事を目撃したのだ。それは、帰りのホームルームの直前のことだった。教室の教壇のそばで、五、六人が、立ってお喋りをしていた。その輪には、秋菜も含まれていた。そして後から、涼子が、屈託なく何事かを口にしながら、そこへ入っていった。みんな、涼子に対しては、好意的な様子に、見えたのだが……。 その時だった。秋菜が、隣にいた須藤仁美にちらりと視線を送り、ほんの一瞬、片側の頬を歪めたのだ。仁美は、秋菜の仕草を見て、目だけで頷く。そして秋菜は、きびすを返してその場から離れていった。 えっ……? その場面を目にした香織は、なぜか胸が高鳴るような、なんとも言い様のない気分になった。香織の目には、しっかりと焼きついていた。涼子がやって来た直後、瞬きをするような間のことだったが、秋菜の顔に、苦々しい表情が浮かんだのが……。 あれには、きっと意味がある。 香織は、真相を探りたいという強い欲求に駆られ、次の日から、行動を起こした。涼子と秋菜が接近したのを見かけたら、友人との会話も適当に切り上げて、すぐに二人がいる場へ向かった。ほとんどのシチュエーションは、涼子が、秋菜のいるグループにさっそうと入っていく、というものだった。香織は、その輪の周りを亡霊のようにうろうろし、二人の動きに神経を集中した。気になる芸能人の色恋沙汰がスクープされ、メディアから目が離せない時の心境に、どこか似ていたかもしれない。 監視を続けた甲斐あって、香織は、いくつもの『傍証』をつかんだ。 涼子が輪に加わると、秋菜が、そこから離れていく。そんな場面を、香織は、繰り返し目の当たりにした。秋菜は、立ち去る直前、そばに親しい須藤仁美がいる場合には、意味ありげに、その背中を、ぽんっと叩いたりしていた。 もはや偶然とは、とても考えられない。滝沢さんは、南さんのことが、苦手なんだ……。香織は、そう確信した。いや、もしかすると、嫌っている、なんてことも……。 涼子のほうも、そんな気配に感づいたらしく、自分が輪にいる時、秋菜が去っていくと、ちょっと切なそうな表情を見せるのだった。 時には、涼子が、思い切って秋菜に話題を振ることもあった。 「あっ、ねえ……、滝沢さんは、この話、知ってた!?」 もしこれが、海外で、言葉の通じない相手だったとしても、一発で仲良くなれる。涼子は、そんな笑顔を見せていた。 しかし、秋菜の対応は、冷めていた。 「うーん……、あんまり、そういうの、好きじゃなくって……」 秋菜は、そう答えて横を向き、口もとに苦笑を滲ませる。いくら以前より口数が減ったとはいえ、素っ気ないとしか言い様がない。 「あっ……、そっかぁ」 涼子は、言葉の接ぎ穂を失うと、自省するように下唇を軽く噛み、もじもじと指をいじった。 その姿の可愛いこと。香織は、なんだか微笑ましかった。そして、涼子の秘密を一つ知ったという、嬉しさみたいなものを感じた。とはいえ、その秘密をどうこうしようなんて、さらさら考えていなかった。この時、香織の胸にあった、涼子に対する感情は、『健全な』憧れだったのだから。あの南さんも、人間関係に苦労したりするんだなあ……、と感慨に浸っただけだ。 それでも涼子は、物事をネガティブには考えない。だから、秋菜のことも、秋菜のいるグループも、避けたりはしなかった。秋菜に対しては、芽生えた苦手意識を克服しようとするかのように、むしろ、勢い込んで話しかけていた。 しかし、よくよく考えてみると、涼子と秋菜の二人が、良好な関係を築けるはずがないのだ。涼子は、天真爛漫、毎日、キャプテンとして部活を率いて汗を流し、校則を守って、携帯電話すら持っていないという、今時珍しい、太陽のような生徒なのだ。かたや、秋菜はどうだ。二年前のことになるが、芝田さんという弱い者を小突き回し、挙げ句には、彼女のスケッチブックの絵を破っていたではないか。人間、中身は、そうは変わらない。そんなふうに思って秋菜を観察すると、あの、クールそうな眼差しだって、なんとなく、同級生たちを、馬鹿だと見下しているような目つきに、見えてくる。 南さん、その子は性格が悪いから、もう、話しかけるのは、やめておきな。ちょっとイタいよ、南さん。滝沢さんなんて放っておいて、あたしと仲良くしてくれたらいいのに……。 ついに、香織の知りたかった答えが、はっきりとした形でもたらされた。学年全体で、学校の周辺の掃除をするという、訳のわからない行事の時のことだ。クラスごとに、場所が割り振られる。 香織は、缶拾いやホウキ、チリトリなどは人任せにして、二人の友人とお喋りをしていた。だが、ふと、視界の端っこに、見過ごせない光景があることに、気づいた。例のシチュエーションである。涼子と秋菜の接近。 香織は、角が立たないように注意して、そっと会話から抜け、涼子と秋菜のいる集団に近寄っていった。二人の間に齟齬があることは、すでに、疑いから確信に変わっていたので、もう、これ以上の大きな発見はないような気がし、徐々に、執着心は薄れ始めていた。だが、興味を失ったわけではなかった。 香織がそばまで近づいた時、秋菜が、ちょうどその輪から離れ、こっちへ歩いてきた。秋菜の表情は、ひどく詰まらなそうだった。珍しく、彼女と親しい須藤仁美も、その後を追ってきていた。 南さんの様子は、どうだろう……? 香織は、瞬間的にそう思った。だが、香織の直感は、なぜか、『滝沢秋菜を張れ』と訴えていた。 香織は、直感に従い、涼子の様子を確かめるのではなく、遠ざかっていく秋菜と仁美に付いていった。 少し離れたところで、その二人は立ち止まった。 そこで秋菜は、穏やかでない声で、言ったのだった。 「もーう……。なんで、あの子、わたしたちの中に、入ってくんの? ノリは変だし、くだらないことで盛り上がるし……。ホンット、うざいんだけど」 仁美は、控えめに笑った。同意も反論もしないような笑いだ。 秋菜は、仁美のそんな煮え切らない態度が、いささか不満なのか、まったくもう、というふうに肩をすくめた。 そして二人は、また歩き出した。 密かにそれを見ていた香織は、わずかの間、その場に立ち尽くしてしまった。ショックにも似た感情が、胸の内で吹き荒れていた。 うそ……。いや、やっぱり、というべきか。薄々予想は付いていたが、秋菜の口から、はっきりと言葉で聞いてしまうと、衝撃以外の何物でもなかった。しかも、あんな攻撃的な口調で。秋菜の言った、『あの子』というのが、涼子であることは、もはや疑いようがない。 確定した。滝沢さんは、南さんを、嫌っている……。 香織が驚くのは、あの、真っ直ぐな性格の涼子を、嫌う人間が、存在するという事実だった。だが、それは秋菜一人だけだ。須藤仁美は違う。香織は知っていた。仁美は、秋菜と親しいが、涼子とも馬が合うのだ。だから、秋菜寄りの立ち位置にいるが、完全に秋菜側に付き、涼子を遠ざけるとは、考えにくい。中立的と言っていい。けれども、秋菜が、頑なに涼子を排除しようとし続けるなら、ひょっとすると仁美は、愛想を尽かして、だんだん、涼子の側に傾いていくかもしれない。いや、それは時間の問題のような気もする。 やっぱり性格の悪い、滝沢。彼女の内面は、二年前、悪人ぶりを周りに見せつけていた頃から、さほど変わっていない。滝沢……、あんたと、南さんとじゃあ、みんな、南さんに付くよ。この異分子め。 香織の胸の内には、秋菜に対する漠然とした不快感が流れていた。しかし同時に、その底のほうでは、なんだか面白いことになってきた、という、わくわく感みたいなものも、かすかにくすぶっているのだった。不思議な気持ち……。 だが、その後、やはり秋菜のことは、どうでもよくなった。いくら秋菜が嫌おうが、秋菜の力だけでは、涼子には、何をすることもできない。また、秋菜に同調する者も、きっと現れない。つまり、圧倒的パワーを持ち、幅広い交友関係を築いている涼子の前では、秋菜など、脅威にならないのだ。 そうして、香織の中で、秋菜の存在は、再び意識下に沈んでいった。その分、涼子に対して、より意識を集中できるようになった。 それから二週間ほど経ち、香織の気持ちに、大きな変化が生じた。人生観が変わったともいうべき、とてつもない変化だ。 怖ろしいことに、香織自身も怖ろしいと感じていることに、涼子に対する憧憬は、ふとしたきっかけで、どす黒い悪意に変質してしまった。 嫌い、とか、憎い、などと思ったことは、一度たりともない。むしろ、同じクラスになれて、本当によかった。しかし、涼子への悪意は、狂おしいまでに膨らんでいった。涼子に対し、何もせずに高校生活が終わるなんて、考えたくもなかった。絶対に、痛めつけてやる、と心に誓っていた。 だが、とてもじゃないが、香織独りでは、涼子は手に負える相手ではない。だから香織は、明日香とさゆりの二人と、徒党を組んだ。そして三人で、涼子をハメることにした。 体育倉庫の地下で、香織の願いは、とうとう実現した。涼子の体から、最後の衣類を剥ぎ取った時、香織たちの勝利が確定した。全裸の涼子は、無力だった。あの、あらゆる意味でパワフルな涼子が、香織たちに何をされようとも、文字通り、手も足も出なくなったのだ。香織は、涼子をなぶった。精神的に。性的に。香織にとって、十七年の人生の中で、最大、最高の出来事だった。 翌日、同じ場所で、それをもう一度繰り返した。涼子に対して、香織たちは、絶対的勝者だった。敗者の涼子は、前日と同様、無惨にも、衣類を何も身に着けていなかった。 高校生活は、夢見心地になった。二度に渡って、あの南涼子を好きにすることができたのだ。そして、三度目の実現も、もはや保証されているようなものである。(この数日後、放課後の教室に涼子を呼び出すことになる。) 授業中、涼子の後ろ姿を眺めているだけで、香織は多幸感を得られた。涼子が、英文の朗読で当てられるなどし、その甘いアルトヴォイスが耳に入ってくると、くすぐられるような快感を覚えてしまう。もはや香織にとって、涼子の存在自体が、麻薬みたいなものだった。 だが、もう一点、麻薬と似たところがあった。耐性が付くことである。 今度、涼子を呼び出したら、何をしてやろうかな……。前回より、もっともっと……、涼子をひどい目に遭わせたい。香織は、そう思っている。こんな調子で、涼子に対する加虐行為は、前回より次回、次回よりその次と、どんどんエスカレートしていきそうだった。もう、前回までと同レベルのことをやっていては、満足できそうにない。物足りない。『耐性』が付いてしまっているのだ。 しかし、考えさせられる。 昨日、体育倉庫の地下で、すなわち二日目の時点で、涼子はすでに、乳首も、陰毛も、臀部も、すっかりさらけ出し、その恥辱に身を震わせながら立っていた。いや、そればかりではない。たとえば……。香織は、涼子の尻の割れ目に、人差し指を差し入れるようなことまでした。そのまま、尻の肉を、横に押し広げてやった。涼子の体の、もっとも不潔な部分が、目に焼きついた。その時、涼子は絶叫していた。あれはまるで、焼きごてを当てられたかのような絶叫だった。 たった二日間で、涼子に対する責めは、かなりのレベルまで行ってしまった、という気もする。次回、自分は、そのレベル以上の激しさで涼子を責めなければ、きっと満足できない。では、どんなことをしたらいいのだろうか……? 自然と、一つ思い浮かんだ。だが、それは、あまりにも不潔な行為で、変態性が強すぎ、同時に、同性愛的な匂いもするので、却下だ。明日香やさゆりの目だって、気になる。香織は、プライドの高い人間だった。クールでニヒル。そんなふうに思われていたい。気持ち悪い女なんて思われるのだけは、耐えられない。 それでは、涼子に憧れている後輩たちを、片っ端から体育倉庫の地下に集めて、彼女たちの前で、涼子にストリップショーをやらせる、というのは……。これならクールなやり方だ。だが……、現実的ではない。涼子を縛りつけて、どこかに吊し上げるというのも、何か違っている。 前回以上の激しさであり、それでいて変態的な雰囲気が漂わない、そんなやり方は、案外、探すのが難しい。 香織は、焦燥にも似た思いを抱いた。まずい。このままでは、次回あたりにはもう、快楽の時間が終わってしまう。なんとかしなくては……。 これからは、涼子をなぶるのにも、何か工夫が必要だという結論に至る。よいアイディアはないだろうか。イメージとしては、もっと、こう、別の角度からも、涼子を責めていくような……。そんなやり方を、思い付ければいいのに。なかなか難しい。なぜかこういう変な時に、自分は、天才的能力を発揮するのだが。 もう少し、涼子の視点に立って考えてみたほうが、いいかもしれない。涼子が、何をされたら嫌がるか。涼子が、嫌なもの、苦手なもの……。 あっ……。 香織は、頭上に、何か光り輝くものが舞い降りてきた気がした。 そういえば、あったのだ。涼子には、そんなものが。いや、ものではなく、人間、このクラスの生徒だが。 香織が目撃したワンシーンが、閃光となって眼前によみがえる。 涼子は、どうにか仲良くなろうと、思い切った様子で話題を振った。しかし、滝沢秋菜は、素っ気なく一言、二言返しただけで、横を向いてしまう。その口もとに、苦笑めいたものを滲ませて。 会話は、それで終わってしまった。 その時の、涼子の様子は……。軽く下唇を噛んだ表情は、自分のふがいなさを反省しているかのようだった。もじもじと指をいじっているのは、だいぶ気まずさを感じているためだろう。どことなく、乙女チックな恥じらいにも似た仕草だ。あの、さばさばとしたボーイッシュなバレー部のキャプテン、南涼子も、そんなところを見せるのだ。滝沢秋菜が相手だと。 苦手意識。涼子のあの姿には、それが、はっきりと表れていた。 苦手意識。ニガテ、イシキ。苦手な子。ニガテナ、コ。香織は、声に出してみる。なんだか、妙に甘美な響きに思えてくる。 もし、涼子のそんな、相性、苦手意識、気まずさ、恥ずかしさ、といったデリケートな部分を、蹂躙することができたら……。 「うわぁ……」 突然、うっとりするほど美しい景色が、眼前に広がったかのように、香織は、つい声を漏らしていた。なんて素晴らしいだろう……。 でも、どういった方法で? 香織たち三人で、そのことを徹底的にからかってやる、とか……。 いや、待てよ……。 その時、秋菜の声が、脳裏に響いた。穏やかな声ではない。その言葉は、香織にとって、立ち尽くすほど衝撃的だったので、ほぼ完全な形で思い出せる。 『なんで、あの子、わたしたちの中に、入ってくんの? ノリは変だし、くだらないことで盛り上がるし……。ホンット、うざいんだけど』 香織は、それを、脳内で何度もリピートするうち、ふと、悪魔のような考えが浮かび、我ながら、ぞくっとした。 それだったら……、涼子を責めるのに、『秋菜本人を』使えばいいんじゃないの……? 秋菜がその気になるなら、香織たちが全面的にバックアップする。つまり、秋菜と手を組むのだ。 このアイディア、けっこう、いけるかも……。 ここで、涼子を嫌っているのが、別の生徒だったら、話は違っていただろう。いやむしろ、期待はできなかった。いくら嫌いな相手とはいえ、なぶりたいとまでは、なかなか思わないはずだから。しかも、微妙に変態的に。 けれども、滝沢秋菜なら……。秋菜の性格の悪さは、二年前、嫌というほど思い知らされた。あの、芝田さんへの仕打ちは、香織ですら、見ていてげんなりしたほどだ。三年になった今でも、秋菜の内面は、本質的には変わっていないと、香織は睨んでいる。そのダーティーな面を、表に出さなくなっただけだ。そもそも、あの太陽のような涼子を、避けるほど忌み嫌っているという時点で、性格が歪んでいるのだ。 だが、今の香織にとっては、その性悪さが、光り輝くほど魅力的に思えてならない。秋菜なら、やる、と言ってくれるのでは……。 しかし、いくつか問題がある。秋菜は、涼子との相性が最悪なのは素晴らしいが、香織とも、肌が合わなそうなタイプだということ。香織も、正直、秋菜のような雰囲気の生徒は、好きではなかった。一年の頃の秋菜を知らなくても、同じだっただろう。それに、仲間に引き入れることに成功したとしても、頭脳明晰で、自分の考えを持っていそうなので、香織がコントロールできるか、不安だった。明日香やさゆりとは違う。 けれども、このままでは、よくないのだ。涼子をなぶるにしても、香織には、すでに強い耐性が付いていて、ちょっとやそっとのやり方では、気持ちが高ぶらない。次回あたりには、得られる快楽も、半減するかもしれない。 それに、と思う。耐性は、下手をすると、涼子の側にも付くのではないだろうか。つまり、そのうち、香織たち三人の前で、服を脱がされているという状態に慣れてきて、その恥ずかしさも、だんだん薄れていく、というような……。怖ろしいことだった。考えたくもないことだった。そうなったら、すべては、無味乾燥なものに変わってしまう。 だが、涼子にしたって、その場に、秋菜が入るとしたら、物の感じ方も、まったく違ってくるだろう。なにせ、涼子にとって、同じ女とはいえ、苦手な子が、目の前にいるのだから。 涼子には、常に新鮮な恐怖や苦痛を与えたい。まずは、驚愕に目を剥いてほしいのだ。そうでなくては、始まらない。 そこまで考え、香織は、ぶるりと胴震いした。そして、秋菜が欲しい、と渇望する。 秋菜は、毒を持っている生き物だ。それも猛毒だ。だから、秋菜をそばに置くのは、リスクが伴う。最悪、香織が噛まれて、えらい目に遭うかもしれない。けれども、その毒が、涼子の体に注入されるとしたら……。きっと、激痛にのたうち回る涼子の姿は、さぞかし絶景に違いない。また、それを眺める自分は、クールだ。 香織は、逸る気持ちを抑えられず、その日の昼休みにはもう、それを明日香とさゆりに話していた。明日香は、あっさりと了解してくれた。誰とでも、そこそこ巧くやる自信があるのだろう。だが、さゆりは、まったく面識のない先輩ということで、少し渋った。そんなさゆりを、別に秋菜と仲良くしなくてもいいからと、なんとか説き伏せたのだった。 そして、同日、六限目の体育のことで、場所は、体育館だった。香織は初めて、秋菜と話らしい話をした。あの時のことは、アルバムの一ページのように忘れられない。 授業はバスケットで、体育館のフロア全体が、ネットで二つに分けられ、ステージ側で試合、出入り口側でシュートやパスなどの練習が行われていた。 香織は、出入り口側にいて、時々ボールを弾ませながら、ずっと秋菜の動きを目で追っていた。秋菜と二人で話ができるような、チャンスを窺っていたのだ。番号やメアドは交換していないし、放課後、捉まえるというのも変なので、こういう時しかないのだ。 話す内容は、頭に入っている。虚実を取り混ぜた一つのストーリーを、授業中に考えておいた。自分の身は、常に安全圏に置きながら、エサで、少しずつ少しずつ、秋菜を引き寄せてくる。そんな話術が要求される。決して深追いはしてはいけない。秋菜には、隠れた危険な牙がある。下手をすると、こちらの命取りになりかねないのだ。 今だ。そう思った。 秋菜が、ひとりで、壁際に腰を下ろしている。彼女から一番近くの生徒も、ある程度離れたところにいる。 香織は、変に思われないよう、ボールを持ったまま、さり気なくそこへ向かった。もしかしたら、相手にもされないかも、という不安で、胸が苦しかった。だが、これを乗り越えたら、すごいことになるかもしれないのだと、自分を鼓舞する。 すぐ隣に座る勇気は、さすがになかった。ああ疲れた、というふうに、香織は、そばに腰を下ろす。 秋菜は、ちらりとこちらを見た。だが、それだけだった。体を動かすため、髪をポニーテールに結び、体操着の白いシャツと紺のハーフパンツ姿の秋菜は、普段より、子供っぽく見える。(この体操着のシャツが、二日後、涼子の体液で汚れることになる。) 少し間を置いてから、香織は、意を決して声を掛けた。 「あっ、ねえ……、滝沢さんって、バスケやってたの? 巧くない? シュートとか、遠くから、よくゴールに届くね……」 まずは、当たり障りのないことから。秋菜を上手だと思っていることは、本当だった。 案の定、秋菜は、きょとんとした。 「えっ……、べつに、やってたことは、ないよ。シュートなんて、ふわっと飛ばしてるだけだし」 秋菜の口もとには、微妙な笑いが浮かんでいる。なんで、この子が、話しかけてきたんだろう、という感じの。 「ふわっと……、かあ。やっぱり、腕の力が必要なのかな……?」 香織は、適当に話をつないだ。 「うーん……。案外、ジャンプのほうが、大事かも……」 秋菜は、ちゃんと答えてくれたが、早くも気まずそうに、視線をそっぽへやった。 どうやら、香織と仲良くなろうという気は、ほとんどないらしい。これ以上、たわいないやりとりを続けるのは、無理な空気だった。 ひどく不自然だが、もう本題に入る。 「そうだ……。滝沢さん、あの、すごいこと知っちゃったんだよね……」 香織は、そう切り出し、ごくりと生唾を飲み込んだ。 秋菜は、小首を傾げてこちらを見ている。 「南さんって、いるじゃん? うちのクラスの、あの、南さん……」 秋菜の片側の眉が、ぴくりと動いた。だが、秋菜は、無表情のまま、うん、と小さく頷いただけだった。 ダムダム、とボールの弾む音が、あちこちから途切れることなく響いている。ステージ側のコートでは、試合の中のかけ声が上がる。そんな中で、香織は口にした。 「うちの学校の、何人かの子から、よく、リンチみたいなことされてるみたいだよ。あたし、その現場、見ちゃったんだよね」 秋菜が毛嫌いしている女の悲劇。このエサで、秋菜が、何も興味を示さなければ、そこで話は終わりにし、計画も取り止めるつもりだった。 「ええっ……? なにそれ……?」 ポーカーフェイスが崩れた。秋菜の顔には、驚きと共に、うっすらと興味の色も漂っているように見える。 よし……! 香織は、思い切って、秋菜のそばへにじり寄った。これで友達同士の距離になった。 「あたしさ、学校から帰る前に、友達と煙草吸っていくことが多いのね。体育倉庫に、地下があって、いつもそこで、吸ってるんだけど……」 煙草は、一度だけ友達から貰って吸ったことがあるが、ひどくむせて苦しい思いをしたため、それきり手を出していなかったが。 「えっ、意外……」 秋菜は、一言、そう言った。悪いことなんて、しなそう、できなそうなのに、と言いたげだったので、香織は、わずかに気分を害される。ただ、今は、そんなことはどうでもいい。 「それで、昨日も、友達と二人で、体育倉庫の地下に降りて、吸おうとしたんだけど……、そうしたら、すごい怒鳴り声と、笑い声が聞こえてきたのね。で、なんだろうって見たら、あの、南さんがいてさ……、三人の子に、取り囲まれてたの。で……」 香織は、意味ありげに言葉を切った。そこまで話して、緊張と不安は、ピークに達していた。 「で……、南さん、何されてたの……?」 秋菜の瞳に、期待の光があるように見えるのは、気のせいだろうか。 「南さん、服……、脱がされてたんだよね……」 香織は、声を落として言った。食いついてきてくれ……、と祈りながら。 秋菜の目が、かすかに見開かれた。 「ええっ? 待って……。脱がされてたって、どこまで?」 それが、クラスメイトを心配するような口調でないことだけは、確かだった。 悪くない反応だ。 「全部。ブラも、パンツも、全部……」 香織は、自分の胸、次に腰のあたりと、手で触れてみせた。 「うっそぉ……、それ、本当なのぉ? 嘘でしょう?」 言外に、本当なら、面白いけど、という響きがあるような気がした。秋菜は、半信半疑の様子だった。 話を信じさせるために、少々リスクを負う必要があった。 「ホントホント。じゃああとで、南さん本人に、確かめてみ? 昨日の放課後、体育倉庫の地下で、何をされたか」 香織は、強気に言ってやった。涼子を避けている秋菜が、涼子本人に、いきなりそんなことを尋ねるような行動には、出ないだろう、という計算があったのだ。昨日の放課後、涼子が、体育倉庫の地下にいたという点は、事実であるが。 秋菜は、戸惑うように口もとに手を当てた。香織が、冗談で言っているのではないことが、どうやら伝わったようだ。しかし、ショックを受けているふうではなかった。 「その、三人の子って、誰なの……? 吉永さん、知ってる人?」 犯人の名が知りたいのは、当然だろう。 「みんな、商業科の子だったから、名前は知らなかったんだけど……」 商業科の生徒は、三年間、A組かB組と決まっており、普通科の生徒と同じクラスになることはなかった。 「ひとりの子が、名前、あたしたちに『教えてくれて』、山本さんって子だった」 聞いていた秋菜の顔に、強い違和感の表情が浮かんだ。 「ちょっとちょっと待って。吉永さんたちは、その、三人の子と、『普通に』喋ってたの?」 秋菜は、親指の爪をかじりそうな仕草を見せている。涼子の服を脱がしてしまうような生徒たちと、涼子を尻目に、コミュニケーションを取っていたのかという意味だ。 「ああ、うんっ。その子たちが、あたしと友達の二人を見て、『こっちおいでよ』って言ったの。だから、そのとおりにして……、一緒に、『見物』してた」 香織は、のんきな口調で言ったが、ここは、一つの山場だった。 今、秋菜の頭の中では、その場面の、香織たちの位置関係が、修正されているだろう。秋菜は、思っていたはずだ。香織たちは、物陰からこっそり覗いていたか、あるいは、その陰惨な光景を目に焼きつけた後は、自分たちに害が及ばないよう、すぐに、そこから立ち去ったかしたのだろう、と。だが、あろうことか、香織とその友達は、加害者連中の輪に加わっていたという。それでは、香織たちのスタンスというものは、第三者というより、加害者寄りではないのか……。 「えええ……。一緒になって、南さんのそんな姿を、見物してたの? あっらーん」 秋菜は、間の抜けた声を出した。どこか愉快そうに。 香織は、大きな手応えをつかんだ。加害者たちにほとんど同化していたという、香織に対して、秋菜が、怒りもしなければ、不快感を示しもしなかったということ。それは重要なポイントだった。 「話の続きなんだけど……、南さん、その子たちに、弱味、握られてるんだよね。南さん、バレー部のキャプテンじゃん? なのに、学校の外で、何か問題を起こしちゃったらしくってさ、それが、どんなことなのかまでは、その子たちも、教えてくれなかったんだけど、でも、もしそれが、学校に知られると、バレー部自体が、大会に出られなくなるようなことみたいで……」 秋菜は、しっかりと耳を傾けていて、うんうんと頷き、先を促す。 「だから、その子たちが、『あのこと、学校にチクるよ』って脅すと、南さん、『それだけはやめて』って、なんでも、言いなり状態なんだよね」 弱味、脅迫……。この、卑劣極まりない加害者たちに対しても、秋菜は、別段、憤りを感じている様子はなかった。 秋菜は、体育座りした膝に頬杖をつき、しんみりと言う。 「南さんが、何をやらかしたのか、知らないけど……、バレー部全体に迷惑が掛かるとなると、自分を犠牲にせざるをえないかもねえ。でもそれで、人前で、下着まで脱がされるなんて、惨めねえ……」 かわいそう、ひどい、といった言葉ではなく、『惨め』と表現するのは、秋菜には、涼子を心配する気持ちが、かけらもないことの証拠だと思う。 「ほんっと。すっごい惨めだった。あの南さんが、裸にされてて、あそこだけ、両手で隠して立ってんだもん。恥ずかしいのか、体がぷるぷる震えてるのまで、わかったし……」 香織の調子も、だんだんと熱を帯びてくる。 「やっだーん。その光景、想像すると、こっちまで恥ずかしくなってきちゃう……」 秋菜は、しっとりとした声で言った。やだ、なんて言っているが、少しも嫌そうではなく、その口もとは、薄ら笑いに歪んでいるようにしか、見えないのだが。 ふと、秋菜の視線が、遠くに向かった。体育館のフロアを二分するネットの向こう、今、試合中のコートのほうだ。 ボールを追いかけて走る生徒たちの中に、話題の涼子の姿もあった。涼子の専門はバレーだが、バスケットでも、その存在感は際立っている。ディフェンスで相手に張りつく姿など、まるで鬼神のようだ。 「はいっ!」 涼子の声が響く。 味方からパスを貰った涼子は、相手を蹴散らすような勢いでゴール下に攻め込み、レイアップでシュートを決めた。 秋菜は、そんな涼子の様子を、奇異なものでも見るように眺めている。 次のステップに進むための条件は、クリアしていた。その条件とは、被害者である涼子への同情も、話の中の加害者たちへの義憤も、秋菜が、感じていないこと。いくら嫌いな相手とはいえ、クラスメイトの女の子が、女として最大の屈辱を味わうような思いをさせられたのだ。正義感に燃え、その加害者たちが許せないと言い出しても、なんら不思議ではなかった。だが秋菜に、そんな気配は、さらさらない。 秋菜に、次のエサをちらつかせる段階に入ったと、香織は判断した。 「あたしたち、その子たちと『仲良く』なっちゃってさ……。二日後、また、同じ場所に、南さんを呼び出すから……、あなたたちも、おいでよって、誘われたんだよね。昨日の二日後……、つまり、明日ね」 秋菜は、何かを考えるように目をしばたたいた。 スイッチを入れる時が来た。 「あたし、『面白かった』から、また、見に行こうかと思ってるんだよね。だって、南さん、あたしの顔見ると、同じクラスの子には、こんな姿、見られたくなかった、みたいに、泣きそうな顔になって、逃げだそうとしたんだよ。あれには、『笑っちゃって』さあ……。次、見に行く時には、ほかにも、『誰か誘って』」 まるで悪魔の人格が表面に出てきたかのように、香織は、おどろおどろしい内容の言葉を吐き出していく。 さすがの秋菜も、大きく息を吸い込んだような顔をしていた。だが、ほどなく、秋菜は、何か言いたそうに、そわそわとし始めた。毛嫌いしている女の悲劇。それに対する強い好奇心で、クールな仮面が、剥がれていきそうな印象を受ける。 ほらっ。極上のエサのはずでしょう。言いたいことがあるなら、自分で、はっきりと言わないとダメだよ。香織は、横目でその様子を窺いながら、そんなふうに思っていた。 言葉が出てこないのは、感情に思考が追いつかないためなのかもしれない。この、頭のいいはずの秋菜が。けど、無理もないか。仕方がない。 「あっ……。滝沢さんも、一緒に見に行く? 大丈夫だよ、その子たちの前だと、南さんなんか、全然怖くないから……」 その言葉で、秋菜の顔に、ぱっと光が当たったかのようだった。 「わたしも、見に行きたい」 秋菜の両手は、ガッツポーズ寸前のような状態だった。 性格最悪。いくら嫌いだからって、南さんの、そんな姿まで見たがるなんてね……。香織は、心の中で毒づいた。むろん、それは賛辞の言葉に他ならなかった。ありがとう、性格の悪い滝沢さん。あなたなら、そう言ってくれると信じてた。 「じゃあ、もうちょっと詳しく話すから、場所、変えない? ここだと、話してる途中で、人が来そうだし……」 香織は、そう言って腰を浮かせた。 秋菜も、うん、そうしよう、と素直な子供よろしく付いてくる。ポニーテールの髪型のせいもあるのか、こうしていると、秋菜にも可愛げがある。 体育の教師は、授業の初めと終わりしか顔を出さないようないい加減さだったので、体育館内なら、どこへ移動しようと問題はなかった。 香織は、バレー部やバスケット部の部室の前を通り過ぎ、階段で二階に上がると、フロアを見下ろすギャラリーのそばで、足を止めた。秋菜も、うきうきとした様子で止まる。 最後に、大仕事が残っていた。だが、ここまで来て失敗に終わるとは、正直思っていない。 「ごめん、滝沢さん。あたし……、嘘、ついてたんだ」 香織は、そう切り出した。 秋菜の顔色が変わった。これまでの話が、全部、嘘だったということ……? そんな静かな怒りが、腹の底から湧き上がってきているのだろう。秋菜の眉間に、しわが刻まれるのが見えた。 すごい迫力だった。さすがは滝沢秋菜。このまま黙っていれば、胸ぐらをつかまれそうだった。でも大丈夫。あなたの期待を裏切るようなことは、しませんから。 「実は……、南さんを、取り囲んでた三人っていうのは、商業科の子なんかじゃなく、あたし自身と、あたしの友達なんだ……。つまり、あたしは、偶然、その場に来た野次馬なんかじゃなく、実行犯? みたいな」 香織は、へへっと苦笑して見せ、上目遣いで秋菜の顔色を窺った。 「えっえへえ……? 吉永さんと、吉永さんの友達が、南さんの服、脱がしたりしてた、ってことなの……?」 秋菜は、優しいお姉さんのように態度が崩れていた。 「そう。だから……、南さんの弱味握ってるのも、体育倉庫の地下に呼び出してるのも、全部、あたしたち……」 さすがの秋菜も、度肝を抜かれたらしい。秋菜は、すがるように香織の腕にちょこんと触れた。 「なんでなんで……? 吉永さんは、なんで、南さんに、そんなことするようになったの……?」 嘘をついていた理由より、話の細かい部分より、まず、それが知りたいらしい。 だが、本当のことは、口が裂けても言えない。涼子への憧れの思いが強すぎて、ふとしたきっかけで、それが屈折し、歪んだ悪意に変わったなどとは。 「だって……、南さんって、もう、なんて言うか、やることなすこと、全部、吐き気がするほど、気持ち悪くない? ムカつくってレベルじゃないんだよね。だから、思いっきり痛めつけてやりたくなって。で、一度やったら、面白すぎて、やめられなくなっちゃってさ……」 あたしたちは、同志なんだよ、滝沢さん。いや、あたしは、あなたの師に当たるのかな。 秋菜は、偉人を見るような眼差しで、香織を見つめていた。 香織は、真実をかいつまんで語り始めた。バレー部のマネージャーである明日香と、後輩のさゆりという、二人の仲間がいること。バレー部の合宿費を盗み、それを利用して涼子をハメたこと。涼子の全裸の写真をすでに撮っており、涼子は、きっと次も、言いなりになるしかないだろう、ということも。 だが、この話をする相手として、秋菜を選んだ経緯や理由については、話をねつ造した。以前、涼子が、友達に、秋菜との関係が巧くいかないと、真剣に相談しているところを、偶然聞いてしまったということにした。本当のことを話したら、ドン引きされるに決まっている。どうしても涼子と秋菜の関係が知りたくて、二人のそばに張りついて監視していたなんて。 香織が話し終えると、秋菜は、柄にもなく少し照れながら、自分からこう言った。 「ねえ、吉永さん。わたしも……、そのメンバーに交ぜてよ」 天は、香織に味方してくれた。いや、味方したのは、天にいるものではなく、悪魔だったのかもしれないが。どちらでもいい。体育の授業が終わり、体育館を出て、雲のかかった空を見上げると、香織は、涙が出そうになった。それほどの悦びだったのだ。逆に、南涼子という人間は、どこまで運から見放されているのだろう……。同情しちゃうよ、南さん。 滝沢秋菜獲得で味を占めた香織は、欲が出てきて、もう一人くらい、仲間に引き入れたいと思うようになった。涼子に対して、絶望という名の外壁を、もう一枚、築くように。 誰が適任だろう……? それを考える時、涼子の視点に立つ、ということを忘れてはならない。涼子は、どんな子が目の前に立っていたら、嫌なのか、恐怖を感じるのか、そして、恥ずかしいのか。すぐには思いつかなかったので、明日香とさゆりに相談することに決めた。 もう止まらない……。あたしは、おまえのことだけを考えて、高校生活を送ってるんだからね……。南涼子。 そして……。 香織と秋菜の前で、涼子が、ラブレターを手渡して走り去る女子生徒のような雰囲気を漂わせながら、教室を出て行き、その後、静かな時が刻まれていた。 秋菜の机の上には、『メッセージ』である保健の教科書が載せられている。そこに貼りつけてあるのは、涼子の全裸の体に、秋菜の顔という、アイコラ的組み合わせの写真だ。あたかも、秋菜が、ヘアヌードを晒しているかのような絵となっている。 秋菜は、それをじっと見つめている。 その時、秋菜の口から、ふふっ、というかすかな笑い声が漏れた。その笑いは、痙攣を起こしたように続き、たちまち品のない大笑いに変わった。秋菜は、腹を抱え、机に頬をこすり付けるようにして笑っている。 香織は、思わず顔をしかめた。もし、涼子の耳に届いたら、どうするというのだ。 「吉永さん、見た……? あの、南さんの、顔。わたしが、この裸のこと、『これ、大人っぽくない?』って言ったとたん、真っ赤になってんの。ゆでだこみたいだった」 秋菜は、興奮気味に言うと、気だるそうに体を起こした。 「南さん、よっぽど恥ずかしかったんだろうね……。ただ、滝沢さんが、打ち合わせと違うこと、いきなり言い出したからさ、あたし、アレって思っちゃったよ。まあ、結果的には、面白かったから、よかったけど」 涼子には、こういうセリフを言わせるから、それに対して秋菜側は、こんなふうに返す……。秋菜とは、そんな感じで、事前に、話の大まかな流れについて、打ち合わせをしておいたのだ。涼子を突き刺した、秋菜のその発言は、完全にアドリブだった。 「だってさあ、ちょっとこれ……」 秋菜は、苦笑いを浮かべながら、写真を指差す。一緒に見てよ、と誘っているらしい。 香織は、座っていた椅子ごと、秋菜の隣へ移動する。 「わたし……、最初に見た時、ぎょっとしちゃったぁ。なによ、この、からだ」 秋菜は、信じられないとでもいう口調で言った。 もう、香織は見慣れた写真だが、秋菜は、涼子の全裸姿の写真を目にすること自体、これが初めてだったのだ。そして、目の前にあるのは、中でも、もっともどぎつい一枚だった。 全裸で、囚人のように両手を頭の後ろで組んでいる、涼子の肉体。背景は、じめじめとした体育倉庫の地下だ。顔がくり抜かれているせいで、何か不吉なイメージを喚起し、顔がそこにあるより、よけいに陰惨な雰囲気が漂っている。 その写真は、万人に見せるために本として出版される、アイドルのヘアヌードのような、一種の美しさを表現したものとは、根本的に別物だった。そこにあるのは、一人の女の、剥き出しの不潔さや、恥といったものだ。裸体のアクセントとなっている、逆三角状の黒い炎のような陰毛もそう。容赦のない写し方のため、よく見ると、腋の下の、ざらりとした剃り跡まで確認できてしまう。上腕や肩、太ももなどに顕著な、女子高生離れした筋肉美も、部活の練習後だったせいか、うっすらと汗ばんで見え、発汗量のすごさを物語っていて、汗臭さが容易に想像できるようだった。 唯一、悪意ある撮影にもかかわらず、みずみずしい果実のような、形の整った乳房だけは、女性としての美しさを湛えているといえるのが、せめてもの救いかもしれない。 秋菜が毛嫌いしている女の、正視に耐えないような無惨な姿。今、秋菜の目には、それが、どんなふうに映っているのだろうかと、香織は興味を覚える。 「なによ、この、まん毛は……。ここまで生えてると、この中に、昆虫の一匹か二匹、棲み着いてるんじゃないの……?」 やはり秋菜も、まずそこを指摘し、涼子の下腹部を、指でぴんと弾いた。さすがの香織も、うなじの毛がちりちりするような比喩だった。 「写真より、実物のほうが、ずっとすごく見えるよ。南さんのそこ、初めて見た時は、あたしたち三人とも、馬鹿にする言葉すら、出てこなかったもん……」 いずれ秋菜も、写真ではなく、実物のそれを確認する時が、来るだろう。 「それに、なに、この、筋肉は……? オリンピック選手でも、目指してるわけ? こんなのに襲いかかられたら、わたし、ひとったまりもないんですけど」 涼子の血の滲むような鍛錬の賜物を、秋菜は、さげすむように言う。 「まあ、そのパワーは、あたしたちが、もう、完全に使えないようにしてあるから、心配することはないよ。反抗されてムカついたら、ビンタ張ってやったって、平気だから」 香織と秋菜は、目を見合わせた。まったく、吉永さんは、悪い子なんだから……。 秋菜の涼しげな眼差しは、そんなふうに語っていた。 「ああーもう、この写真見てると、なんか、臭ってきそう……」 秋菜は、鼻を押さえ、冗談めかして手を振った。 「滝沢さんに、そんなこと言われてたって、知ったら、南さん、ショックで、気、失うかもよ」 香織は、くくくっと笑った。 「吉永さん。今頃、南さんが考えてることを、わたし、当ててあげるよ」 秋菜は、なにやら、目を細めて口を半開きにし、切なそうな表情を作って、言い始めた。 「どうしよう、顔が真っ赤になっちゃったから、もしかしたら、あの裸が、わたしの体だって、滝沢さんにバレたかも……。恥ずかしい。怖い。明日っから、顔を合わせられない。こんなことなら、いっそ、滝沢さんも、わたしみたいに、服、脱がされちゃえばいいのに……。って」 秋菜は、舌をちょろりと出しそうな表情をした。 「本当だよ。間違いないよ。わたしには、わかる。今頃、南さんは絶対、こう思ってるから」 そう言われて、香織は、涼子の心理を想像してみた。たしかに、そんなふうに考えているかもしれないな、と思う。いや、きっとそうだ。涼子は、だんだん、自分本位、自分のことしか考えないような、人間として醜い部分が、目立ち始めてきている。 「あっ……、ありえる!」 香織は、勢いよく同意した。そんな自分勝手な考え、許せない。まさに幻滅ものではないか。そして、そういうのは、面白くて仕方がない。 秋菜は、身を乗り出し、人差し指を振って、饒舌に喋る。 「さっきもさ、あの……、南さんが、『もし、滝沢さんが、この写真の人みたいな目に遭わされたら、どうする?』って、わたしに言った時、あるでしょう?」 香織が涼子に言わせた、最後のセリフのことだ。 「その質問に、わたしが、『人前で服を脱ぐなんて、そんな気持ち悪いこと、わたしは、まかり間違っても、しない』って、突き放すように答えたの。そうしたら、南さん……、なんか、ちょっと寂しそうな顔してんの」 秋菜は、肌寒そうに両手をさすり、涼子への嫌悪感を示した。 なるほど、と香織は思う。 「ああつまり、南さんは、滝沢さんのことを、『仲間』みたいに思ってたのに、なんだか、自分ひとりだけ、取り残されるような気がしたんだろうね。滝沢さんもハメられて、脱がされちゃえばいいのに、みたいな?」 香織は、自分なりの分析を口にした。 秋菜は、腋をくすぐられているかのように、全身で快感を表現した。 「そうそうそう……! 滝沢さんは、こんな目には遭わないのかな、もしかして、滝沢さんは、助かるのかな、仲間だと思ってたけど、なんだか、距離が離れていくように感じる……、っていうような、寂しそうな顔、見せてたから……。わたし、見てて、へどが出そうになった」 秋菜は、吐き捨てるように言うと、無惨な涼子の写真が貼られた教科書を持ち上げ、そこに語りかける。 「残念、南さん……。こんな惨めな目に遭うのは、あんただけなの。わたしが、こんな恥ずかしい格好、するわけないでしょう? わたしは、あんたとは違うの。ひとりで頑張ってね。……今度、わたしも、その姿、見に行ってあげるから」 ふふっと秋菜は笑う。二年前、秋菜が、芝田さんのスケッチブックにいたずら書きをしていた時、彼女の顔に浮かんでいた、あのサディスティックな薄笑い。今、香織は、なぜかそれを思い出していた。 つと、秋菜は、香織に向き直って言う。 「あっ、そうだ……。結局、どこまで脅したら、南さん、わたしの写真を盗んでくることを、決めたの?」 秋菜の写真を、涼子に盗んで来させるということ。あれは、なにも、秋菜の写っている写真を、香織たちが必要としていたわけではない。涼子に、『盗ませること自体に』意味があったのだ。秋菜が言うには、自分の身を守るために、他人を裏切るような行為に走るのは、人間として、もっとも恥ずべきことらしい。そして、それを、あの、正義感や責任感を絵に描いたような、南涼子にやらせたい、と秋菜は強く望んだ。むろん、その写真は、秋菜が、わざとバッグの中に入れておいたのだ。 そして、今日の昼休みの時間、ひと気のないトイレで、涼子に対して、一種の『テスト』を行った。香織たちは、涼子に写真を盗ませるため、『段階的に』脅迫した。第一段階は、検尿。第二段階は、検尿プラス、ギョウ虫検査。最終段階は、汚れた秋菜の体操着と、その犯人が涼子であることを示す写真の、二つのセットを、秋菜本人に送りつけるというものだった。要するに、軽い段階で心が折れ、盗みを引き受けるほど、涼子は、人間として卑しいという評価となる。 香織は、その時のことを思い返しながら、少し逡巡していた。涼子は、最終段階まで、盗みを拒絶したのだ。香織にとって、それは、面白味のない結果だった。秋菜も、同様に感じるはずだ。 だったら……。 「ああ、それねえ……。写真、盗んでこなかったら、放課後、トイレで、また、服、脱がすよって、かるーく脅した程度で、あの子、あっけなく、『わかった、盗んでくる』って、言ったよ。盗んでくるから、もう、ひどいことは、やめて……、みたいに」 香織は、嘘を口にした。事実を話しては、興ざめだと思ったのだ。それに、秋菜は、涼子への脅しについては、最終段階の内容しか知らないので、検尿だのギョウ虫検査だのと、悪趣味な発想で脅迫をしたことは、なんとなく話すのが憚られた。 「ええ……? それ、本当?」 秋菜の眼差しに、懐疑的な光がある。あの南涼子が、そんなに弱いはずはないんだけど、と疑っているのだろう。 ここは、勢いで押し通そう、と香織は決めた。 「うん、ホント。あの子、もう、自分のことしか、考えてない感じで……、だから……」 「吉永さん。それ、本当……?」 秋菜は、香織の言葉をさえぎり、もう一度、静かに言った。 香織の勢いは、急停止してしまった。なんだか、冷徹な大人のお姉さんを相手にしているような気がしてくる。 「あっ……、あれっ、ちょっと違ったかな……」 香織は、へどもどしながら、今一度、ちゃんと思い返すフリをした。なによ、白けさせないでよ……。 「そうだ、最後の段階まで、行ったんだった。南さんのまん汁で汚れた、滝沢さんのシャツと、南さんが、それをやってる決定的瞬間を写した写真の、二つを、滝沢さんに送りつけるっていう、脅迫まで」 香織は、ばつが悪くなった。 「うーん、やっぱりそうか……。そうだよねえ。南さん、正義感の強い人だもんねえ。精神的にもタフそうだし。ちょっとやそっとの脅しじゃあ、悪事に手を染めるようなことは、しないだろうねえ」 秋菜は、ようやく納得したように、また、やや残念そうに、そう言った。最後の『切り札』を使えば、涼子といえども、盗みを引き受けざるをえないだろうことは、香織も秋菜も、予想が付いていたのだ。むしろ、涼子のような真面目な生徒だからこそ、最終段階の脅迫内容は、脅威だったに違いない。最悪の場合、高校生活が破滅するという事態が、涼子の頭には、浮かんでいたはずだから。 香織は、舌打ちしたい思いだった。これではまるで、秋菜の中で、涼子の好感度が上がり、逆に、香織の信用度が落ちてしまったみたいではないか。なんとかして、涼子の名誉を貶めなくてはならない。そうすることが、自分の名誉回復にもつながる。このままでは、気が済まない。 と、そこで、香織の脳裏に、ある一場面が浮かび上がった。そうだ……! 「あっ、でもでもでも……、あいつ、すごい気持ち悪かったんだよ」 香織は、反転攻勢に出るような意気込みだった。 秋菜は、ぼんやりと小首を傾げている。 「あたしがさ、『今、あたしたち、滝沢さんに、目、付けてるんだよね』って言った瞬間……、あいつ、なんか、ちょっと期待するように、ほっぺたが、かすかに緩んだの……。これは、助かるチャンスかも、みたいに、計算してる顔だった。あたし、それ、見逃さなかったもん」 これは嘘ではない。少なくとも、香織の目にはそう映った。あの時、香織は、涼子の内面のさざ波を読み取るがごとく、その表情や仕草に、神経を集中していたのだ。 「それ、ほんとーう!?」 一転、秋菜は、興奮した声を上げた。今度は、疑わしげな表情などではなく、きらきらと目を輝かせている。 「ホントホント。そうだ、あとさ、あと……、滝沢さんに、メッセージ届けるっていう時だって、あいつ、『そんなの、滝沢さんの机に、勝手に入れておけばいいじゃん』とか言い出したし。あいつ、もう、自分が助かることしか、考えてないの。滝沢さんのことなんて、全然心配してないの」 香織も興奮して、唾を飛ばしそうな勢いで喋った。 「うっそーん……。なーんだ、南さんも、その程度かあ。そこらの子と、たいして変わらないんだあ……。それじゃあ……、わたしが、また、仲間と思わせるような芝居を打ってやれば、案外、ものすごい醜態、さらしてくれるかも」 秋菜は、うっとりとした三白眼の目つきで、なにやら想像を巡らしていた。 これで自分の名誉は、挽回できたという感じがする。香織は、得意な気分になっていた。 「もう、あいつ、人のものを盗んだから、窃盗で、立派な犯罪者だよね。しかも、このメッセージ、視聴覚室で発見したとか、滝沢さんに嘘ついて、渡すことまでしたし。こんなものを受け取る、滝沢さんの気持ちとかは、まったく考えずに」 秋菜へのメッセージ。それも、秋菜に対しては、なんの意味も持っていなかった。メッセージの目的は、『涼子の手で、それを渡させること自体に』あったのだ。まず、秋菜に嘘をつかなければならないので、また一つ、涼子の罪が増えることになる。そして何より、苦手意識のある相手に、自分の顔はくり抜かれているとはいえ、全裸の写真を見せなければならないという、そのじりじりとした屈辱感を味わわせるためだった。最後、秋菜の発言で、真っ赤になった涼子の顔は、傑作だった。 ふと、香織は、本質的なことを尋ねた。 「ねえ。南さんは、滝沢さんに、苦手意識があるわけだから……、苦手な子の見てる前で、ブラもパンツも脱がされるって、すごい屈辱じゃない?」 まさに、その点こそ、秋菜を仲間に加えたポイントなのだ。本人である秋菜の意見も、ここで聞いてみたいと思った。 秋菜は、はにかむように唇を曲げ、やや思案してから、答えた。 「うん、それはもう、間違いなく……」 香織と秋菜は、互いの目を見て、含み笑いをこぼした。 秋菜は、自分が涼子の脅威となっていることが、この上もなく嬉しい様子で、言い始める。 「わたし、南さんのこと、問い詰めるつもりなの。『どうして、わたしの写真、盗んだの?』って。徹底的に責める。謝ったくらいじゃ、許さない」 「そうだよね。滝沢さんは、写真を盗まれた被害者だもんね……。怒る権利があるよ。今度ばかりは、悪いのは、全部あいつだから」 あの真っ直ぐな性格の涼子が、秋菜に対し、どう言い訳をするのかが、愉しみだった。 「吉永さん。人間にとってね、自分を守るために、ほかの人を、あしげにするような真似をしたってことを、人から責められるっていうのは、すぅーんっごく、惨めなことなの。それも、自分だけ、服を脱がされてるなんていう状況だったら、もう、頭がおかしくなっちゃう」 秋菜は、両手の拳を握り、天にも昇るような仕草を見せていた。 「うんうん。……だろうね」 頭のいい子は、やはり、考えることが少し違うなと思いながら、香織は相づちを打った。つまり、涼子には、二重三重の地獄が襲いかかるわけだ。 「それでね、人間ってさ、自分が、惨めすぎる時って、なんか、脳の、大脳皮質とか、そのあたりが、異常を起こして、その影響が、表にも出てくるみたいなのね……。そうすると……」 秋菜は、一オクターブ声を低くし、うなり声のようなものを出した。 「うーうーうっうー……、みたいな、変な声を出し始めるらしいよ」 そして、秋菜は、にっこりと微笑んで付け加えた。 「南さんが、そんなふうになるところ、見てみたくない?」 その言葉に、さすがの香織も、背筋が薄ら寒くなった。 秋菜は、猛毒を持った生き物だ。今一度、それを再認識した。脳裏に、こんなイメージが思い浮かぶ。 体育倉庫の地下だった。部活の練習を終えた後、涼子は、そこに呼び出されていた。Tシャツとスパッツ姿だ。まだ、服は脱がされていないのだ。 涼子の視線の先には、秋菜がうずくまっており、不気味な微笑を浮かべている。涼子は、明らかに秋菜を怖がっていた。ようやく、秋菜が危険な生き物であることを、悟ったらしい。 『早く、前に進みなって』と香織は涼子を急かした。 しかし、涼子の足は、前に出ない。 『やだぁ。やめて……。わたし、こわい……』 涼子は、泣きそうに顔を歪め、首を振っている。 香織、さゆり、明日香の三人が、涼子の体を押さえにかかった。両腕を、それぞれ、さゆりと明日香がつかみ、香織は、後ろから、胴体に抱きつくような格好となった。Tシャツは、部活の練習で掻いた汗のせいで、じっとりと湿っている。いや、もしかすると、恐怖のあまり、全身から脂汗が噴き出しているのかもしれない。 『ちょっと! やだやだ、やめて、離して! 離してよっ!』 涼子は、パニックに陥った。 香織たちは、その暴れる体を、前へ前へと押し出していく。香織も、全力で押していた。涼子の逞しい上半身を、撫で回すようにしながら。 あと一メートルという距離まで迫ると、秋菜は、機嫌のいい猫のように、にんまりと笑ったかと思うと、突然、大きく口を開けた。どう猛な肉食獣のような牙が現れる。猛毒の牙だ。 涼子は、目を剥いて叫んだ。 『わかった! わたし、なんでもするから、それだけはやめてぇ! お願いだからぁ!』 どさくさに紛れ、香織は、涼子の乳房を揉み始めた。豊満な肉の潰れる感触が、掌に伝わってくる。 『そんなこと言って、本当は、興奮してるんでしょう?』 香織は、涼子のうなじに囁きかける。だが、涼子は、香織のそんな行為を気に留めている余裕すらないようで、荒い息を吐きながら、死に物狂いで秋菜から逃げようとしている。 秋菜が、ついに立ち上がり、ゆらりと涼子に歩み寄った。そして、キスをするような動作で、ためらいもなく涼子の首筋に噛みついた。毒牙が、皮膚に沈み込む。まるで吸血鬼だ。 『いったぁぁぁーい! やめてぇぇ! いたぁぁーいぃぃ!』 香織に、初めて肛門を見られた時以上の絶叫が、涼子の口から発せられている。秋菜は、首筋に食らいついたまま離れない。 涼子の肉体が、びくびくと痙攣し始める。香織は、その振動を、指が食い込むほど乳房を押し潰しながら、体で堪能していた。その時、香織の下腹部は、燃えるような熱を帯びていた……。 そこで、そのイメージは、すうっと頭から遠ざかっていく。 「南さん、滝沢さんのことが、怖くてしょうがなくなって、裸のまま、外に逃げ出しちゃったりしたら、どうしよう……?」 涼子の運命を思うと、香織は、なんだか同情の念すら湧いてきそうだった。 「もしかしたら、わたしのせいで、途中で、南さん……、オシッコ、漏らしちゃったりするかな? 人間って、恐怖が限界を超えると、失禁するっていうじゃない?」 その『オシッコ』という単語が、いやに生々しく聞こえた。秋菜は、下品な言葉を、それ以上はつつしむかのように、口もとに手を当てている。 「うっはぁ。裸で、おしっこなんて漏らしたら、流れ出てるのが、一発でわかるし……。ちょう惨めぇ」 香織と秋菜は、揃って下品な声を立てて笑った。 ふと、一年の頃を思い出す。秋菜に目を付けられた、可哀相な芝田さん。しかし、秋菜の本物の悪意を向けられる涼子に比べれば、あの芝田さんが、幸せな女子高生だったように思えてくる。 秋菜は、艶めかしい仕草で髪をかき上げると、しっとりとした声で言う。 「わたしって、性格がいいからさあ、わたしに対して、何もやってない子には、ひどいこと、できないんだよねえ」 嘘つけ。この、性格最悪のくせして。香織は、心の中でそう突っ込んだ 「でも、南さんは、わたしの写真を盗んじゃったから、アウト。このけじめは、きっちり取ってもらう。もう、まともな生き方なんて、できないくらい、プライド、ずたずたにしてやるから」 香織は、ごくりと生唾を飲み込んだ。 そして、秋菜は、机の上にある無惨な涼子の写真に、再び目を落とし、苦笑混じりに呟くのだった。 「それにしても……、きったならしい、体ねえ……」 香織の胸は、期待にどきどきと脈打っていた。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.