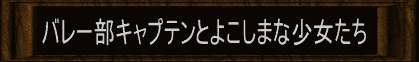
第二十章〜地獄からの脱出口
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
いつしか、ラブソングが大嫌いになっていた。だから、自分から聴くことはしないが、たとえば学校からの帰り道、街中を歩いていると、どこからともなく流れてくる。 あなたに、会いたいだけなのに……。 もう、絶対に離れることはないよね……。 二人、永遠に……。 別れの時が、こんなにつらいなんて……。 そういったフレーズを耳にするたび、無性にイライラさせられる。たかが恋愛のことで、そんなふうに深く思い悩んでいられたら、どれだけ幸せだろうか。 このところ、電車に乗っている間は、無意識のうちに人間観察をしていることが多い。その対象は、たいていの場合、自分と同じ女子高生である。スマートフォンをいじっている子。友人のお喋りを聞きながら、面白くもなさそうに相づちを打っている子。座席でウトウトしている子。そんな彼女らを横目で眺めながら、決まって考えるのだ。この子は、今、どんな悩みを抱えているのだろう? 友達関係。勉強。部活。家族のこと。恋。色々とあるかもしれない。しかし、これだけは断言できる。どれも、深刻じゃない。なぜ、それがわかるか。その表情を見れば、一目瞭然である。言葉で言い表せないほどの苦悩を背負っている女の子は、そんな平然とした顔をしていられない。 彼女らは、心にゆとりを持っている。ただそれだけのことが、どうしようもなく羨ましくて仕方なかった。というより、この感情は、ほとんど妬みに近いような気もする。 いや、同年代の少女たちだけではない。 電車を降りたところで、駅構内を見回してみる。 疲れた表情で歩くサラリーマンも。階段を急ぎ足で降りてくるOL風のお姉さんも。忙しく立ち回る駅員も。 誰も彼もが、自分とは比べようもないほど、安楽に生きているように思えてならない。 なんで、わたしばっかり、こんなに苦しまないといけないの……!? 南涼子は、もう数え切れないくらい、心の中でそう叫んでいた。 無間地獄。 一時たりとも、安息の時は訪れない。一日、二十四時間、地獄の苦しみに耐え続ける。誇張ではなく、それが涼子の生活だった。 あの、バレー部の練習場における、思い出すのも忌まわしい体験から、三度目の夜。 涼子は、部屋の電気を消すと、倒れ込むようにベッドに横たわり、布団をかぶった。 それから、一時間、二時間と、時間が過ぎていく。意識は、相変わらず覚醒したままだ。前夜も、また、その前の夜も、こうだった。泥沼に沈み込んでいるかのように、心身ともに疲れ果てているというのに、睡眠らしい睡眠を取ることができないのだ。ようやく、浅い眠りにつけたとしても、十分と経たないうちに、びくりと飛び起きてしまう。極度のストレスのせいで、自律神経が、がたがたになっているのは間違いない。だが、眠れぬ理由として、それ以上に大きいのは、明日への恐怖だった。震えて眠る、という言葉があるが、涼子の場合は、もっと悲惨である。一晩中、震えながら丸まっている。そういう状態なのだ。 しかし、それでも、布団の中にいられる間は、比較的、平穏な時間だといえた。 やがて、窓の外が白み始め、朝が来る。そして、とうとう、目覚まし時計の音が鳴った。 その瞬間から、自分自身との過酷な戦いが始まる。 すぐに体を起こすことは、不可能に等しい。布団のぬくもりに包まれている限りは、いつまでも現実逃避を続けてしまうのだ。だから、涼子は、寝たまま、ベッドから床に転がり落ちた。それが、起床の第一歩である。しかし、そうすると今度は、カーペットの床が、この世の何より恋しくてたまらなくなる。とてもじゃないが、身を引き離せそうにない。そういう時は、まず、おしりから持ち上げることを、涼子は学んでいた。もぞもぞと下半身を動かし、おしりを上に突き出す。イモムシのような格好になるわけである。しばらく、その無様な態勢を維持していると、徐々に足腰が痛くなってくる。もう痛くて無理だ、と感じたら、二つに一つだ。上体を起こすか、それとも、腰を床に落とすか。後戻りはしない。思い切って両腕を突っ張る。それから、雄叫びを発するくらい気力を振り絞り、勢いをつけて立ち上がる。そのようにして、涼子の一日は始まるのだった。 登校途中、ふと、これまでの高校生活の記憶がよみがえる。 南せんぱーいっ! 思えば、毎日毎日、後輩たちから黄色い声援を浴びてきた。 学校内において、自分は、それなりに有名な人間である。うぬぼれるわけではないが、そのことは、前々から自覚していた。もしかしたら、バレー部のキャプテン、南涼子を知らない生徒のほうが、むしろ少数派であるのかもしれない。普通であれば、名誉な話である。しかし、現在に至っては、そのネームバリューが完全に裏目に出ていた。 衝撃のニュース。なんと、あ・の・南涼子が、体育館のバレーコート上という、不特定多数の生徒が見ている場で、『吐き気がするような』痴態を演じた。南涼子は、変態的な性癖を持っている。その情報は、またたく間に、学校中を駆け巡ったのである。 学校の最寄り駅に降り立ってから間もなく、涼子は、その暗澹たる現実を突きつけられることとなる。 駅構内に散見される、自分と同じ制服を着た生徒たち。なかでも、数人で連れ立って歩く後輩グループは、涼子の姿を目にしたとたん、露骨な反応を示した。おのおのが、互いに顔を寄せ合い、こちらを見ながら、何事かささやき交わし始める。嫌なのは、彼女たちの眼差しだった。涼子のことを、好奇と侮蔑の入り混じった目で見ている。そのことが、一発でわかるのだ。 わたし、人にどう思われても気にしないから。涼子は、かねてから、周りの友人たちにそう豪語してきた。しかし、そんなのは、物事がうまくいっている間だけの、ただの強がりでしかなかった。今では、後輩たちから白い目を向けられることに、ひどく敏感になっている自分がいる。 バスの中は、当然ながら、同校の生徒たちがひしめき合っている状態だ。そのため、涼子は、早くも、息の詰まるような思いがしていた。 右から左から、おのずと聞こえてくる、ひそひそ声。 「あ、いたいた。噂の変態さんが……。なんか、しれっとした顔で登校してきてるのが、ウケる」 「部員の子が言ってたんだけど、もう、見てるほうが恥ずかしくてたまらなかったって」 「え? え? 具体的に、どんな格好だったの? 下は、きわどい水着みたいな?」 「今までずっと、部活一辺倒の生活を続けてきたせいで、案外、色々と欲求不満が溜まってたんじゃないの? それが、一気に爆発しちゃった、とか」 「でもさ……、羞恥プレイっていっても、学校内だから、女子しか見てないわけじゃん? 女子しか見てないのに、興奮とかできるものなの?」 それらの言葉が、涼子のことを指しているのは、もはや疑う余地もなかった。 涼子は、歯を食いしばるようにして、つり革につかまっていた。 その時である。 「うそぉ。その動画、実際に見た子いるの?」 「隣のクラスの子が見たって。めっちゃ汚くて、本当に、オエってなったって」 耳に飛び込んできた言葉を、頭の中で反復する。 次の瞬間、心臓の凍りつくような感覚を覚えた。 動画……? まさか、あの日、バレーコート上で起きていた出来事を、体育館にいた生徒の誰かが、なんらかの形で撮影していたとでもいうのか。そして、撮影者は、その動画を、ほかの生徒たちにも見せて回っている……。もしも、それが真実だとしたら、この先、どのような事態が起こるだろうか。 涼子の脳裏に、暗黒の情景が浮かんだ。 学校内を、涼子は移動する。教室、廊下、食堂、トイレ……。どうも妙だと感じる。涼子の持っていない携帯電話やスマートフォンを、これ見よがしに手にしている生徒の姿が、やたら目に留まるのだ。なにやら、生徒たちの間で、ある動画が大流行しているらしい。そう。彼女たちの手にある携帯端末の液晶画面には、涼子の体の汚いものが映し出されている……。 涼子は、その場に崩れ落ちそうになった。身を支える脚が震える。 いや、そんなの、絶対にいや……。そんなことになったら、わたし、耐えられない……。 おそらく、現状としては、ほぼ全校生徒が所持しているのであろう、携帯電話やスマートフォンが、今や、涼子の人生をめちゃくちゃにする凶器に思えてならなかった。 だが、あくまでも単なる想像でしかない。もう少し、冷静になってみよう。自分は、悪いほうに物事を考えすぎではないだろうか? なにも、どこからか聞こえてきた、『めっちゃ汚い』という言葉が、涼子の姿を指していたとは限らないのだ。そうだ。同校の生徒たちの声を、すべて自分の悪口だと捉えるのは、被害妄想以外の何物でもない。たぶん、その言葉を発した生徒も、涼子とは関係のない、何か別の話をしていたのだろう。そうに決まっている。だから、だいじょうぶ。自分の動画など、撮られているはずがない。だいじょうぶ。 涼子は、必死の思いで、自分自身にそう言い聞かせた。 しかし……、もしも、自分の痴態を撮影した動画が存在していて、最悪の未来が到来したとしたら……。 答えは、すぐに出る。 もう我慢できない。そんな学校、辞めてやる。 校門の前で、涼子は、ひとり足を止める。 涼子の目には、校舎が、まるで監獄のように映っていた。一度、校門の中に入ったら、出てくるのは、十年先か、二十年先か……、と錯覚を覚えるほどに、果てしなく長い、拷問のような時間が始まるのだ。もしかすると、もう、まともな体では出てこられないのではないか。そんな不吉な予感さえ、頭の片隅をよぎる。 できるなら、逃げ出したい。だが、バレー部の合宿費を奪われている自分には、それが許されないのだ。 たっぷり三十秒ほど、その場で立ち止まっていた後、涼子は、ゆっくりと歩き出し、校門を通った。 南涼子、監獄に収監。 そして、あの竹内明日香が、部活の練習後、涼子を引き留めてきたのは、その日のことだった。 教室に足を踏み入れると、涼子は、窒息しそうな圧迫感を覚えた。 クラスメイトたちの視線が、次々と涼子に集まってくる。それと同時に、聞こえていた喧騒が、にわかに静まっていく。涼子の登場によって、教室内の空気が、明らかに変わったのだ。 涼子は、誰とも目を合わせないようにして、しかし暗すぎる表情には見えないよう、ごくかすかな微笑を口もとに滲ませ、自分の席に向かった。 席に着くと、顔の片側を隠したい心理も働いて、頬杖をついた。まるで、教室内で、自分ひとり、半裸をさらしているような、身の置き場のない思いに耐えながら、始業時間を待つ。 例の噂が広まってから、涼子の周囲にいたクラスメイトたちは、潮が引くように離れていった。今まで、涼子が友達だと思っていた生徒たちの大半が、本当の友達ではなかったということだ。なんと、そのなかには、高校生活で最高に愉快な出来事とばかりに、嬉々として涼子の陰口を叩いている生徒たちもいるらしい。それを知ってからは、もはや、周りが敵だらけのような気さえして、クラスメイトたちに自分から話しかけることが、怖くてできなくなった。そのため、休み時間や移動教室の時には、しばしば孤立状態におちいってしまう。 けれども、何人かの心優しい生徒は、涼子を見捨てておらず、以前のように声をかけてきてくれたり、一緒に行動しようと誘ってきてくれたりする。そんな時、涼子は、表情筋を最大限に使って、とびっきりの笑顔で応えるのだ。たとえ、その笑顔が、ほかの生徒たちから見れば、どれだけ滑稽なものであっても……。 授業中は、別の形で苦しまされた。 この何日間は、まったくといっていいほど睡眠が取れていないため、常に頭の芯が朦朧としている状態で、机に向かっているのだ。当然ながら、授業の内容は、何一つとして理解できないし、黒板を写したノートに書いてあることを見直しても、意味のない文字の羅列にしか思えない。そのため、涼子は、教師に当てられないよう、ひたすら祈り続けるしかなかった。 しかも、やっかいなことに、不定期的に、脳が睡眠を求めてくるのだ。そうなると、もう、一瞬でも気を抜いたら、意識が、深い谷底に転がり落ちていきそうな感覚が続く。実際、前日の古文の授業中、涼子は、知らぬ間に眠り込んでいた。一度だけではない。二度も、居眠りをしてしまったのである。そのせいで、古文の教師を激怒させることとなり、今まで築き上げてきた信頼関係は、完全に崩れ去ってしまった。ほかの教科で、同じことを繰り返すわけにはいかない。そう強く思っている。 だが、居眠りが許されない理由は、もう一つあった。 自律神経の狂いが原因であろう、腸内環境が、著しく悪化しているためだ。ちょっと前までは、下痢に悩まされていたのだが、それが治まったと思ったら、今度は、ひどい便秘が待っていた。もう、かれこれ、一週間は、まともに便が出ていない。こんなのは、生まれて初めての経験だった。そして、便秘で何より苦しいのは、大量にガスが溜まることである。授業中は、席を離れられないので、お腹がぱんぱんに張ってしまう。そんな状態で、もし、眠りに落ちたら、制御不能となったガスが、一気に噴出しそうで怖かった。授業中に、大きな音のオナラを放ち、その、おそらくは公害レベルであろう悪臭を、辺り一帯に漂わせる……。それは、もはや、教室から逃げ出したくなるほどの大失態である。これ以上、恥をかくのだけは、絶対にごめんだ。 そういった事情があるため、涼子は、猛烈な眠気が襲ってくるたびに、青あざになるくらい、腕や肩、太ももなどの肉をつねり、自分の体に痛みを与え続けることで、遠のく意識を懸命につなぎ止めていた。 要するに、涼子にとっては、授業もまた、大変な苦行なのである。 自分の体は、壊れ始めている。昼食時に、そのことを、はっきりと認識させられた。 午後一時少し前、教室に残っているのは、クラスメイトの半分ほどだった。 涼子は、自分の席で、バレー部の仲間、二人と一緒に食事を取っていた。お互いに話しやすいように、涼子は、右を向いて座っている。涼子の正面、つまり右隣の席には、同じクラスの柏木里美が座っており、二人が向き合っている形である。また、涼子の右側、つまり後ろの席には、別のクラスの浜野麻理が着席していた。浜野麻理は、友達の少なくなった涼子を心配して、わざわざやって来てくれたのだ。 涼子の手には、学校の売店で買った、コロッケパンが握られていた。正直、食欲なんて、まったく湧いていなかった。それでも、とにかく栄養を取らねば、一日を乗り切れない。そういう気持ちで、涼子は、パンにかぶりつく。 柏木里美と浜野麻理の二人は、涼子が、バレーコート上で痴態を演じたことなど、すっかり忘れたかのように、屈託なく振る舞ってくれた。それが嬉しくて、涼子も、周りの目など気にせず、手を叩いて大声で笑ったり、イエーイ、というかけ声と共に、二人とハイタッチを交わしたりしていた。 そんな最中のことである。 涼子の左側、つまり前の席に、ある生徒が腰を下ろした。それは、滝沢秋菜だった。 思いがけぬことに、涼子は、どきりとした。 秋菜は、その右隣の席のクラスメイトと話すために、そこに座ったらしかった。そのため、秋菜も、涼子と同じ方向を向いている。涼子と秋菜の距離は、わずか一メートル程度しかない。 あの、バレー部の練習場での一件があって以来、涼子にとって、滝沢秋菜は、魔物みたいに怖ろしい存在だった。それゆえ、涼子は、秋菜のことを徹底して避けていたのである。そればかりか、絶対に目を合わせたくないので、彼女のいるほうには、極力、顔を向けないように意識していたほどだ。また、秋菜のほうも、涼子に対しては、間違いなく不快な感情を抱いているはずだった。その秋菜が、すぐそばにいる……。 秋菜は、その右隣の席のクラスメイトと、たわいないお喋りをしている。一見、涼子には、まったく関心のない様子だ。だが、それは、ポーズのような気もする。ひょっとすると、涼子への当てつけの意味を込めて、そこに座っているのではないか。そんな疑念が、頭をもたげる。 涼子は、恐怖に硬直していた。秋菜のその、しっとりとした話し声を聞いているだけで、動悸が速まってくる。 滝沢さん……。いくらなんでも、わたしとの距離が、近すぎるでしょっ……。もしかして、わたしに、何か言いたいことでもあるの……? 柏木里美も浜野麻理も、涼子の異変に気づいたらしい。 「おーい、りょーこー。どうしたのっ? 急に黙っちゃってさあ」 浜野麻理が、涼子の肩を揺すってくる。 涼子は、明るい自分に戻ろうと努めた。しかし、それは無理だった。笑顔ひとつ作れない。 「うっ、うん……」 それだけ口にするのが、精一杯だった。目の前の光景が、二重にぶれて見える。 柏木里美と浜野麻理の二人は、いよいよ怪訝そうに顔を見合わせる。 「ちょっと、涼子、本当にどうしちゃったの!?」 今度は、柏木里美が、真剣な口調で尋ねてきた。 涼子は、内心で絶叫していた。やめて……! 横にいる滝沢さんの注意を引くようなことは、やめて……! だが、もう駄目だった。滝沢秋菜と、その話し相手であるクラスメイトも、涼子たちから、ただならぬ空気を感じ取ったらしく、二人の顔が、こちらに向けられた。 秋菜の視線が、自分に注がれているのを感じる。 恐怖は、たちまち頂点に達した。 パンを持つ右手が、かたかたと震え始めた。 バレー部の仲間、二人も、また、秋菜たちも、涼子の震える右手を凝視する。 「涼子……」 柏木里美が、呆然とつぶやく。 手の震えは、激しくなる一方だった。パンを取り落としてしまいそうである。 「だいじょうぶ!? 落ち着いてっ! どうしたの!?」 浜野麻理が、身を乗り出し、涼子の右手を、がっちりと握り締めた。これ以上、涼子を見世物にしたくない、というように。 涼子は、はあっ、はあっ、と荒い息を吐き出した。とにかく、呼吸を整えようと思った。バレーの試合で、サーブを打つ前のように、ゆっくりと深呼吸をする。それを何度も繰り返す。そして、浜野麻理の手のぬくもりを意識した。今は、かけがえのない友達である浜野麻理が、自分を守ってくれている。その安心感もあって、だんだん、気持ちが落ち着いてきた。 柏木里美と浜野麻理は、涼子の身を案じる言葉をかけ続けてくれた。 しかし、そんな彼女たちとは真逆に、滝沢秋菜は、いつものあの、冷ややかな眼差しで、じっと涼子のことを見すえていた。きっと、涼子に対して、こう思っているに違いない。こんなふうにはなりたくない……、と。 その時、涼子は、恐怖に震えるのではなく、言いようのない屈辱感を噛み締めていた。 やがて、その昼休みが終わり、次の授業が始まった。 授業の間、涼子の胸の内では、滝沢秋菜に対する呪詛の念が、延々と渦巻いていた。 滝沢さん……。あなた、わたしのことを、心の底から軽蔑してるんでしょう? わかってる。ちゃんと、わかってる。南涼子は、変態? うん、そう思われても仕方がないよねえ。なんていったって、自分の裸の写真を、あなたの保健の教科書に貼りつけて返したり、犯罪的に恥ずかしい格好で、部活の練習に出たりしたんだもん。でも……、滝沢さん。すべては、この学校にいる悪魔たちが、わたしにやらせたことなの……! 普通の高校生活を送っている、あなたには、とても信じられないでしょうけど。わたしと違って、あなたは、気楽な身分で、いいよねえ。本当に羨ましい。だけどね……、そうやって、のうのうとしていられるのも、今のうちだからね。あの悪魔たちの、次のターゲットは、滝沢さん、あなたなんだよ? 確実に、あなたも、地獄に引きずり込まれるでしょうね。そうなったら、どうなるか? 決まってんじゃない。わたしの裸の写真、あなた、見たでしょ? あれが、近い将来の、あなたの姿なの……! プライドの高そうな、あなたに、耐えられる? もしかしたら、それだけじゃなく、わたしみたいに、大勢の生徒が見てる前で、恥をさらすことになるかもね。そういう目に遭えば、わたしの気持ちも理解できるでしょうよ。早く、一刻も早く、あなたも、わたしのところまで堕ちてきなさいよ……! もうこれ以上、あなたに上から見下されてると、わたし、本当に壊れちゃいそうなの……。 休み時間は、人間関係で神経がすり減り、授業中は、体の様々な不調と戦い続け、また、しばしば、ショックに打ちのめされるような出来事が起こる。そうして、身も心もボロボロになりながら、涼子は、ようやく終業時間を迎えた。 しかし……、本当の地獄は、むしろ、これからだった。 帰りのホームルームが終わった後、涼子は、トイレの個室の壁に寄りかかり、ぐったりとしていた。 部活の練習が、そろそろ始まる頃だ。だが、体育館に向かう気になれない。 バレー部の部員たちの目には、まだ、生々しく焼きついているに違いない。涼子のあの、浅ましい姿が。涼子の体の汚いものが。ある意味、この学校内で、涼子のことを、もっとも軽蔑しているのが、ほかならぬ部員たちであろう。その部員たちと、顔を合わせることを考えるだけで、足がすくんでしまう。しかも、である。先ほどまでは、自分の席で、頬杖をつきながら、じっと苦痛に耐え続ける、という受け身の姿勢が許されていた。だが、これからは違う。自分自身が、恥ずべき存在であることを承知のうえで、キャプテンとして、率先的に行動していく必要があるのだ。自らのプレーで手本を示し、部員たちに大声で指示を出し、時には、後輩たちに活を入れ、そうしてバレー部全体を引っ張っていく……。考えれば考えるほど、絶望感で、気が遠くなってくる。 しかし、いつまでも、こうしてトイレに閉じこもっているわけにはいかない。 行くしかないのだ。 涼子は、なまりのように重たい体にむち打ち、個室のドアを開けた。 その後は、立ち止まることなく、体育館へと歩いていった。 部室に入ると、涼子は、制服を脱いで、白いTシャツと黒のスパッツに着替えた。壁に備え付けられた縦長の鏡に、練習着姿の自分を映してみる。制服を着ている時とは違い、上半身、下半身ともに、筋肉の盛り上がりが、顕著に現れている。これまで、厳しい練習を重ねてきた、そのたまものだ。心なしか、自分が、頼もしい存在に見えてくる。それと同時に、徐々に覚悟が芽生えてきた。 涼子は、気持ちを奮い立たせるつもりで、両手で、体中をばちんばちんと叩いていった。ほっぺたから始まり、肩、腕、脇腹、背中、おしり、太もも、すね、と。それを終えると、おしっ、と声に出した。 もう、よけいなことは考えない。わたしは、自分のやるべきことを、やり通すだけだ。 「しゅーうぅぅごーうぅ!」 体育館フロアに入るなり、涼子は、腹の底から声を張り上げた。 三十人を超える部員たちが、こちらに集まってくる。だが、以前に比べて、一人ひとりが、なんとなく、とろとろと動いているように見えてならなかった。しょうがないから、行ってやるか。部員たち全体から、そんな空気が伝わってくるのは、気のせいではあるまい。 涼子は、初っぱなから、気勢をそがれる思いがした。 心の準備は、できていたはずだ。しかし、目の前に集合した、部員たちの顔を見渡すと、どうしても気後れしてしまう。そんな自分を、心の中で叱りつけ、ミーティングを始めた。むろん、中心的に話すのは涼子だが、ほかの部員たちに発言させることも大事だ。だから、試しに、何人かの部員に、話を振ってみた。けれども、彼女たちの反応は、極めて鈍いものだった。 「まあ、メニューは、昨日と一緒でいいんじゃない?」 「とくに、ありません」 「まだ、そういうことは、わからないので」 こんなのは、ミーティングとは呼べない。 涼子は、ため息をつきたくなったが、ここは、キャプテンである自分が、どうにか空気を変えなくては、と前向きに考え直した。まず笑顔だ。今のバレー部には、笑顔が、決定的に足りていない。直感的に、そう感じた。なんでもいい。部員たちの笑いを誘うようなセリフを、口にしてみよう。 「あと……、一年生、とにかく声出し。今日の練習で、全然、声が出てなかったら、一年生、全員、罰ゲーム。そうだねえ、何をやってもらおうかなあ……」 あごに手を当て、つかの間、考えを巡らした。 「いいこと思いついた。校舎の屋上から、一人ずつ、初恋の人の名前、大声で叫んでもらう」 涼子は、不敵な笑みを浮かべてみせた。渾身のジョークだった。 しかし、期待外れなことに、笑いは起こらなかった。それどころか、部員たちの間には、寒風が吹いたような雰囲気さえ漂っている。以前ならば、こういう時、誰かしらから、突っ込みが入ったものなのに。 「……っていうのは、もちろん、冗談なんだけどさ、それくらい、気合い入れてねってこと」 涼子は、ひどく決まりの悪い思いに耐えながら、ふたたび喋り始めた。 だんだん、頭の中で、ネガティブな思考が膨らんでくる。 結局、みんなが言いたいのは、こういうことか。南涼子は、キャプテン失格。それも当然かもしれない。わたしは、恥ずべき存在なのだ。部員全員の前で、あれほど恥ずかしい姿をさらした女が、いったい、どのツラ下げて、リーダーとして振る舞っているのか。自分で自分の顔を見てみたい。さぞかし、馬鹿みたいな顔をしているんだろう。 そんなことを考えながら、口を動かし続ける。それは、まさに拷問のような苦痛を伴うことだった。 バレー部の練習は、校外でのランニングから始まる。それを走り終えて、体育館に戻ってくると、涼子は、自分の身の異変に、戸惑いを覚えた。軽く体を動かしただけなのに、早くも、全身に、ぐっしょりと汗をかいていたのである。健康だった頃ならば、あり得なかったことだ。おそらくは、これも、自律神経の狂いが根本的な原因で、汗を分泌する汗腺の働きが、異常に活発化している状態なのだろう。しかも、噴き出した汗は、爽快感とは、ほど遠い、べたべたとしたもので、臭いも、強いような気がする。 涼子は、自分の体の不健康な要素を、また一つ、知ってしまったことで、やるせない気持ちになった。天に向かって叫びたい。お願い……! わたしの元の体を、返して……! 練習が始まってから、二時間ほど過ぎた頃のことである。 スパイクの練習中に、とうとう、涼子は、仲間と深刻な揉め事を起こしてしまった。 肉体的にも、疲労は、極限に達していた。この何日間は、まともな休息を取れていないのだから、当たり前のことである。一歩、脚を動かすごとに、体中の骨の、みしみしとした音が、聞こえてきそうな気がした。 スパイクの順番待ちの列に並ぶと、間もなく、自分の番が回ってきた。 トスが上がる。 涼子は、助走をつけ、持てる力を総動員してジャンプし、ボールを叩き込んだ。 しかし、そのボールは、相手コートのエンドラインの外に飛んでいった。 「ああ、くっそぉ!」 つい、そう言葉を漏らした。先ほどから、スパイクが、ろくに決まらないのだ。 涼子は、コートの外に出ると、両手を膝についた。はあああっ、と焼けるように熱い息を吐き出す。今や、涼子の体は、滝を浴びたかのように、汗で濡れそぼっていた。顔や髪の毛はもちろん、Tシャツやスパッツからも、汗のしずくがしたたり落ちる。恐ろしいくらいに汗が出るせいで、体力をよけいに消耗している感じだった。それと、はっきりとわかったことがある。この大量の汗が、ひどい臭いを発しているのだ。その臭さといったら、まるで、自分だけ、ドブの水か何かで水分補給をしているのではないかと思うほどである。この原因については、おおよそ見当がつく。今でも、お腹に意識を向ければ、大腸の下のほうに、ずっしりと便の詰まっている感覚がある。おそらくは、溜まりに溜まった便が、かなり腐敗してきており、それによって発生した有害物質が血液に溶け込んで全身に回り、毛穴から汗として排出されている状態なのだろう。想像するだけで、気が滅入ってくる。自分の体が、どんどん汚いものに変わっていくという感覚は、思春期の女の子にとって、泣きたいくらい悲しいものだった。 涼子は、うめき声を漏らしながら立ち上がる。ともかく、自分で、自分の汗臭さに閉口してしまうのだから、周りの部員たちには、さぞかし不快感を与えているに違いない。その根本的な原因であろうものを、どうにかしたいと、痛切に感じる。つと、へその下に触れた。常に便意だけはあるのだ。だから、学校のトイレで踏ん張ることも、再三だったが、毎回、小動物のそれのようなものしか出てこない。しかし、今度こそ、という思いで、フロアの出入り口に向かう。出入り口を出てから、館内通路の途中で、冷水機の水を、これでもかというほど、がぶ飲みし、それから、トイレへと歩いて行った。 十数分後、涼子は、トイレから出た。案の定、結果は、貴重な体力を馬鹿みたいに削っただけだった。そのせいで、全身の脱力感が半端ではなく、真っ直ぐに歩くことすら難しい。しかし、練習は、まだまだ終わらないことを思うと、恐怖にも似た感情に襲われ、ぐらぐらと目まいがした。ひょっとすると、自分は、練習中に血を吐いて倒れるかもしれないな……。本気で、そんなふうに思い始めた。 フロアに戻ると、涼子は、両手を腰に当て、しばし、部員たちの様子を眺めていた。とにかく苛立たしい気分だった。自分の体の問題に悩まされているせいもある。しかし、それだけではない。練習が始まってから、ずっと思っていたのだが、声出しをしない部員が、多すぎるのだ。とくに問題なのは、やはり、ボール拾いをしている一年生たちである。今日の彼女たちは、まるで、入部当初の頃に逆戻りしてしまったように活気がない。おのおのが、ただ黙々と動いている、という感じなのだ。バレーにおいて、声出しは、基本中の基本だ。そのことを徹底的に教え込むのは、キャプテンである自分の役目だろう。 涼子は、両手を強く叩いた。 「ちょっと一年生! 全員、集まって!」 厳しい声で叫ぶ。 一年生たちが、こちらにやって来る。 十数人の部員が、涼子の前に集合した。 「あのさあ、あんたらのなかで、自分は、しっかりと声出ししてますって、自信を持って言える人、手、挙げてみて」 涼子は、威圧的な口調で言う。 十秒近く待った。 誰も手を挙げない。 「そっか……。わたし、今日のミーティングでも、言っておいたよね? 声を出せって。なのに、なんなの? 自分たちは、黙ってボール拾いしていれば、それでいいと思ってんの?」 涼子は、一人ひとりに、鋭い視線を送っていく。 一年生たちは、そのほとんどが下を向いている。 「……あんたらさ、やる気ある?」 涼子は、立て続けに問いかけた。 だが、返事をする者はいなかった。 その無反応ぶりに、涼子は、頭に血が昇るのを感じた。 「聞いてるんだから、返事くらいしなさいよっ!」 つい、大声で怒鳴ってしまった。 だが、それでも、一年生たちは、まるで示し合わせたかのように、口をつぐんでいる。 反抗のつもりか……? 涼子は、一年生たちの態度に、怒りを通り越し、驚きの念すら覚えた。 「もういいっ……。一年、全員、校庭の横で、ダッシュ往復三十本。今すぐ行って」 投げやりに命じ、フロアの出入り口のほうを、親指で指した。 しかし、一年生たちは、誰一人として動こうとせず、どうしようかと迷うように、互いに視線を交わし合っている。なかには、ふて腐れたような顔をしている部員も、何人か見受けられる。 「早く行けぇぇぇぇぇぇ!」 涼子は、雷のような怒号を発した。 それにより、一年生たちは、ようやく、しぶしぶとフロアの出入り口へと歩き始めた。 そんな彼女たちの背中に、涼子は、言葉を投げつける。 「あと、しっかりと声出しする気になれないんだったら、もう戻ってこなくていいから」 一年生たちは、無言でフロアの出入り口から出て行く。 涼子は、深いため息をついた。 「南先輩、やりすぎですよお」 背後から、いきなり聞こえた。 振り向くと、二年生の部員、沼木京香が立っていた。 「なに? わたし、何か、間違ったことしてる?」 涼子は、強い語気で尋ねる。 京香は、言いにくそうに唇を噛み、それから答えた。 「今、南先輩が、一年生たちに厳しく当たるのは、逆効果にしかならないと思うんですよ」 意味がわからなかった。 「何が言いたいわけ……? わたしには、キャプテンとしての責任があるの。今日は、一年生たちから、ちっとも、やる気が伝わってこなかった。だから怒った。当たり前のことでしょっ? だいいち、なんで、二年のあんたが、わたしの指導のことに、口を出してくんのよっ。すんごい腹立たしいんだけど」 涼子は、興奮してまくし立てた。 すると、京香は、呆れたような顔をした。 「南先輩……。自分の立場、わかってないんですか?」 その言葉に、一瞬、涼子は、唖然とした。 しかし、その直後、京香に詰め寄った。 「どういう意味よ?」 自分より、五、六センチ背の低い京香の顔を、にらみつける。 京香は、やや身を引くような素振りを見せた。こちらの気迫に怯んだのだろう、と最初は思った。が、京香のその、苦々しげな表情を見て、ぴんときた。もしかしたら、京香は、涼子の強烈な体臭に不快感を抱き、つい後ずさりしそうになったのかもしれない。 涼子は、羞恥を感じたが、それでも、京香の顔を、にらみ続けた。 だが、気の強い二年生の部員は、鼻に微妙なしわを寄せながらも、涼子の目を、じっと見返してくる。 その時、横から聞こえた。 「もう、みんな、あんたには、付いていきたくないってことよ。涼子」 副キャプテンの高塚朋美の声だった。そちらを見やると、朋美は、片手を腰に当て、いかにも傲然と立っている。 涼子は、おもむろに京香から離れ、朋美のほうに歩いていった。そして、朋美のすぐ前に立ち、両腕を組んだ。今にも、互いに胸ぐらをつかみ合わんばかりの距離である。朋美は、百七十センチを超える長身であるが、迫力では、涼子も、まったく引けを取らないはずだった。 涼子が口を開こうとした、その直前に、朋美は、京香とは違って、あからさまな反応を示した。鼻をつまみ、顔を横にそらしたのだ。涼子のことを横目で見る、その侮蔑的な眼差しが、はっきりと語っている。あんた、くさい……。 涼子は、激しい屈辱感に、体が熱くなるのを感じた。しかし、一歩たりとも後ろに引こうとは思わなかった。努めて冷静な声で問う。 「それだったら、みんな、誰になら、付いていくっていうの? 朋美」 やや間が空いた。 朋美は、実に嫌そうに鼻から指を離すと、涼子の顔を真っ直ぐに見て答えた。 「わたしが、キャプテンを務める。最後の大会までは、わたしが、みんなを引っ張っていく」 どうやら、本気で言っているようだ。 涼子は、ごくりと生唾を飲み込む。かつてない窮地に立たされていた。 これ以上、自分がキャプテンを続けるのは、バレー部にとってよくない。そんなことは、充分に理解している。だが、ここで、朋美にキャプテンを交代したら、どうなるか。まず間違いなく、涼子が、バレー部の合宿費を『紛失』したということが、白日のもとにさらされるだろう。その事態だけは、何がなんでも防ぎたかった。それゆえ、涼子は、合宿費を全額、取り戻すまでは、どんなに苦しくとも、キャプテンの座を譲るわけにはいかないのだった。一言でいえば、自己保身である。 涼子は、後ろめたい思いもあって、朋美から視線を外し、そして口にした。 「言っておくけど、わたしは、キャプテンを辞めるつもりはないから……」 すると、朋美は、はんっ、と笑った。 「勘弁してくんない? 涼子、あんた、自分が何やったか、もしかして憶えてないの? ……この前のゲームの時、信じられない格好でプレーしてたよね? わたし、目を疑ったもん。え? 何事って……。あの時のあんた、完全に変質者だったから。いい? ちゃんと自覚して。あんたは、部員全員に、とんでもない迷惑をかけたの。それでいて、キャプテンを辞めるつもりはない? 笑わせないで。どこまで厚顔無恥なの?」 涼子は、床の一点を見つめていた。朋美の言うことは、もっともかもしれない。だが、その、過剰なまでの攻撃的な口調には、腹が立ってならなかった。 朋美は、涼子の顔を、のぞき込むようにしてきた。 「一年生たちが、声出ししなくなったのは、誰のせい? 二年も三年も、ぐだぐだな感じがするのは、誰のせい? 涼子、ぜーんぶ、あんたのせいよ? その当たり前のことを、あんたひとりだけ、わかってないっていう状況なの。あんたみたいな人間を、裸の王様って言うんだろうねえ……。いい? これだけは断言できる。あんたが、キャプテンでいる限り、元のバレー部に戻ることはないの。わたし、こーんな状態で、最後の大会に臨むなんて、耐えられないなあ。だって、絶対に悔いが残っちゃうもん。今まで、色んなことを犠牲にして頑張ってきたのは、なんだったんだろうってね」 もはや、その物言いからは、悪意すら感じ取れた。 涼子は、朋美に対し、強い敵対心を持った。 「嬉しいんでしょ、朋美……」 ぼそりと言う。 「はっ?」 朋美は、聞き返してくる。 涼子は、朋美の顔に、視線を戻した。 「嬉しいんでしょ、本当は……。あんたさ、一年前、自分がキャプテンに選ばれなかったことに、すごい不満を持ってたらしいじゃん。だから、今になって、わたしが、部員たちの人望を失ったことが、嬉しくてしょうがないんでしょ? なんていったって、キャプテンになれるチャンスだもんねえ?」 どんどん口調が熱を帯びていくのを、自制できなかった。 朋美の顔には、驚愕の表情が浮かんでいる。 「なに言ってんの……? あんた、心が歪んでる……」 「念のために、もう一度、言うけど、わたしは、キャプテンを辞めるつもりはない。だって、次にキャプテンになるのが、あんたみたいな身勝手な人間じゃあ、辞めるに辞められないから」 涼子は、そう言い残して、その場を去ろうとした。 が、次の瞬間、左頬に、衝撃が走った。 朋美の右手が挙がっている。ビンタを喰らったのだと気づく。 驚かされたが、すぐに、燃えるような闘争心が湧き上がってきた。 涼子は、右手を振り上げると、手加減なしに、朋美の頬を平手で打ちつけた。朋美のビンタの、二倍、いや三、四倍の威力だったはずだ。 かなり効いたらしく、朋美は、痛そうに左頬を押さえた。 涼子は、つんっと、あごを反らした。取っ組み合いの喧嘩なら、受けて立つ。そういう覚悟だった。 そこで、涼子と朋美のやり取りを見ていた沼木京香が、二人の間に割って入った。 「二人とも、やめてくださいよっ!」 京香は、両手を突っ張り、涼子と朋美を離れさせる。それから、朋美の側に付いた。向こうに行きましょう、というように朋美の体に腕を回しながら、涼子のことを、非難がましい目で見てくる。 朋美は、目じりをつり上げていた。 「あんたには、絶対、キャプテンを降りてもらうからっ! この、バレー部の恥さらしっ!」 がなり声で捨てゼリフを吐き、京香と共に、向こうに歩いていく。 気づけば、二、三年生の部員、全員が、かたずを飲むようにして、涼子たちの成りゆきを注視していた。 涼子は、スパイクの順番待ちの列に並ぶ気力もなく、その場で天井を仰いだ。照明がまぶしく、ぎゅっと目を閉じる。もはや、精神的にも肉体的にも、壊れる寸前だという気がする。人間って、壊れたら、どんなふうになるんだろう……? そんな疑問が、ぼんやりと脳裏に生じた。 部活の練習は、永遠に終わらないかのように思われたが、どうやら、時間は、ちゃんと流れていたらしい。 午後七時過ぎ、涼子は、自分の前に集合した部員たちに、練習の終了を宣した。 最初に部室を使用できる三年生の部員たちが、三々五々、フロアを出て行く。 だが、涼子は、彼女たちの後に続くことはせず、ひとり、壁にもたれかかっていた。これ以上、人と行動を共にするだけの余力は残っていなかったのだ。やむなく、壁に右腕を当て、そこに額をのせた。すさまじい疲労感が、体中の細胞に張りついている。まるで、血の最後の一滴まで絞り尽くしたかのような感覚だった。今や、指一本、動かすことさえ、しんどいくらいである。それに、意識も混濁しており、フロアに残っている、一、二年生の部員たちの喧騒が、どこかの遠い事象のように感じられてならない。いっそ、このまま倒れてしまってもいい、と思う。しかし……、果てしなく続いた、拷問のような時間は、ついに終わったのだ。それは、紛れもない事実だ。 涼子は、むくりと顔を上げた。わたしは、最後まで乗り切った……! ようやく、家に帰れるのだ。この時を、ひたすら待ち続けていたではないか。出よう。この、監獄のような場所からは、一分一秒でも早く、出よう。そう思い直すと同時に、脚が動き始める。まるで、ゾンビと化したような、ふらふらとした足取りだった。しかし、着実に、前に進むことができる。だいじょうぶ。これなら、なんとか、家までたどり着ける。その安堵と喜びを胸に、フロアの出入り口を通ろうとした。 その時、背後から、とんとんと肩をつつかれた。 涼子は、誰だろうと思って振り返る。 そこには、紺色のジャージの上下を着込んだ、マネージャーの竹内明日香が立っていた。どれだけ憎んでも憎み足りない相手であるが、相も変わらず、この学校には場違いなほどの美少女だと思わされる。実のところ、未だに、間近で顔を見合わせている時など、そのフランス人形じみた美貌ぶりに、不覚にも、息を呑むような気持ちになってしまう。しかし、だからこそ、とてつもなく穢らわしい存在に思われてならないのだった。今、その明日香の顔には、ほんのりと微笑が浮かんでいる。 「……なに?」 涼子は、疲れ切った声を出した。 「りょーちん、色々と疲れてんでしょっ。今日は、久しぶりにぃ、体の、マッサージしてあげる」 明日香は、柔らかい口調で言う。 「いや結構……」 涼子は、即座に断り、明日香に背を向けようとした。 だが、涼子の着ている白いTシャツの左袖の部分を、明日香は摘まんで引っ張ってきた。 「いいからいいからぁ、遠慮しないでっ、りょーちん」 涼子は、大きくかぶりを振った。 「遠慮とかじゃないのっ。わたし、今日は、もうすぐに帰りたいの」 すると、明日香は、すねたような表情をした。 「そんなに急いで帰ること、ないでしょっ。あたしが、りょーちんのこと、マッサージでぇ、気持ちよくしてあげるっ」 涼子は、震える吐息を吐き出した。 「いいって言ってんでしょっ……。とにかく離してよっ!」 Tシャツを握っている明日香の指を、手で押しのけようとする。 しかし、明日香は、かたくなに涼子のTシャツを離そうとしない。 「あたしは、りょーちんのこと、癒してあげたいだけなのっ……。それなのに、そんな、つれない態度されると、なんか悲しいなぁ」 そのしつこさに、涼子は、腹の底がけいれんするほど、うんざりさせられた。いっそ、明日香の腕をたたき落としてでも、今すぐ部室へと向かいたいところだ。しかし、弱みを握られているため、明日香に対して、乱暴な行為に出ることなど、決して許されない。なので、涼子としては、懇願するしかなかった。 「お願い、明日香……。わたし、今日は、色んなことがありすぎて、へとへとに疲れてるの。もう、本当に、立ってるのが、やっとなくらい。だから、今日だけは、もうすぐに帰らせて……。ね? お願い……」 半分、涙声になっていた。 明日香は、哀れむような目で、じっと涼子の顔を見つめる。それから口にした。 「りょーちんが、そんなに疲れてるんじゃあ、マネージャーとして、なおさら放っておけないよぉ。あたし、りょーちんの体、マッサージし終えるまでぇ、絶対に帰らないからっ」 涼子は、その言葉を聞くと、失意のあまり、がっくりと首を垂れた。もはや、何を言っても無駄だと悟らされた。こうなると、結局のところ、立場の弱い涼子のほうが折れるしかない。いったい、何が目的なのか知らないが、明日香は、涼子の体をマッサージしたくてならないらしい。この女には、自分の体に、指一本、触れられたくないのだが、それは我慢するしかなさそうだ。それと、逆に考えれば、いい機会でもある気がした。明日香と二人だけで話せる。バレー部の合宿費を返してもらうためには、たとえ相手が悪魔であろうと、その心に訴えかける以外に方法はないのだから。 涼子が観念したのを見て、明日香は、にんまりと笑った。 「さ、りょーちん、こっちこっち」 弾むように言い、涼子のTシャツの左袖を握ったまま、フロアの出入り口を通っていく。それに引きずられ、涼子も、よろよろと館内通路に出た。 愚かにも、まだ、明日香のことを、献身的なマネージャーだと信じ切っていた頃から、彼女による部員へのマッサージは、館内通路で行われるのが通例だった。フロア内で、あくせくと動き回っている、主に一年生の部員たちの、邪魔にならないよう、という配慮からである。 明日香は、フロアの出入り口を出てから、十メートルほど歩いたところで、足を止めた。 涼子は、肘と膝に着けているサポーターを外すと、明日香の足もとに、力なくへたり込んだ。そのまま、身を反転させ、両腕を枕代わりにする形で、うつ伏せに寝る。奇妙な感覚だった。なにしろ、自分は今、憎くてたまらない女の前で、無防備に横たわっているのだ。まるで、煮るなり焼くなり好きにして、と自分の身を差し出しているかのような状況である。そう考えると、なんとも心もとない気持ちになる。 明日香は、ふわりと腰を落とし、床に膝をついた。 彼女の両手が、涼子の肩に当てられる。その瞬間、涼子は、明日香に体を触られる不快感に、思わず顔をしかめた。 マッサージが始まった。 涼子の着ている白いTシャツは、汗でびしょ濡れの状態であり、その生地が肌に張りついているため、下に着用している、同じく白い色のブラジャーが、完全に透けており、また、肩甲骨の出っ張りや、背筋のラインに至るまで、はっきりと視認できる有様だった。きっと、こんな汗まみれの涼子の体には、親しい友達でさえ、触れることを躊躇するはずだ。しかし、明日香は、ちっとも気にならないらしい手つきで、涼子の肩の筋肉を、ぎゅっぎゅっ、と揉みほぐす。 涼子は、それから一分ほど、黙ってされるがままになっていた。 どうも妙だと思う。涼子のことを侮辱するのが大好きなはずの明日香が、何も言ってこないのである。今なら、格好のネタがあるというのに。この、見苦しいことこの上ない、大量の汗のこと。また、その汗の、ひどい臭いのこと。 明日香は、ただ黙々と涼子の体をマッサージしている。 涼子は、明日香に体を触られていることによる精神的苦痛が、だんだんと薄らいでいくのを感じ始めた。いや、そればかりか、この竹内明日香という女だって、やはり、血の通った人間であり、きっと、話せばわかってくれるはず、という思いをも抱く。その思いに突き動かされ、意を決して口を開いた。 「あの……、聞いて、明日香」 地の底から届いたような、恐ろしく低い声だった。 「うーん?」 明日香は、やんわりとした声を出した。 涼子は、薄目を開けた状態で、目の前の床を見るともなく見ながら、とつとつと話し始めた。 「わたしさ……、高校に入学してから、ずっと、部活に明け暮れる生活を送ってきた……。あなたも、知ってると思うけど、うちの高校のバレー部、強豪校としての伝統を受け継いでるからさ、もう、遊ぶ時間なんて、全然ないの。彼氏を作るとか、そんなこと、考えられもしなかった。……練習は、過酷そのものだし、なんで、わたしは、こんな苦しいことに、耐えないといけないんだろう、って思ったことも、一度や二度じゃない。わたし、みんなが思ってるような、強い人間じゃないから……」 明日香は、両手の位置をずらし、涼子の肩甲骨の下あたりをマッサージし始めた。 涼子は、話を続ける。 「……でも、自分なりに、練習を、がむしゃらに頑張ってきて、その結果、キャプテンに選ばれた。その時は、すごい誇らしかったけど、同時に、不安でたまらなかったの。わたしなんかが、キャプテンになったせいで、この高校のバレー部の、強豪校という地位が、失われちゃうんじゃないか、って。だから、それからは、本当に、死にもの狂いの気持ちで、バレー部を引っ張ってきたつもり。わたしって、要領が悪いから、散々、空回りもしたけど。それで……、とっても長かったような、でも、なんだか、あっという間だったような、この部活中心の生活も、いよいよ終わりが近づいてきた。やっぱり、自分が必死になってやってきたことだからさ、最後の大会も含めて、なるべく、いい形で終わりたいっていう思いだった。だけど……、最後の最後になって、今まで積み重ねてきたものが、全部、崩れていっちゃった……」 そこで言葉を止めた。 明日香は、何も言わず、次は、涼子の腰の上に両手を当てた。体重をかけるようにして、その部分を強くこすってくる。 涼子は、思いを巡らす。果たして、明日香は、涼子の言葉に、きちんと耳を傾けているだろうか。はなはだ疑問ではあるが、明日香の心に訴えかけるなら、今しかないはずだ。 「明日香も、知ってるでしょ? わたしが今、バレー部のなかで、どれだけ悲惨な立場でいるのか。今はもう、部員たちのほとんどが、わたしの言うことを、ろくに聞いてくれない。でも、そんなんでもさ……、わたしは、キャプテンとして、自分のやるべきことを全うしないといけない。だから、まずは、部員たちの信頼を、もう一度、取り戻すためには、どうしたらいいのかって、そのことを、懸命に考えながら行動し続けた……。だけど、全然だめ。なんていうか……、今のわたしは、頑張れば頑張るほど、キャプテンらしく振る舞おうとすればするほど、部員たちに嫌われていく、っていう感じ。それに……、今日は、朋美に言われちゃった。『あんたは、バレー部の恥さらしだ』って。すごい悔しかったけど、言い返す言葉がなかった。だって、本当に、そのとおりなんだろうし。もう、わたし……、苦しくて悲しくて、胸が押し潰されそうだよ……」 込み上げてきたおえつを抑えられなくなり、えうっ、と声を漏らした。 「……可哀想な、りょーちん」 明日香は、それだけ言うと、今度は、涼子の下半身へと手を動かした。涼子の両脚の太ももを、黒のスパッツ越しに両手でつかむ。そのまま、左右にぶらぶらと揺すり始めた。太ももの筋肉疲労を取るには、極めて効果的な方法だった。 涼子は、何とはなしに回想する。明日香が、バレー部のマネージャーとしての活動を始めてから、間もない頃のことだ。練習が終わった後は、よく、こうして、明日香に全身のマッサージをしてもらっていた。明日香が素人とはいえ、涼子の体は、どこもかしこも筋肉がぱんぱんに張っている状態だったから、マッサージの間は、極楽気分を味わえた。とくに、酷使し続けた太ももの筋肉を揉みほぐされている時には、あまりの気持ちよさに、思わず声が出てしまうほどだった。だから、明日香の手が、太ももから別の部位に移動してしまうと、涼子は、柄にもなく、甘ったるい声で、『やーん、もうちょっとだけ、今のところやってえ』と、おねだりしていたのを思い出す。まさに、身も心も、明日香の手に委ねていたのである。 あの頃と同様、今、涼子のたくましい太ももを、明日香は、いたわりのこもった手つきでマッサージしている。 涼子は、体の緊張が、最初に比べると、驚くほどほぐれていることを感じ、両脚を、軽く開いた。自分でも不思議なことに、今一度、明日香に対して、心を開いてもいいような気さえしてくる。そして、ふたたび口を開いた。 「あの……、何が言いたいかっていうとさ……、わたしは、もう、自分の守りたかったものを、ほとんどすべて失っちゃったってことなの……。本当だよ? 部活内だけのことじゃない。明日香は、知らないかもしれないけど、わたし、今は、クラスで、ひとりぼっちになることが多いの。わたしが、変態だっていう噂が、クラスにも広まったことで、いつも、周りにいた子たちが、わたしから、どんどん離れていった。そのなかには、一年の頃から、ずっと仲がよかった子もいるんだけどさ……、今日なんて、わたしが、近づいただけで、露骨に嫌な顔をされちゃった……。結局、わたしには、本当の友達なんて、指で数えるくらいしか、いなかった、ってことなんだよね……。でも、それは、わたし自身のせいだって、自覚してる。わたしって、生意気だし、周りから、ちやほやされると、すぐ調子に乗っちゃうし、それに、結構、自分のことしか考えられないところがあるし……、短所を挙げると切りがない。そういう部分を、周りの子たちは、ちゃんと見てたんだろうなあ……、って思う。あの……、明日香たちもさ、これまでの高校生活で、わたしの嫌な面を、色々と目にしてきたんでしょ? それで、そんなわたしのことを、たっぷり痛めつけてやろう、っていうふうに思ったんだよね? だから、今、わたしが、こうして苦しんでるのは、完全に自業自得……。うん、本当に、そう思う。でも……、だけどさ……」 涼子は、一呼吸、間を置き、それから話を続けた。 「もういいでしょ……? もう気が済んだでしょ……? だってさ、今までに、明日香は、ここまで惨めな女を、実際に見たことがある……? ないよね? 今……、わたしは、大げさでもなんでもなく、地獄の底で這いずり回るような学校生活を送ってる。はっきり言って、そのうち、気がおかしくなりそうなくらい、つらくてしょうがない。それに、体のほうは、とっくに壊れ始めてる。今日は、ちょっとしたことがきっかけで、手の震えが止まらなくなっちゃった。もう、わたしは、そんな状態なの……。ねえ、だから、これ以上、わたしを痛めつけようとするのは、やめて……。それで、お願いだから、バレー部の合宿費を返して……。もし、返してくれたなら、わたし、あなたたちから、散々、恥ずかしい思いをさせられたこと、全部、忘れる。あなたたちに、何らかの形で復讐しようなんて、絶対に考えない。そうして、今までの自分の悪い部分を、徹底的に反省して、それからは、目立たない生徒として、ひっそりと残りの高校生活を送っていく。約束する。だから、お願い……」 言うべきことは言い終えた。明日香から、どんな反応が返ってくるかと待つ。 「……りょーちん、変なこと言わないでっ。あたしはぁ、バレー部の合宿費を取ってなんて、ないもん」 「えっ……」 涼子の胸の底に、黒いしずくが落ちた。 その直後、涼子の両脚の太ももをマッサージしていた、明日香の両手が、ずずっとせり上がってきた。太ももの付け根の上をも通り過ぎ、そのまま、おしりの肉をぎゅうっと押し上げてくる。 突然、おしりを触られたことで、涼子は、たちまち体中に緊張が走るのを感じた。 明日香は、まるでヒップアップマッサージをするかのように、同じ動作を繰り返し始めた。着衣の状態でも、というより、スパッツを着用している状態だからこそ、その密着性ゆえに、涼子のおしりは、ことさらボリュームが強調されて見える。それは、涼子自身も、正直、わかっていることだった。そんな豊満なおしりの肉が、明日香の手の圧力によって、下から上に、下から上にと盛り上げられ、そのたびに、黒のスパッツからは、生地に染み込んでいる涼子の汗が、じゅわっと滲み出る。 涼子は、強い戸惑いを覚えていた。 いくら、練習を終えた直後ということで、体中の筋肉が張っている状態であろうと、おしりまでマッサージされる理由はない。ここは、学校の体育館であり、エステではないのだ。当惑の念は、だんだんと激しい不快感に変わっていく。ついさっきまでの、リラックスした気分は、すっかり吹き飛んでおり、今や、体のあらゆる部分が、がちがちにこわばっていた。 やだ……。そんなところ、触らないで……。 同性の手だとしても受け入れたくない。学校内では、生徒たちが、女の子同士ということで、気軽に胸を触り合うなどして、スキンシップを図っている場面を、たびたび目の当たりにするが、涼子は、そういうのが大の苦手だった。だから、過去、ふざけて胸を揉んできた生徒に対しては、はっきりと、『やめて!』と拒絶の意思を示してきた。それなのに、今は、延々とおしりを撫で回されながら、身じろぎもせず、無防備に横たわっているのだ。しかも、相手は、涼子に対して、これまでに数え切れないくらい、変態的行為を繰り返してきた女である。 涼子は、ぞわぞわと悪寒を感じ始めた。 「やっ……。やっ……。い……、や……」 かすかに声が漏れる。断固とした拒絶の言葉を、すんでのところで呑み込んでいる状態だった。もう少しだけ、明日香に対して、和やかな雰囲気のなかで語りかけたい。そういう思いを抱いていたのである。 しかし、それから間もなく、そんな涼子の思いは、完全に打ち砕かれた。 明日香は、ヒップアップマッサージのような動作をやめたかと思うと、今度は、涼子のおしりの、もっとも盛り上がった部分に、両の手のひらを張りつけ、その部分の肉を、ぐにぐにと揉みだしたのである。それは、どう善意に解釈しても、涼子のおしりの肉の感触を愉しむ、性的意味合いのこもった手つきだった。 涼子は、全身が総毛立つ感覚に襲われた。 「んんー?」 明日香は、挑発するような声を出した。 それを聞いて、遅まきながら認識する。今、自分は、侮辱されているのだ。いや、辱めを受けているのだ。 もう、我慢ならない。 「明日香、変なところ触るの、やめて!」 涼子は、きっぱりとした口調で訴えた。 それにより、ようやく、明日香の手が止まった。 「りょーちん、おしり、きもちくないのぉ……?」 明日香は、残念そうな声で訊いてくる。 「気持ちいいわけないでしょっ!」 涼子は、枕代わりの両腕に向かって吐き捨てた。 すると、明日香が、何事か考えるような沈黙が流れた。 「それじゃあ、りょーちん……。ここは、どうぅ?」 明日香は、わずかに開かれた涼子の股の間に、そっと右手を差し入れた。そうして、ぷっくりとした性器の部分に触れると、その肉をこねるように指先でいじり始める。 涼子は、頭の中に紅蓮の炎を見た気がした。がばっと上体を起こし、明日香のほうに身を反転させる。 「変なところ触るの、やめてって言ってんの!」 言葉を発し終えたと同時に、明日香の両手が顔面に飛んできて、ぱしっと頬を包まれた。両頬を押され、唇が前に突き出る。 意外にも、明日香の顔は、笑っていなかった。 今、自分が何をされているのかも理解できない心境で、困惑していると、次に、嗅覚が刺激された。涼子の汗で濡れているせいだろう、明日香の手のひらから、生ゴミの腐ったような臭いが、ぷーんと鼻腔に流れ込んできたのである。自分の汗の臭いだというのに、涼子は、思わずむせ返りそうになった。 明日香は、あくまでも真顔のまま、さらに涼子のほうに顔を近づけてくる。 恐ろしく美しい女の顔が、涼子の視界を占める。涼子は、またぞろ、明日香の美貌ぶりに圧倒され、対する自分は今、唇を前に突き出した、見るに堪えない間抜け面をさらしているのだろう、という劣等意識を抱かされる。ほどなくして、明日香の息が、顔にかかるのを感じた。思い出したくもないが、以前、彼女のその唇が、突然、涼子の唇に押し当てられたことがある。女同士の行為、しかも、その相手が、穢らわしい存在としか思えない女だったせいもあり、あの一瞬、唇に受けた、ぞっとするほど柔らかい感触は、忘れたくても忘れられなかった。今、また、それが再現されるのではないかという警戒心を抱き、涼子は、唇を引き結ぶようにして引っ込める。 明日香の口が開かれた。 「りょーちん。これから、体育倉庫の地下に来いっ。いいなっ?」 彼女にしては珍しい、有無を言わせぬ口調だった。 そうして、明日香は、涼子の頬から手を離し、さっと立ち上がった。 涼子は、たった今、言われた言葉を、頭の中で反復する。聞き間違いであってほしいと思いながら。 体育倉庫の地下……。 恐怖が、じわじわと胸一杯に膨れ上がっていく。あの、陰鬱極まりない空間で、着ているものをすべて脱がされ、恥辱に打ち震えていた記憶が、暗黒の世界の出来事のように、脳裏にフラッシュバックする。涼子にとって、体育倉庫の地下は、この学校という監獄の中でも、もっとも怖ろしい、二度と足を踏み入れたくない場所だった。 「いやぁ……。わたし、あんなところ、行きたくない……」 涼子は、わななく声で拒否する。 「ダメ。これから、来いっ」 明日香は、涼子を見下ろしながら、冷然と言う。今や、彼女の顔からは、笑いめいたものが、すっかり消え失せており、その眼差しには、無機質なまでの厳しい光が宿っていた。 涼子は、今になって悟った。明日香が、涼子の体をマッサージしたがった、その真の意図を。単純なことである。涼子を足止めし、ほかの三年生の部員たちから引き離すのが狙いだったのだ。自分は、まんまとそれに引っかかり、あまつさえ、この悪魔にも良心が残っていると信じて、苦しい胸の内を語り続けていた。そんな自分のお人好しぶりを思うと、涙が出そうになる。そして、明日香は、こうまでして、涼子のことを、体育倉庫の地下に連れて行こうとしているのだ。ならば、こちらとしては、なおさら、それに従うわけにはいかない。 「わたし……、これ以上、あなたたちに、何か変なことされたら、本当に、心も体も壊れちゃう……。絶対に、絶対に、行かないからっ!」 涼子は、断固たる意思を込めて言い放った。それこそ、身を引きずられたとしても、この場から動かないつもりだった。 すると、明日香の口もとに、うっすらとした笑みが浮かんだ。 「りょーちん。実はねえ、りょーちんに、会わせたい子がいるの……」 思いがけない言葉に、涼子は、眉をひそめた。 「……会わせたい子? それって……、誰なの?」 そう尋ねずにはいられなかった。 明日香は、吹き出すのを堪えるような表情をする。 「それは、会った時の、おたのしみぃ……。今、体育倉庫の地下でぇ、その子が待ってんの。りょーちんも、来たほうが、いいと思うよぉーん。だってぇ、その子はぁ、りょーちんの、『な・か・ま』なんだもんっ」 仲間……。 涼子の胸の内で、色々な想念が生じて絡み合う。 明日香は、皮肉っぽく唇を曲げ、言葉を続けた。 「りょーちんにとっては、せっかくできた、『な・か・ま』なのに、会わずに帰っちゃって、いいのかなぁ……。もしかしたら、その『な・か・ま』と、いい関係になれるかもしれないのにぃ」 涼子は、明日香から視線を外し、何もない壁を見つめた。頭の中を整理しようと思う。だが、思考の断片が、とりとめもなく渦を巻いており、論理的に物事を考えようとすればするほど、混乱が増し、頭がくらくらするような状態だった。 果たして、明日香の言う、涼子の『仲間』とは、誰なのか……? 皆目、見当がつかない、というわけではない。むしろ、脳裏には、ある生徒の顔と名前が、すでに、おぼろげな蜃気楼のように浮かんでいる。もし、今、体育倉庫の地下で、その生徒が待っているのだとしたら、自分は、どうするべきか……? 会っておきたい……! 胸の内を浮遊する想念のひとつが、そう強く主張する。 だが、場所が場所である。体育倉庫の地下に降りるなど、まるで、自ら、鉄格子の中に入りにいくようなものだと思う。下手をすると、そこで、両手を鎖でつながれ、身をつるし上げられる事態にもおちいりかねない。そうして抵抗するすべを奪われたら、あとはもう、悪魔たちのなぶり者にされる未来しかないのだ。 考えただけで、体中に戦りつが走る。 本能は、体育倉庫の地下に向かうことを、激しく拒絶していた。 しかし、今、あの場所で待っているという生徒に、会っておきたい、顔を確認しておきたい、という思いを、どうしても捨てきれなかった。もし、このまま帰路に就いたとしても、その生徒のことが頭から離れず、どこかの時点で、自分は、学校へと引き返してくるような気がした。よしんば、家に帰ったとしても、一向に気持ちが落ち着かず、今夜は、布団に入って目を閉じることさえ難しいだろう。それに、涼子の胸の内には、不思議な予感があった。その生徒に会えば、現在、自分を取り巻いている、多くの物事が、よい方向に変わっていきそうな、そんな予感だ。 「ほらっ、立って、りょーちん」 明日香は、こちらに手を差し伸べてくる。 その手を握り返すことはしなかったが、彼女に促される形で、涼子は、そろそろと重い腰を上げた。そして、一筋の光が差した明日を目の当たりにしているかのように、前方だけを見つめながら、明日香と並んで歩き出した。 しかし、それから何分も経たないうちに、またしても明日香と押し問答をすることになった。 体育館の玄関で、涼子は、バレーシューズを脱ぎ、ランニングシューズを突っかけると、前を行く明日香に向かって抗議した。 「ねえっ! なんのつもりなの!? わたしのバッグ、返してよっ!」 二人で部室に入ってから、間もなくのことである。 涼子は、自分のバッグを探し当てると、かがみ込み、そのチャックを開けようとした。だが、それを見ていた明日香は、いきなり、涼子のバッグを奪い取ると、そのまま、部室を出て行ってしまったのである。 そのため、今、涼子も明日香も、制服には着替えておらず、練習の時と同じ格好でいた。 明日香は、玄関を出ると、こちらを振り返った。 「だいじょーぶ。あとで、ちゃんと返してあげるからっ」 ぶっきらぼうに、そう答える。 「なんで!? わたしは、今、返してほしいの!」 涼子も、引き下がらなかった。 「今はダメ」 明日香は、ぷいっと横を向く仕草をする。 「どうして!? その理由を教えてっ」 涼子は、強く問いただす。 「うるさいっ。ダメったらダメなのっ」 明日香の態度は、取りつく島もない。 これ以上、食い下がって、明日香の機嫌を損ねるのは、賢明ではないような気がし、涼子は、いったん口をつぐんだ。理由は不明だが、明日香は、どうあっても涼子にバッグを返さないつもりらしい。もしかすると、涼子が逃げるのを防ぐためかもしれない、と思う。だが、涼子としても、これだけは譲れない、というものを抱えていた。 「わかった……。なら、バッグは、明日香が預かってて。でも、わたし、何よりもまず着替えたいの。ものすごい汗かいてて、気持ち悪いし……。だから、せめて、着替えのものだけは、渡してもらえない? それならいいでしょっ?」 そう言っているうちにも、汗で体に張りついたTシャツが気持ち悪くなってきたので、胸もとの部分を指でつまんで、ぱたぱたと扇ぎ、中に空気を送り込むようにした。いくらなんでも、この最低限の要求は受け入れられるはずだと思っていた。 ところが、明日香は、首を縦に振ろうとはしなかった。 「いいのっ。着替えなんて、する必要ないのっ」 その返答を聞いて、涼子は、あんぐりと口を開けた。 「えっ、えっ……。意味がわからない。必要ない、とかじゃなくて、わたしは、どうしても着替えたいの。だから、着替えのものだけは、渡してくれる?」 なるべく、腹立ちを露わにしないよう、あくまでも穏やかな口調で要求する。 「着替えなんて、する必要ないって、言ってんでしょっ。りょーちんは、あたしの言うことに、黙って従ってればいいのっ」 明日香は、眉間にしわを寄せている。 理不尽にもほどがある。怒りのあまり、目のくらむような感覚を覚えた。 「どういうこと!? 着替えもさせてくれないなんて。わたしが着替えると、あなたにとって、何か不都合なことでもあるの!? ないでしょっ? わたし、この格好で誰かと会うなんて、嫌でしょうがないの!」 涼子は、声を荒らげながら、自分の体を守るように両肩を抱いた。 すると、明日香は、気だるげな表情をし、それから言った。 「香織にぃ、言われてんのっ。絶対に、りょーちんを、着替えさせないで連れてくるように、って。だから、その格好で、来いっ」 吉永香織……。 涼子を辱めることを目的としているグループの、主犯格の女。 いったい、あの女は、どのような思惑で、明日香にその指示を出したのか。それは、考えても無駄だろうし、また、考えたくもなかった。しかし、なんにせよ、あの女に対しては、底知れぬ気色悪さを感じる。 そして、ようやく、明日香が涼子のバッグを奪った、その意図を理解した。最初っから、バッグというより、その中に入っている、涼子の着替えの衣類が目当てだったのだ。明日香のかたくなな態度からするに、どう懇願しても、それを返してもらえる見込みはないだろう。取り返すためには、それこそ腕力を行使するしかない。しかし、そのような手段は、悪魔たちの策謀によって、完全に封じられているのだ。涼子は、自分の無力さが、心の底から恨めしくなり、下唇を噛んだ。 明日香は、こちらに手を伸ばす。 「はい、りょーちんが、今、持ってるものは、バッグにしまってあげるから、よこして」 涼子は、肘と膝のサポーター、それにバレーシューズを手に持ったままでいた。ため息がこぼれる。これらのものを、後生大事に自分で抱えていても仕方があるまい。その三点を、投げやりな手つきで明日香に渡した。 明日香は、涼子のバッグのチャックを開け、それらを中にしまうと、すっきりしたような表情で言う。 「これでよし、と。じゃあ行こっか、りょーちん」 そうして、くるりと体の向きを変え、体育倉庫へと歩き始めた。 涼子は、少しばかり遅れて、その後ろを付いていった。 数メートル先を行く、明日香の後ろ姿を、じっと見すえる。華奢な体のライン。おまけに、涼子が後ろを歩いていることなど、気にも留めていないかのように、油断しきっている様子である。いっそ、力ずくでバッグを取り返そうか、と思い始める。もちろん、涼子が欲しているのは、着替えの衣類だった。 その気になれば、たやすいことだ。なにも、明日香に怪我を負わせるわけではないのだから、深刻に考える必要もないはずだ。まず、ほっそりとした彼女の身に、軽い体当たりを喰らわす。それで、彼女が驚いたその隙に、自分のバッグを奪い返す。一瞬で終わることだ。その後は、ダッシュで部室まで戻り、急いで着替えを済ませればいい。明日香は、烈火のごとく怒り狂うだろうが、それに対しては、ひたすら謝り続ける。ひょっとすると、暴力を振るわれるかもしれないが、明日香の非力さを考えれば、その痛みなど、蚊に刺されるようなものだろう。そして、こちらに、逃げる意思がないことを、どうにか伝えられれば、いずれ許されるはずである。そうだ。そうしよう。こんな、自分でも閉口するくらい、汗臭い格好で、バレー部以外の生徒と会うなんて、想像もしたくない。それに、今、体育倉庫の地下で待っているのが、もし、脳裏に浮かんでいる生徒だとしたら……。そのことを考えると、より一層、着替えておきたい、という思いが強まる。やっぱり、力ずくでバッグを取り返そう。今なら、まだ間に合う。絶対、行動に移すべきだ。 涼子は、じりじりと明日香との距離を縮めていく。 さあ、やれ……! そう自分に命令する。 しかし、明日香の背中に向かって、あと一歩、踏み出す勇気が、なかなか湧いてこない。 ふと、涼子は、さらに向こうへと視線を飛ばした。 目的の場所は、すでに視界に入っている。夕闇の風景に溶け込んでいる、小さなやしろのような建物。周囲が暗いせいもあり、涼子の目には、その建物が、ことさら、おどろおどろしいものに映る。本当に、わたしは、あの場所に入っていくつもりなの……? 自分の正気を疑いたくなると同時に、冷たい恐怖が、足もとから這い上ってくる。それでも前に進み続けていると、だんだん、自分の格好を気にするだけの余裕すら、失われていく感じがした。 結局のところ、涼子は、明日香に対して、なんら行動を起こすことなく、体育倉庫の前まで来てしまった。 明日香は、鉄製のドアをがらがらと開けると、涼子のほうを見て、小馬鹿にするような含み笑いを浮かべた。その顔は、こう語っていた。何もかも、あたしたちの思いどおり……。 涼子は、ドアの中の暗闇を、しばし凝視していた。まさに、いよいよ、鉄格子の中に閉じ込められるという心境だった。 危険だ。危険すぎる。考え直したほうがいい……! そう本能が警告してくる。 今一度、自分には、このまま帰るという選択肢もあることを思う。勇気を振り絞って明日香と戦い、バッグを取り返せばいい。そうすれば、すぐに、この監獄から抜け出し、自宅へと向かうことができるのだ。それは、ある意味、夢のような話である。しかし、目の前にある闇の向こうには、きっと、自分の運命を変えてくれる何かがあるはず……。その予感が、涼子の足を留めていた。 「なにしてんの、りょーちん。早く入って」 明日香が、ささやくような声で言う。 涼子は、軽く息を吸い込み、それを吐き出すと共に覚悟を決め、暗闇の中へと入っていった。 奥へと進み、地下への階段の降り口に立つ。 そこから見下ろした地下の空間は、昼のように明るかった。すでに、明日香が言うところの、涼子の『仲間』が待っている、何よりの証左だ。 涼子は、緊張のせいで、膝が小刻みに震えるのを自覚しながら、階段を降り始めた。 こんな時間に、こんな場所で待っているのは、いったい誰なの……? 疑問の念が、頭の中をぐるぐると回っている。 まさか……、あなたなの……? 脳裏に浮かんでいる生徒に対し、胸の内で問いかける。 しかし、次の瞬間、その彼女の像は、急速に薄れていった。根拠はないのだが、あの彼女が、こんな陰鬱極まりない場所で待っているという状況は、どうも現実味に乏しいような気がしたのだ。では、彼女でないとしたら、誰なのか? もしかしたら、自分とは、まったく面識のない生徒なのではないだろうか? だんだん、そっちの可能性のほうが高いような気がしてきた。けれど、明日香が、涼子の『仲間』と表現したからには、もはや、彼女以外には考えられないような……。 涼子は、もうすぐ顔を合わせる人物について、自分の予想が当たってほしいような、それでいて外れてほしいような、なんとも複雑な心境で、階段を、一段一段、踏みしめながら、ゆっくりと降りていった。 階段の残りは、あと、四、五段だ。 地下で待っている生徒と対面する瞬間は、目前に迫っている。 いったい、誰なの……!? 涼子は、もう一段、階段を降りると同時に、地下全体を視界に入れた。 テニスコート一面分ほどの広さのある、地下スペースの、ちょうど中央に、その生徒は、ぽつねんと立っていた。 予想は、的中した。 クラスメイト。三年に進級してから、この何ヶ月間、涼子は、ずっと、彼女との距離感を縮めたいと願ってきた。しかし、それが一向に叶わず、やがては、彼女に対して、苦手意識を抱くようになった。そして、現在、涼子にとって、彼女は、その顔を見るだけで身がすくんでしまうほど、恐怖を感じる対象だった。その彼女との、衝撃的な対面。 充分、覚悟はしていたにもかかわらず、実際に滝沢秋菜の姿を見て、涼子は、目をむいた。 滝沢さん……! やっぱり……、というか、そんな、嘘でしょう……!? 驚愕したのも、つかの間、自分が、部活の練習の時と同じ格好で、この場に来てしまったことを、猛烈に後悔させられる。今思えば、明日香の腕をねじり上げてでも、着替えの衣類の入ったバッグを取り返すべきだった。いや、今からでも遅くない。すぐに、着替えてこなくては。その衝動に襲われ、涼子は、身をひるがえして階段を駆け上がろうとした。しかし、上を見て、はっとする。 階段の半ばほどの段で、明日香が、仁王立ちして立ちふさがっていたのである。 「りょーちん。どこ行く気なのっ」 その声音は、明らかに涼子の行動をとがめていた。見ると、彼女は、バッグを肩に提げていなかった。上に置いてきたのだろう。 「そこ、どいて! わたし、バッグを取りに行く! どうしても邪魔するなら、力ずくでもどいてもらうからっ!」 涼子は、内に秘めた野性味を全開にして怒鳴った。 「うっさい。いいから、降りてろっ」 明日香は、しかし、まるで怯んだ様子もなく、尊大に命令してくる。 その言葉を無視し、涼子は、大股で階段を踏み鳴らしながら昇っていった。 すると、明日香が、右足を宙に上げた。 「言うこと聞かないと、顔、蹴り飛ばすよ」 彼女の履いているランニングシューズの裏が、こちらに向けられている。 そんな脅し、ちっとも怖いとは思わない。 涼子は、さらに一段、二段と階段を昇り、明日香の足もとまで迫った。このまま、明日香の身を突き飛ばすつもりだった。 だが、そこで、明日香のシューズの裏が、本当に顔面に飛んできた。すんでのところで、左腕を上げてガードをする。左腕の前腕に、がすっ、という衝撃を受けた。一拍遅れて、その部分に痛みを感じた。 「……いったぁ」 ぽつりと声を漏らした。蹴られた部分を見てみると、皮膚が赤くなっている。どうやら、明日香は、ひとかけらの躊躇もなく、渾身の力で、涼子の顔を踏みつけようとしたらしい。 涼子は、怒気を露わに、上にいる明日香の顔をねめつける。 明日香は、冷たい眼差しで、涼子を見下ろしながら、ふたたび右足を浮かせる。 涼子が、反撃してくることはない。その確信を持っているから、涼子とパワー比べをしたら、幼子も同然のくせに、そんな強気な行動に出られるのだ。一回、目に物を見せてやる……。そう思い、涼子は、上に向けて突進の構えを取った。 しかし、その時、斜め後方から、声が届いた。 「南さんっ! 待って。行かないでっ。南さんが、どうしてここに来たのか、その理由を、教えてくれない!?」 滝沢秋菜が、そう叫んだのだった。その声には、どことなく悲痛な響きがこもっていた。 涼子は、それを聞いて、当惑させられた。秋菜に話したいことは、それこそ山のようにある。しかし、今のこの格好で、秋菜のそばに寄ることには、耐え難い抵抗を感じるのだ。 「ほらっ。りょーちんの『仲間』が、ああ言ってんだからっ、早く行ってあげなよぉ」 明日香が、刺々しい声で言う。 仲間か、と思う。そう。今や、涼子と秋菜は、仲間同士の関係にあるらしい。だが、その本当の意味は、まだわからない。秋菜と話せば、それが解明されることだろう。しかし、今の涼子にとっては、とにかく制服に着替えることが、最優先事項なのだった。 「南さんっ! お願いだから、こっちに来てっ!」 秋菜が、再度、大声で涼子を呼ばわる。 涼子は、意味もなく、両手で首の後ろを押さえ、その場で逡巡した。今すぐ、そちらに行ってあげるべきなのか……。 明日香が、一段、下に降りてきた。 「あんまりぐずぐずしてるとぉ、また、蹴り飛ばすよっ」 そう恫喝を受ける。苛立たしげな明日香の態度を見るに、あと、何秒もこうしていると、本当に足が飛んでくるに違いない。 上には、明日香が立ちふさがっており、下からは、秋菜が呼んでいる。もはや、後ろに下がる以外に選択肢のない状況だった。 涼子は、まさに断腸の思いで、着替えを諦め、階段を降りていった。 地下の地面に降り立つと、改めて滝沢秋菜と対面した。秋菜との距離は、十メートル以上あるだろうか。むろん、涼子のほうから、秋菜に近づく気にはなれない。やや不自然に距離を保ったまま、お互いに見つめ合う。秋菜の表情や仕草を見ていると、これは、本当に、あの滝沢秋菜かと疑いたくなる。何よりもまず、普段のような冷然たる余裕が、微塵も感じられないのだ。そわそわとして落ち着きがなく、その顔には、不安の影が色濃く表れている。秋菜が、何かしら、せっぱつまった立場に置かれていることだけは、間違いないと判断していいだろう。 階段の足音から、明日香も、降りてくるのがわかった。 涼子は、後ろを振り返る。 明日香は、地面から一段上の段で足を止めた。涼子たちのことを見ながら、ふふふっ、と笑う。 「お二人さん。『仲間』同士、仲良くしてねっ。色々と話したいこともあるでしょっ? 邪魔者は消えるんでぇ、どうぞ、ごゆっくりぃ」 そう言い残し、弾むような足音を立てながら階段を昇っていく。 涼子と秋菜が残された。 お互い、何から話せばいいのかわからず、言葉を探している。そういう状況だった。 涼子は、つと、周囲を見回す。 灰色のコンクリートの壁には、あちこち、ひび割れができており、なんとなく、学校側も、校内にこんな場所があることなど、完全に忘れているのではないかとさえ思う。あるものといえば、もはや、十年以上、誰も使っていなさそうな、ほこりかぶった体育用具だけだ。空気は、異様なくらい、じめじめとしており、汗まみれのTシャツとスパッツが、よけい肌に張りついてくる感じがして、不快でたまらない。 恥辱に満ちた過去の体験を抜きにしても、ここは、地下牢を連想させられるような、なんとも嫌な場所だと思う。 それは、秋菜にしても同じはずだった。 今、秋菜は、怯えているようにさえ見える。おそらくは、この空間の環境も、彼女の心理に大きな影響を与えているに違いない。 涼子のほうから口を開いた。 「あの……、滝沢さんは、誰に呼ばれて、こんなところに来たの……?」 そう問うと、秋菜は、一瞬、涼子と目を合わせたが、しかし、視線を落とし、口に出すのをためらうような素振りを示す。 数秒の間、涼子は、秋菜の返答を待った。 だが、秋菜は黙っているため、思い切って尋ねる。 「ねえ、もしかしてだけど……、うちのクラスの……、吉永香織?」 かなり高い確率で、当たるだろうと思った。 案の定、秋菜は、はっとした表情を見せる。 「どうしてわかったの……!? まさか、南さんも、あの、吉永香織に呼ばれて、ここに来たってこと!?」 その名前の言い方から、秋菜にとっても、吉永香織は、単なるクラスメイトではない、憎んで当然の相手であることが、はっきりと伝わってきた。 涼子は、どのように答えようかと迷う。 その直後、秋菜は、いかにも打ち解けて話せる仲間と出会えたとでもいうように、唐突に駆け寄ってきた。 お互いの距離が、五メートルを切ろうとしている。 ちょっと待って……! 涼子は、心の内で悲鳴を発した。 瞬時の判断で、体の向きを右に変え、壁に向かって、逃げるような早足で歩いていく。 壁のところまで行くと、ふたたび、秋菜と、十メートルほどの距離を取ることができた。 秋菜は、涼子の行動に、いささかショックを受けたのか、切なげな眼差しをこちらに向ける。 「あっ、いや、うーん、まあ……」 涼子は、意味のない声を出しながら、ごまかすように笑った。 今、近寄られた瞬間、秋菜に、汗臭い、と思われなかったか、心配で仕方がない。いや、もしかすると、こうして離れていても、自分の体が発する強烈な汗の臭いは、秋菜の鼻孔に届いているのではないか。それを思うと、羞恥の情でいたたまれなくなる。 だが、そんな内心を押し殺し、平静な表情を作って口を開く。 「なんていうか、わたしは……、あの吉永香織と、色々あったんだけど……。揉め事。……ううん、違うな。嫌がらせ……。そう。すごい嫌がらせを、散々、受けてきて……。あのっ、滝沢さんも、吉永香織との間に、何かあったの?」 まだ、今の段階で、多くのことを語る気持ちにはなれなかった。 秋菜は、人差し指を頬に当て、考え込むような表情をした。話そうかどうか迷っているようだ。 涼子は、続けて尋ねる。 「ねえ、もしかして……、滝沢さん、吉永香織に、なにか弱みを握られてない?」 すると、秋菜の目が見開かれた。図星だったらしい。 「どうして、そこまで知ってるの……?」 秋菜は、茫然とした様子で言う。 「お願い、話して……! いや、わたしから話す。実は、わたしも、吉永香織に、弱みを握られてるのっ」 涼子は、勢い込んで打ち明けた。 「南さんも……?」 秋菜は、ひどく驚いている。 「うん。正確に言うと、吉永香織っていうか、あいつを含めた三人のグループに、弱みを握られてる。一人は、さっき、わたしとここに来た、竹内明日香。もう一人は、一個下、二年の、石野さゆりっていうやつ。三人とも、人間じゃないと思うくらい、腐りきった性格してる」 涼子は、思いっ切り顔をしかめた。 「三人なんだ……? それで、南さんの握られてる弱みって、なに……?」 当然の質問だろう。 涼子は、唇を舐め、腹を決めて話し始めた。 事の経緯を、秋菜に、よく理解してもらえるよう、話の起点は、竹内明日香が、バレー部のマネージャーに志願してきたところからにした。その内容に続き、明日香は、表向き、バレー部のために献身的に活動していたが、その目的は、涼子を罠にハメるのに、何かいい機会がないか、それを探ることであったのだと説明する。 そして、話は、バレー部の合宿費を、あの三人に奪われた日のことに移った。 涼子は、あの日、起こったことを、順を追って細かく話していった。 消えた合宿費。竹内明日香によって、この体育倉庫の地下に誘導され、その後、ひとりで待っている間、いかに心細かったか。竹内明日香が、部外者である、吉永香織と石野さゆりを連れて戻ってきた時、自分は、怒りを通り越して呆れるしかなかったこと。さらに、その、石野さゆりという後輩に対しては、最初に会った瞬間から、生理的に受けつけない生徒だという印象を持ったこと……。 いよいよ、話の核心部分に入る。 吉永香織は、状況的に、バレー部の合宿費を盗むことができたのは、涼子しかいないのだから、涼子には、身の潔白を証明する義務があると主張した。その証明とは、服を脱いで、体のどこにもお金を隠していないことを、三人の生徒に確認させる、というものだった。もちろん、涼子は、拒否をした。すると、吉永香織は、それならば、涼子のことを、窃盗の犯人として、学校側に報告すると言い始めたのである。涼子は、それを聞いて怖ろしくなり、正常な判断能力を失った。そして……。 涼子は、秋菜の視線から逃れるように、下を向いた。同学年の生徒、二人に加え、後輩まで見ている前で、着ているものを、すべて脱がされた、あの、屈辱そのものの体験。それを、いったい、どのような言葉で表現したらいいのか、途方に暮れる思いである。だが、ここで、変なプライドから、話をあやふやにしてしまえば、秋菜との関係は、まったく前進しないだろう。それでは、意味がないではないか。 「……わたしは、下着だけの格好になった。当然、そこまでしたんだから、無実の証明になると思った。だけど、吉永香織は、わたしに、下着も脱ぐことを要求してきた。わたしが、それを拒んでると、もう、無理やり……。自分でも情けないって思うんだけど、わたし、全然、抵抗できなかったの。あまりに非日常的な事態だったせいで、頭が混乱しすぎてたっていうのもあるし、もちろん、下着だけの格好にさせられた恥ずかしさで、すっかり気持ちが萎縮してたこともあるし、あとは、何をされるかわからない恐怖心で、体が、ほとんど硬直してた感じもする。それで……、わたしは、結局……、裸にさせられた。そうしたら、あの三人、スイッチが入ったように、大喜びではしゃぎ始めたの。さすがに、その時になって、わたしも、ハメられたってことに気づいた。それと、バレー部の合宿費を盗んだのは、吉永香織たちだってことも、確信した。もう、その時には、何もかもが遅すぎたんだけどね……。そうだ。最後の最後、わたしは、裸で立ってる姿を、デジタルカメラで撮られたの。その写真が、要するに、わたしの弱み……」 話していて、苦しくてたまらなかった。正直、誰にも知られたくなかった体験を、今まで、苦手意識を抱いていた相手である、滝沢秋菜に語ったのだ。 涼子は、秋菜の顔を、ちらりと見る。 秋菜は、口もとを手で覆っていた。涼子の話の内容に、ずいぶん衝撃を受けている様子だ。 自分が握られている弱み。そのことについて、十五分くらい時間を使って語ってきた。 だが、実際には、まだ、真実の半分も明らかにしていないといえる。 なぜなら、現在、涼子にとっての、一番の弱みは、単なる裸の写真ではなく、ほかでもない滝沢秋菜がらみのものなのだ。涼子の体液で汚れた、滝沢秋菜の体操着のシャツ。それと、その体液が、紛れもなく涼子のものであることを示す写真。そのセットが、香織たちの手中にある。しかし、そのことを、今、秋菜に説明するには、それこそ、自分の味わった、身を焼かれるような恥辱の数々を、赤裸々に打ち明ける必要がある。まだ、秋菜に対して、そこまで心をさらけ出すことはできない。いや、できれば、最後まで、自分の胸の内に秘めておきたいと思う。 ただ、いくつか、この場で、秋菜に告白しておくべきことがある。 「滝沢さん……。頭のいい、あなたなら、もう、勘付いてることだと思うけど……、わたし、あなたのバッグから、写真を盗んじゃった……。もちろん、わたし、そんなこと、絶対にやりたくなかったんだけど、吉永香織たちに、滝沢さんの写ってる写真を盗ってこないと、どうなっても知らないよ、って脅迫されて、それで、逆らうことができなかった……。あの、今さら謝って済む問題じゃないって、自分でも、よくわかってるんだけど……、本当に、本当に、ごめんなさいっ」 涼子は、秋菜に向かって、腰を折り、深々と頭を下げた。 「……ああ、そういうことだったんだ」 秋菜は、納得したように言う。だが、低頭している涼子に対し、それ以上のことは口にしなかった。おそらくは、涼子が、写真を盗んだのも、致し方ないと思う反面、完全に許していいものか迷っているのだろう。 涼子は、そろそろと顔を上げた。秋菜に対する罪悪感で、胸を締めつけられる思いである。 「あと、それと……」 二つ目の告白だ。それは、文字通り、自らの恥部をさらすようなものだった。 「滝沢さん……。あの……、あなたの保健の教科書に、……裸の写真が、貼りつけてあったでしょ? あれ……、わたしを、写したものだから。ねえ……、滝沢さんも、そのこと、とっくにわかってたよね?」 涼子は、おそるおそる尋ねる。 すると、秋菜は、斜めに視線を落とし、答えにくそうに唇を歪めた。 「……あ、まあ、うん」 それを聞いて、涼子は、少なからず動揺した。充分、予期していたとはいえ、いざ、そう答えが返ってくると、どう気持ちを整理していいのかわからない。案の定、秋菜は、例の写真に写っている全裸の女について、これは、南涼子の裸だ、という確信を持っていたのだ。ならば、この数日間、秋菜が、涼子に対して、どのような感情を抱いていたのかは、容易に察せられる。変態。変態。毛深くて汚らしい体の、変態女……。そういう目で見られていたと思うと、今さらながら、ぶるりと身震いしてしまう。 「そうだよね……。わかってたよね……。まあ、ああいう写真を……、吉永香織たちは、わたしの弱みとして握ってるってわけ……。それで、もし……、滝沢さんの家に、まだ、あの写真が残ってるなら、さっさと捨てちゃってね。あんな、気持ちの悪いもの」 涼子は、かろうじて苦笑の表情を作ることができた。 「……うん、わかってる」 秋菜は、気まずそうに横を向く。 どうやら、例の写真を、まだ、処分していなかったようだ。処分するにしても、最低でも、あと一回は、秋菜が、写真の中の光景とはいえ、涼子の全裸を目にする機会があるということ。なるべく、秋菜には、その裸体から目をそらし、写真を、手早くゴミ箱の奥に突っ込んでほしいと思う。 最後に、秋菜に弁明したいことがあった。 「あの……、三日前のことなんだけどさ……、滝沢さん、バレー部の練習を見に来たよね? あの時……、わたし、なんていうか、見るに堪えない格好で、練習に出てたでしょ? 実はさ、あれも、吉永香織たちに脅迫されて、無理やり、やらされたことなの。わたし、ゲーム中は、もう、泣きたいくらい恥ずかしくて、本当に、地獄の思いだった。でも、それを見てたみんなは、当然、そんな裏の事情は知らないから、わたしが、自ら望んで、あんな格好をしてたと思ってる。だから、わたし、キャプテンとしての面目を完全に潰されたし、それに、わたしが変態だっていう噂が広まったせいで、たくさんの友達を失ったし、高校生活は、何もかもめちゃくちゃになっちゃった。もう、最悪としか言い様がないよ」 涼子は、髪の毛に両手を突っ込み、くしゃくしゃとかきむしった。 秋菜は、同情的な眼差しで、涼子のことを見ている。 「そっか……。わたしも、あの時は、なんで、南さんは、こんな格好で練習に出てるんだろう、って不思議でしょうがない思いだったんだけど……、そういう事情だったんだ……。なんか、南さんに対する誤解が、全部、解けた感じがする……」 彼女の言葉に、涼子は、大いに救われた。 「ありがとう。滝沢さんに理解してもらえただけでも、わたし、すごく嬉しい」 両肩にのしかかっていた重荷が、すーっと軽くなっていく気分だった。 涼子は、胸に手を当て、秋菜の顔を真っ直ぐに見すえた。 「わたしのほうから話せることは、すべて話したつもり。今度は、滝沢さんが話してくれる? 吉永香織に、どんな弱みを握られてるのか」 沈黙が落ちる。 お互いに目と目を見合わせていた。普段は、あれほど冷ややかな光を湛えていた、秋菜の眼差しが、今では、湿り気すら帯びているように感じられる。涼子は、そんな秋菜に、視線で言葉を送る。わたしのことを、信頼して……。 やがて、秋菜は、観念したように目を伏せ、おもむろに語り始めた。 「わたしには、どうしても行きたい大学があって、三年に上がった頃からは、もう、昼も夜もなく勉強をしてきた。毎日の睡眠時間は、三、四時間くらいで、まさにカフェイン漬けの状態。そんな生活を続けてきたから、最近は、だいぶ体にガタが来てたんだよね。勉強の時も、集中力が続かなくなってたし、頭の働き自体が鈍ってるのを、自分でも痛感してた。だからって、休んでいたら、その分だけ、志望大学の合格率が、じりじり下がっていく感じがして、気が変になりそうで、わたしは、空回りしてるってわかっていても、勉強し続けるしかなかった。そんな時、学校で、あの吉永香織が、わたしに言ってきたの。ものすごく勉強の能率が上がる、薬があるんだよっ、て」 「くすり……?」 涼子は、思わず、その単語を口にした。 秋菜は、うなだれるように、ゆっくりとうなずいた。 「吉永香織から、その薬を一錠、もらった。わたしは、なんとなく、やばいもののような気がしたし、それに、本当に効果があるのかも疑わしかったから、飲もうかどうか迷ったんだけど……、夜、勉強の前に、試しに飲んでみた。そうしたら……、びっくりしちゃった。まさに目が覚めるっていう感じ。溜まってた疲れは吹っ飛ぶし、勉強に取りかかったら、どんどん知識を吸収していくのを実感できるし、何より、集中力が、朝まで途切れることはないの。わたし、涙が出るくらい感動しちゃった。だから、その翌日、吉永香織に、同じ薬をちょうだい、って頼み込んだ。そうしたら、吉永香織は、薬を売ってくれる店を紹介してあげる、って答えた。それを聞いて嬉しくなって、放課後、わたしは、吉永香織と一緒に、駅のそばにある、地下の、喫茶店みたいなところに入った。その店が、いかにも怪しげでさ。それで、店員の男に言われて、わたしたちは、一番奥のテーブルに着いた。そのテーブルには、錠剤だけでなく、何種類かの粉も置いてあってさ、それを見て、わたしも、ああ、やっぱり、違法な薬だったんだ、って思ったんだけど……」 涼子は、秋菜の話の深刻さに、どくどくと動悸を感じ始めていた。 秋菜は、悔恨の念に満ちた表情をする。 「志望大学に行くためなら、どんな手でも使うつもりだった。だから、たとえ覚醒剤だとしても、構わないって思った。それで、わたしは、財布の中に、一万、持ってたから、そのお金を出して、薬を下さいって、店員の男にお願いした。そうしたら、店員の男は、受験生にはぴったりの薬があるから、それを、この場で試してみるといい、って言って、わたしの前に、白い粉を置いたの。わたしは、その男に言われるままに、ストローで、その粉を吸引した。受験生にぴったり、なんて言葉は、大嘘だった。わたしは、粉を吸引した直後、頭の中が、ぐちゃぐちゃになるような感覚に襲われた。ただ……、その代わり、例えようもない、快感が、体を突き抜けてったの。快感のあまり、わたし、しばらくの間、失神しかかってた。どんな快感かっていうのは、なんか、下品な言葉でしか表現できなそうだから、説明はやめておくけど……。それで、わたしは、店員の男に騙されたことに気づいたんだけど、まだ、快感の余韻に浸ってたこともあって、怒る気にもなれなかった。そのあと、結局、一万払って、吉永香織がくれたのと同じ薬を、二十錠、買ったんだ。だから、その日は、なんていうか、こういう世界もあるんだな、って気分で、薬も買えたことだし、吉永香織に、お礼を言って、家に帰った。でも……、今日になって……、すべてが、仕組まれた罠だったことが、わかったの……」 涼子は、この世の深い闇を見せられている気分だった。 秋菜は、どこか虚ろな目で、地面を見つめている。 「今日、吉永香織に、保健室前のトイレに呼び出されたの。わたしは、また、薬を譲ってくれるんだと思って、胸を弾ませてトイレに行った。でも、違った。そこで、吉永香織は、わたしに、何枚かの写真を見せてきた。それを見て、わたしは、頭の中が真っ白になった。だって、写真には、わたしが……、ストローを使って、白い粉を吸引してるところが写ってたの。また、別の写真には、覚醒剤を吸った後の、わたしの、浅ましく乱れた姿が写ってた。写真の中のわたしは、ほとんど白目をむいてて、だらしなく口を開けて、その口から、よだれを垂らしてた。要するに、あの店には隠しカメラが設置されてて、わたしは、それで撮影されてたってこと。どうやら、吉永香織と、あの店員の男は、わたしを罠にハメるための、グルだったみたい。わたしは、ほとんどパニック状態で、吉永香織に、どういうつもりか問いただした。そうしたら、あの女は、わたしが、覚醒剤を使用してる、その証拠の写真を、匿名で学校に届けて、わたしを、退学にしてやるって言い始めたの。それで、もし、退学になりたくなかったら、今日の七時に、体育倉庫の地下で待ってろ、って言われて。わたしは、その指示に従うしかなくて、ここで、待ってた……」 怖ろしい……。 涼子は、震えおののかされた。 吉永香織という女が、腐った人間であることは、充分すぎるほどわかっていた。しかし、香織の外道ぶりは、涼子の想像以上だった。まさか、標的とした生徒の弱みを握るために、その生徒に、覚醒剤を使用させることまでするなんて。あの女は、人の皮をかぶった悪魔だ。改めて、吉永香織への憎しみを覚える。 そして、明日香の言う『仲間』の意味が、はっきりした。予想していたとおり、致命的な弱みを握られた者同士、ということだ。 そう……。とうとう、滝沢秋菜も、涼子と同じ立ち位置にまで堕ちてきたのだ……。涼子にとって、あれほど脅威だった、あの滝沢秋菜が。それは、すなわち、どういうことか。 涼子は、奇妙な感覚を抱き始めていた。 たしかに、秋菜の話の内容は、非常にショッキングだった。しかし、なぜだか、今、自分の体の奥底から、気、のようなものが、じわじわと湧き上がってきているのを感じる。いや、これは、エネルギーだ。いったい、自分の体のどこに、そんなものが残っていたのかと、自分でも不思議でならない。だが、エネルギーが体に満ちてくるのは、確かな事実だった。それだけではない。今まで、頭の芯が、もやに覆われているような状態だったが、一転、まるで別世界を体験しているかのように、意識が鮮明になっていく。 秋菜の話に出てきた覚醒剤ではないが、まさに、疲労が吹っ飛んでいく感覚である。もう、何日間も、まともな睡眠を取っていないことなど、嘘のようだった。今や、四肢の隅々まで、力がみなぎっている。生きる。それは、こういうことなのだ。 しかし、どうして、自分の生命力は、このように劇的に復活したのだろう。 それは、考えるまでもないことだった。 希望。 薄ぼんやりとではあるが、その光を、眼前に見たからだ。 滝沢秋菜が握られている弱み。覚醒剤を使用しているところを写した写真となると、涼子が、香織たちに握られている弱みより、断然、破壊力が上だろう。そんな写真を学校側が確認したら、まず間違いなく、秋菜は、退学処分となるからだ。秋菜の今後は、いったいどうなってしまうのか、クラスメイトとして心配である。だが……、秋菜の状況が、絶望的であればあるほど、逆に、自分が救われる可能性は高まっていくような、そんな気がした。 今まで、涼子は、自分が、秋菜の体操着のシャツを使って、自慰行為をしたという、その『物証』が、秋菜本人の元に届けられることを、何よりも怖れていた。しかし、今や、その秋菜も、涼子と同じ地平に立っているのだ。なので、吐き気がするくらい嫌な話だが、かりに、この先、例の『物証』を、秋菜が手に取ることになったとしても、それが、涼子の高校生活の破滅に直結することはない。秋菜だって、事情を完璧に理解しているのだから。すべては、吉永香織が、涼子に、無理やり行わせたことなのだと。 そう……。滝沢秋菜も堕ちてきたために、涼子にとっては、最大の脅威が消えたことになる。香織たちは、そのことに気づいていないのだ。 予感は当たった。 勇気を持って、この場に来れば、自分を取り巻く多くの物事が、よい方向に変わっていくのではないか。そんなふうに感じていたのだ。そうでなければ、竹内明日香に、どれほど脅されようとも、こんな場所には来なかった。 今、自分の中に、自己保身の権化と化した自分の姿が見える。その自分は、目が血走っていて、さらに、病的なほど青白い顔をしており、実に不気味な印象を受ける。真っ暗な地底で、もがき苦しむばかりの生活を送ってきたために、そんな風貌に変わってしまったのだ。しかし、その自分が、雨の恵みを受けるかのように、両手を挙げて、野太い声で吼える。 わたしだけは……、助かる……! 「ねえ、南さんっ」 我を忘れかけていたところで、秋菜に呼ばれる。 涼子は、びくっとして、そちらに目をやった。 すると、秋菜は、ふたたび、唐突に駆け寄ってきた。 「吉永香織の目的は、いったい、なんなの!? 南さん、わかる!?」 ちょっと、来ないで……! 涼子は、先ほどと同様、心の内で悲鳴を発した。秋菜の言葉が終わる前に、さっと体の向きを変え、走るような足取りで、その場を離れていく。奥の壁まで到達すると、秋菜との距離は、十五メートルほどになった。 秋菜は、今度こそ、本当にショックだったらしく、頬に手を当て、悲しげな素振りを示す。どうして、涼子が、秋菜を避けるように離れてしまうのか、その理由を知りたいはずだ。 涼子は、両手の指で、髪の毛のサイドの部分を両耳にかける。この仕草は、人前で困惑したり、気まずい思いをしたりした時の、自分のくせであることを、涼子自身も自覚していた。 「うーん、そうだなあ……。吉永香織の、目的は……」 あやふやな言葉を返して、場を取りつくろう。 お互いに『仲間』であることを確認し、弱いところをさらけ出し合った。今となっては、秋菜に対して、変に格好を付ける必要はないはずだ。しかし、それでも、自分の体臭に関する部分まで、無防備にするのは、全裸の写真を見られる以上の抵抗を感じる。今まで、ずっと苦手意識を抱いていた相手であるせいか、どうしても、秋菜の前では、プライドを捨て去ることができないと感じる自分がいた。 秋菜としては、今の、涼子との距離感が、もどかしくてたまらないのだろう、またぞろ、彼女は、こちらに駆け寄ろうとする動作を見せた。 それを瞬時に察知して、涼子は、素知らぬふうで向かいの壁へと歩いていく。 まるで、今までの涼子と秋菜の関係を、そっくりそのまま逆にしたような状況である。涼子は、高校生活のなかで、秋菜との距離感を、わずかでも縮めたいと、あれこれ試行錯誤をしながら振る舞ってきた。しかし、涼子が歩み寄った分、いつも、秋菜は、そっと離れていったのだった。そのせいで、これまでに何度、やるせない気持ちにさせられたことだろう。ところが、今はどうだ。秋菜が涼子を追い、涼子が秋菜から逃げている。ようやく、秋菜と接近できる時が訪れたというのに、今度は、反対に、こちらが、一定の距離を取り続けているというのは、なんとも皮肉なことだと思う。 秋菜は、もの問いたげな眼差しで、涼子を見つめている。その表情は、こんなふうに語っていた。どうして行っちゃうの……? 南さん、わたし、何か悪いことした……? 涼子は、申し訳ないと思いながらも、額に手を当て、絶えず足を動かし続けた。深く物事を考える際には、うろうろ歩き回る性分なのだというように。 「あいつの目的っていうのは……、なんていうか、嫌がらせ、みたいなものじゃないかなあ……」 口を動かしながらも、頭の中は、別のことで占められていた。 最大の脅威は消えた。だが、香織たちが、涼子の全裸を写した写真を保持していることに、変わりはない。それに、奪われたバレー部の合宿費は、まだ、半分も取り返せていない。もし、この状況で、涼子が、香織たちへの服従をやめたら、どうなるか。涼子の弱みである写真は、学校中にばらまかれるかもしれないし、合宿費は、もう一円も返ってこなくなるだろう。その二つの問題に、どう対処すべきか、神経を集中して考える。 数秒後、よし、と心に決めた。 涼子の全裸の写真を、全校生徒が、目にするような事態に発展したら、もう、何もかもを話そう。親しい友達、全員に、また、一番、信頼できる女性教師にも。それでも、出回った写真を一枚残らず処分するのは、まず不可能だし、自分は、毎日、顔を隠したいくらいの恥ずかしさと戦いながら、高校生活を送ることになるだろう。けれど……、その苦痛には耐える。 それと、合宿費に関しては、まず、家族に相談しよう。だが、それでも、どうにかなる額でないことは、涼子も、充分にわかっている。だったら、この身を動かせばいい。この高校では、アルバイトが、校則で原則的に禁止されているが、涼子には、やむにやまれぬ理由があるのだ。しばらく、部活は休み、どこかで、それも何件も掛け持ちして働くことにしよう。今、自分の体の中には、エネルギーが満ちているのを感じる。しっかりとした休息を取れば、すぐに健康な体に戻るはずだ。体力には自信がある。ぶっ倒れるのも覚悟で働けば、結構なお金を稼げるのではないか。そんな気がしてきた。 香織たちに反旗をひるがえしたなら、自分には、いばらの道を裸足で歩くような毎日が待っているのかもしれない。しかし、自分は、そちらを選ぶ。これ以上、香織たちから辱めを受けるよりは、ずっとずっとマシだ。 そう腹をくくると、一段と気分が高揚した。 もう、香織たちを怖れることはない。これから、あの三人が、揃って姿を現すはずだが、自分は、その横を堂々と歩いて通り過ぎ、階段を昇り、この地下牢のような場から出ることができる。 わたしは、助かる……。 だが、その一方で、秋菜は、どうなるだろう。 覚醒剤を使用している証拠の写真。それを、香織に、弱みとして握られているとなると、どう考えても、秋菜には、服従以外の選択肢は残されていない気がする。つまり、おそらくは、これから、この場で、香織たちによって、身に着けているものを、すべて脱がされ、女としての誇りを蹂躙される運命が待っているのだ。考えただけで、心が痛くなる。 そんな秋菜を見捨てて、自分だけ、この場から抜け出すというのは、いかがなものか。それに、もし、涼子が、そうして帰ってしまったら、香織たちが、その不満をぶつけるように、より激しいやり方で、秋菜に辱めを加えるだろうことは、想像に難くない。それでも、自分が助かるためには、やむを得ないと、開き直ってしまっていいのだろうか……? 心に手を当てて、自らに問いかける。 ダメだ。いくらなんでも、それは、冷酷すぎる。 共闘するべきだ。秋菜と知恵を出し合い、手と手を取り合って、二人が、共に救われる方法を模索するのだ。しかし、その方法を見つけるのは、容易なことではない。 秋菜が、暗い声で言う。 「嫌がらせ……。そのために、わたしに、覚醒剤を使わせることまでしたってことは……、きっと、並大抵じゃない嫌がらせをしてくるよね……。わたし、何されるのか、怖くてしょうがなくなってきた……」 どうやら、涼子との距離を縮めることは諦めたらしい。 涼子は、足を止めて秋菜のほうに顔を向けた。いったい、今までの自分は、この子の何を怖れていたんだろう。そう思うくらい、秋菜が、弱々しい存在に見えてならない。 それにしても、秋菜も、愚かなことをしたものだと思う。いくら志望大学に合格したいからとはいえ、違法な薬物だとわかっていながら、それを服用するなんて。だが、秋菜にしてみれば、わらをもつかむ思いだったのだろう。飛び抜けて学業優秀であると知られている秋菜だが、彼女は、それ相応の苦悩を抱えていたのだ。そして、そんな脆い部分を、あの吉永香織に嗅ぎつけられ、そこに付け込まれてしまった。 自分もそうだが、秋菜も、なんて哀れな人間なのだろう。わたしたちは、仲間だ、という念が、今になって、ひしひしと身に迫ってくる。もし、今、こんな汗まみれの格好をしていなければ、秋菜の肩を、そっと抱いてあげていたはずだ。 その時、上から、話し声と足音が聞こえてきた。あの三人であることは間違いない。 秋菜は、怯えた様子を見せる。 それとは対照的に、涼子は、落ち着いて身構えた。 階段を降りてくる足音。 最初に現れたのは、吉永香織だった。続いて、制服に着替えた竹内明日香が姿を見せる。 二人が、地面に降り立った。 あの性悪の後輩がいないことに、涼子は、少し疑問を抱いた。だが、そんなのは、どうでもいいことだと、すぐに頭を切り替える。 香織は、ひひひっと野卑な笑みを浮かべる。まさに、享楽の生贄である涼子と秋菜を前にして、悦びを抑えられないという表情である。 「どうどう? 南さんと滝沢さん。仲間同士、打ち解けて話し合うことができた? もう、すっかり、親友の関係になれたかな?」 秋菜が、居ても立ってもいられなくなったように、香織たちのほうへと、少しばかり走り寄る。 「ねえ、吉永さんっ。わたし、考えてたんだけど……、来週までに、十万、払う。絶対に払うって、約束する。いや、もし、それでも足りないっていうなら、わたしに、時間をちょうだい。わたし、お金をかき集めて、もう十万、払うから。だから、もう、帰らせて。それで……、わたしを退学にしようとするのは、考え直してほしい。どうか、お願いしますっ」 うーん、ちょっとな……、という感想を涼子は抱く。滝沢秋菜といえば、いつだって、涼しげな雰囲気をまとわせているイメージだったが、今は、別人のような狼狽ぶりを見せている。いくら致命的な弱みを握られているとはいえ、もう少し、自分らしさを保てないものか。 「お金……、ねえ。なんでも、お金で解決できるっていう考えは、ちょっと、違うんじゃないかなあ……。あたしたちとしては、滝沢さん、あなたの、もっと大事なものを、捧げてもらいたいんだけど……、その辺のことは、南さんが、よーくわかってるから、教えてもらうといいよ」 香織は、秋菜の心を手玉に取るように話す。 秋菜は、涼子を振り返った。今や、その顔は、恐怖と不安に引きつっている。 「よしながっ」 涼子は、香織のことを初めて呼び捨てにした。もはや、恭順の態度を示す必要はないのだ。 「あんたが腐った人間だってことは、うんざりするくらい知ってたけど、あんたの腐りっぷりは、わたしの想像以上だったわ……。あんたの脳みそさあ、どろどろに腐りすぎて、虫が、大量に湧いてんじゃないの?」 人に対して、こんなに汚い物言いをしたのは、生まれて初めてのことだった。それだけ、香織への憎しみが燃えたぎっていたのである。 香織は、愕然としたように目を見開いた。 「はあ……!? なんで、そこまで言われないといけないわけ……? 信じられない……。ちょっと、滝沢さん。南さんが、何を血迷ったのか、あたしに、とんでもない暴言を浴びせてきたの。許されないことだよ。滝沢さんが、仲間として、南さんを注意して。連帯責任だからね」 かなり焦っている様子で、秋菜に命令する。 「南さんっ! 吉永さんを怒らせるようなこと言うのは、やめてっ!」 秋菜が、すぐさま、必死の形相で、涼子に訴えてくる。 涼子は、小さく舌打ちした。どうやら香織は、秋菜を使って、涼子の言動に掣肘を加えることにしたらしい。香織の汚いやり方には、つばを吐きたくなる。 「っていうかさ……、南さん、そもそも、なんで、そんな格好してるわけ?」 香織が、妙なことを言う。 「あんたが、明日香に、言ったんだろうが。わたしを、着替えさせないで、ここに連れて来るようにって……。いったい、なに考えてんのか、わからないけどさ。ほんんっとーうに、気色悪い女」 涼子としては、これでも、控えめな言葉で返したつもりだった。 だが、香織は、秋菜に目線を飛ばし、涼子を注意しろと促した。 「南さん……、お願いだから、抑えてっ」 秋菜は、すがるような眼差しを、こちらに向けてくる。 まったく、やりにくいなあ……。そう思い、涼子は、軽く宙を仰いだ。 「違うわよ。そういうことじゃないわよ……。なんで、南さんは、服を着てるのかってことよ。あたしたちが来るって、わかってたんだから、あらかじめ、服を全部、脱いで、裸で待機してるのが、礼儀ってもんじゃないの? 南さんは、ちゃんと、そのお手本を示さなくっちゃ……。なんていったって、滝沢さんのほうは、今回が、初脱ぎなんだから」 香織は、大真面目な顔で、そんな馬鹿げた話をする。 改めて確信した。この女は、完全に狂ってる……。 秋菜は、今の話を聞いて震え上がったらしく、亡霊でも見ているかのような表情を浮かべている。まさか、秋菜が、これほどまでに苦境に弱いとは意外だった。残念だが、彼女の様子を見るに、共に知恵を出し合い、香織たちに立ち向かうことは、期待できそうにない。頼りになるのは、自分だけだ。 だが……。 「脱がねーよ。わたしも、それに、滝沢さんも」 涼子は、低い小声で、しかし力強く口にした。 考えろ……。どうしたら、自分と秋菜の二人が、恥辱にまみれる運命から逃れられるか。 「えっ……。よく聞こえなかったんだけど……、脱がない……? なに言っちゃってんの。今日の南さんは、なんで、そんなに反抗的なわけ? もしかして、自分の立場を忘れちゃった? 記憶喪失? でも、ダメだからね……。だって、あたし、今回のショーのために、スペシャルゲストを呼んじゃったんだから」 香織は、意味深なことを言うと、階段の上に向かって、大声で呼んだ。 「さゆりー! 連れてきてーっ!」 石野さゆり。やはり、あの性悪の後輩は、来ていたらしい。だが、香織の言葉からすると、それ以外にも誰かいるようだ。 やがて、上から、話し声が聞こえてきた。 「……だいじょうぶ、だいじょうぶ。全然、怖がらなくていいから」 さゆりの声だ。 「……えっ。でも、本当に、いいんですか? なんか、あたし……、緊張してきちゃった」 ひどく子供っぽい声だ。その声に、聞き覚えはなかった。 「……へいき、へいき。さっ、降りて降りて」 それから間もなくして、階段から、足音が鳴り始めた。 涼子は、にらむように階段を注視する。 いったい、誰が、こんな場所に来るのか……? 数秒後、二人の生徒の姿が、ほぼ同時に視界に入った。 先に降りてきたのは、小学生のように小柄な生徒だった。 涼子は、その彼女の顔を見て、あっ、とかすかに声をこぼした。 続いて、二年の石野さゆりが、階段を降りてくる。相変わらず、見ていて、胸のむかむかするような薄笑いを浮かべて。 その二人が、地面に降り立った。 小柄な生徒は、両手を胸に当て、どぎまぎした様子で、涼子のことを見てくる。 「あっ、あっ、南先輩だ……」 涼子との対面に、感激しているような口ぶりである。 そんな彼女の肩を、後ろから、さゆりが押して歩き、二人が、香織たちの陣営に加わる。 これで、涼子と秋菜は、十メートルほどの距離を空け、四人と対峙する形となった。 すると、それまで黙っていた明日香が、小柄な生徒の背後に近づき、さゆりと入れ替わって、その子の両肩に手を置いた。 「りょーちん。この子のこと、憶えてるぅ?」 明日香の顔には、かつて見たことのないくらい、狡猾そうな含み笑いが浮かんでいる。 悪魔の微笑みだ。 ああ、そうきたか……。 涼子は、香織たちの意図を把握した。 今、明日香の前にいる、思春期を迎えたばかりのように幼い容姿の彼女のことは、鮮明に記憶に残っている。 あれは、一週間ほど前のことだ。 放課後、部室に向かって、体育館の館内通路を歩いていると、突然、その彼女が、涼子に接触してきた。香織たちからの言伝を、涼子に伝える、という形だった。そのやりとりは、すぐに終わった。それから部室に入り、ほどなくして、涼子は、自分と、その彼女との間に、接点があることを思い出した。彼女は、さかのぼること、一ヶ月以内に、直接、涼子にファンレターを手渡してきた生徒だったのだ。 この一ヶ月以内。そのことが、やたらと意識に引っかかった。なぜなら、それは、竹内明日香が、バレー部のマネージャーとして、活動を始めた以降、ということでもあるからだ。それに、その彼女から、ファンレターを受け取った場所は、ほかでもない体育館である。もしかすると……、その場面は、明日香に目撃されていたのかもしれない。そして、明日香は、涼子を辱める目的で、その彼女を利用するという、悪魔も真っ青の奸計を思いついた。だから、香織たちが、涼子への伝言役に、彼女を選んだのには、深いわけがあった。涼子に対して、こんなメーセージを送りつけるような。こっちは、その子を仲間に引き入れるために、すでに動き始めているから、せいぜい、気をつけるんだね……、と。 そういう可能性もある気がして、あの時、自分は、ものすごく不吉な胸騒ぎを感じたことまで、昨日のことのように、よく憶えている。 そして……、どうやら、それは、現実のものとなったらしい。 だが、今ならまだ、その現実を覆すことは可能だろう。 涼子は、その彼女の顔を、真っ直ぐに見つめ、それから、さらに記憶をたぐり寄せた。 「あの、きみ……。たしか、一年生の、足立さん、だったよね?」 一年C組。足立舞。間違っていないはずだ。 彼女は、はっとした顔をする。その表情は、いかにも純真無垢な感じである。 「はっ、はい……」 消え入りそうな声で答える。 「きみ……、そこにいる先輩たちに、どんな話を聞かされてるのか知らないけど……、ここは、きみが、いるような場所じゃないんだよね。だから、申し訳ないんだけど、今すぐ帰ってもらえるかな? それでさ、今度、いつでもいいから、三年E組の教室まで来てくれる? そうしたら、わたし、きみと話す時間を作る。その時に、二人で、お話しようっ。ねっ?」 涼子は、やんわりと首を傾け、小さな子供に向けるような笑顔を浮かべてみせた。 舞は、丸っこい大きな目を、ぱちくりさせながら、涼子のことを見返してくる。だが、ちょっとすると、そばにいる三人の先輩たちの、一人ひとりに、意見を求めるような視線を投げかけ始めた。 香織も、明日香も、さゆりも、その舞の視線を、横目で受け止める。しかし、誰も言葉を口にしない。 すると、舞は、とぼとぼと、香織のそばに寄った。 「香織先輩……。あたし、帰ったほうが、いいですかぁ……?」 不安げな表情で、香織に、そう尋ねた。 香織は、舞の肩を抱き寄せる。 「帰らなくて、いいの。舞ちゃんは、スペシャルゲストなんだから……。南せんぱいったら、見かけによらず、ものすごく照れちゃってるみたい。いくら、舞ちゃんから、告白の手紙をもらってるからって、そんなに照れなくてもいいのにね」 「えっ……、あっ、えっ……」 舞は、慌てふためいた。その、お餅のように柔らかそうな頬が、見る見るうちに桜色に染まっていく。告白の手紙、と言葉に出されたことで、羞恥心を強く刺激されてしまったようだ。 そう……。 涼子は、舞から受け取った手紙の内容についても、だいたい思い出すことができる。あれを、ファンレターと表現するのは、正確性に欠けるだろう。回りくどいことが、色々と書いてあったけれど、その最後のほうには、紛れもない涼子への告白の言葉がつづられていたのだ。 女同士ではあるが、舞は、涼子に対して、恋心のようなものを抱いている。それは、男の子が女の子を好きになったり、また逆に、女の子が男の子を好きになったりするのと、さほど変わらない感情なのかもしれなかった。 現在は、そんな舞が、香織たちの側に立っている。涼子にとっては、この状況それ自体が、屈辱感を抱かされるものだった。こんな時間は、一秒でも早く終わらせねばならない。 「ねえ、きみ……。実を言うとさ……、わたしと、そこにいる先輩たちは、ちょっと揉めてて、これから、言い争いになりそうなの。もしかしたら、すごい喧嘩になるかもしれない。そんな時に、きみみたいな一年生の子がいると、わたし、やりにくいんだよねえ……。だから、わたしからの、お願い。申し訳ないけど、今すぐ帰ってくれるかな? ごめんねえ、こんなこと言っちゃって。でも、近いうち、きみと、ゆっくり話したいって思ってる」 涼子は、舞に向かって、にっこりと笑いかけた。 舞は、ぼんやりとした目で、涼子のことを見返してくる。だが、ほどなくして、また、香織のほうに顔を向けた。 「香織先輩……、あたし、どうしたらいいんですかぁ……?」 その舞の行動に、涼子は、イラッときた。 「いいのいいの。南せんぱいは、あんなふうに偉そうなこと言ってるけど、本当は、あたしたちのほうが、断然、強い立場なんだから。……で、南さんさあ、いい加減、しらばっくれるのは、やめてくれる? なに、いつまでも、立場をわきまえず、服を着てんのよ……。あたし、舞ちゃんに、約束しちゃったんだから。南せんぱいの、過激なセクシーショーを見せてあげるって。だから、早く、服を脱いで。でも……、もしかしてだけど……、自分のことを好きな女の子の前では、絶対、服を脱ぎたくないって思っちゃってるぅ?」 香織の、つり上がり気味の目が、ぎらぎらと光る。 涼子だって、ほかの年頃の女の子たちと同様、デリケートな心を持っている。相手が同性とはいえ、自分に対して好意を抱いている生徒の前で、格好悪いところを見せるのは、プライドが深く傷つく。ましてや、この場で、着ているものを脱ぐなど、もってのほかである。そんな、人間として当たり前の心理を、香織は、もてあそぶように、舞を、この場に留まらせているのだ。とことん下劣さを極めたサディストである。 涼子は、香織に対して、殺意に近い感情を抱き、両手の拳を、ぎゅっと握り締めた。それから、目力を込め、舞の顔を見すえる。 「あのさあ、きみ。今の話、聞いてたでしょ? その先輩が言ってること、どう考えても、おかしいって思わない? 思うよね? この人の言ってることは、正しい。この人の言ってることは、間違ってる。そういう判断は、もう、高校生なんだから、自分でできるよね? わたしは、きみに、帰ってって言ってるの。それでもまだ、この場に残るつもり? きみも、その先輩と同類? 違うよね?」 もう、笑顔を向けることもしなかったし、優しく語りかける口調でもなかった。どちらかというと、叱っているような物言いだった。 だが、舞は、またしても、香織のほうに顔を向ける。香織に救いを求めるように。 涼子は、それを見て、苛立たしさのあまり、思わず、右足で地面を踏みつけるような動作を行っていた。 「南さんさあ……、往生際が悪すぎて、見苦しいよ。舞ちゃんの見てる前では、服を脱ぎたくないって思ってるんなら、そんな、くだらないプライドは、捨てちゃえばいいの。言っておくけど、南さんが、セクシーショーをやり終えるまでは、たとえ、舞ちゃんが帰るって言っても、あたしが、絶対に帰らせないからね」 香織は、舞と腕を組んだ。 舞は、困惑した様子を示しているものの、帰る素振りは少しも見せず、その場に留まっている。後ろめたい思いがあるためか、もはや、涼子とは、目を合わせようとしない。 涼子は、そんな舞を眺めながら、色々なことを思い始めた。 舞は、涼子に対して、恋心のようなものを抱いている。それは、動かぬ事実だ。しかし、だからといって、同性愛者と捉えるのは、早計に過ぎるだろう。思春期の女の子が、同性を好きになるのは、たいてい一過性のものであり、特別、珍しいことではないのだと聞く。それに、かりに、舞には、第二次性徴期に入った頃から、すでにレズビアンの傾向があったのだとしても、現在、好意の対象である涼子のことを、性的な目で見ているとは考えにくいし、また、考えたくもなかった。涼子にとっては、女の子が女の子を、性の対象として見るという心理が、どうにも想像しづらいのだった。 しかし、果たして、断言できるだろうか……。 舞の、ぷーっと頬を膨らませたような、その表情を見つめる。なんとなく、その顔には、密かな期待の思いが表れているような、そんな感じを受けないでもない。 ひょっとすると、舞は、涼子に対して、恋心のようなものを抱いているだけではなく、性的好奇心をも持っているのではないか。だから、仕方なく香織に従っているフリをしてはいるが、本当は、涼子の生脱ぎを見たくて、うずうずしているのではないか。そうして、衣類をすべて脱ぎ去った後に現れる、涼子の裸の肉体を、目に焼きつけたいという欲求で、胸が一杯の状態なのではないか……。 そこまで思い、涼子は、ぞっとしてしまった。 もし、そのような心理状態の女の子の前で、裸をさらすとしたら、それは、考えうる限り最大級の屈辱だという気がする。そんな屈辱には、とても耐えられない。秋菜には申し訳ないが、自分だけでも、この場から抜け出したいという思いが、ふつふつと胸に込み上げてくる。 香織は、今度、秋菜へと矛先を変えた。 「ちょっと、滝沢さん。なに、ボケッと突っ立ってんのよ。今回は、南さんと滝沢さんの、いわば共演のセクシーショーなんだよ。主演、南涼子。助演、滝沢秋菜。だから、まずは、滝沢さんが、責任を持って、南さんの服を脱がせて。それで、南さんが裸になったら、今度は、滝沢さん、あなたが、服を脱ぐ番だからね。もし、それができないっていうなら、あなた、覚醒剤の件で、退学だよ。退学になりたくなかったら、早く行動して。あたし、あなたたちの服が、だんだん、目障りでしょうがなくなってきたのよっ!」 秋菜は、見るも無惨に、おろおろし始めた。それから、泣きべそをかいたような顔で、涼子のほうに駆け寄ってくる。 来ないで……! 涼子は、心の内で訴える。しかし、先ほどまでのように、秋菜から逃げることはしなかった。もはや、秋菜と距離を置いている場合ではないのだから。 秋菜は、涼子のすぐそばまで来て、足を止めた。 「ねえ、南さん。わたしたち、どうすればいいの……? わたし、後輩たちも見てる前で、服を脱ぐなんて、絶対にいやっ。なんとかできない? いい考えはない?」 まるで、今にも、涼子の身にすがりついてきそうである。 いい考え……。助かりたいなら、もう少し、冷静になって、自分自身で頭を働かせてほしい、と思う。涼子としても、秋菜に、これほどそばに寄られると、自分の体が発する汗の臭いが気になりすぎて、とても物事を考えられる状態ではないのだ。 そして、涼子は、秋菜の顔を見て、どきっとした。 秋菜は、今、すごく酸っぱいものでも口に入れたような表情を浮かべている。真一文字に結ばれた唇。間違いない。涼子の強烈な体臭に耐えられず、息を止めているのだ。本当なら、あの高塚朋美が、涼子の前で見せたように、鼻をつまんで、顔を横にそらしたいところに違いない。 やだ、恥ずかしい……。涼子の乙女心は、たちまち、火だるまになった。 顔に、どんどん血が昇っていくのを感じる。 涼子は、じっとしていられなくなり、髪の毛を押さえたり、シャツの胸もとの部分をつかんだりと、無意味な動作を繰り返した。今や、自分の赤面ぶりは、先ほど、告白の手紙、と言葉に出された時の、足立舞さながらかもしれない。 香織が、にたにたと笑いながら言う。 「あらあら……。あんたらを見てると、地獄の底で芽生えた、熱い女の友情って感じがして、微笑ましいねえ。でも……、滝沢さんに、ひとつ、忠告してあげる。あんまり、南さんを信頼しないほうが、いいよ」 涼子も秋菜も、香織のほうを向いた。 「実はね……、南さんって……、レズなの。レズで……、しかも、滝沢さんのことが、好きなの」 その突拍子もない言葉を聞いて、涼子は、呆れ果ててしまい、逆に、肩の力の抜けるような思いがした。 だが、秋菜は、えっ、という顔で、こちらを見る。 「滝沢さんことを、好きっていうだけなら、まあ、別に問題はないかもしれないけど……、南さんの場合は、違っててね。滝沢さんのことを考えると、なんていうか、やらしい気持ちを抑えられなくなっちゃうみたいなの」 涼子は、馬鹿らしくて、鼻で笑ってやった。 だが、秋菜は、やや真に受けたのか、涼子に対し、何か不信感を抱いたような視線を、こちらに送ってくる。 そのことが我慢ならず、涼子は、左手をひらひらさせながら、口を開いた。 「ああ、気にしないで、気にしないで。あの女、完全に、頭の中が腐ってるからさっ」 香織は、にわかに気色ばんだ。 「はあ!? 滝沢さんのことを考えると、やらしい気持ちを抑えられなくなるのは、本当のことでしょうが。嘘だっていうなら、南さんさあ、なんで、あんな変態行為をやったのよ?」 もしかしたら、秋菜の体操着のシャツを使った、あの自慰行為のことを言っているのかもしれない。だとしても、あれは、涼子の意思で行ったことではないのだ。 「いったい、なんのこと?」 涼子は、すました顔で問い返した。 「あっ、そう……。そうやって、とぼけるんだ? それなら、あたし、言っちゃおうかな……。滝沢さん、聞いて。南さんったらねえ……、何したと思うぅ? 放課後……、教室に残って、滝沢さんの、机の角に、股間をこすり付けて、感じちゃってた……、みたいな、そういう類のことなんだけど、実は、もっと、いけないことをしてたの……。南さん、忘れたとは、言わせないよぉ?」 香織の、ねちねちとした物言いには、へどが出そうになる。 「わたしは、そんな変態みたいなこと、やってませんからっ!」 涼子は、一語一語、力を込めて言葉を返す。 「そっかそっか……。それが、南さんの答えってわけね……。南さんが、あくまでも、とぼけるつもりなら、しょうがないなあ……。あたし……、これは、封印しておいてあげようと思ってたんだけど、やっぱり、滝沢さんに、見てもらうことにしようっと」 香織は、肩に提げているバッグのチャックを、おもむろに開けた。バッグの中に手を入れて、何かを探り始める。 まさか……。涼子は、香織の手もとを凝視する。心臓の鼓動が激しくなる。 やがて、香織は、バッグから写真を取り出した。三枚の写真だ。何が写っているのかは、もはや、見るまでもないことだった。 涼子は、体中の毛が逆立つ感覚を覚えた。 香織は、その写真を手に、こちらに歩いてくる。 「滝沢さん。ちょっと、これを見てくれる?」 その呼びかけに、秋菜も、さっと涼子のそばを離れ、そちらに歩いていった。 「あっ、待っ……」 涼子は、つい、そう声を漏らし、秋菜の背中に向かって、右手を伸ばしていた。 香織と秋菜が、互いにくっつくようにして足を止めた。 「まず、この写真から……。滝沢さんさあ、体操着のシャツ、なくなっちゃったでしょ? 実はねえ、それは、南さんのせいなんだよ……。ほらっ、ここに、滝沢って文字が見えるでしょ? 南さん、あなたのシャツで、こんなことしてたの」 おそらく、その写真は、全裸の涼子が、秋菜の体操着のシャツを広げ、赤く縁取りされた丸首の部分を、口にくわえているところを写したものだろう。シャツの胸のところに刺繍された、『滝沢』という苗字まで、はっきりと確認できるはずだ。 今、秋菜は、こちらに背を向けて立っている。いったい、どんな顔で、その写真を見つめているのだろうかと思う。 「次は、この写真……。問題の変態行為は、これなの……。南さんの、ま○こに食い込んでるの、もちろん、滝沢さんのシャツだよ? どうどう? どう思う? どん引きでしょう?」 その写真には、全裸の涼子が、嬉し恥ずかしそうな表情で、秋菜の体操着のシャツを、自らの手で、恥部に深く食い込ませているところが写っているはずだ。 秋菜の後ろ姿を見ると、写真の中の、世にも淫猥な光景を目の当たりにし、硬直しているような雰囲気が伝わってくる。 「それでね……、南さんったら、滝沢さんのシャツを使ったオナニーが、最高に気持ちよかったらしくって、エッチな汁を、たくさん垂れ流しちゃってたの。嘘じゃないよ。本当だよ。その証拠も、あたし、ちゃんと持ってきててね……」 香織は、バッグの中に手を突っ込むと、こちらを見て、涼子の反応を観察する。やがて、がさがさと、衣類の入った透明なビニール袋を取り出した。 滝沢秋菜の体操着のシャツだ。 涼子は、限界以上に目を見開いていた。わなわなと唇が震え始める。 香織は、ビニール袋越しに、体操着の丸首の部分を、指で撫でてみせた。 「ここの部分、がびがびになってるでしょう? ここに、何が染み込んでるのか、もう、言わなくてもわかるよね……? 南さんが、こんなに汚しちゃったものを、滝沢さんに、そのまま返すのは、ちょっと気が引けたから、あたしが預かってたんだけど、やっぱり、滝沢さんに返しておくよ……。あっ、でも、この場で、ビニールのチャックを開けるのは、やめてね。だって、あまりの激臭に、滝沢さん、絶対に悶絶しちゃうから。今、滝沢さんに倒れられても、あたしたち、困るんだよねえ」 そう話す香織の声は、愉悦に満ちていた。 秋菜は、無言で、自分の体操着の入ったビニール袋を受け取る。 「あと、そうだ……。南さんが、付けた汚れは、それだけじゃなくってね」 香織は、思い出したように言い、体操着の肩口のところを指差した。 「ここを見て。なんか、黄土色っぽい線があるでしょう? これ、なんだと思う? わからないなら、この、三枚目の写真が、ヒント」 その写真は、全裸の涼子が、後ろに顔を向けたカメラ目線で、恥部に食い込ませた秋菜の体操着のシャツを、おしり側に、思いっ切り引っ張り上げているところを写したものだろう。 秋菜は、その写真を、穴の空くほど凝視しているふうである。 「南さんって、見た目からして、さばさばした感じがするじゃん? そういう性格が、きっと、トイレの時も、出ちゃうんだよ。なんていうか、ちょっとくらいの汚れは、気にしない、みたいな。でもさあ、滝沢さんのシャツで、こんなことするんなら、おしりは、もっと、清潔にしておいてほしかったよねえ?」 涼子は、いっそ、この場にうずくまって、目を閉じて耳をふさぎ、外からの情報を、すべてシャットアウトしたい気分だった。 「はいっ。ついでに、この三枚の写真も、滝沢さんにあげる。南さんの、愛の証だから、受け取っておいて」 香織は、秋菜に写真を渡すと、あざ笑うような視線を涼子に向け、それから、その場を離れた。明日香たちのほうに戻っていく。 一方、秋菜は、体操着の入ったビニール袋と写真を手に持ったまま、身じろぎもせずに立ち尽くしていた。 わずかの間、息苦しい沈黙が流れる。 涼子は、黙っているのが耐えられなくなり、秋菜のほうに歩いていった。 「ごめん、滝沢さん……。わたし、前もって、ちゃんと、何もかも話しておくべきだった。それは、全部……」 「きもちわるい」 秋菜から、そう聞こえた気がした。 思わぬ言葉に面食らい、涼子は、つと立ち止まる。 「えっ……。滝沢さん……?」 不安な気持ちで、秋菜の背中に呼びかける。 秋菜は、くるりとこちらを向いた。凍ったような目つきをしている。 「なに考えてんのよ、あんた! まるっきり変態じゃないの! 今まで、わたしのことを、どういう目で見てたのよ!」 怖ろしい剣幕で、がなり立てる。 涼子は、秋菜の発言が、自分に向けられたものだとは、とても信じられない思いだった。 香織が、面白がってからかってくる。 「あれれぇ……? あたし、悪いことしちゃったかな……? 南さんと滝沢さんの、熱い女の友情を、引き裂いちゃったみたい」 涼子は、香織の言葉を無視し、秋菜のほうに進んでいく。 「なにそれ、滝沢さん……。待ってよ。わたしの話を、聞いて……」 「わたしに、近づかないで! この変態! わたしの半径、五メートル以内には、絶対に近づかないで!」 秋菜は、涼子に対して、激しい嫌悪感を抱いているようだ。 涼子は、頭の混乱を覚える。 どうして、秋菜が、香織の明らかな作り話をうのみにしたのか、まったくもって理解できない。 秋菜のほうに歩み寄りながら、怒鳴るような声で抗議する。 「違う……! わたしは、自分から好きで、そんな変態みたいなこと、やったんじゃないからっ! 全部、吉永たちに、無理やり……」 「だから、わたしに、近づかないでって言ってんでしょっ! それと、はっきり言うけど、あんた、ものすごい汗臭い。近づかれると、わたし、息ができないの。いったい、どういう食生活してたら、そんな、ひどい体臭になるわけ?」 秋菜は、顔をしかめて鼻をつまみ、しっしっ、と手を払った。 その発言を聞いて、涼子は、ショックのあまり、立ちくらみを起こした。自分の体を守るように肩を抱く。滝沢秋菜にだけは、汗臭いと思われたくない、体臭のことを指摘されたくない。そういう思いだったのに。もはや、言葉を発する気力を失ってしまった。 香織が、声を上げた。 「あぁぁー。滝沢さん、いくらなんでも、それは、残酷じゃないのお? 南さんの気持ちも、少しは考えてあげなよ。大好きな滝沢さんに、くさい、なんて言われたら、南さんの乙女心が、ずたずたになっちゃうでしょう?」 「だって、本当に、この人、異常にくさいんだもん。吉永さんも、こっちに来て、この人の体臭、嗅いでみてよ。鼻で息してると、体調を壊すレベルだから」 もはや、秋菜は、涼子のことなら、何を言ってもいいと開き直っているようだった。 「そうなの……? たしかに、ここから見ても、南さんの着てるシャツ、汗でびしょびしょなのが、よくわかるからねえ。すごい汗の臭いがしそう。あたしも、その臭い、確かめてみようかなあ。どれどれぇ……」 香織が、喜色満面の顔で、こちらに歩いてくる。 この場に留まっていたら、自分は、耐え難い侮辱を受けることになる。 涼子は、さっと体の向きを変え、そこから足早に遠ざかった。 香織は、愉快そうに言う。 「あ、逃げた逃げた……。まあ、でもいいや。あとで、南さんの体臭に関することは、時間をかけて、徹底的に調査させてもらうから。南さんが、着てるものを、全部、脱いだら、シャツやスパッツとかの臭いもチェックするしぃ、もちろん、南さんの体自体が、どんな臭いなのかも、よーくチェックする」 そちらを見ると、香織の顔には、今にもよだれを垂らしそうな、品のかけらもない表情が浮かんでいた。 涼子は、嫌いな虫より不愉快なものを見ている気分で、香織から目をそらした。 秋菜が、そんな香織のところに、おずおずと歩いていく。 「ねえねえ、吉永さん。お願いだから、わたしを、あんな変態女と一緒にしないでっ。ストリップショーならさ、あの変態女だけが、脱げばいいのよ。なにしろ、レズで、女の子たちに裸を見られたら、興奮するんだろうし。わたしなんかが、脱いだって、ちっとも面白くないよ? ねっ?」 その口調からは、香織に媚びる思いが、これでもかというほど伝わってきた。 なるほど、そういうことか……。 涼子は、ようやく、秋菜の真意を読み取った。 秋菜にしても、涼子が、自らの意思で変態行為に及んだなどとは、微塵も思っていないのだ。おそらく、秋菜は、三枚の写真と、汚れた自分の体操着を見て、香織たちが、想像をはるかに超えた加虐趣味者の集まりであることを悟り、血も凍るような恐怖を覚えたのだろう。涼子と同じような運命を辿ることだけは、絶対に回避したい。そう思ったはずだ。そして、導き出した答えは、仲間であるはずの涼子をとことん罵倒し、逆に、敵である香織には媚を売る、というものだった。そうすれば、香織たちに気に入られ、自分だけは助かる可能性もあるのではないかと、そう考えた。究極の自己保身である。いくら、絶望的な運命を突きつけられ、気が動転したからとはいえ、秋菜のその考えは、涼子としても許せるものではない。涼子は、自分と秋菜の二人で、この地獄から抜け出すのだという気持ちが、一気に冷めていくのを感じた。 「うーん……。そう言われてもねえ、今回、あたしたちは、南さんと滝沢さんの、共演のセクシーショーを愉しみにして、ここに来たんだから、片方でも脱がないとなると、興ざめなんだよなあ」 香織は、おごり高ぶった態度で、そう答える。 「……そんなあ」 秋菜は、なんとも情けない声を出した。 「あ、そうだ……。滝沢さん、その写真、貸してくれる?」 香織は、手を伸ばした。 秋菜は、うやうやしい手つきで、三枚の写真を、香織に手渡す。 「この写真……、舞ちゃんにも、見せてあげようっと」 香織は、ステップを踏むような足取りで、舞のところに引き返していく。 その言葉を聞いて、涼子は、肺腑が引きつるような怒りを覚えた。 「見て、舞ちゃん……。南せんぱいったら、好きな女の子のシャツを使って、こーんな穢らわしい行為をしてたんだよお」 香織が、舞のそばまで行き、写真を差し出した。 舞の両手が挙がり、その可憐なサイズの手のひらに、いかがわしい三枚の写真が載せられようとしている……。 涼子は、こめかみの血管が、ぴきぴきと動くような感覚を味わった。全エネルギーを用いて、怒号を発する。 「そんなモノに、触るなあああぁぁぁぁぁぁぁ!」 この空間全体に、割れんばかりの大音声がとどろく。 舞の小さな体が、びくっと跳ねた。 涼子は、舞の顔を、じろりとねめつける。 舞は、天変地異に見舞われたかのように、おたおたと怯えきっている。 「なに、一年生の子を、怖がらせてんのよ。可哀想でしょ? ちょっと、滝沢さん。あなたの口から、南さんを、厳重注意して。これ以上、南さんが、問題行動を起こしたら、連帯責任で、滝沢さんにも、あとで、きっつい罰を受けてもらうからね」 香織は、涼子のほうに、あごをしゃくる。 秋菜は、にわかに顔色を変え、こちらに、攻撃的な眼差しを向けてくる。 「うるっさいのよ、あんたは……。なんで、吉永さんたちに、盾突こうとするわけ? 自分の立場をわきまえて。それに、写真くらい、どうでもいいでしょ。これから、あんたは、素っ裸になるんだから。裸の写真を見られるくらいで、恥ずかしがってて、どうするのよ?」 涼子は、どっと疲労感に襲われた気分で、大きなため息を吐いた。 もはや、秋菜の頭の中にあるのは、いかにして香織たちの側に付くか、という一念だけらしい。秋菜との共闘を思い描いていた自分が、まったく、馬鹿みたいである。いっそのこと、秋菜など見捨てて、自分だけ、一足先に帰ってしまおうかと思う。しかし、平常心を失った人間が、自分のことしか考えられなくなる心理は、理解できなくもない。その一抹の同情心が残っているため、涼子は、この不快極まりない場に留まっているのだった。 「さっ、舞ちゃん。手に持って、じっくりと見てあげて。南せんぱいの裸も、前代未聞の変態っぷりも」 香織は、舞に写真を差し出す。 舞は、ためらう素振りを示しながらも、結局、その三枚の写真を、包み込むようにして両手で受け取った。 間もなく、舞の、すべすべの頬が、ぼわっと紅潮した。 「うわぁ……、南先輩の、はだか……」 舞は、度を超した刺激に、頭がくらくらしているような目つきで、三枚の写真を順番に見つめている。 涼子は、これ以上、そんな舞の様子を見ていると、頭の血管が、本当に切れてしまいそうな気がしたので、斜めに視線を落とした。大っ嫌い、あの子……。 やがて、舞は、涼子から、にらまれていないのを、いいことに、熱に浮かされたような、とろんとした眼差しで、こちらを見始めた。写真の中の光景と、実物の涼子とを、交互に見ている。まるで、涼子の身に着けている衣服の中を、透視するかのような、性的好奇心を多分にはらんだ視線に感じられた。その視線が、涼子の上半身、それから、下半身へと、ねっとりと絡みついてくる。ひょっとすると、今、舞の脳裏では、こんな、やましい想像が膨らんでいるのかもしれない。もし、涼子が、香織の命令に服従し、着ているものを、すべて脱ぎ去ったなら、Dカップはありそうな豊かな乳房も、ジャングルという表現がぴったりの、毛深い恥部も、実際に、目にすることができるのだ……、と。 涼子は、乳房を覆い隠すように、両腕を交差させた。うめき声が漏れるほどの屈辱感に、指の爪が、上腕の皮膚にめり込む。もう、我慢の限界だ、と感じる。本当は、この場から抜け出すことのできる、わたしが、どうして、こんな辱めに耐えなくてはならないのだろう。 「どう? 舞ちゃん。もしかして、刺激が強すぎて、鼻血が出ちゃいそうな気分?」 香織は、三枚の写真を、舞の手のひらからつまみ上げる。 舞の顔には、感動の念が、ほんのりと表れているように見えた。 涼子は、両腕を解くと、右手で、荒っぽく前髪をかき上げた。 「ああもうっ……、あったま来るっ」 こちらの怒りを、舞に伝えるように、そう言葉を吐く。 「滝沢さん。写真、返してあげる」 香織は、秋菜に声をかけた。 「あっ、はいっ」 秋菜は、従順を示すように返事をし、すぐさま走り寄る。香織から写真を受け取ると、なにやら、横に立っている舞の両肩に、手をあてがった。厳しい処罰を言い渡された、力なき者が、権力者に対して、慈悲を乞うかのように。 「ねえ、あなたさあ……、あなたが期待してるのは、あっちの先輩の、ストリップショーなんでしょう? そうよねえ? わたしの脱ぐところなんて、見たくもないわよねえ? ねえ、お願いだから、そう言ってよっ」 舞は、困り切った表情で、香織の顔をうかがう。 秋菜は、香織に向き直った。それから、香織の右腕に、両手でちょこんと触れる。 「吉永さんっ。今回のストリップショーは、この子のためにやるのよね? この子、わたしには、まったく興味がないみたいよ? うん、絶対にそう。この子の顔が、そう言ってるもん。間違いない。だから、今回、脱ぐのは、あの変態女だけでいいんじゃないかな? ほらっ、二人同時に脱いだりすると、この子も、逆に、気が散っちゃって、本命のほうに集中できないっていう、デメリットがあると思うの。それを考えると、わたしは、不要よね? わたしだけは、もう、帰ってもいいでしょう?」 今にも、香織の身にすがりつき、泣き崩れそうである。もはや、恥も外聞もなく、自分だけ助かればいいという思いだけで、行動を起こしているのだ。 その姿は、恐ろしく見苦しかった。醜悪だ。 涼子からすれば、秋菜は、何もわかっていない、と思う。香織は、色々な意味における、人間の醜い部分を見るのが、大好きなのだ。だから、秋菜が、自己保身に満ちた姿を見せれば見せるほど、香織を悦ばせるだけである。それを理解できない、秋菜の浅はかな言動には、軽蔑を通り越して、哀れみすら覚えてしまう。 「滝沢さん……。あなたの、どうしても脱ぎたくないっていう、必死さを見てると、あたしも、胸を打たれるよ……。でも、だーめ。今回は、南さんと滝沢さんの、共演のセクシーショーなの。それは、今さら、変更できない。だいぶ、時間が経っちゃってるから、早く、準備して。まず、あなたが、やるべきことは、主演の、南さんの着てるものを、何もかも、はぎ取ることだよ。それは、あなたの責任だからね。それが終わったら、次に脱ぐのは、あなた……。これ以上、ぐだぐだ言って、行動に移さないなら、滝沢さん、あなたのほうから先に、脱いでもらうことにするよ」 当然ながら、香織は、懇願する秋菜を突き放した。 秋菜は、がっくりと頭を垂れた。絶望というものを、如実に体現した少女の姿だった。その数秒後、そろそろと脚だけ動かし、体の向きをこちらに変えた。まるで、ホラー映画に出てくる怨霊のように、うなだれたまま、一歩一歩、涼子に近づいてくる。つと、その瞳だけ、涼子に向けてきた。生気の失せた眼差し。彼女の口が開かれる。 「これから、あんたの着てるものを、脱がさせてもらう……。無駄な抵抗は、やめて」 表情とは裏腹に、静かな闘志の秘められた声だった。 秋菜が、人間性を奪われるくらい、追い詰められているのは、充分、承知している。だが、涼子のほうも、ここで、女としての誇りを捨てるわけにはいかなかった。 「言っておくけど、もし、わたしの服に、手をかけたら、あなた、泣き叫ぶくらい、痛い思いをすることになるからね」 涼子は、右脚をやや後ろに引き、戦闘態勢を取った。 だが、秋菜は、涼子の腕力よりも、香織の鬼畜ぶりのほうが怖いらしく、立ち止まることなく、こちらに歩いてくる。 その時、香織が、割って入るように言い始めた。 「あっ。待って……。考えてみれば、滝沢さんの言うことも、一理あるような気がしてきた……。今回のセクシーショーで、一番、尊重するべきなのは、スペシャルゲストの、舞ちゃんの気持ちだよねえ。たしかに、舞ちゃんからすれば、あくまでも本命は、南さんであって、滝沢さんは、脇役、っていうか、むしろ、どうでもいい存在なのかもしれない」 それを聞いて、秋菜は、希望の光を目にしたのか、ぱっと明るい表情になり、香織のほうを振り返った。 涼子は、怪訝の念を抱く。 「そうだ、いいことを思いついた……。南さんさあ、滝沢さんのことが、大好きなんでしょ? そんな南さんに、チャンスをあげる。滝沢さんに向けて、無限大の愛情を示すチャンス。滝沢さんのために、自分の身を犠牲にする姿を、ここで見せられるかなあ?」 香織は、もったいぶるように話す。 涼子も秋菜も、香織の言葉の続きを待っていた。 「南さん、もし、どうしても、滝沢さんを守りたい、っていう気持ちがあるなら……、今すぐ、ここまで来て」 そう言いながら、香織は、舞の前に移動した。舞の立っている位置から、一メートルほど前の地面を、とんとんと右足で踏む。 「ここね。ここ……。それで、舞ちゃんの目の前で、着てるものを、全部、脱いで。舞ちゃんが、手を伸ばせば、触れられるような距離で、裸になるの。もし、それができたら、南さんの、その、美しい自己犠牲の精神に免じて、今回、脇役である滝沢さんのほうは……、脱がなくてもいいことにする」 香織の、試すような視線が、こちらに向けられている。 秋菜は、たちまち目の色を変えて、涼子に訴えかけてきた。 「ねえっ、お願い! 南さん、そうして。もし、そうしてくれたら、わたし、あなたに対する感謝の気持ちを、絶対に忘れない。だから、早く、あの子の前に行って! 吉永さんの気が、変わらないうちに。わたしからの、心からの、お願い!」 理性を失ったような、ほとんど半狂乱の口調だった。 涼子は、秋菜の言動に、心底、呆れてしまった。いったい、この子は、どこまで身勝手なのかと思う。 それにしても、香織の発言は、実に不可解だった。香織は、秋菜を享楽の生贄にするために、覚醒剤を使用させることまでしたのだ。そうして捕らえた獲物なのだから、香織の性格を考えれば、心ゆくまで、秋菜を辱めたいはずである。なのに、涼子の行動いかんによっては、その秋菜に、手を出さない、だと……。ひょっとすると、秋菜をぬか喜びさせ、後々、地獄に突き落とすという魂胆なのかもしれない。 ただ、香織の真意がどうであれ、涼子は、秋菜のために、そんな、考えうる限り最大級ともいえる屈辱を、甘んじて受け入れるつもりなど、毛頭なかった。 「わたしは、誰がなんと言おうと、あんたらの見てる前で、服を脱ぐことなんて、絶対にしないから」 この場にいる全員に、自分の強い決意を宣言する気持ちだった。秋菜にしても、また、舞にしても、失意を味わえばいい。 「あらっ、そう……。南さんの、滝沢さんに対する愛情っていうのは、しょせん、その程度なんだ……? それじゃあ、滝沢さんを、心から愛してたっていうより、滝沢さんのことを考えて、やらしい妄想に溺れてただけ、って思われても、しょうがないよねえ。南さんって、最低さん……。まあ、いいや。だったら、当初の予定どおり、二人とも、脱いでもらうことにする」 おそらくは、香織も、涼子が、そんな自己犠牲の姿を見せるとは、まったく思っていなかったのだろう。最初っから、その嫌味を言いたかっただけなのだ。 秋菜は、涼子に対して黙っていなかった。 「なんなの、あんたは!? あんたが、いさぎよく脱げば、わたしは、助かるの。二人とも脱ぐ必要が、どこにあるっていうのよ!? もしかして……、あんた、わたしの体に、興味があるんじゃないでしょうね……? あんた、本当に、レズなんじゃないの? レズじゃないっていうなら、自分ひとりで脱いで!」 言っていることが、もはや支離滅裂である。 涼子は、小さな笑い声を漏らしてしまった。人間は、自己保身の本能が爆発すると、これほどまでに醜くなるのかと、人生における新たな教訓を得た気分である。 秋菜は、さらに続けた。 「ねえ、あんたさあ……、もう、とっくの昔に、吉永さんたちの前では、パンツまで脱いでんじゃないっ。あんたの、その体は、隅々まで、それこそ汚いところまで、見られてるんでしょう? 今さら、何を恥ずかしがってんのよ。早く、あの、一年生の子の前で、素っ裸になって!」 その、とても同じクラスの少女から出たとは思えない、無神経極まりない言葉に、涼子の頭の中で、何かが、ぷっつんと切れた。 「あっ……、わたし、帰る」 涼子は、機械的な声で言った。 一瞬、場が静まり返った。 「はあ?」と香織。 涼子は、歩き始めた。地上への階段に向かって。 「なに? 南さん、どこに行くつもりなの?」 香織が、呆気に取られた様子で訊いてくる。 「だから、帰るって言ってんの」 涼子は、当たり前のように返す。 「ふざけないで……。自分の立場を、忘れたわけじゃないでしょ? 立派にセクシーショーをやり終えるまで、帰るのは許さないよ。もし、あたしたちの命令に従わないっていうなら、南さん、あんた、あとあと、どうなっても知らないからね」 心理的な余裕を失っているのだろう、香織は、あからさまな脅しをかけてきた。 「ああ、好きにしてっ」 涼子は、香織の脅迫を受け流し、さらに階段に向かって歩いていく。 もはや、最大の脅威は消えたのだ。香織は、秋菜をも支配下に置いたとしたら、涼子の立場を、有利にしてしまうことまで、頭が回らなかったらしい。涼子としては、本当に助かった。もし、涼子の全裸の写真を、学校中にばらまくつもりなら、そうすればいい。悔しいが、残りのバレー部の合宿費も、くれてやる。こちらは、すでに、あらゆることに対する覚悟ができているのだ。これからは、必要以上に、未来を怖れることはしない。 今度は、後ろから、秋菜が声を発した。 「ちょっと! 南さん、待ちなさいよ……。あんた、わたしを置いて、なに、自分だけ、助かろうとしてんのよ!?」 その言葉に、涼子は、つと足を止めた。一度、とぼけるように宙を見上げ、それから、ゆっくりと秋菜のほうに体を向ける。 「滝沢さん……。わたしは、あなたと力を合わせて、吉永たちに立ち向かいたい、って思ってた……。わたし、本当は、いつでも帰ることができたんだけど、それを、ずっと我慢してたの。あなたを、見捨てたくなかったから。わたしはっ、あなたと二人で……! ここから、出るつもりだった……! でも、あなたは、違った……。なに? わたしは、レズで、変態で、あなたの体操着のシャツを使って……、その……、写真に写ってるような行為をして、興奮してたって、あなた、そう思ってるんでしょっ!? あなた、そう言ったよねえ!? だったら、そんな気持ちの悪い女に、助けなんか、求めないでよ。あなたは、最後まで、吉永に、媚びへつらってたらいいじゃないっ。それで、結果的に、助かればいいけどねっ!」 感情の高ぶりを抑えられず、口の端から、つばが飛びまくっていた。 お互いに、目を見合わせる。 秋菜は、口を半開きにした、間の抜けた表情で立ち尽くしていた。これから、彼女を待っているのは、加虐趣味者たちの、なぶり者にされる運命だ。涼子の目には、そんな無力で哀れな女にしか映らない。 「さようなら、滝沢さん」 涼子は、秋菜に別れを告げ、くるりと身をひるがえした。 ふたたび、階段に向かって進み始める。 香織たちも、この不測の事態に、戸惑っているふうだった。 だが、それから間もなく、香織は、次の手を打った。 「ちょっと、滝沢さん。南さんが、自分の使命を放棄して、帰ろうとしてんの。仲間なんだから、なんとかして、引き留めなさいよ。もし、このまま、南さんが帰ったら、仲間である滝沢さんにも、責任を取ってもらうからね。責任を取るっていうのは、退学ってことだよ」 香織の口調からは、大事な獲物を逃してたまるかという、強い焦りの思いが伝わってきた。 後ろから、秋菜が慌てて叫ぶ。 「ねえ! 今の話、聞いたでしょ!? わたし、責任を取らされて、退学になるのよ!? それでも、わたしなんて、どうなってもいいっていうの!?」 その言葉に、涼子は、うんざりする思いで立ち止まった。顔だけ、秋菜のほうに向けてやる。 「ああ、そのことなら、心配しなくてもいいと思うよ……。吉永の、最大の目的は、あなたを、オモチャにして遊ぶことなの。たぶん、わたしが帰ったあと、吉永たちは、あなたの服を、全部、脱がしたうえで、あなたが、恥ずかしがるようなことを、色々と命令してくるはず。それに、ひたすら従っていれば、退学になることだけはないから、安心して。まあ……、プライドの高そうな、あなたが、そんな屈辱に、最後まで耐えられるかどうかは、知らないけど」 完全に他人事のように言い、また、前を向いて歩き出した。 香織たちは、何か策はないかと問うように、互いに視線を交わし合っている。 涼子は、その三人を、侮蔑の眼差しで眺めた。 もう、自分の身を縛っていた鎖は、断ち切られ、遠い彼方へと飛んでいったのだ。いい機会だから、邪魔する者の入らない、この場で、報復を始めようか。 吉永香織。竹内明日香。石野さゆり。 この、腐りきった女たちを、一人ずつ、順番にリンチしていく。やるとしたら、馬乗りになり、それこそ、気絶するまで、顔面に拳を叩き込んでやる。今まで、自分が、味わわされてきた恥辱の数々を思えば、それでも生温いくらいである。 しかし、と思う。 もし、今、涼子が、そうして暴れ回ったら、後々、滝沢秋菜が、香織たちから、八つ当たりの罰を受けるだろうことは、容易に想像がつく。いくら、秋菜には愛想が尽きたとはいえ、そこまで無責任に振る舞うのは、少々、冷たい気がする。だから、ここは、暴力の衝動を、ぐっと抑え、このまま、香織たちの横を通り過ぎるべきだろう。 だが、涼子には、もう一人、どうしても許せない生徒がいた。 香織たちとの距離が、七、八メートルほどのところで、涼子は、ぴたりと足を止めると、舞の顔を、じっと見すえた。 目が合うと、舞は、涼子から、殺気じみたものを感じて、怖くなったのだろう、後ずさりするような素振りを見せた。 「ねえ、きみ……。きみって、『ゲスト』として、ここに来たんだったよね? 当然ながらさ、事前に、ここで、どんなことが行われるか、その、頭の中の腐った先輩から、教えてもらってたわけでしょ? で……、色々と、変なことを期待してたわけだ? あのさあ……、わたしの裸の写真、見ることができて、嬉しかった……? あっそ、おめでとう。それはそれは、よかったね。……はっきり言っておくけど、わたし、きみみたいな子、大嫌いなんだよね。もう、わたしを見るために、体育館に来るのは、やめてね。わたし、きみの顔、二度と見たくないから」 舞の大きな目が、徐々に潤み始める。目の端に、涙が溜まってきた。ほどなくして、涙のしずくが、頬を伝った。ぎゅっとまぶたを閉じると、舞は、両手で顔を覆った。小さな体が、ひくひくする。 「ああー、一年生の子、泣かしたぁー。最低……。南さん、いくらなんでも、その、鬼みたいな言い方は、ないでしょう?」 香織は、涼子をとがめ、舞の背中を撫でる。 うわーん、という幼稚園児のような泣き声が、舞の口から聞こえた。 涼子は、そんな舞を横目に見ながら、また歩き始めた。ちょっと、言い過ぎただろうか。いや、そんなことはあるまい。もし、舞が、バレー部の部員だったら、一年生とはいえ、頬を叩いているところだ。それに、舞の泣いている理由の、三分の一くらいは、香織の言うところの、涼子のセクシーショーを見られずに終わった悲しみである気がして、むしろ、不愉快な思いがする。 そうして、負け犬感の漂う香織たちの横を、堂々と通り過ぎた。 ふと、そこで、涼子は、バッグのことを思い出し、明日香のほうを振り返った。もはや、下の名前で呼ぶ道理はない。 「竹内……。わたしのバッグ、隠したりしてないでしょうね? もし、隠してんなら、今から、わたしと一緒に、上に来て、バッグを出して。そうしたほうが、あんたの身のためだよ?」 明日香は、ふんっと、そっぽを向く。唇を尖らせている。涼子に逃げられるのが、よっぽど悔しいに違いない。 「そっか。まあ、いいけど。わたし、上に行って、すぐにバッグが見つからなかったら、また下に戻ってくる。それで、あんたの髪の毛をつかんで、上まで、引きずっていくからね」 ただの脅しではなく、本気で、そうするつもりだった。 明日香の返事はない。 涼子は、鼻歌でも歌うように、何度もうなずきながら、階段へと歩いていく。 地獄からの脱出口は、もう、目と鼻の先である。 ようやく、解放されるのだ。 それにしても、ここは、この世の掃きだめに放り込まれたような、とにかく忌まわしい場だった。腐臭すら伝わってきそうな、腐りきった女、三人。それに加え、自己保身に狂奔するクラスメイトと、涼子のことを、性的な目で見ているような、一年生の生徒。この空間には、そんな五人の吐く息の成分が、充満している気がし、それが、じめじめとした空気と共に、肌にまとわりついてくるようで、腕をさすりたくなるほど不快である。 家に帰ったら、なにより先に、熱いシャワーを浴びて、汗も、この場の残滓も洗い流し、自分の体を綺麗にしたい。それと、普段は、忙しさのせいもあり、湯船に浸かる時間は、ほとんど取らないのだが、今夜は、たっぷり三十分くらい、湯の中で、疲れた心と体を癒すことにしよう。その後は、どうしようか。なぜか、無性にコーラが飲みたい気分だ。健康面を考えて、もう、この何年かは、炭酸飲料を口にしていなかったが、今夜だけは、特別、自分にご褒美をあげよう。香織たちの呪縛から解き放たれたことを記念して、コーラで乾杯だ! 涼子は、後ろにいる五人に、余裕を見せつけるように、両手の指を組み、両腕をぐっと上に伸ばした。そのまま、両腕を左右に動かして、ストレッチをする。五人とも、涼子が帰ることに、さぞかし、やるせない思いを抱えているのだろう。ザマアミロ。心の中で、そう吐き捨ててやった。 それから、悠然と階段へと歩いていく。 最後に、涼子の背中に、言葉を投げかけてきたのは、滝沢秋菜だった。 「そうやって、自分だけ、帰っていくわけね……。それなら、いいわよ……。わたし、学校の友達、全員に、こう証言するから。実は……、わたし、南涼子から、何度もしつこく、告白をされてたんだ、って」 何を言っているんだ……? 涼子は、眉をひそめ、後ろを振り返った。 秋菜は、能面のように無表情だった。 「告白をされるたびに、わたしは、女同士で付き合うのは、考えられないって、断り続けた。そうしていたら、ある日、南涼子に、屋上に呼び出されて、わたしは、なんか嫌な予感がしたけど、ひとりで、そこに行った。そこで、顔を合わせると、南涼子は、突然、わたしに抱きついてきて、無理やり、キスをしようとしてきた。わたしは、全力で抵抗して、危機一髪のところで、難を逃れた。正直、顔を殴ってやりたいくらい腹立たしかった。だから、南涼子に向かって、あんたは、わたしにとって、世界中で一番、気持ちの悪い女だから、もう、二度と、わたしに関わらないでって、強く言ってやった」 意味不明な作り話である。 もしかして、秋菜は、恐怖に耐えられなくなり、正気を失ったのではないかと、涼子は、本気で思い始める。 「さすがに、それだけ言ってやったから、南涼子も、わたしのことを諦めるだろうと思ってた。だけど、南涼子は、違った。わたしが、ほかの友達と仲良くしてると、なんか、悲しそうな目で、こっちを、じっと見てきたし、事あるごとに、わたしと、二人っきりになろうとしてきた。わたし、本当に怖くなってきたから、誰かに相談したかったけど、そうしたら、南涼子に、何をされるかわからない気がして、誰にも言えなかった。わたしの、そんな弱気なところが、南涼子を、よけい付け上がらせたみたい。それで、とうとう、南涼子は、こーんなモノを、わたしに渡してきたの……、ってね」 秋菜は、両手に、あの三枚の写真と、体操着の入ったビニール袋を、それぞれ持って、そのセットを顔の高さまで掲げた。 涼子は、金縛りに遭ったように動けなくなった。徐々に、意識が後方へと遠ざかっていく。 「なっ……」 言葉が出ない。 喉もとが、けいれんし始めた。 この空間が、氷の世界に変貌したかのような、冷たい沈黙が続く。 だが、やがて、涼子の胸中では、秋菜に対する、どう猛な怒りが燃え上がった。 涼子は、せきを切ったようにまくし立てた。 「あんたさあ……! いったい、どういう精神構造してるわけ!? あんただって、その写真に写ってるのは、吉永たちが、わたしに、無理やりやらせたことだって、それくらい、当然わかってんでしょう!? それに、なに、その作り話は!? わたしが、いつ、あんたに、告白したり、抱きついたりしたっていうのよ!? ふざけんのも、いい加減にして!」 「関係ないわよ、そんなの……。わたしは、あんたが、自分だけ助かればいいっ、っていう態度で、帰ろうとしてるのが、許せないの」 涼子は、絶句してしまった。 秋菜は、面白いものを見るように、右手で掲げた三枚の写真を眺める。 「まあ、この写真を見ただけだと……、あんたが、誰かに強要されて、こんな変態行為をやらされたように見えるかもしれない。だけど……、わたしが、今、話した内容の『証言』をすれば、どうなるかな? この写真は、あんたが、前代未聞の変態であり、女の性犯罪者であり、レズのストーカーであることを、証明する代物になるのよぉ……? それと、わたし、友達を集めて、この、体操着の入ってるビニール袋のチャックを、開けることにするわ。あんたの、汚いところから流れ出た体液なんて、きっと、とんでもない臭いがするんでしょうねえ」 涼子は、天地が、ぐるぐると回って見えるほどの、激しい目まいを起こしていた。 秋菜の目に、涼子の事情は、お見通しだというような光が宿る。 「ねえ、南さん……。あんた、このところ、ひとりぼっちでいることが多くて、ずいぶん寂しそうじゃない。クラスの子たちに、露出趣味のある変態だっていう目で見られて、距離を置かれてるのは、どんな気分? 時々、親友っぽい子と話してる時は、『わたしは、大丈夫だから』みたいな笑顔を見せてるけど、本当は……、もう、つらくてつらくて、心が折れそうなんでしょ? そんな、あんたに、わたしが、とどめを刺してあげようか? わたしの『証言』と、この三枚の写真と、この汚物のこびり付いた体操着のシャツ。わたしが、その気になれば、この学校の、どこにも、あんたの居場所はなくなる。もちろん、かけがえのない親友からも、あんたは、軽蔑されることになる。要するに、あんたは、すべてを失うってわけ」 もはや、涼子は、身体感覚までも喪失している状態で、今、自分が、地に足をつけて立っているのかどうかすら判然としなかった。 「わたしを見捨てて、帰りたいなら、帰ればいいじゃない……。その代わり、わたしは、絶対にあんたを許さない。この学校から、あんたを、抹殺してやるから」 秋菜は、怒気を滲ませた表情で、そう言った。 いやあぁぁぁぁぁぁぁぁ……! 涼子は、絶叫しそうなほど震かんした。 まるで、壊れかけのロボットのように、ぎこちない動きで、首だけ後ろに回す。 地上への階段は、すぐ、目の前、三、四メートルほどの距離にあるのだ。勇気を出して、あと、ちょっとばかり、そちらに歩けば、階段に足をかけることができる。しかし、自分の両脚は、石化したように動かない。近くにあるはずの階段が、途方もなく遠いところに設置されているような錯覚を覚え始める。 思い返せば、このところ、しばしば、こんなイメージが脳裏に浮かんでいた。 地面に空いた、深くて暗い大穴。 秋菜は、そこに落ちかかったものの、かろうじて穴の縁に手をかけ、なんとか地上に這い上がろうと懸命になっているところだ。しかし、彼女の両脚には、自己保身の権化と化した全裸の涼子が、死にもの狂いでしがみついており、秋菜を、道連れにしようとしている……。 それは、とてつもなく後ろ暗い気持ちになるイメージだった。 しかし、現実では、涼子と秋菜を逆にしたことが起こった。 全裸だった涼子は、すでに、きちんと衣服を身に着け、穴の縁に手をかけていた。もはや、地上に這い上がるのは、造作もないことだった。これからは、前途多難ながらも、自由に生きることができる。そう信じて疑わなかった。 ところが、その時、涼子の右の足首が、突然、がっちりとつかまれた。下を見ると、秋菜が、そこにぶら下がっており、涼子をにらみ上げていた。秋菜は、まだ、衣服をまとってはいるが、目が血走っていることも、顔が病的に青白いことも、以前までの涼子の姿そのものである。そればかりか、秋菜のその顔は、人智を超えた怨念のために、醜く歪みきっている。まさに、化け物だ。 その秋菜が、荒々しい声で叫ぶ。 『あんただけ、助かろうったって、そうはさせないわよっ! どっちかが、助かるとしたら、わたしのほうでしょうが! あんたは、永遠に、地獄の底で、のたうち回ってればいいのよぉ!』 秋菜の握力は、思った以上に強い。 このままだと、秋菜と共に、穴の底へと転落してしまう。 どうしたらいいんだろう……!? 涼子は、顔だけ、階段のほうに向けたまま、身動きが取れないでいた。 すると、誰かが、すっと動いた気配がした。竹内明日香だ。 明日香は、涼子と階段の間に、割り込むように立つ。それから、こちらに近づいてきて、涼子の背中に、両手を当てた。 「とっとっとっとっとっとっとととととと」 愉しげなかけ声を出しながら、涼子の体を押してくる。地上への階段から、涼子を遠ざけるように。 「あっ……。やっ……。いや……。ちょっと……」 涼子は、途中で、何度か抵抗して足を止めるも、精神的にも肉体的にも踏ん張りがきかず、十メートル以上、強制的に進まされた。 そして、結局、秋菜の横まで戻ってきてしまった。 明日香は、低い笑い声を漏らし、香織たちのところに戻っていく。 涼子は、後ろを振り向いた。十数メートル向こうにある、地上への階段を、狂おしい思いで凝視する。階段は、一キロ以上、離れた場所に存在するかのように、やたらと小さく見えてならなかった。 しばらく、家には帰れない。きっと、そうだ。だんだんと、その現実を認めざるを得なくなってくる。 熱いシャワーを浴び、風呂上がりに、コーラで乾杯したい……。涼子のそんな、ささやかな望みすら、夢まぼろしのごとく叶わぬものとなっていく。 穴の縁にかけていた、涼子の手は、ついに離れてしまったのだ。秋菜と共に、穴の底に、どすんと落ちる。全身に、ものすごい衝撃を感じた。 今、香織たちは、互いに、肩を揺すったり、腹をくすぐったりしながら、悦びを露わにしていた。 見ると、舞も、まだ目を赤くしているものの、すっかり泣き止んでおり、涼子が、この場に押し戻されたからだろう、気を取り直しているふうだった。 香織は、歯茎まで見せるような笑い顔を、こちらに突き出すようにした。 「ミ・ナ・ミっさーん。リョ・ウ・コっちゃーん。残念だったねえ。惜しかったねえ。もうちょっとで、ここから出られるところだったのにぃ。あたしも、南さんに、帰られるんじゃないかと思って、冷や冷やしちゃったぁ。本当に、滝沢さんが、機転を利かせてくれて、あたしたちは、助かったよ。ありがとう、滝沢さん……。それに比べて、南さんは、使命を放棄しようとしたんだから、罪は重いよ。その体で、たっぷりと罰を受けてもらうからね」 涼子は、悪夢の中にいるような心地で、香織の話を聞いていた。 香織は、目を細めて、斜めに涼子を見る。 「それにしても……、南さんが、クラスメイトを見捨てて、自分だけ助かろうとするなんて、なんか幻滅しちゃうよね。バレー部のキャプテンで、責任感が、すごい強い生徒だとか、生徒会長よりも校則を守ってる優等生だとか、困ってる子を見たら、放っておけないタイプだとか、みんなから言われてたけど、あんたも、そこいらの子たちと、全然、変わらないじゃない。言っておくけど……、南さん、もう逃げられないからね。南さんと滝沢さんは……、一心同体、じゃなくて、二人三脚、じゃなくて、一期一会、じゃなくて、なんか、そういう四字熟語、あったじゃない。あの……、最後まで、運命を共にする、みたいな」 「いちれんたくしょう、って言いたいの?」 秋菜が、頭の優秀ぶりを発揮する。 「あっ、そうそう。それ……! さすが、滝沢さんだね……。いい? 南さん、よく頭に叩き込んでおいて。南さんと滝沢さんは、一蓮托生だからね」 香織は、釘を刺すように言う。 「……だってさ」 秋菜は、なにか勝ち誇ったような薄笑いを浮かべて、涼子のことを横目で見る。その目は、こんなふうに語っていた。逃げられるものなら、逃げてみなさいよ。その代わり、あんたの高校生活を、破滅させてやるから……。 涼子は、これ以上、秋菜の顔を見ていたくない気分で、顔をそらした。 滝沢秋菜と、一蓮托生……? 冗談じゃない……! 気持ちを落ち着かせよう。冷静になれ。まず、自分が助かるためには、秋菜を突き放さねばならない。それを可能にする妙案を、なんとしてでもひねり出すのだ。もし、考えるのをやめたら、そこで、自分も、秋菜と同じ運命を辿ることが決まる。 つまり……。 下劣極まりない加虐趣味者、三人と、さらに足立舞も見ている前で、涼子と秋菜は、着ているものを、一枚一枚、脱がされていき、やがては、無残にも、全裸をさらすことになるのだ。想像するだけで、気が変になりそうだった。 それに、先ほどから、香織が、同性愛にまつわる発言を繰り返していることが、妙に気になる。 全裸になった、少女二人。 いくらなんでも、そういう類の行為を強要してくるはずはないと信じたいが、なにしろ、香織たちのことだ。ないとは言い切れない。 脳裏に、涼子としては、不潔にしか感じられない情景がまたたいた。 涼子と秋菜は、一糸まとわぬ姿で、向かい合うように立っている。お互いが、歩み寄り始めた。二人の間の距離は、もう、一メートルほどしかない。涼子は、嫌悪感に顔を歪めている。秋菜は、唇をへの字に曲げ、今にも泣き出しそうな表情だ。とうとう、そんな二人の体が密着した。乳房と乳房が、ぶつかり合い、柔らかいデザートのような質感を示して潰れる。涼子は、秋菜を抱擁した。秋菜もまた、涼子の背中に両腕を回した。それから、相手の顔を、決して見るまいと、目を固く閉じた、涼子と秋菜の唇が、ぶちゅっと重なり合う……。 涼子は、頭を振って、その情景を追い払う。体中の毛穴から、体を動かしている時とは明らかに違う、あぶら汗が噴き出しており、肌が、より一層、べたついているのがわかった。 日頃から、神仏に対して、多大な敬意を持っていたわけではない。だが、今は、それらの超自然的な存在に、自分の運命について問いたかった。 まさかまさかまさか……、そんな最悪なことには、絶対になりませんよね……? 神様……。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.