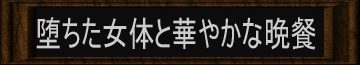
第二章
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
「千尋ちゃん、待って」 亜希に呼び止められた。千尋は、そちらへわずかに顔を巡らせた。 「立ったままでいいから聞いて。これから、どうするの?」 虫酸の走ることに、亜希の顔は、不敵さに満ちていた。 「家族と合流するわ……。わたしの家族にも、それと、あなたのお父さんにも、あなたがわたしを侮辱したことは、言わないから安心して。なんせ、わたしたちの家は、菅野さんに助けてもらってる立場だもんね。菅野家の娘に暴言を吐かれたからって、告げ口なんてできるはず、ないもん……」 千尋は、自虐的な調子で言っだが、その実、悔しさで、奥歯がかちかちと鳴りそうだった。 「ア・ン・シ・ン・し・て……」 亜希は、おうむ返しに呟くと、突然、吹き出した。つられて、加納までもが、口を押さえて笑っている。 千尋は、唖然として二人の様子を眺めていた。 ひとしきり笑った後、亜希は、上気した顔を千尋に向けて言う。 「安心して……、って、千尋ちゃん、それは勘違いし過ぎだよお。ま、本当のことを知らないんだから、仕方ないかなあ」 「なによ。もったいぶってないで言いなさいよ」 すでに、千尋は喧嘩腰になっていた。 その時、亜希の目つきが一変した。かっと見開いた目で、千尋を直視している。 「教えてあげるよ」 亜希は、自信たっぷりに言った。 「千尋ちゃん衝撃のじじつー。うちのパパは、安城家を助けるつもりなんて、本当はなかったんでーす。リスクが大きすぎるってね。それを説得したのが、このわたしなんでーす。千尋ちゃんが可哀想だから、あの家の人たちを助けてあげてー、ってね。でないと、わたしグレてやるうー、とも言いましたあ」 自慢話のように話す亜希は、一度言葉を切り、また話を続ける。 「要するに、千尋ちゃんの家族を助けたのは、パパじゃなくって、このわたしなの。だから、わたしの一言で、あなたたちの運命は、どうにでもできるってわけ。わたしたちに見放されたら、安城さんの家族は、本当にどうなっちゃうんだろうねえ。こわーい、こわーい」 目の前が暗くなってきた。漠然とした、だが、とてつもなく巨大な恐怖が、千尋の精神と肉体を支配し始めていた。冷静さを失ってしまいそうだった。いったい、亜希は、何が言いたいのだろう……。まず、それが知りたかった。 「あんたは、わたしに、どうしろって言うわけ?」 千尋は、内心の動揺を悟られまいと、取り澄ました口調で訊いた。 「この家で働いてほしいだけだよ。そのために呼んだんだから。千尋ちゃんがここで働くならば、千尋ちゃんの家族も助かって、すべてが丸く収まるってわけ」 大切な家族の姿が、脳裏に浮かんだ。 「働くって、何の仕事をすればいいの?」 とても悔しいが、もう亜希の意向を無視するわけにはいかなかった。 「詳しい仕事内容は、おいおい教えていくからさ。まず、千尋ちゃんには、繰り返しになるけど、適性検査を受けてもらうよ」 すでに亜希は、勝ち誇った仕草を見せ始めていた。 「ふざけないで。本気で言ってるの……?」 なぜ、わたしは、こんな馬鹿げた話に付き合っているのか。自分でも不思議に思えてならない。 「嫌なら別にいいけどね。でもね、千尋ちゃんが働かないつもりなら、安城さんの家族は全員、パパに追い出してもらうよ。そのためには、なんだって言っちゃうから、わたし……。千尋ちゃんが、わたしに嫉妬して、ひどい暴言を吐いてきたのー、……って言おうかな。どんな嘘であろうと、加納さんが、証人になってくれる予定だからね」 千尋は、亜希の悪知恵に言葉を失った。亜希の性根の悪さは、底無しだと思い知り、背筋が寒くなったほどだ。 「どっちにすんのお?」 腹立たしいが、亜希は、すでに勝った気でいるらしい。 千尋は、怒りで熱くなった頭の中で、逡巡していた。だが、頭の片隅では、半ば結論が出ていた。 今、菅野社長に見捨てられたら、家族全員が、社会の闇に呑み込まれてしまう。わたしひとりが、すべてを耐えることで、少なくとも、その間は、家族が救われるのだとしたら……。 「ほらぁ! どうするのか答えなさいよ!」 加納に怒鳴られて、千尋はびくりとした。 「……ここで、働くわ」 聞こえるか聞こえないかの声量で言う。 「聞こえなーい!」 加納が、大げさに文句を付けてくる。千尋は、小さく溜め息をついた。 「この家で、……働きます」 千尋の敗北宣言によって、亜希と加納は、顔を見合わせて笑った。そして加納が、つかつかと歩いてきて、千尋のかたわらに立った。 「お嬢さまに、ちゃんと頭を下げるのよ。千尋お・じょう・さま」 語尾には、もう令嬢でも何でもない千尋に対する皮肉が込められていた。 亜希は、ソファにふんぞり返り、負け犬を見るような目で、千尋を眺めていた。幼少の頃から姉妹のように遊んできたというのに、安城家が失墜したのを機に、態度を豹変させた、この小娘。 千尋は、怒りに体が震えそうだったが、すべての感情を押し殺して頭を下げた。 「働かせてください」 安城家の長女というプライドを、完全に捨て去った瞬間である。腰を折った千尋の頭上に、亜希と加納のせせら笑う声が浴びせられた。 「いいよっ。千尋ちゃん。じゃあ初めに、適性検査をするから、服を脱いでねっ」 亜希の下劣さには、吐き気を催しそうだ。適性検査なんて言葉は、あまりにもふざけきった口実である。亜希の本心は、裸になって、女として最大の屈辱を味わう千尋の姿を見たいだけなのだ。そうして、優越感やら征服感やらに浸りたいのだろう。 だが、目の前の小娘が何を考えていようと、千尋は従うほかない。カーディガンを外し、半袖のカットソーに手を掛ける。家族一人ひとりの顔が、脳裏にちらついた。彼らに向かって心の内で言う。わたしが、犠牲になってあげるからね……。 カットソーを首から引き抜くと、グレーの色をした綿のブラジャーが現れる。ここで間を置いてしまうと、その後が余計きつくなる。すぐに、タイトな黒のジーパンのホックを外し、太ももの下まで引き下げた。 頬が紅潮してしまうが、何でもないことのような手つきで、両脚からジーパンを抜き取った。 ブラジャーと上下揃いの、グレーを基調に黒いラインで縁取りされているパンツを身に着けていた。ひとりだけ下着姿になるのは、予想よりはるかに恥ずかしいことだった。すべてを脱ぐ覚悟を決めていた千尋だが、ここまでが限界だった。 その時、亜希が、思いがけないことを訊いてきた。 「千尋ちゃん。その下着、いつから着けてるの?」 意表を衝かれた千尋は、思わず亜希の顔を見ていた。 「なんでそんなことが知りたいの?」 そう聞き返した直後、加納の怒鳴り声が、千尋の耳朶を打った。 「おい! おまえ、まだ立場がわかってないんだなあ。お嬢さまには敬語を使うんだよ。それと、訊かれたことには、すべて素直に答えろ」 使用人である加納に『おまえ』呼ばわりされたうえに、刑務所の囚人扱いのような命令を受ける。もはや、何が何だかわからなくなってきた。 「返事をしろ!」 非情な追い打ちに、体が竦み上がり、千尋は慌てて返事をする。 「はい。わかりました」 どうやら、これからは、加納に対しても、へりくだった言葉遣いをしなければならなそうだ。そして、亜希の質問にも答えなくてはならない。たとえ、それが、どんなに不快な内容であったとしても。 「これは……、おとといから着けてる。……んです」 すると亜希は、くすくすと笑い始めた。 「そんなことだろうと思ったあ。だってさぁ、股のところが、染みで汚れてるんだもん、千尋ちゃんのパンツ。安城家の娘なのに、パンツも替えられないなんてえ。惨めねえー」 恥辱と憤怒で、火が出るように顔が熱くなった。この、クソガキ……。 「ほらあ千尋ちゃん、いつまでブラとパンツを着けてるつもりなのお? はやく裸になりなさいよ」 怒りに震える千尋を嘲笑うかのように、亜希は余裕に満ちており、そして、どこまでも冷酷だった。 この憎い小娘を殴りつけることができたら、どれほど胸がすっとするだろう。だが、そんなことは、空想の世界でしか叶わない。 全裸。もうすぐ自分が、そうなるということを実感する。なりふり構ってはいられない。土下座でもして、もう勘弁してほしいと頼んだら、亜希は許してくれるだろうか。 いや、きっと許してはくれない。許してくれるはずがないじゃないか。それこそ、裸になった時、余計に惨めな思いをするだけだ。結局のところ、他に選択肢はないのだった。 千尋は、両手を背中に回してホックを外した。わざと投げやりな手つきで、肩ひもを腕から抜き、ブラジャーをぽいとソファに放った。 最後に、泣きたくなるのを必死に堪えながら、パンツを膝まで引き下げる。とたんに、強い酸性の臭いが、その布地から立ち上って鼻を突き、千尋は、思わず手を止めた。 グレーの股布の部分を、ちらりと確かめると、おりものが、べったりと白くこびり付いているのが、目に映る。何とも言い様のない感情に、胸を締め付けられるが、汚れたパンツを脚から抜き取り、ソファの上に手放した。 震える両腕を動かして乳房と陰毛を隠すと、千尋はうなだれた。 なんという屈辱だろう。悔しい……。悲しい……。とてもじゃないが、亜希のほうを向くことができない。亜希の口から、次に発せられる言葉を、戦々恐々として待つばかりだった。 「千尋ちゃん。脱いだものを全部、このテーブルに載っけて」 唯々諾々と指示に従い、千尋は、脱ぎたての衣類をソファからテーブルに移した。さり気なく、パンツをカーディガンにくるんでおく。 亜希は、千尋の衣類に手を伸ばした。カーディガンを選んで両手に持ち、目の前に広げる。見られたくないパンツは、はらりとテーブルに落ちていた。 「このカーディガン、かわいい。いいなぁ千尋ちゃん……」 裸になった女の子が、それまで身に着けていたものを、いちいち鑑定するとは、なんと悪趣味だろう。そして何より、亜希が『あれ』を見逃すはずはなかった。 案の定、次に亜希は、グレーのパンツに手を掛けた。その布地が捲り返されて、股布の部分が表に曝される。 そこで、千尋は思わず目を背けた。だが、視界の端から伝わってくる気配から、亜希の動作や表情は、否応でも頭に入ってくる。 亜希は、下卑た好奇心から、千尋が、丸二日間着けていたパンツの汚れ具合を、まじまじと確かめていた。あからさまに臭いを嗅ぐような真似はしないが、まず間違いなく、鼻腔に、あの臭気を感じていることだろう。 亜希は、侮蔑の笑みを浮かべ、ちらちらとこちらに目を向けてくる。恥ずかしがる千尋の様子が、面白くて仕方がないらしい。 情けない、と千尋は痛切に感じた。安城家の娘であるわたしが、下劣で性悪な小娘に欺かれた挙げ句、こんな辱めを受けるなんて。 「千尋ちゃん。これから、あなたの適性検査を始めるからね。心の準備はできてる?」 汚れたパンツの検分に気が済んだらしい亜希は、愉快そうに言った。 千尋は、ごくりと生唾を飲み込んだ。こっちは全裸にまでなっているというのに、まだ、物足りないというのか。というより、むしろ、これからが本番だということを告げられているのだ。亜希の言う『適性検査』の、底の知れない怖ろしさに、ほとんど絶望的な気持ちになる。 しかし、拒否権のない千尋は、必ずイエスと返事をしなくてはならない。加納の射るような厳しい視線を、ひしひしと感じるのだ。いつからか、スーツ姿の使用人の存在が、千尋にとって大きな脅威となっていた。 「……はい」 千尋は、かすれる声で、いかがわしい『検査』を受けることを承諾した。 「加納さん。千尋ちゃんの適性検査をお願いしまーす」 亜希は、ひときわ明るい声音で言った。 「はい。了解しました」 加納は、亜希に対してかしこまると、千尋のほうへ、ずかずかとやってくる。背が高く、いかめしい顔をした加納は、まるで鬼教官とでもいう風情だった。千尋は、まともに目を合わすことすらできない。 加納からしたら、自分より十歳以上、年下の少女が、全裸で乳首と性器を両手で隠しているのだ。普通であれば、同じ女として、その痛ましさに胸を痛めるような状況だろう。しかし加納は、少しの容赦もしないとでもいうような目つきで、千尋を見下ろしているのだった。 「両手を腰に付けろ」 加納が、言葉少なに命じた。 千尋は、どきりとして、おずおずと加納の顔を見上げる。 「え、え……。あ、あのう……」 舌がもつれて、まったく言葉にならない。 「こうするんだよ!」 加納は、いきなり千尋の両腕を引っつかむと、いったん強引に胴体から離してから、腰の両脇に、ぴしゃりと両手を当てさせた。 「ひうっ……」と、千尋の喉元から、空気の漏れるような声が出る。 「ほら! まずは、お嬢さまに、おまえの体をしっかりと見てもらえ」 加納はそう言って、千尋の背中を邪険に押した。勢いよく押されたために、どたばたと脚が前に送り出され、テーブルで膝頭をしたたかに打った。 痛い……。だが、痛みを感じている余裕もない。今、千尋は、目まいのするような恥ずかしさに、精神も肉体も押し潰されそうになっていた。 「もじもじしてるんじゃないよ! ちゃんと背筋を伸ばせ!」 羞恥心に体を縮こまらせる千尋に、加納は、情け容赦なく怒鳴り声を浴びせる。 千尋は、徐々に背筋を伸ばしていき、直立に近い姿勢を取った。腰に宛がっている両手に、どうしても力が入り、おしりの肉を強くつかんでいた。 今まさに、完全に無防備な格好で、乳房や陰毛を亜希の視線に晒しているのだ。呼吸がひどく浅くなっている。視界がぼんやりと霞み始め、意識が遠のきそうだった。 「千尋ちゃんの胸って、綺麗な形してるねえ。まん丸い果物みたい。でも、大きさなら、わたしのほうが勝ってるかなあ」 亜希は、身を乗りだし、千尋の裸体を品定めする。乳房が終わると、亜希の視線が下がっていくのを感じた。当然ながら、その視線は、千尋の下腹部に留まった。 両手に一層力が入り、おしりに爪を立てていた。恥部を隠すことすら許されない自分の立場が、惨めで惨めでたまらなかった。 乳房よりもずっと長く、そしてひどく無遠慮に、亜希は、そこを凝視している。陰毛の濃さや、その奥に覗く、縦の筋を観察されているのだろうか、などという嫌な思いが、脳裏をよぎる。 ようやく、亜希は満足げに何度か頷くと、加納に向けて目顔で合図を送った。加納は、了解を示すように顎を引くと、俊敏な動作で、千尋の正面に移動した。 なにをされるのだろう。千尋は、びくびくしながら、背の高い使用人の顔を窺う。加納は、ぞっとするほど冷たい双眸で、千尋を見下ろしていた。 白い袖の両手が脈絡なく伸びてきて、千尋の肉体にかぶりついた。 「いやっ!」 金切り声の悲鳴を上げた千尋は、体を弓なりに反り返らせていた。今、加納の両手に乳房が捕らえられ、その指が、肉にめり込んでいるのだった。 辱めるというより、なぶるような乱暴な手つきで、乳房が揉み潰された。指の圧力は凄まじく、指と指の間から肉がはみ出している。加納が、あまりにも荒々しく手を動かすので、千尋は、幾度もよろめくことになった。 きつく乳房がつかまれるたび、女としての大切な何かを奪われていくような思いがした。大きな恐怖感が、徐々に、身を裂かれるような悲しみへと変わっていく。 あんたは、わたしに何かの恨みでもあるの……。千尋は、そう問いかける目で、加納の顔を見やった。 加納は、千尋の視線に気づいても、眉一つ動かさない。何の感情も持ち合わせていないような、その表情。 しかし、乳房をなぶる両手の動きには、変化があった。突然、乳房の上部を、きつく絞り上げてきたのだ。ピンク色の乳首が、見るも無惨にみるみるとせり出していく。 「ああぃ……!」 千尋は、たまらず声を上げた。乳房の先端の、ずきずきとした鋭い痛みが、加速度的に増していく。 「やめて下さい! いたい、いたいです!」 千尋は、身をよじりながら哀願した。 それを聞き入れたのか、ふいに加納の手の力が緩んだ。だが今度は、その指が、双方の乳首にピンポイントに接触した。 加納は、千尋の性感帯を指で挟むと、こね回すようにこすり始めるのだった。今しがた、激痛に見舞われた乳首が、おぞましくも、同性による愛撫を受けているのだ。 ぞっとして、全身にびっしりと鳥肌が立った。 頭の中が混乱の極致に陥ったため、抑えていた感情が、ほとばしった感じがした。 目から、生温かいものが流れだし、頬を伝う。 今、千尋の乳首は、前に引き伸ばされているところだった。加納は、千尋が涙しているのを認めると、手を離して、亜希のほうに半身を向けた。 「お嬢さま……。この子、泣いてしまいましたよ」 亜希は、ぽかんと口を開け、千尋を眺めた。 「千尋ちゃん、悲しいの……? でも、これは働く前の検査で、仕方のないことだから、つらくても頑張ってね?」 そう言った亜希が、そのすぐ後、下を向いて笑いを堪えるような仕草をしているのが見えた。 千尋は、鼻を啜り上げた。わたしの馬鹿……。なんで涙なんか。余計に惨めになるだけなのに……。腕で、ぐっと目を拭う。 その時、ふいに、乳房を両手で強く押し上げられた。 「ふうっ!」 油断していた千尋は、気張ったような、無様な声を発していた。 「胸は合格だ。これから、おまえのここを検査する」 加納の右手がすっと下り、その人差し指が、千尋の肌にぴたりと触れた。そこは、臍の下、わずかに肉が盛り上がったところ、ちょうど陰毛の生え際のあたりだった。 心胆を寒からしめられる宣告に、全身が硬直する。泣きついて許しを乞いたかったが、イエスと答えるしか選択肢のないのが、今の千尋の立場なのだ。 「……はい」 加納は、軽やかな動作で、立て膝の体勢になった。千尋の陰毛の茂みと、加納の目の高さが同じになる。 加納は、太ももの外側を、がしっと両手で押さえつける。そうして、顔を、陰毛の毛先に触れるか触れないかのところにまで寄せてきた。だが、すぐに顔を離し、苦々しい表情になった。 「しっかし、ひどい臭いだね……。おまえ、あの汚れた下着と同じで、一昨日から風呂に入ってないだろ?」 加納は、侮蔑の目つきで、千尋の顔を見上げながら言った。 無防備な体勢で、性器の臭いを嗅がれた上に、自尊心を深く傷つけられるようなことを訊かれても、イエス、なのだ。 「……はい」 それを聞いた亜希が、はしゃいで笑った。 「千尋ちゃんったら、お風呂にも入れなかったのおー? きったなぁーい」 パンツの汚れや体の不潔さといったものを、千尋の凋落の象徴と捉え、ことさら愉しんでいるようだった。 加納が、右手の親指を恥丘の肉に押しつけてきた。 「おまえ、恥垢も、だいぶ溜まってるんじゃないのお?」 そう言いながら、恥丘の肉を吊り上げたり戻したりを繰り返し始める。それに合わせ、性器の裂け目がぐいぐいと上部に引っ張られ、陰唇やクリ○リスが見え隠れした。 女の聖域ともいうべきところを、平然ともてあそぶ同性の仕打ちに、千尋は、脳髄が痺れるようなショックを感じていた。わたしは、今、悪い夢でも、見ているのではないだろうか……。 「ねえねえ……、千尋ちゃんって、処女だよね?」 突然、亜希が、突拍子もないことを訊いてきた。いや、今の千尋の姿からすれば、むしろ、当然とも言えるような質問なのかもしれないが。 加納は手を止め、下から無言の圧力を掛けてくる。 「処女です」 千尋は、端的に言った。それは本当だった。 「そうだよねえ……。千尋ちゃんから、彼氏ができたって話、聞いたことないもん。そんなに可愛いのに……。理想が高いのかな? あ、いや、それとも……」 亜希は、疑うような目つきになり、千尋を斜めに見ている。 「わたしには内緒にしてたのかな……? その可能性があるから、ちゃんと調べないといけないねえ。……加納さん、千尋ちゃんが言ってることが、本当かどうか、確かめてみてくれる?」 「了解しました」 千尋は、すぐには、亜希の発言の意味が呑み込めないでいた。しかし、ほどなくして、体中からさっと血の気が引いた。 そんな……。うそでしょう。 「両脚を開け」 加納は、言葉少なに命じた。千尋の人権など、一顧だにしていない口調だった。 これまで、加納の脅威に圧倒され、言いなりになってきたが、さすがに今度ばかりは従えない。精神と肉体が、激しく拒絶している。 「とっとと開くんだよ!」 加納は、怒号を上げた。 悪魔……。 千尋は、その言葉を、足もとから睨みつけてくる加納に対してではなく、ソファでアイスティーを啜りながら、成り行きを面白おかしそうに見ている、亜希の顔に当て嵌めた。 「いやです……。できません」 消え入るような声だったが、千尋は、勇を鼓して拒否した。 「はあ!?」 聞き捨てならないというふうに、加納が威嚇の声を出す。 その直後、加納の手が、勢いよく千尋の太ももを打った。千尋は、衝撃と激痛に飛び上がりそうになった。 「お嬢さまの命令なんだよ! どんなことでも従うの!」 さらに、同じところを、もう一発強打される。 千尋の意志は、非道な暴力によって、へし折られてしまった。千尋は、恐怖に衝き動かされ、そろそろと両足を外側へと開いていく。叩かれたところは熱を持ち、びりびりと痛んでいた。 「のろのろしてんじゃないよ、まったく」 加納は、苛立った手つきで、両脚の太ももの内側に手を宛がい、こじ開けるようにして千尋を開脚させた。 自分の取っている体勢を、頭で客観的に認識した瞬間、千尋は、奈落の底に落とされたような気分を味わった。うそ、ひどい……。なんて惨めな格好なの。惨めすぎる……。 身を焼かれるような恥辱に、膝が震え始める。だが、ショックに打ちひしがれる余裕さえなく、加納の両手が、剥き出しの股間へと伸びてくる。両手の親指が、陰唇に食い込んで、ぱっくりと陰裂が開かれた。 加納は、千尋の股の下のスペースに顔を潜り込ませると、覗き込むようにして性器を調べ始めた。 鮮やかな色の粘膜まで露出した性器は、当然、亜希にも見られている。今、亜希の表情には、卑猥な好奇心が、露骨に表れていた。 陰唇の中を這っていた加納の指先が、膣口のそばに移ったのを感じた。膣口が、じわじわと広げられていく。 千尋は、すさまじい恐怖に襲われて、ほとんど半狂乱に叫んだ。 「やめて、やめて、やめて下さい! 痛いんです!」 実際に痛みを感じたわけではないが、加納という女の非情さ、野蛮さからすると、膣に指を突っ込んできても不思議ではなかった。処女膜を傷つけられるのではないかと、恐怖を感じたのだ。 「嘘を言うんじゃないよ! ただ調べてるだけでしょう。適当なこと言ってると、本当に痛い思いをすることになるからね」 加納に怖ろしい恫喝をされ、千尋は、もうそれ以上、抗議することはできなくなった。 どのくらい、そうして耐えていただろう。ようやく、加納が、千尋の足もとを立った。 「お嬢さま。この子が、れっきとした処女であることを確認致しました」 「千尋ちゃん、ちゃんと処女だったかあ……。あっ、もちろん、わたしだってそうだよ。……でも、考えてみると、裸になって、初めて、マ○コの中を見せた相手が、わたしと加納さんだっていうのも、ちょっと可哀想な話かもしれないねえ」 亜希は、そのことを、千尋にわざと意識させるように言った。 「適性検査の一環ですから、仕方ありませんよ。お嬢さま、それより、この子の性器は、労働には問題なく合格なのですが、いかんせん不潔過ぎます。ですので、風呂および手洗いは、使用させないほうが、よろしいかと思います」 千尋は、唖然とさせられた。風呂も手洗いも、使わせてもらえないというのか。もっとも、より問題なのは、手洗いのほうである。したくなったら、外でしろとでもいうのか。 「うーん、そっかあ。そんなに汚いんだあ、千尋ちゃんのマ○コ。……そうだ、加納さん。千尋ちゃんの、おしりの穴のほうも調べてもらえる? トイレのほうは、おしりの汚れ具合で、判断することにしようと思うの」 とても信じられない話だった。この小娘は、どこまで性根が腐っているのか。どうしたら、そんな下劣な発想を思いつくのか。 「はい、了解しました。労働という観点からも、この子の肛門の検査は、必要であると思います。では、さっそく」 加納はそう言って、冷ややかな目つきで千尋を見下ろした。 今、千尋は、何のリアクションも取ることができずにいる。視線を落とし、浅い呼吸を繰り返しているだけである。 「ぼけっとしてるんじゃないよ! 今の話を聞いてただろう? 後ろを向くんだよ!」 加納に肩を押さえられ、千尋の体は、強引に半分ほど回される。 横向きになってしまったので、千尋は、やむなく自ら脚を動かし、背中を向けた。 ぼんやりとした夢うつつの状態だが、ある種の覚悟を持って立っている。 ほどなく、おしりの割れ目に、何本かの指が差し挟まれた。反射的に、肉体がそれを拒絶し、おしりの肉を引き締めていたが、加納の力で、一気に限界まで開かれた。あまりの勢いだったので、悲鳴を上げそうになったが、危ういところで、それを呑み込んだ。 「あらら……。こっちの穴もまた、ひどい臭いだね。お嬢さま、極めて健康的な肛門ですが、この臭いからすると、ばい菌が、だいぶ繁殖していると思われます。この子には、やはりトイレも使用させないほうがよいでしょうね。……ご覧になりますか?」 途方もない恥ずかしさと屈辱感で、千尋は、ぐらぐらと目眩を起こした。 信じていた女の子に裏切られて、服従を余儀なくされ、その子の下劣な好奇心から、肛門まで見られて臭いを嗅がれる。そんな女子高生など、間違いなく、この世でわたしだけだろう。惨めなんて言葉では片付けられない。 「うっわー。きったないしぃ、くっさそーうだしい……。千尋ちゃん、これはちょっと幻滅もんだよー」 亜希は、わざとらしい嘆くような口調で、千尋を侮辱した。 「おい。もう検査は終わりだ。お嬢さまのほうを向け」 加納が、おしりの割れ目から手を抜いて告げた。 亜希のほうに向き直った瞬間、千尋は、様々な感情の波に、どっと襲われた。 悲しみや屈辱感、そして羨望もあった。 権力や財力をバックに、お姫様然としてソファに腰掛け、自室にいる人間を意のままに操れる立場の亜希。かたや、絶対の服従を強いられて全裸になり、膣や肛門まで調べられるという有様の千尋。 ほんの数ヶ月前まで、千尋と亜希は、大企業の社長の令嬢同士、同等の関係であった。だというのに、今では二人の間に、血も涙もないような主従関係ができあがっているのだ。この、世界がひっくり返ったかのような現実を直視させられ、千尋は、半ばパニック状態にあった。 わたしが亜希の立場になりたかった……。いや、わたしは、今だって以前と変わらず、なんでも持っているはずなのに……。こんなの嘘よ、悪夢よ。 「千尋ちゃん……。あなたは、適性検査に合格したので、この家で、これから働いてもらうことになります。でも、ちょっと体が不潔だから、うちのお風呂やトイレは使わせてあげられない。納得してくれるよね?」 まがまがしい話を聞かされて、千尋は、惨憺たる現実に釘付けにされる。 「はい。……わかりました」 千尋は、絶望に沈んだ低い声で返事した。 「あっ! もしかして、千尋ちゃん、おしっことかは、どうすればいいんだろうって心配してる?」 千尋は、唇を引き結んだまま、小さく頷いた。 「そんなこと、心配しなくても大丈夫だよっ。加納さん、ちょっと……」 亜希は、加納の耳もとに、こそこそと囁きかける。何を頼まれたのか、加納は、部屋を出ていった。 五分ほどして、加納が部屋に戻ってきた。加納は、なにやら、水槽のような透明なガラスの容器を持っていた。そして、薄気味の悪い笑みを浮かべ、こちらに視線を送っている。 「その入れ物が、千尋ちゃんのトイレだよっ。おしっこやうんちは、そこにしてね」 狂ってる……。千尋は、目を剥いてガラスの容器を凝視した。 「ちゃんと、この便器の中にするんだぞ。外にこぼして、お嬢さまの部屋を汚すような真似は、絶対にするなよ」 「千尋ちゃん。したかったら、してもいいんだよ……。今は平気なの?」 亜希は小首を傾げ、心配そうな表情を作っている。 千尋は、無意識のうちに、頭を左右に振る動作を繰り返していた。 「大丈夫、……です」 尿意は、だいぶ感じていたが、あんな容器になど、どうしてできようか。しかし、いずれ我慢には限界がくる。 幼なじみの部屋が、千尋にとっては、先の見えない牢獄へと変貌していた。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.