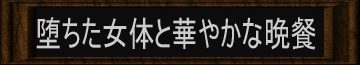
第六章
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
頭の中にモヤのようなものが入り込んできて、思考能力が落ちていった。しかし、正気を保っていられなくなるような恐怖だけは、意識の中心から膨れ上がってくる。 目の前の光景が、ぶれて霞んでいる。 千尋は、体を動かすことも、声を出すこともできなかった。 「お嬢さまから言われたことが、聞こえなかったのかなあ、千尋は。もう……、仕方ないわね。わたしが『アレ』を持ってくるから、すぐに出せる準備をしておきなさいね」 加納が、促すように千尋の背中を撫でた。 「ひっ……。え、えぇ……」 いきなり体に触れられて、千尋は、小さな悲鳴を上げていた。加納の言葉は、千尋の頭には、まったく届いていなかった。 時間の感覚もおぼつかない。 記憶を失って、気づいたら砂漠のど真ん中に立っていた人のように、千尋は、きょときょとと視線をさまよわせていた。 やがて、背後から加納の声が聞こえた。 「お嬢さま、申し訳ありません。この子ったら、ちょっと前に、大きいほうも出してしまったようで、臭いが、ものすごいんですよ……。もうすぐ食事ですし、朱美さまが、これをどう思われるかと心配なんですが……」 「え!?」 亜希が、目を丸くして驚きの声を発した。 朱美も、視線を真っ直ぐに加納のほうに向けている。 事の成り行きがうまく呑み込めず、千尋は立ち竦んでいた。だが、背後から漂ってくる禍々しい気配は、ひしひしと肌で感じている。 朱美は、魅入ったように目を向けていたが、その表情が、しだいに変化していった。頬が引きつり、唇がへの字に曲がる。 「えっ、やだ……。あの茶色っぽいのって……。もしかして……」 その時、亜希が物静かな声で告げた。 「加納さん。千尋ちゃんのトイレはそれしかないんだから、しょうがないですよ。テーブルの上に置いて下さい」 驚きを浮かべていた亜希の表情は一変し、その口もとは、白い歯を覗かせて不気味に緩んでいた。 それを聞いた朱美が、小さく呟く。 「え。待って、うっそお……」 「かしこまりました」 加納が、千尋の横を通り過ぎ、亜希と朱美の待つテーブルに歩いていく。 著しく思考能力の低下している千尋だったが、加納の持っているものに、目が釘付けになった。そして、それがテーブルの上に載せられた時には、目を剥いた。 向かい合わせに座っている、亜希と朱美に挟まれる位置に、千尋が用を足した、透明なガラスの容器が、熱帯魚の水槽よろしく鎮座しているのだ。当然、二人の少女の目は、容器の中のものに向けられている。 そこから放たれる臭気は、少し離れたところに立つ、千尋の鼻孔にも流れ込んでくる。千尋は、ショックのあまり、思わず口もとを手で覆っていた。 「ごめんね、朱美ちゃん。まさか千尋ちゃんが、うんちまでしちゃってるとは思わなかったのぉ」 亜希の顔の上半分は苦々しそうに歪んでいたが、下半分、その口もとには、うっすらと笑みが浮かんでいた。容器の中に、黄色い液体だけでなく、茶褐色の塊までもあったことは、亜希にとっては、愉快な誤算だったに違いない。 「ねえ、ちょっと息ができないよ、亜希ちゃん。どうにかして……」 朱美は、鼻を摘んで訴える。亜希とは違い、心の底から不快に感じている様子だった。 「うん、ごめん朱美ちゃん。少しの間だから我慢して」 亜希は、苦笑しながら友達を取りなしている。そうして、ゆっくりと千尋のほうに顔を巡らせた。 千尋は、亜希と目が合った瞬間、ぎりぎりと全身を締めつけられるような感覚を味わった。亜希の表情に表れた、剥き出しの軽蔑と嘲り。 そして、朱美も、顔をこちらに向ける。まるで、あんたのせいで、こんな臭いを嗅がされている、とでも言いたげな、怒りすら含んだ表情だった。 最後に加納が、千尋の反応を窺うように振り返った。 人間としての恥の極みの塊。恥の極みの臭い。それを初めて亜希に見られ、嗅がれる時を、千尋は怖れていた。しかし、やってきた現実は、予想以上に残酷だった。まさか、亜希の友達までいるところに晒されるとは。 苦しい……。自分だけ、酸素の無い部屋にいるかのように、千尋は喘いだ。どこ……。わたしの出口は、どこ……? 「千尋ちゃん。わたしたちも、食事の席に、こんなものをずっと置いておきたくないの。だから、お願い、早くやってくれるかな」 「あ……、はい……」 取りあえず返事はしたものの、千尋は、了解を伝えたわけではない。亜希に何を命じられているのか、理解できていなかったのだ。だから、意味もなく指をいじったりと、おろおろしているばかりだった すると、能面のような顔をした加納が、千尋に迫ってきた。千尋の背後に回ったかと思うと、突然、千尋のおしりの肉に、ぴしゃりと手を貼りつけた。 「ひっ!」 驚愕の悲鳴と共に、千尋は、背筋を反り返らせていた。 「ぼうっとしてちゃ駄目じゃない、千尋ぉ。早くこっちに来なさいよ……」 加納は、おしりに貼りつけた手で、千尋の体を前に押してくる。ものすごい力だった。 テーブルのほうへと、脚が、強制的に数歩送り出された。それでも加納は手を緩めない。おしりを押す、という加納の行為には、千尋に対する、表に出せない苛立ちが込められているのを、千尋は強く感じ取っていた。あからさまに怒りをぶつけてこないのは、客人である朱美の目を気にしているのだろう。 千尋は、テーブルクロスに手がつく位置にまで、前進させられた。両手でテーブルの端をつかむ。 目の前の透明な容器には、自分の体から排泄されたものながら、見るもおぞましい恥の極みの塊が、黄色い液体に浸っている。そこからは、恥の極みの臭いが濃密に漂っていた。 今、この瞬間も、亜希や朱美が、それぞれの目と鼻で、それを捉えていることを思うと、気が触れそうなほどの羞恥に襲われる。千尋の息遣いは、ひどく荒くなっていた。 千尋は、亜希に視線をやった。 「ねえ、わたし、どうすればいいの……」 千尋の無様な様子を眺め、含み笑いを浮かべていた亜希が、唖然とした顔になる。 「え? ねえ千尋ちゃん。さっき説明したでしょ。新鮮なおしっこを出してねって言ったじゃなあい。もう忘れたの?」 「え……。ああ、うん、うん」 自分でも意味不明な返答をしていた。そうだ、たしかに亜希は、そんな狂ったことを言っていた。それで、自分は拒否することなど許されないので、おしっこを出さないといけない。で、その場所というのが……。もう、何もかも訳がわからない。 すでに、千尋の体はテーブルにくっついている。しかし加納は、少しも手を休めずに千尋のおしりを押してくる。そのせいで腹部がこすれて痛い。 いや……。千尋は、そこで気づいた。加納は、前に押しているのではない。下から押し上げているのだ。 亜希が、中指でとんとんとテーブルの上を叩いた。 「千尋ちゃん、上がってよ早く。トイレは、ここにあるでしょう?」 亜希の顔に、みるみると悪意に満ちた笑みが浮かんでいく。昨夜、ベッドから身を乗り出し、千尋の乳房をつかんだ時に見せた、あの、悪魔のように怖ろしい笑みがオーバーラップする。 逆らうことはできない。だが、どうしてそんなことができようか。千尋は、泣きそうになっていた。すでに頬や唇はぴくぴくと震えていたが、必死になって涙を堪える。 なおも、加納は、テーブルに乗らない千尋に対し、腹立った手つきで、ぐいぐいとおしりを突き上げてくる。その凄い力に、千尋の両足が、何度か浮き上がった。だが、その度に千尋は、ほとんど反射的に、体を持ち上げられまいとして、テーブルをつかむ両手に力を込め、踏ん張っていた。 二人のせめぎ合いに、がたがたとテーブルが揺れている。 地獄……。この世の地獄だった。 その時、おしりの肉を押し上げる加納の手が離れた。 それに気づき、おや、という思いが脳裏をよぎった、次の瞬間。 千尋の股間を、衝撃と鈍痛が襲った。下から打ち付けるようにして、性器を鷲づかみにされたのだった。性器全体が強く圧迫され、デリケートな部分に指がめり込んでいる感触があった。 脳の神経の一部が、ぷつりと飛んだ感じがした。 「ひいああぁぁ……!」 宙を見上げながら、千尋は絶叫した。 それでも容赦なく、加納は、股間に掛けた手で、千尋の体全体を引き上げようとする。性器が、苛烈な圧迫と激しい摩擦を受け、千尋は、たまらなくなって自らテーブルによじのぼった。 この女はどこまで非道なんだ……。わたしが上がるのを拒んでいるからといって、女の子の聖域に手を掛けて、押し上げようとするなんて。 テーブルの上で、横座りの姿勢になった千尋は振り返り、加納に抗議の目を向けた。 「どうしたの、千尋。まったく、もたもたしちゃって。お嬢さまや朱美さまを、お待たせてしたら駄目でしょう」 加納は、素知らぬ顔で言った。その態度もまた、朱美の手前だからだろう。 だが、朱美は、加納の千尋に対する暴虐ぶり目の当たりにし、不穏なものを感じ取っている様子だった。ちらちらと横目で千尋を見ながら、亜希に向かって言う。 「亜希ちゃん。ねえ、もしかして、この人、ものすごい嫌がってる……?」 亜希の顔に、戸惑いの色が浮かぶ。 「ちがっ、ちがうって、朱美ちゃん。千尋ちゃんは嫌がってるんじゃなく、ちょっと緊張してるだけで……」 頭の回らない亜希に、加納が助け船を出した。 「朱美さま、ごめんなさい。見苦しいところを見せてしまって。お客様を愉しませるのは、この子の仕事なんですよ。自分でも、それをわかっているはずなんです。ただ今回は、朱美さまが、まだお若いので、ちょっと恥ずかしがってるだけだと思います。でも、恥じらいを見せるほうが、なんとなく、風情があると思いません? ですから、朱美さまには、何も気にせずに愉しんで頂ければ、と」 「はあ……」 朱美は、あふやな返事をし、千尋のことを見やる。絶対にこんなふうにだけは、なりたくない、という軽蔑の目つきをしている。亜希のようにサディスティックでもなく、かといって、千尋を庇う気など、さらさらない。要するに、朱美の反応は、普通の女の子のそれなのだ。しかし、そんな少女の軽蔑の視線を受けるのは、千尋にとって、露骨な嘲笑を浴びるのと同等か、むしろ、それ以上に耐え難いことだった。 千尋は、俯いたまま顔を上げることができなかった。 「どうしたの、千尋。座るためにテーブルに上がったんじゃないでしょう。ほら、次は、どうするんだっけ?」 加納が、千尋をせき立てる。口調は柔らかだが、言っている内容は、怒鳴り声を上げる時のものと、なんら変わりはない。 千尋は、そろそろと立ち上がった。 一歩脚を動かすと、もう、そこには、亜希と朱美の間に置かれた、ガラスの容器がある。信じられない思いでくらりと目眩がし、脚がふらついた。下唇をぎゅっと噛んで感情を押し殺し、股を開いていく。 亜希が頬を膨らませ、笑いを堪えているのがわかる。朱美は、ぽかんと口を開けている。世間には、人前で、こんなことまでする人間がいるのかと、半ば呆れているような表情である。そして、朱美の目は、徐々に形状や色などが露わになっていく、千尋の局部をも、しっかりと捉えていた。 千尋は、両脚で容器を挟む格好になった。斜めに突っ張った両脚のバランスが、緊張の震えのせいもあって、妙に頼りなく感じる。安定した体勢を求めるように腰を下げていく。 太ももの裏が容器の縁にぶつかる。とうとう、千尋は『便器』に跨った。両手のやり場がないので、ぎゅっと容器の縁をつかんだ。 すぐ下から昇ってくる臭気が、鼻を突く。今も、その臭いを亜希と朱美にも嗅がれているのだ。それを思うと、もはや、女として、いや人間としての尊厳など、保てるはずがない気持ちになる。 「千尋……。これに入れなさい」 加納が、ワイングラスを差し向けた。グラスを右手で受け取り、顔の前に持ってくる。 うそ……。いや、こんなことって……。 人間としての誇りをすべて捨てなくては、到底、この地獄からは抜けられないことを、千尋は思い知らされた。 「ええううぅ、うう……」 感情を司る脳の部分が痙攣したかのように、知らず知らずのうちに、千尋は奇妙な声を漏らしていた。 加納も、亜希の隣の席に座り、千尋の放尿を鑑賞する態勢に入る。 「あ、ねえねえ、朱美ちゃん。ちょっと、これ見て……」 亜希は、いきなり千尋の股へと手を伸ばしてきた。その指が、おしりの肉、それも極めて肛門に近い部分に触れた。 「いやっ」 弱々しい悲鳴と共に、千尋は、腰を少し浮かせていた。 何のつもりなの……。そう亜希に目で問いかける。すると、虫酸の走ることに、亜希は残念そうな顔をして、こちらを見つめ返してくる。 「こらこら、なんで逃げてるの、千尋。体勢を元に戻しなさい」 加納は、千尋の右脚のすねをつかんだ。ぎりぎりと力を入れてくる。怒鳴ったり叩いたりする代わりに、このような方法で、千尋を従わせようとしているのだ。 千尋は怖気をふるい、腰を落とした。 そこでもう一度、亜希が、股間に手を伸ばしてきた。同じように肛門のあたりに触れられたが、もはや逃れることはできなかった。 「朱美ちゃん、ちょっと、これ見て……」 亜希は臆面もなく、千尋が嫌がったために中断した、行為の続きを再開したのだった。すると、朱美までもが、千尋の膝に手を置き、それを支えに身を乗り出した。開脚した千尋の股間を、じっと注視している。 亜希は、下卑た薄笑いを浮かべながら、おしりの肉を、ぐいっと外側に引っ張った。 「ここ、ここ……。うんちしたあとに拭いてないから、おしりが茶色く汚れてるのぉ」 「うわあ、ホントだあ……。この人、こんなんで気持ち悪くないのかなあ?」 普通の感覚じゃ理解できない、とでも言いたそうに、朱美は呟いた。 千尋は、前方の一点に目を向けたまま、血の逆流するような汚辱に、ただただ耐えていた。 おしりから手を離し、亜希が言う。 「そろそろ出して、千尋ちゃん。ほら、ワイングラスをもっと下げないと、おしっこを入れられないでしょ」 右手に持っているグラスは、腹の高さにあった。 千尋は、浅く荒い息を吐きながら、グラスを性器の下へと動かしていった。手が激しく震え、取り落としてしまいそうになる。手の震えで安定しないせいもあり、小さなグラスの口に入れるのは、困難に感じられた。そもそも、至近距離で見られている状況で、尿など出せる気がしない。 「うわー。千尋ちゃんったら、ぶるぶる手が震えてるう。緊張してるのお?」 亜希が、追い打ちを掛けてくる。 明らかに正常ではない千尋の様子を見ていた朱美が、亜希に向かって言う。 「ねえー。この人、ホントに出せんのお?」 「やってくれるよお、千尋ちゃんは。だって、これが仕事なんだから」 亜希は、きっぱりと断言した。 「ふーん」 朱美は、半信半疑のように唇を突き出し、ぞんざいな手つきで、千尋の片脚を外側へと引いた。性器を見やすくするために、そうしたのだ。 朱美は、しみじみとした口調で言った。 「なーんか、変なきぶーん。知らない女の子のアソコを、生で見てるのって……。でもやっぱり、他人のって汚らしいねえ」 朱美の言葉は、千尋を傷つけてやろうという、悪意のもとに吐かれているわけではないと、千尋は感じている。ただ単に、千尋のことを、人権に配慮する必要のない下等な女と見なし、歯に衣着せぬ本音を口にしているだけなのだろう。 しかし、逆にその、ある意味客観的な言葉は、千尋の胸に突き刺さった。そして、その胸の痛みは、女としての根源的な悲しみに変わっていった。 人前で裸になり、性器を晒しているという現実。普通に考えれば、それだけでも、有り得べからざる出来事なのだ。ましてや、尿を出すところを、人に見せるなど……。完全に、狂っている。 千尋は、深く息を吸い込んでから、亜希を睨んだ。 「でません。とても出せません……」 「えっ……?」 忌々しいことに、亜希は、わざとらしく悲しげな眼差しを作っていた。 「そんなあ、千尋ちゃん……。みんな待ってるのに、それはないよお……」 ふざけた物言いに、はらわたが煮えくり返る。いっそ、この小娘の顔にワイングラスを叩きつけ、罵声を浴びせてやりたい。 沈黙を通そうと決意した時、千尋は、足の甲に痛みを感じた。そっと見やると、そこに、加納が爪を立てていた。 加納は、じりじりと皮膚を引っ掻きだした。皮膚が削れていく。血が滲んできそうだった。 痛い……。痛い。本格的に痛くなってきた。 この女は、いったい……。千尋は、加納に目を向ける。そこには、千尋の態度を責める、凍てつくような双眸があった。 「出せないんじゃしょうがないわねえ……。でも、待ってて下さった朱美さまに申し訳ないから、ちゃんと謝罪をしなさい。廊下で言っておいたとおり、しっかりとした誠意を見せてね。そうしよっか、千尋……?」 誠意……。 ずきり、と足の甲に痛みが走る。見ると、うっすらと血が滲み始めていた。血だ……。 千尋は、傷つけられた足を呆然と見ていた。だが、次の瞬間には、急激に体温が低下していくような感覚があり、ぷつぷつと肌が粟立った。 「いえ……。だせます、わたし、やります……!」 誓いの言葉が、口を衝いて出ていた。 加納は、そこで指を止めた。 「そうよね、千尋。これは、おまえの仕事なんだから、できないなんて言えないはずよ。さ、責任を持ってやりなさい」 千尋は息を呑み、股の下にあるグラスに目を移した。手が震えているため、グラスは常に揺れている。 千尋は覚悟を決め、膀胱に力を込めた。けれども、一向に尿は出てこない。何か、体の奥底にある、取り除ききれない羞恥心が、放尿を阻止しているように感じられる。 そんな千尋に焦れたのか、突然、亜希が、臍の下に手を宛がってきた。 「手伝ってあげるよ、千尋ちゃん。みんな待ってるんだからあ……」 苛立ちのこもった声で言いながら、千尋の下腹部をポンプのように押し、膀胱を刺激する。 「うっ……、ううっ……」 恥辱の喘ぎが、口から漏れる。 その時、反対側から、棘のある声が千尋にぶつけられた。 「ねーえ、いつまで、このうんちの臭い嗅がせるつもりなの!? 早く出してさあ、この汚い入れ物、片付けてほしいんだけど。あんたさあ、本当に、おしっこできんの!?」 その口調に、千尋は竦み上がった。千尋に対し、朱美が直接文句を言ってきたこと自体、これが初めてなのだ。 朱美のけばけばしい両眼を見ながら、千尋は答える。 「はい……。やります、すみません」 年下の生意気そうな令嬢に怯えさせられる情けなさ。またぞろ、以前のわたしだったら、という思いが脳裏をよぎり、余計に悲しくなる。 朱美は、千尋の顔に向けていた視線を、下のほう、性器へと移した。汚らしい、などと言ったくせに、尿が出る瞬間は、見逃さないようにしようという様子である。 「ほら、千尋!」 加納が、鋭い声を上げた。千尋のせいで、朱美の機嫌が悪くなったことに対し、相当怒っているらしいことがわかる。 もはや、やるしかなかった。 「あっはあぁぁ」 己の感情を断ち切るように、千尋は、魂を声に変えて吐き出した。 下腹部が、じんわりと温かくなる。 「あ! ようやく出てきたあ!」 亜希が嬌声を上げ、千尋の下腹部から手をどけた。 「でも、この人、グラスのほう見てないから、全然入ってないし……。っていうか、この人、なんか、目がいっちゃってる……」 朱美が、苦笑して言った。 千尋は、焦点の合わない目を前方に向けた状態で、膀胱から絞り出すように放尿していた。 「おーい、千尋ちゃん、グラスに入れなきゃ、駄目だよーう」 亜希に肩を叩かれ、千尋は視線を落とした。グラスの中は空のままで、それを持っている腕が、びしょびしょになっている。 千尋は、荒い息を吐きながら、がたがたと震える手を動かし、グラスに尿を溜めることに意識を傾けた。それでも、尿を出し尽くした時点で、グラスの半分も満たされていなかった。 「もう出なぁい?」 亜希が訊いてくる。 千尋はこくりと頷いた。無我夢中でやったことだった。後ろの穴からも、便が出かかっていた。 亜希が席を立ち、タオルを取ってきた。 「ワイングラスをちょうだい。そっとね……」 もはや、千尋は唯々諾々と従い、大事なものを捧げるように尿の入ったグラスを差し出した。 亜希は、それを直に触らないようにタオルでくるみ、料理や食器類の載った大きなテーブルのほうに歩いていった。 精神的にも肉体的にも、ひどく疲れていた。何も考えられないし、体は、脱力したように動かない。長距離を走り終えた直後のような、自分の荒い息遣いを、千尋は、ただ聞いていた。 加納が、別のタオルを千尋に突きだした。 「千尋、これで拭きなさい……。ぼけっとしてるんじゃないよ。朱美さまの前に、ひどい臭いのする、おまえの便器を、いつまでも置いておいていいわけがないでしょう?」 千尋は、タオルを受け取ると、小便でびしょびしょになった右腕と、性器を拭った。 加納は、そのタオルを取って容器に落とした。タオルは、数回分の小便に浸った。加納が、容器を後ろに引いたので、千尋は、慌てて立ち上がる。 「申し訳ございませんでした、朱美さま。お食事の前だというのに、こんな汚いものを、目の前に出してしまって……。ひどい臭いですし、ご気分など、悪くなってはおりませんか?」 「あっ……、けっこう参りましたけど、気分のほうは、平気です」 朱美は、曖昧に頷いた。加納は、軽く頭を下げ、ガラスの容器を両手に持って、リビングの外に出て行った。 テーブルの上で突っ立ったまま、どうすることもできない千尋は、ぼんやりと大きなテーブルのほうを見ていた。 豪勢な料理の脇で、亜希が、なにやらタオルにくるんだグラスの中の液体、千尋の尿を、そばに置いた新たな三つのワイングラスに注いでいる。それで乾杯をするとか、先程言っていた。 これほどまでに悪趣味な行為が、許されてよいのだろうか、と千尋は思う。いつの日か、亜希が、何らかの形で報いを受ける時は、やって来るだろうか。そんな時は、きっと永久に来るまい。この小娘は、菅野家という強大なバリアによって、どこまでも手厚く保護されているからだ。 誰に何をしようとも、人生が危機に晒されることもなく、人の何倍も幸福な将来が約束されている。理不尽だ、と今更ながら千尋は感じる。 加納が、戻ってきて言った。 「千尋。さっき、お嬢さまから聞いたでしょ。今夜の女体盛りに、おまえの体を使って頂けるんだよ。こんなに光栄なことはないはずよ。さあ、そろそろ始めるから、そこに仰向けになりなさい」 「……はい」 千尋は、消え入るような声で返事をし、その場に膝をついた。ゆっくりと体を反転し、仰向けに横たわる。わざわざ、小さなテーブルを用意したのは、千尋の体へ、箸やフォークを伸ばしやすいからだったのだ。 「料理を載せますので、この子の体の表面を、ざっと消毒させて頂きますね」 加納は、朱美にそう言うと、千尋には何の断りもなく、消毒液を染み込ませたタオルで、体を拭き始めた。可憐な十代の素肌を、ぞんざいな手つきで。乳房や性器など、女の恥じらいの部分も、無遠慮にごしごしとこすられる。 それを終えると、加納は言った。 「お嬢さまとわたしで支度を致しますので、朱美さまは、寛いでお待ち下さい。よろしければ、食べ物を載せる器となる、この子の体の肌触りなんかを、お確かめになっていては如何でしょう?」 加納は、人当たりの良さそうな笑顔を朱美に向ける。以前ならば、千尋にも向けられていた顔だ。 「あ……、あ、はい」 朱美は、曖昧に頭を下げた。 女として、いや人間としての誇りが失われるというのは、このような境地に至ることなのかもしれない。今、年下の少女が、全裸の自分のことを、文字通り見下している。だが、恥ずかしさや屈辱感といったものを、それほど強く感じないのだ。強制的に放尿させられた瞬間、自分の中の、ある種の限界を超えてしまい、心のヒューズが飛んでしまったのかもしれない。 「ねえ」 朱美に呼ばれた。無機質な声音だった。 千尋は、黒目だけ動かして、そちらを見た。 朱美は、すーっと顔を寄せてきて、声のトーンを落として言い始めた。 「あんたさあ、本当は、つらくってしょうがないんでしょ。こんなこと、本当はしたくないんでしょ」 亜希と加納には聞こえないように意識した話し方だ。 アイメイクで黒々と縁取られた朱美の目を見つめたまま、千尋は、間を置かずに答えた。 「いいえ、そんなことはありません。仕事ですから」 「嘘を言わないでよ。わたしだって馬鹿じゃないんだから気づくよ。加納さんに乱暴されて、亜希ちゃんには嫌味言われてさ。それであんたの様子見てれば、誰でもわかるよ」 千尋は、天井を見上げた。シャンデリアの輝きが、目に厳しい。 たしかに、朱美の言うとおりだ。溜め息を吐き、千尋は口を開いた。 「つらいです。理由があって、やらされてます」 朱美は、鼻で笑った。 「あんたみたいな不幸な人も、世の中にはいるんだねえ。それにしても、亜希ちゃんも残酷だねー。ここまでやらせるなんてさ……」 千尋は黙っていた。これといった感情も湧かなかった。 そして朱美は、素っ気なく付け加えた。 「でも、勘違いしないでほしいんだけど、わたしも、あんたに気を遣ったりはしないから」 承知している、というふうに千尋は顎を引いた。 すると、ふいに、朱美の人差し指に、ほっぺたを突かれた。怪訝に感じた千尋は、指先で押されている顔を抵抗するように動かして、朱美に目を向けた。 朱美の口もとには、薄ら笑いが浮かんでいた。心の内に、胸騒ぎの雲が漂い始める。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.