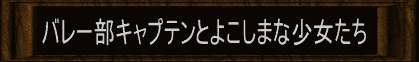
第十九章〜しんしんと
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
ひとりの時。 たとえば、部屋のカーペットに寝転び、ぼーっと天井を眺めながら……。あるいは、学校からの帰り道、他校の女子高生たちとすれ違った後に、ふと……。学校内でも、周りに、誰も生徒がいなければ……。 吉永香織は、しばしば、こう声に出していた。 「ミナミ・リョウコ……」 もはや、その名前の響きからして、ダサい気がする。いかにも、不幸を背負って生きている女、という感じではないか。哀れな。 このところ、どうしても錯覚しがちだった。あの、南涼子というクラスメイトは、もともと、あらゆる面において、レベルの低い人間だったのではないか、と。 まず、頭が悪いように思えてならない。 涼子は、香織たちに脅迫されると、それをはね返すことができずに、結局のところ完全服従する。つまり、恥にまみれた姿をさらす。毎回、毎回、その同じことを繰り返しているのだ。そうして回を重ねるごとに、どんどん泥沼の深みへと沈み込んでいく。香織にとっては、笑いの止まらない話である。しかし一方で、香織は、涼子のそんな間抜けぶりに、少々、失望感を覚えてもいた。南涼子って、この程度の女だったのか……、という思い。だから時には、涼子に向かって、本心から言ってやりたくなる。馬鹿だね。あたしたちのオモチャにならないように、もうちょっと、知恵を働かせたらどうなの? しかし、涼子は、決して頭の悪い人間ではないのだ。というより明らかに、優秀な頭脳の持ち主である。学年トップクラスに入るに違いない、高い学力。それに、勉強だけではない。クラス随一ともいえるコミュニケーション能力や、バレー部のキャプテンを務めるだけのリーダー性といったものも備えている。つまり、本当の意味で、知的能力に優れた生徒だということ。 では、なぜ、その聡明なはずの涼子が、香織などに翻弄され続けているのか。 答えは簡単だった。 香織は、自分のオリから涼子を逃がさないように、幾重にも幾重にも柵(策)を張り巡らせている。そして、そのオリをさらに堅牢なものとするべく、毎夜、何時間も、思索にふけるような生活を送っている。そんな自分の異常性には、自嘲せざるを得ない。だが、芸術的なアイディアというのは、えてして狂気の世界に入り込んだ者にこそもたらされるものである。要するに、いくら涼子の頭脳が優秀だろうと、『常識的に』物事を考えている限り、異次元から降り注ぐ知略の前には、ただただ、愕然と立ち尽くすしかないのだ。 そう。だから、涼子が、実は馬鹿な女だった、などという興ざめな結論に至ることはない。そのように考え、香織は、涼子に対する失望感を打ち消すのだった。 しかし、涼子には、ほかにも残念な点があるのだ。 これまでに幾度となく、涼子が、感情を爆発させるところを、目の当たりにしてきた。 目尻をつり上げた憤怒の形相で、獣じみた怒号を浴びせてきたり。 「ふざけるのもぉぉぉっ、いい加減にしてよおぉぉぉっ!」 「あんたの頭の中はぁぁぁっ、どうなってんのよぉぉぉっ!」 あるいは、頭を振り乱して、ヒステリックに絶叫したりと。 「もおぉぉぉぉうっ! いやぁぁぁぁぁっ!」 「わたしぃっ、バレー部の子たちの前で、恥かくくらいだったらぁっ、家に、帰るっ!」 理性のかけらも感じられないような、見苦しい言動の数々である。涼子のそういった姿ばかり、脳裏に浮かべていると、どうも思ってしまうのだ。ひょっとすると、涼子は、もとから少々、情緒不安定なところのある人間だったのではないか……。もし、そうだとしたら、そんな女のことを、憧憬の眼差しで見ていた自分は、いったいなんだったのか……。 けれども、どうだろう。 三年に進級してから、この数ヶ月の間、クラスメイトである涼子のことを、様々な角度から事細かに観察してきた。そして自分は、南涼子という人間から、何を、もっとも強く感じていたか……。それは、心の健全性……。真っ直ぐで、伸びやかで、ゆとりがあって、常に晴れ晴れとしたオーラを発散させているような生徒だった。あの涼子に限って、病的な一面を持ち合わせているなどということは、絶対にあり得ない。そのことには、自信が持てる。 では、なぜ、その健全なる精神の象徴のような涼子が、香織たちの前では、見るに堪えないほど非理性的な言動を、たびたび繰り返しているのか。 これも、答えは簡単かもしれない。 香織の、涼子に対する基本方針は、生かさず壊さず、である。とにかく、涼子の苦しむ姿が見たい。とはいえ、涼子というオモチャが、完全に壊れてしまったら、それ以上、遊びは続けられない。そのため、度を超した加虐行為は、自制する必要がある。当初、自分には、そのコントロールが可能だと考えていた。しかし、実際には、それが、なかなか難しいことに気づかされた。もっともっと、涼子に大きな苦痛を与えたい。その欲望ばかりが先走り、涼子への責めは、無制限にエスカレートしている。それに対して、涼子が、激烈な拒絶反応を示すのは、香織たちによる破壊行為から、自分を守りたいという、いわば人間としての本能である。生身の人間ならば、当たり前のことなのだ。要するに、涼子の言動を見苦しいと感じる時は、香織たちが、暴走状態にあるということ。その点は、念頭に置いておくべきだろう。 そう。だから、涼子は、情緒不安定だとか、精神面に問題があるとか、そういう捉え方をするのは、明らかに間違っている。とんでもない思い違いである。 香織は、ひとり納得した。 ほかにも、涼子のことを、低レベルな人間だと判断したくなる理由は、いくつも挙げられるのだが、それらもきっと、自分の思い違いなのだろう。 たとえば……。涼子は、高校生活における苦悩、つまり香織たちのことだが、それを、バレー部の仲間たちにも、親しいクラスメイトにも、打ち明けられないでいる。プライドなのか。それとも、誰かに相談するのは、リスクが大きすぎると考えているのか。その両方かもしれない。だが、ちょっと勘ぐってしまう。いくら性格が明るく、社交性が高くても、それらに比例して、心から信頼できる友達も多いとは限らないのだ。もしかして、案外、涼子には、本当の友達など、一人もいないのではないか……? 香織たちから散々、辱めを受けているにもかかわらず、誰にも助けを求められない、また、誰からも助けてもらえない、南涼子。なんだか、哀愁を誘うほど、涼子が、孤独で惨めな存在に思えたりする。 あるいはまた、休み時間や昼食時のこと。香織は、友人たちとお喋りをしている最中でも、涼子の姿が視界に入っている限り、その動向を目で追い続けている。時たま、そんな香織のほうに、涼子も、ふと、視線を向けてくることがある。まるで、香織の顔色を覗うかのように。目が合ったとたん、涼子は、視線をそっぽに泳がせるのだ。そして、何事も感じていないふうを装う。どうやら、こちらをにらみ返す度胸もないらしい。そういう時、香織は、涼子の横顔を眺めながら、心の内で毒づくのだった。あんたってさ……、本当は、ものすごい小心者なんじゃないの……? 弱虫で弱者の、南涼子。 ……そういった涼子のネガティブなイメージは、自分の馬鹿げた思い違い、錯覚に過ぎないのだ。どう考えても、涼子が、孤独な存在とか、弱者であるとか、そんな話は、現実からかけ離れているではないか。 うん、うん。そうだ。 香織は、ひとりうなずいていた。 だけれど……。まだ、拭いきれない思いが、胸の中に残っている。 今。 香織は、後輩の石野さゆりと共に、体育倉庫を出たところだった。これから向かう先は、バレー部の練習場である体育館だ。 やや歩行速度を落とし、さり気なく後輩を先に歩かせるようにする。前を行く後輩が、こちらに注意を向けないことを祈りながら、右の手のひらを、そっと自分の鼻に当てた。 先ほど、体育倉庫の地下での出来事である。 涼子のボディチェック。腋毛の処理は禁止、という言いつけを、ちゃんと守っているかどうか、涼子に両腕を上げさせて、腋の下を検分した。結果は、文句なし。むしろ、毛深い子は、数日間、手入れを行わないだけで、こうも汚らしい状態になるのかと、ある意味、舌を巻くほどだった。続いて自分の取った行動は、少し悪乗りが過ぎたな、と自覚している。香織は、涼子の腋の下に、容赦なく、べたりと右手を押し当てた。揉み込むように皮膚を撫でると、伸び始めの硬い毛が、手のひらに、寒気を催すような感触を伝えてきた。手のひら全体に、じっとりとした腋汗を充分に付着させてから、その手で、自分の鼻を覆った。息を吸い込むと、脳を覚醒させられるような刺激臭が、鼻腔に流れ込んできた。あの時、涼子は、もう見るのも嫌だというふうに、その香織の行為から目を背けていた。そんな涼子に、さらなる屈辱を与える方法を、香織は思いついた。臭気のこびり付いた自分の手のひらを、涼子の鼻先に当てた。舐めるように命じた。あんたの腋汗の臭いを、舐めて落として、と。それを聞いた涼子のなかで、プライドとの激しい戦いが起こっているのが、ひしひしと感じ取れた。当然だろう。しかし結局、涼子は、例のごとく服従したのだ。だらしない涼子の顔つき。その唇から出ている、淡いピンク色の舌。指の間まで這う舌の、ぬめぬめとした生温かい感触。あの、肌のあわ立つような背徳感を、きっと自分は、生涯忘れないだろうと思う。 あれから、すでに二十分ほど経っている。それでもまだ、手のひらの匂いを確かめると、涼子の唾液の臭気が、そこはかとなく残っているような気がしてならないのだった。 くっせーな。侮蔑を込め、香織は、内心でつぶやいた。いったい、涼子に対して、幾度、そう思ったことだろう。唾液で上塗りされる前に、手のひらにこびり付いていた涼子の体液、あの腋汗の臭いも、思い出すだけで頭痛がするくらい強烈だった。だいいち、涼子は、部活の練習中に呼び出したりすると、目の前に立った瞬間から、ぷんぷんと汗臭さが伝わってくる有様なのだ。着ているTシャツが、どれだけ大量の汗を吸っているのかと、まったく、苦笑してしまう。 鼻を摘まみたくなるような臭いの記憶は、同時に、涼子の体の、視覚的に汚らしい部分を想起させる。手のひら大に密生した腋毛。下のほうに視点を移動すると、陰毛も同じく、海藻のごとく多量にはびこっている。さらに、なんといっても、あの最悪に汚い穴である。おびただしい縮れ毛の奥に覗く肛門は、便の付着が視認できそうなくらい、不潔極まりないものに見えた。 そういう涼子に関する数々の知覚情報が、頭の中に集積している。そんなわけで、今では、南涼子というと、どうしても、不潔で、臭い、ブタのような生き物、といったイメージが付きまとってくる。……これは頂けない。幻滅もいいところではないか。にわかに、涼子のことが腹立たしくなってきた。次に顔を合わせたら、このブタが、と罵倒してやろうかとも思う。 しかし、とまた、自分に反論する。 こればっかりは、香織たちが悪いのだ。涼子は、いつだって抵抗していた。女としての矜持にかけて、自分の体の恥ずべき部分を、必死に覆い隠していた。香織たちが、それを、無理やり暴き立てたのだ。腋の下に手を押し当てたり、パンツを引きずり下ろしたり。そうした行為の結果、その被害者たる涼子に、怒りを向けるというのは、我ながら筋違いだと感じる。 そもそも、思い返してみればいい。香織にとって、涼子が、まだ、雲の上の存在に見えていた頃。涼子に対して、女を捨てているような印象を持ったことが、一度でもあっただろうか。女子校という環境下、男子の目を意識しないため、生徒たちの言動や素行に含まれる恥じらいは、霧のごとく希薄化している。汚い言葉が飛び交うのは、日常茶飯事だし、下ネタで大いに盛り上がる声が、教室中に響くような事態も、珍しくない。だが、涼子が、その発信元となっていたケースは、いくら記憶を探っても思い起こせなかった。むしろ、涼子の場合、そういう下品な空気を、どことなく避けながら、また受け流しながら、周囲とコミュニケーションを取っていたようにも思うのだ。クラス全体を見ると、はしたない、汚らしい、と感じる場面には事欠かない。体育の授業で着替える時になると、上は下着の格好で歩き回る子の姿も、目に入ってくる。ジャージや靴下など、見るからに汚れた衣類が、なぜか床に放置されていることもある。しかし、そうした出来事と、涼子の性格との間には、まるで水と油のような線引きがあることを、香織はよく知っている。 バレー部のキャプテンという肩書き。また、それにふさわしい堂々とした体格。いかにも部活少女らしいショートヘア。それらが相まって、涼子からは、たしかに野性味みたいなものを感じさせられる。しかし、普段の涼子の、クラスメイトと接する時の立ち振る舞いを観察していると、そんなワイルドな印象は、肩透かしを喰うように薄れていくのだ。友人たちに『バイバイ』をする、その声音は、アルトボイスながら実に柔和で、無邪気に手を振るジェスチャーは、見ていて微笑ましい気持ちにさせられた。意外と照れ屋の一面もあるのか、交友関係のない子に話しかけている時には、表情や一つ一つの動作が、どうにもぎこちなかったりする。思いがけない事態に困惑すると、気後れをごまかすかのように、ショートの髪を両耳にかける仕草をするのは、涼子のくせだ。世の中で起きた猟奇的な事件の内容を、友人から聞かされると、大げさなくらい怯え、艶っぽく肩を抱きながら、悲鳴じみた声を発していたこともあった。何か、重大なへまをしてしまったらしく、バレー部の仲間から、慰めのように頭を撫でられていた涼子の、あの、赤裸々なはにかみ顔……。 そう。日頃、香織の見聞きしてきた涼子の言動集からは、むしろ、乙女的ともいえる気品ばかりが伝わってくるのだ。総合的に見て、涼子は、クラスの中で間違いなく上品な部類に入る生徒である。あろうことか、そんな生徒のことを、まるで家畜みたいな生き物として捉えてしまう自分の心理は、まさに錯覚としか言い様がない。それも、非常に愚かな錯覚だ。 もういい加減、自分が苦心に苦心を重ねて捕らえた獲物を、いたずらに過小評価するような思考は、ストップしよう。 今一度、初心に立ち返ってみればいい。 彼女に夢中になり始めたばかりの、あの頃の気持ちに。 何がなんでも、彼女と仲良くなりたい。心の底から、そう願っていた。けれども、気の弱い自分は、彼女に声をかけることさえできなかった。そのやるせない思いゆえだろう、何度も、彼女の登場する夢を見た。夢の中で、彼女とお喋りしている間は、とても幸せな気分だった。途中で、薄々、これは夢だと気づき始めると、目が覚めないよう、精一杯、意識のコントロールを試みた。夢ならば、いっそ、思いっ切り彼女に甘えてみよう。そんなふうに欲を出したとたん、たいてい、現実世界の、布団の中に帰ってきてしまう。 夢の中ですら、彼女をひとり占めすることは叶わない。それほどまでに遠い遠い、憧れの人……。 現在、自分の作り上げたオリの中に入っているのは、その女なのだ。自分でも信じられないくらいだが、それは、紛れもない事実である。そして、当然のことながら、オリの主である自分は、その彼女の生殺与奪の権を握っている。彼女の人生を一刀両断に断ち切るも、じわじわと時間をかけて責め苦を与えるも、はたまた神のような慈悲でオリから解放してやるも、すべては自分の意思ひとつである。 普通に考えて、これは、とてもすごい状況だろう……。背筋を伝うようにして、得も言われぬ感情が込み上げてくる。ぴょんぴょんと、飛び跳ねて歩きたい気分だ。この充足感、多幸感を、一時も忘れることなく常に噛み締めながら、自分は今を生きるべきなのだ。 日の陰り始めた風景のなか、体育館の窓からは、室内の煌々とした明るさがうかがえる。ボールが床を叩く音も、バレー部やバスケット部と思われる勇ましいかけ声も、通常どおり聞こえてくる。そんな日常的空間に紛れ込んだ非日常性に、香織は想像を巡らす。 香織が願うのは、バレー部のマネージャーである竹内明日香が、お目付役としての役目を果たしていることだ。そうすれば、あの、遠い憧れの存在だった女は、今頃、全身から火を噴くような辱めに遭っているはずだった。 好奇の視線を一身に集めるような変態的な格好となり、それでいて、部活の練習着として着用するのに、ある程度の合理性を持つアイテム。香織たちは、そんなものを、ネット上で探したのだった。はなっから、スポーツ用品として販売されている商品など、眼中になかった。いかがわしいコスプレの通販サイトを巡っていて、香織は、あるサンプル写真に目を引きつけられた。二十歳前後と見られるモデルが、上は体操着のシャツ、下には紺色のビキニみたいなものを着けた格好で、嬉し恥ずかしそうな表情を浮かべて立っていた。それが、前近代的な体操着のブルマという衣類であることに気づくまでに、しばらくの時間を要した。なにしろ、その衣類は、肌を覆う面積が削られ過ぎていて、もはや、運動着としての体裁すら保っていないような代物だったからだ。どう見ても、その下に普通のパンツをはけるような余地はない。写真の中のモデルは、明らかに、それをじかに着用していた。見れば見るほど、生理的嫌悪感の湧いてくるような写真だった。そこで香織は、バレー部の練習着、白いTシャツに黒のスパッツ姿の涼子を、頭の中に思い描いた。そうして、モデルの下半身と同じ条件にするべく、涼子の体から、スパッツもパンツもはぎ取ってしまう。初めて目にした時は、衝撃を受けたほどの、発毛範囲の広い下腹部が露わになる。その部分に、モデルの着用している極小のブルマを重ね合わせると……。愉快な光景が浮かんだ。この商品を取り寄せようと、香織は決めた。明日香もさゆりも、同意した。サイズは、あえてMを選んだ。涼子のあの、日本人離れした大きなヒップを思い起こすと、L以上が妥当なのは明白だったが、それでは面白味に欠ける。かといって、Sだと、はち切れる可能性が高かった。生地が破れてしまっては、さすがに、それを着けて練習に行け、とは言えない。涼子を辱める享楽のために購入する品であるが、香織たちは、身銭を切るつもりなど毛頭なかった。もちろん、その費用は、涼子のバッグから盗んだ、バレー部の合宿費から支払ったのだ。 先ほど、体育倉庫の地下で、その『プレゼント』が涼子に手渡された。香織たちの『好意』なのだから、涼子のほうは、それをありがたく受け取らなくてはならないのだ。それに着替え終えた涼子を前にして、香織は、実のところ小さなためらいを感じていた。ブルマをじかに着用した涼子の下腹部が、あそこまで悲惨なことになるとは、香織にとっても想定外だったからだ。涼子の陰毛の量には、毎度、驚かされるが、それ以上に、ブルマのフロントの部分の、いかにも寒々しい切れ上がりに、改めて唖然とさせられた。正面から見て、下腹部を覆う紺色の逆三角形の面積より、陰毛の黒い領域のほうが、あからさまに広いという状態だった。何も知らない生徒がそれを目撃したら、まず自分の目を疑うことから始めるだろうと、香織は想像した。それと案の定、Mサイズのブルマは、涼子の腰回りには、痛々しいくらい窮屈に見えた。肌と同化したように張りついた紺色の布地の表面には、恥丘のこんもりとした盛り上がりや、その下の、割れ目を挟む肉の形状さえもが、鮮やかなまでに浮かび上がっていた。その下腹部は、下手をすると、見る者にグロテスクな印象すら与えかねないほど、不潔感に満ちた有様を呈していたのだった。誤算……。香織は内心、涼子に対して、少しばかり申し訳なく思っていた。ごめん、南さん。まさか、ここまでひどいことになるとは、予想してなかったんだよね。でも……、せっかく買ってあげたんだから、その格好で練習に行ってよ。っていうか、絶対に行かせるからね。涼子は、泣き叫ばんばかりに激しく拒絶した。まともに知性を有する者として、当然の反応だったといえる。しかし、こちらは、涼子を好きに動かすことのできる『切り札』を握っているのだ。涼子の致命的な弱点に炸裂する爆弾の存在。その話を聞かされた涼子は、両手を膝につき、苦悶の声を漏らした。もはや、予定調和的ともいえる涼子の屈服である。地上への階段に向かう涼子の顔は、絶望の土気色に染まりきり、生気が消え失せていて、二十才以上も老け込んで見えた。あの焦点の合わない瞳の先には、どんなものが映っていたのだろう。これから自分自身を焼く、地獄の炎の赤々とした燃えさかりか。 体育館の目の前まで来た時だった。 猛獣か何かが、断末魔の咆哮を上げたかのような音が、館内からとどろいてきたのだ。 「サァッーブウウゥゥゥッ! ミナァーミリョウコニッ、コイオイウオォォォォォォー!」 突然のことに、ぎょっとした。それまで絶え間なく聞こえていたかけ声の数々とは、けた違いの大音声だった。 前を歩いていた後輩も、驚きに足を止めている。 少女の声帯から発せられた音とは、とても思えなかった。が……、間違いない。南涼子の絶叫以外に、何が考えられるというのだろう。 確かなことがある。現在、バレー部の練習場において、涼子は、すでに狂気に近い精神状態に追い込まれている。それは、すなわち……、筋書きどおりに事が運んでいるということ。さすがは明日香だと、改めて感心する。今頃、現場では、さぞかし悪魔的に立ち回っているに違いない。とはいえ、今の涼子の声は、いくらなんでも破滅的すぎるとも思う。明日香に『声出し』を強要されてのことだろうか。だとしたら、少々やりすぎのような気がしないでもないが……。 さゆりが、こちらを向いて、ひひっと笑う。 「なんか……、南せんぱい、もうだいぶ、イッちゃってません?」 「もしかしたら、なかで、大惨事になってたりして……」 香織たちは、足早に体育館の玄関を入った。革靴を脱ぎ、持ってきた上履きに履き替える。通路を進み、突き当たりの階段を上がっていく。香織たちの観覧席は、二階のギャラリーにすると、あらかじめ決めておいたのだ。 どきどきと、胸の鼓動が高まる。涼子の恥辱の舞台を、一刻も早く、この目で確かめなくてはと、期待に気持ちがはやっている。だが反面、それを実際に目にするのが怖いような、そんな境地でもあった。思えば、涼子の下腹部は、決して人の目に触れさせてはならないような有様だったこと。それに、たった今、聞こえてきた、どう考えても尋常ではない涼子の絶叫。ひょっとすると、バレー部の練習場では、すでに、生徒間では収拾のつかない大問題にまで、事態が発展しているのではないか、という懸念も、頭の片隅に浮かんでいたのだ。 香織たちは、二階のギャラリーに到着した。 バレー部の練習場を見渡すのに適した位置に、移動する。と、そこには、制服姿の後輩が、五人、固まって立っていた。おそらく、と見当がつく。十中八九、憧れのバレー部キャプテン、南涼子を目当てに集まっている後輩たちだ。連日のことだから、すぐにわかる。 その後輩グループの横で、香織とさゆりは、舞台を見物することにした。 現在、バレー部では、その練習スペースの大半を占めるバレーコートを使って、ゲームが行われていた。三年生対二年生の対戦なのだと、明日香から聞いている。香織たちの位置からだと、そのコートを縦に見下ろす形となる。コートの左手の壁に、ゲームに出ない部員たちが、ずらりと並んでいる。ゲームは、サーブからのプレー再開を待っているところだった。こちらから見て、バレーネットの手前側、つまり背中を向けて立っている六人が、三年生の選手だ。顔を確認せずとも、一目瞭然である。なにしろ、そのなかに、ひとり、異質な格好をした生徒が混じっているのだから。本来、黒のスパッツに覆われているはずの、膝上から腰にかけて、その大部分の肌を、あられもなく露出させている。スパッツの代替物となっているものは、ほんの申し訳程度の面積しかない紺色の布地だった。それが、おしりの中央部と股間という、最小限の部位だけを隠すように、肌に張りついている。ド迫力のヒップであることも災いして、そこは、見るも無惨な有様となっていた。紺色の布地の外側に、わしづかみして有り余るほどあふれ出した肉塊。その、下半身の極限まで露わになった後ろ姿の生徒をよそに、周囲の部員たちは、みな、普段どおりの練習着姿をしているというコントラストは、現実のものとは思えないような残酷さだった。 香織は、その光景を目にし、一瞬、くらっときた。 あー、やばい……。やっちゃったかも、という気分だった。 「うっわ、きっつ……」 隣のさゆりも、そう口にする。 二年生チームのサーブを打つ選手が、もう位置についている。 ひとり、場違いな格好で異様に浮き立った、その生徒、キャプテンの南涼子は、前衛の中央のポジションに立っていた。サーブに備え、涼子が、後ろに腰を突き出すようにして構える。その姿の見苦しさといったら、直視していると、こちらが恥ずかしくなってくるほどである。後衛の選手たち、とくに、涼子の真後ろの選手は、今頃、目のやり場に困る思いをしているのではないかと想像する。涼子の構えが、いささか不自然に見えるのは、この位置からだとわかりにくいが、両手で引っ張ったTシャツの前すそを、股間に押しつけるようにして、その部分を隠しているせいだろう。しかし、そんな恥じらいの体勢も、あと何秒かという短い時間で崩れるはずだ。 香織たちの横にいる後輩グループの間から、刺々しい声が聞こえてくる。 「なんで……? そもそも、意味がわかんなくないっ? なんで、南せんぱいだけ、水着なんかで、練習に出てるわけ?」 「さあ……?」 水着、と見えるのも無理はないかもしれない。 「あーっ、なんか……、あんな人にずっと憧れてたとか、うちらみんな、馬鹿みたいだよね」 「ほんとほんと」 後輩たちを、そこまで失望させるに至った、最大の要因は……。 もうすぐ、その瞬間を目撃することになるのかと、香織は、心の準備を整えるような気持ちになっていた。 二年生チームを応援する一年生部員たちが、気負い立って声を張り上げる。 「ナイッサァー、イッポン! 入れてけっ! 入れてけっ! ナイッサァー、イッポンッ!」 その、どこか必要以上に攻撃性のこもった響きは、まるで、バレー部の異分子となっている南涼子の、葬送曲みたいに聞こえてならなかった。 ボールが、三年生側のコートに飛んできた。 それに反応して、涼子の体が、こちらに向いた。羞恥の血色に染まった頬。同時に、それまでの恥じらいの体勢が嘘のように大胆に、両の腕が宙に上がった。注目の下腹部は、先ほど、体育倉庫の地下で確認した時と、寸分たがわぬ状態だった。しかしながら、衆人環視の状況にあるバレーコート上でさらけ出された陰毛は、まったくの別物に見えた。その想像を超えた穢らわしさに、香織は、頭の中で何かが弾けたように言葉を失った。 「ぎゃぁぁぁーっ」と、さゆりが愉快げにダミ声を出した。 香織たちの横の後輩グループが、一層うるさくなる。 「もうっ、勘弁してって感じなんだけど!」 「なに、あの、ちっちゃい水着は!? 馬鹿じゃないの?」 「きったなーい。あそこの毛、あんなにはみ出しちゃってんのに、お構いなしにプレー続けるなんて、どーいう神経してんだろ?」 「だめだ……。どう見ても、露出趣味のある人としか思えない」 「実際、そういう性癖を持ってるんでしょっ。でなきゃ、あんな格好してることの、説明がつかないもん」 「やっぱりそうだよね……? 学校の体育館で、露出プレイするなんて、南せんぱい、キモすぎ」 「うん。キャプテン失格とか以前に、人として終わってる」 憧憬の人に裏切られたという思いが、彼女たちの怒りの源泉になっているのだろう。 急激な現実の移り変わりだった。香織たちとは、なんら関係を持たない後輩たちまでもが、涼子のことを、くそみそにこき下ろすようになったのだ。そのことが、にわかに信じられないというか、どうも現実に意識がついて来ない感じがする。 コート上では、ラインの外にボールが出たところだった。三年生側に点が入ったらしい。コート内の三年生たちが、自陣の中央に寄り集まってハイタッチを交わす。だが、涼子だけは、その輪に加わっておらず、ネット前の自分のポジションで、こちらに背を向けて直立していた。あごを苦しげに上向けている様からすると、その視線は、虚空の一点に向けられているようだった。誰とも目を合わそうとしない姿勢である。正面にも背後にも、左右にも、つまり平面上のあらゆる方向に、自分の姿を白眼視する眼差しがあることを、ひりひりと肌で感じ取っているからだろう。針のむしろとは、このことだと香織は思った。そして、ふたたび涼子の両手は、不自然にも、股間の辺りへと突っ張ったように下ろされているのだった。Tシャツの前すそは今、生地が伸びてしまうほど下に引っ張られているに違いない。せめて手が使える間だけでも、自分の体の汚いものを、ほかの生徒たちの目に触れさせたくない、という涼子の情念が、その後ろ姿から、嫌というほど伝わってくる。 その時、香織は、ぼんやりと思い出していた。一見、野性的ともいえる外見とは裏腹に、その胸の中には、誰よりもナイーブな乙女心が詰まっている……。普段の涼子に対して、常々抱いていた、そんな印象を。 よく見ると、遠目にも、涼子の体の震えが確認できる。あまりの恥辱に、膝がわなないているのか。それとも、すでに精神に異常を来し始めていて、発作的な全身のけいれんでも起こっている状態なのか。とにかく、涼子が震えていることだけは間違いない。なぜなら、人間の体のなかで、それがとくに顕著に現れる部分、むき出しのおしりの肉の表面が、脚を止めているにもかかわらず、ぶるぶると揺れ続けているのだから。今の涼子は、女の子として、いや人間として、最低限の誇りさえ奪われたような存在に成り果てていた。 香織は、思い描いていた青写真を超えた、地獄絵図を見せられている気分だった。というより、自分のせいで、眼下に、こんな凄惨な光景が展開されていると思うと、どうしても恐怖を禁じ得ないのだ。やはり自分は、気が小さいと感じ入る。調子に乗って悪事を働いて、いざ大事になると、後悔や不安に駆られてしまう。そういう経験が、これまでの人生で、幾度あっただろうか。 だが、不思議なことに今は、怖ろしさとは真逆の感情も、腹の底が引きつれを起こすようにして湧き上がってきていた。もう、どうにでもなってしまえ……。そんな、やけ気味なおかしさ。 眼下の涼子の様子を観察すると、今や、失神する一歩手前といったところではないかと推測される。 自分は、ともすると、涼子のことを、精神的にも肉体的にも常人離れした存在のように思いがちだ。しかし、忘れるべきではないだろう。しょせん涼子は、香織と同じ、高校三年生の女の子なのだ。それを考えれば、今もなお、コート上で踏ん張り続けていること自体、驚異的であり、賞賛に値するといえるかもしれない。その状態が、あと、どのくらい続くか……。ゲームの終了まで、涼子が、自分の脚で立っていられるかどうかは、五分五分だという気がした。もしも、途中で、涼子の肉体が崩れ落ち、倒れ伏したまま起き上がらなくなったとしたら、その後は、どうなるだろう。バレー部の部員たちの間で、先生を呼ぶべき、との声が上がるまでに、時間はかからないはずだ。駆けつけてきた教師たちは、現場を見て、どんなことを思うか。バレー部のキャプテンが、コート内で倒れている。高校の体育館という場には、およそふさわしくない格好で。そこに、事件性を感じるな、というほうが無理な話である。であれば、その後、息を吹き返した涼子に対して、大人たちによる、徹底的な聞き取り調査が行われるのは明白だ。そうなったら、涼子は、望むと望まないとにかかわらず、何もかもを、吐露することに……。 しかし、どうすればいいのか。その最悪の事態を回避するために、今から何らかの手を打とうとしても、完全に手遅れである。この先のことは、成り行きに任せるしかない。要するに、やってしまったことは仕方がないのだ。それだったら……、今を、この状況を、たのしまなくては損ではないのか。そうだ。だんだん、『前向きな』考えができるようになってきた。 どうなったっていい……。いっそ、ど派手にぶっ倒れちまえ、南涼子……。 香織は、そんな開き直った気持ちで、涼子の一挙手一投足に注目した。 サーブからプレーが再開されると、涼子は、人間の尊厳というものをかなぐり捨て、ボールを追い始める。その赤面した顔が、なんとも凶暴な表情に歪んでいることに気づいた。まるで、仁王様が乗り移ったかのような顔貌である。凄絶なのは、それだけではない。脚を止めている間は、倒れる寸前のような雰囲気を漂わせていたというのに、今、その肉体は、猛然たる躍動を見せているのだ。全身全霊でプレーに当たっている……。少なくとも香織の目には、そう映る。二年生チームに一セットでも取られたら、明日の練習も、そのブルマの格好で行わせると、明日香から脅されたせいに違いない。つまり涼子にとっては、生き地獄の恥辱に耐える時間であると同時に、絶対に負けられない戦いの真っただなかということになる。……笑える。すさまじく滑稽な話ではないか。 それにしても、遠目からだと、涼子の着用しているブルマの小ささが、一段と際立って見え、さすがの香織も、それを選んだ自分の判断ミスを認めないわけにはいかなかった。時々、Tシャツのすその下に覗く、ブルマのサイドの部分など、ほとんどヒモも同然に見える。運動用の衣類ですらない、コスプレ用の、しかも、いやらしさを限界まで追求して作られたかのようなアイテム。腰回りには、そんな下品な代物しか身に着けず、そこに収まりきらない陰毛をさらしているのだから、今の涼子の姿は、誰の目にも痴態として映るだろう。それも、陰毛は、もっさりとはみ出しているのだ。硬そうな毛質が、手に取るように伝わってくるほどに。近くで見たら、縮れ毛の一部に、流れ出した汗がしたたっている様子まで、視認できてしまうかもしれない。今この瞬間にも、不特定多数の生徒の視線が、そんな涼子の下腹部に一点集中している……。そのことを考えると、涼子と同じ女として、心胆の寒くなる思いで、香織はなぜか、自分自身の体毛まで、ちりちりと逆立っていくような感覚を覚えた。それに、見る者に与える精神的衝撃の度合いは、おしりの側もいい勝負である。涼子が飛んだり跳ねたりするたびに、二つの爆弾のようなむき出しの肉塊が、ぶるんぶるんと荒々しく波打つ様は、有害そのものという卑猥感を放っていた。 惨劇……。まさに、その言葉がふさわしい。今の涼子は、ただただ、恥辱という種類の苦痛を感じるためだけに、呼吸を繰り返す生命体のようだった。いや、もはや涼子の肉体それ自体が、恥の肉塊ともいうべきものに化しているという印象すら抱く。 笑える。おかしくてならない。なんていう無様な姿だろう。南さん……、あんた、本当にあの南さん? もう、別人みたい。というか、人間ですらなくなっちゃったみたいに見えるんだけど。 コートからボールが出る。 涼子は、すぐさま、Tシャツの前すそを両手で下に引っ張る。涙ぐましくも、まだ、女の子であることをやめたくないらしい。 その時、左手の壁に並んだバレー部員たちの、一番向こうの端から、素っ頓狂な声が発せられた。 「りょーちん! どうしたっ、またぁ、声が止まってるぞっ! 気合い入れろっ!」 ひとりだけ紺色のジャージを着込んだマネージャー、我らの竹内明日香である。 どこまで怖いもの知らずなのかと、香織も、半ば呆れさせられる。 非情な追い打ちをかけられた、涼子のほうは……。 「あーっ、ちょっと待ってーっ」 なにやら、抗議めいた返事をすると、コートの左手へと向かった。ゲームを見学する部員たちの前で足を止めると、いきり立った様子で言葉を投げかける。 「ねえっ、三年側(三年生を応援する側)の一年生、ぜんっぜん声出ししてないよね!? さっきも注意したのに、どーいうこと!?」 みな、無言だった。 涼子は、大声で怒鳴りつける。 「三年側の一年生っ! スクワットひゃっかいっ!」 そうして身をひるがえし、どたどたと自分のコートポジションに戻っていく。 ほとんど一年生部員への八つ当たりである。涼子が、そのような醜い行動に走ったということに、香織は、愉快さと失望の念の入り交じった、微妙な気持ちにさせられた。なーんだ。南さんも、やっぱり、ただの人なんだね……。 涼子に命じられた一年生部員たちは、ためらうように互いに視線を交わし合っていたが、やがて、いかにもやる気なさそうにスクワットを始めた。 香織たちの横の後輩グループが、憤りを示す。 「はー!? ありえないしっ!」 「一年生、かわいそーっ。目の前に、あんな格好でプレーする人がいたら、気持ち悪くなっちゃって、いつもどおりの声出しなんて、できるはずないじゃんねえ?」 「ねーっ」 「ああいうのを、パワハラって言うんだろうね」 「もう無理……。あたし、南せんぱいの何から何まで、生理的に受けつけなくなってきた」 聞いていて、痛快である。 香織は、バレーネットの真横、フロアの出入り口に目をやった。そこにも、制服姿の後輩たちが固まっているのが見える。寒さに身を寄せ合うような彼女たちの風情からするに、会話の内容は、香織たちの横の後輩グループと大同小異だろう。むろん、二階とは違って、そばにいるバレー部員たちに聞こえないよう、声をひそめているはずだが。そして、フロアの出入り口には、もう一人、生徒が立っていた。ほかでもない、滝沢秋菜である。 いささか戸惑いを覚えるほど、何もかも筋書きどおりに現実化している。 今から、一時間半くらい前だろうか。秋菜の保健の教科書を用いて作成した、『メッセージ』。涼子の手で、それを秋菜に渡すイベントが、終わった後のことである。香織と秋菜は、段取りを話し合った。まず、香織たちが、体育館にいる涼子を呼び出し、体育倉庫の地下で、下はブルマ一枚の格好に着替えさせる。そうして涼子が、明日香と共に体育倉庫を出たら、香織は、頃合いを見て、別の場所で待機している秋菜に、メールを送る。メールを受け取った秋菜は、体育館内に移動し、戻ってきた涼子に声をかけ、バレー部の練習を見学する旨を告げる、と。 香織は、涼子心理の専門家である。だから、涼子の心のデリケートな部分にこそ、探究の目を光らせているのだ。日頃から涼子は、苦手意識を抱いている相手、滝沢秋菜との『距離感』を、とかく気にしがちだった。遠くもなく近くもない。二人の間の距離は、常に一定であり、涼子が歩み寄ると、その分、秋菜のほうは離れてしまう。涼子にしてみれば、もどかしくてやるせない、そんな感覚である。 この舞台の特等席に、その秋菜を座らせることが肝要だった。舞台に立つ涼子の側にも、秋菜の顔が、否が応でも確認できるように。要するに、涼子の身を恥辱で焼くには、秋菜の視線というものが、何よりの油となるのだ。涼子は、館内で、秋菜の姿を発見した瞬間、目玉が飛び出るほど驚愕したに違いない。後で、明日香が、話して聞かせてくれるだろう。涼子が、どのように泣きついてきたのか。『滝沢さんの、見てる前でだけは、いや……!』。涼子の口から、そんな言葉が出たのだとしたら、香織のもくろみは大成功といえる。 陰毛を人目にさらしながらも、汗まみれになってプレーを続けるしかない涼子と、その姿を、涼しげに鑑賞する秋菜の、過激な近接。まるで、涼子の肉の焦げる臭いが、ここまで漂ってきそうな光景だった。 そして、何より愉快なのは、未だに涼子が、その秋菜の存在を、自身の『致命的な弱点』だと思い込んでいることだ。本当は、涼子に、そんな弱点などありはしないのに。なにしろ、すでに秋菜は、香織たちの側に取り込まれているのだから。涼子にとって、秋菜とは、事情を知らない(だからこそ脅威の)第三者、ではなく、単なる敵対者であって、それ以上でも以下でもないのだ。そんな裏の相関図が出来上がっているとは、夢にも思わないらしく、涼子は、香織たちの『切り札』が、秋菜の手元に届くことを、ひたすら怖れている。そうなったら、高校生活の破滅だ……、と。 言うなれば、涼子は、実体のない幻影に怯えているようなものだった。そうして怯え続けた挙げ句が、眼下のあの、醜悪な成れの果ての姿である。 世の中に、これほどまでの馬鹿が、ほかにいるだろうか。やはり、あの女の頭の中には、粗悪な脳みそが詰まっているとしか思えない。ちょっとばかり、残念な話ではあるけれど……。 だがそこで、違うな、と考え直す。涼子の頭脳に問題があるのではなく、きっと、香織のアイディアが、素晴らしすぎるのだ。芸術的なまでに。仲間に引き入れた滝沢秋菜を、ただちに、涼子を責めるコマとして使用するのではなく、機が熟すまでは、第三者のポジションにすえ置くという、その発想が。人や物事を、真っ直ぐに見つめながら生きている涼子の思考回路では、察知できないのも無理はない。いや、よく思い起こせば、この案は、香織の単独ではなく、秋菜と共同で考え出したものだったかもしれない。まあ、それはどちらでもいいか。 そういえば、その秋菜は、先ほど、段取りを話し終えた後に、こんなことを言っていた。そばに立って見物する秋菜に対して、涼子は、恥ずかしさを感じるだけでなく、ある種の恐怖さえ抱くはずである。そういった感情は、いずれ、秋菜への憎しみに変わっていくことだろう。涼子が、その憎しみの思いを、秋菜自身に向けて露わにする様子、それが見たいのだ……、と。 香織には今ひとつ、ぴんとこない話だった。簡単にいえば、秋菜は秋菜で、何か求めるものがあるということなのだろう。 「りょーこーっ! あんた、練習のしすぎで、気が、変になってんじゃないの!?」 その笑いまじりの声は、バレーコートの右手、一階のフロア全体を真ん中で二分する、ネットの向こうから聞こえた。三年生のバスケット部の部員だ。彼女を含めて十人近くが、野次馬となって、涼子の姿に目を向けている。 バレー部側のゲームは、サーブからのプレー再開を待っているところだった。 「みーなくってっ、いいからぁぁぁ!」 涼子は、憤まんやるかたない様子で、そう叫んだ。バレー部の部員たちとは違い、部外者であるバスケット部の生徒たちは、露骨なあざけりの態度を示している。そのことに相当、いらいらとさせられているのだろう。 香織たちの横の後輩グループから、突っ込みが入る。 「なに言ってんだか。注目されるのが嫌なら、あんたが、今すぐ、普通の格好に着替えてくればいいんでしょって」 「そうだそうだ」 ついに、あんた呼ばわりされるまでに至った。 「いい加減、バレー部の誰かさあ……、あのキャプテンのこと、一発、本気でぶったたいて、目、覚まさせたほうが、いいんじゃないのかなあ」 「ぶったたくって、顔を?」 「いや……、たとえばあの、水着から思いっ切りはみ出てる、でっかいケツとか」 失笑が漏れる。 「やだっ。なんか、めっちゃ汗ばんでそうだし、あんなところ、誰も触りたくないでしょ」 「あたしが、バレー部員だったら、むかついて、絶対、やってるなあ……。『ここ、海やプールじゃないんだから、水着なんかで練習するの、やめてくださいよ!』って言って、あのケツ、ばちーんて平手打ちする」 「で、そのあと、どうすんの?」 「えっ……。半殺しにされそうで怖いから、ダッシュで逃げる。そんで……、いちおう、手、消毒しておく」 「消毒する、とかいって……。南せんぱいのおしり、ばい菌だらけ、みたいな扱いじゃん」 今や、涼子の存在は、嫌悪の対象であるがゆえに、ただでさえ、綺麗とは言い難い体の部分が、よけい不潔に見えてしまうのだろう。 「あっ、ようやく謎が解けた……。南せんぱいのあの格好は、機能性、だけを重視した、究極の練習スタイルなんだよ」 「……ははーん、なるほど。下半身の動かしやすさとか、服装の軽量化とかを、徹底的に追求した結果ってことか」 「そういうこと。最後の大会が近づいてきたから、南せんぱいが、いよいよ本気モードに突入したみたい」 「うっわぁ……。ますます、かっこよく見えてきちゃったあ」 冗談の応酬である。 「まあ、百歩譲ってさ……、かりに、そういう正当な理由があるにしても、あんな水着で練習に出るなら、その生地の面積に合わせて、事前に、毛の処理くらい、しておけよって話」 「そっか……。やっぱり、今の南せんぱいを擁護するのは、無理か」 「擁護する気なんて、全然ないくせに」 「残念ながら、あの人は、どっからどう見ても、露出狂です」 「ねーねー。っていうかさ……、あの、まん毛、どう見ても、量、多すぎじゃない?」 「あたしも! 実は、最初に見た時から、ずーっと、それ思ってた」 「だよね、だよね。強烈なインパクトだよね?」 「なんか、ケダモノって感じがする」 怒りを通り越したのか、彼女たちのなかでも、涼子の姿は、物笑いの種でしかなくなりつつあるようだった。 ちょっと前までは、夢想すらできなかった事態である。連日、後輩たちの黄色い歓声を浴び、時には、ファンレターともラブレターともつかぬものを受け取ることもあったという、あのバレー部キャプテン、南涼子が、だ。その後輩たちから、嘲笑の的にされる時が訪れるなんて……。 隣のさゆりが、やたらと面白がっている。 「天下の南せんぱいが、年下から、ぐっちゃぐちゃに言われまくってる……」 その時だった。バレーコート内から、空気を裂くような鋭い怒声が上がったのだ。 「ブロックが遅れてるって、何度、言わせんのよっ!」 声の主は、三年生、香織も知っている、副キャプテンの高塚朋美という生徒だった。長身の彼女が、つかつかと涼子のそばに歩み寄る。どうやら、怒られているのは涼子のようだ。 だが、涼子も負けない勢いで応戦する。 「わたしだって、加奈子のマークに引っ張られてるんだからっ、しょうがないでしょっ!」 体格のいい二人が、間近でにらみ合う。けれども、涼子のほうは、両手でTシャツの前すそを引っ張った、情けない格好なので、迫力には大きな差があった。 ほかの三年生の選手たちが、二人の間に割って入る。そうして、それぞれが、かろうじて自分のコートポジションに戻るも、三年生チームは、完全に空中分解しているといえた。キャプテンの南涼子のせいで……。 涼子の顔が、おもむろに真上に向けられた。表情を見ると、その両目は、泣いているようにぎゅっと閉じられていた。気力を振り絞って、遠のく意識を懸命につなぎ止めている、という感じに見受けられる。精神的にも肉体的にも、とっくに限界を超えてしまっているのだろう。もう、いつ、前のめりに崩れ落ちても、不思議ではないように思う。 だが、そんな涼子の身に、さらなるムチが飛んでくるのだった。 「りょーちん! こーえっ、こーえっ」 明日香の、後先考えない暴走ぶりに、香織も、頭を抱えたくなる。あんた、やりすぎだって……。ほんとうに、南さんが、ぶっ倒れちゃうじゃない……。 突然、ゾウの鳴き声に似た、なんとも奇妙な音が耳に入ってきたので、一瞬、何事かと驚いた。それは、涼子の口から吐き出された、地獄の悲嘆だった。続いて、けたたましい奇声がほとばしる。 「カァァァァァァァットバシテ、イゴォォォゼェ! ヨォォッ! ヨォォッ! ヨォォーッ!」 声の拍子に合わせて、その恥まみれの肉体が、びくんびくんと伸び上がる。もう、見ていて怖くなるような狂態ぶりである。 その煽りを、もっとも受けるのは、ほかの三年生の選手たちだった。彼女たちは、チームの仲間として恥を感じるのか、ひどく肩身の狭そうな様子を見せる。 香織は、涼子の姿に、本物の狂気を見た気がした。もし涼子が、まだ、正気を保っているとしたら、それこそ人間として不自然だと思う。 香織たちの横の後輩グループから、涼子の口真似をする者が出る。 「ヨォッ、ヨォッ、ヨォーッ」 「ちょっと、声、大きいって……」 「いいじゃん。誰も南せんぱいに、声、合わそうとしないから、あたしが言ってあげてんの」 そこで、彼女たちの間から、ぼそりと聞こえた。 「ねー、あのマネージャーの先輩、ちょっと、おかしくない?」 香織は、どきっとした。 「マネージャー? ああ、竹内先輩でしょ? どこが?」 「だって、さ……。こんな状況で、なんで、さっきから楽しそうにしてるわけ? あたしには理解できないんだけど」 「言われてみれば……」 「たしかに、南せんぱいの毛のことは、とっくに知ってるはずなのに、ね……」 「ひょっとして、だけど……。あのマネージャーの先輩が、南せんぱいに、あんな格好で練習やらせてる、なんてことはないよね?」 まずい……。香織は、血の気の引く思いがした。 「まさか」 「なんのために?」 「いや、ただなんとなく、そんなふうに思っただけ……」 「なんとなく、って……、いくらなんでも、竹内先輩のこと、悪く考えすぎでしょっ」 「そうだよーっ。竹内先輩って、チャラい感じもするけど、一、二年の部員にも、すっごく優しくしてるの見るし、絶対、性格いいってー」 「えっ、うん……。ごめん、あたしの言ったこと、気にしないでいいから。忘れて」 しょせん、愚か者の集まりだったと、香織は、ほっとする。けれども、普通に考えて、明日香の言動が、恐ろしく周囲から浮いていることは確かだ。あれでは、疑念の目を向けられるのも、当然といえるかもしれない。心の中で、明日香をしかりつける。あんまり調子に乗るの、やめなさいよ……。ほかの子たちに、勘づかれるでしょ……! 後輩グループの会話は続いている。 「それはそうとさ……、今日ここに、マドカがいたら、大変なことになってたと思わない?」 「ああ、そりゃあもう……」 「マドカが、あの南せんぱいの姿を見たら、その場で泣き崩れてたかも」 「ありうる……。あの子、『夏休みに入る前に、絶対に南せんぱいに告る』って決意表明してたもんね。『もし告らなかったら、夏休み中、ずっと後悔し続けそうで、それだけは耐えられない』とか言って思い詰めてたし」 「あの子、最近、よく言ってるよ。『南せんぱいのことは、男にも女にも渡したくない』って」 「それ、あたしも聞いた」 なにやら、ファンのなかでも、図抜けて涼子に夢中な生徒がいるらしい。 「でも……、今回のこと、マドカに、はな……す?」 「はな……す」 「うん、話さざるをえない。っていうより、話すべきでしょっ。南せんぱいは、露出狂の危ない人間だったってことが、判明したんだから」 「だけどさ……、あのマドカが、信じるかな? こんな話」 「うーん……」 「マドカに話しても、うちら、嘘つき呼ばわりされるだけじゃない?」 「たぶん……。『はー!? なに言ってんの? やばいのは、南せんぱいじゃなくって、あんたたちの頭のほうでしょ!』みたいに返されると思う」 「だよね? 想像がつくもん」 「下手すると、キレられるかもよ、あたしたち」 「マドカに、そういうふうにされるのも、なんかシャクだよね……」 「だったらさ……、証拠、残しておけばよくない?」 「証拠?」 「南せんぱいの、あの姿、ムービーで撮っておくとか」 香織もさゆりも、思わずそちらに目をやっていた。 後輩グループは、すでに、ほの暗い、よこしまな空気に包まれているように見える。 「そう……、しよっか」 「名案かも」 「えっ……。そこまでする……?」 「だって、南せんぱいの本性は、マドカにも教えてあげないと、じゃん?」 「うん、そのとおり。あんな危険人物に告ったりしたら、はっきりいって何されるか、わかったもんじゃないしね」 「そっ。マドカのため」 「うちら、友達思いだからね」 彼女たちは、がさごそと携帯端末を取り出す。 「あ、待って……。バレー部の人たちに、撮ってるのがバレると、もしかしたら怒られるかもよ」 「怪しまれないように、誰かひとりが、代表で撮ることにしよっか?」 「じゃあ、誰が?」 「一番、新しい機種を持ってる人」 「もしかして……、なるべく高画質で撮れるように、ってこと?」 「イエス」 「それならエリじゃん? 先月、買い換えたばっかだから」 「あたし? 構わないけど」 「よし、エリが代表で撮るんで決まり」 「なるべく、スマホが目立たないようにね」 「あたしのバッグで、こうして、隠すようにするといいかも」 撮影係となった生徒は、バレー部の部員たちに悟られないように、友人のバッグの陰でスマートフォンを操る。横向きになったスマートフォンが、バッグの上に少し突き出る形で、ギャラリーの鉄柵の間から、バレー部の練習場へと向けられる。無情にも、そのカメラが捉えようとしているのは……。時代遅れの校則を守り、それらの携帯電話の類は、未だに持っていないという、純朴を絵に描いたような生徒、南涼子の、コンプレックスでもあろう陰毛なのだ。 えらいことになっている……。香織も、笑うに笑えない事態だった。 「南せんぱい、大ピーンチ」 隣のさゆりが、そうつぶやく。 後輩グループの面々は、そろって嫌な薄笑いを浮かべていた。涼子の熱狂的ファンだったというだけで、彼女たちの精神構造自体は、香織やさゆりとさして変わらないのかもしれない。 「それっ」と、撮影係の生徒が口にする。 ぴこっ、という録画開始の音が鳴る。 「どう? 撮れそう?」 「あっ、だいじょうぶ。今あの、きっしょい後ろ姿が、画面に入ってる……。もうすぐ……」 「来るよ来るよ」 「こっち向いたっ」 「撮れてる?」 「ばっちり……。南せんぱいの顔はもちろん、あそこの毛も、なんていうか、ごわごわっぷりが見て取れるくらい、しっかりと写ってる」 「やだっ。超、生々しい映像になりそう」 「最低でも、二分は撮っておいてね」 「りょーかい。……誰か、コメントして」 「学校の体育館に、露出狂を発見! 激写しました!」 「マドカー、見てるー? コートのなかに、変な格好の人が混じってるでしょ? 誰かなぁ? あんな人には、くれぐれも近づかないように」 「完全に、マドカ宛てになってるし……」 「だって、違うの……?」 「マドカのほかにも、目を覚ます必要のある人、たとえばさ……、モエ、ミンミン、ココノ、タチバナさんあたりには、この動画、見せたほうがいいじゃん。……あ、あと、商業科の、あの、ちょっとオタクっぽいグループもいたね」 「もういっそ、全校生徒向け、にしちゃう?」 聞いていて、涼子のことながら空恐ろしくなる。 もとより、香織も、ある程度のことは想定していたのだ。この日、バレー部の練習場で起こった出来事は、明日になったら、学校中に噂として広まるのではないか、と。だが、噂ではなく、決定的な場面を捉えた映像が、後輩たちの悪意によって拡散されるとしたら……。いったい、涼子の高校生活は、どうなってしまうのだろう。 それにしても、だ。涼子の救いようのない運のなさには、ある意味、感心させられる。香織たち三人に加え、滝沢秋菜にも包囲網を形成されたのみならず、今度は、別の後輩グループからも、害意を向けられるという始末である。南涼子という人間には、超ド級の不運が、何重にも重なっているのだ。そんな涼子の哀れさが、無性におかしくなってきて、腹がひくひくとし始める。 香織は、込み上げる笑いを抑えながら、初めてこんなことを思ってしまった。南涼子にだけは、生まれなくてよかった……。 「あ、香織先輩、あの子……」 さゆりに肩を叩かれる。 彼女の指差す方向、横にいる後輩グループの、その向こうに目をやる。 ひとり、小さな人影が、ぽつんと立ってバレー部の練習を見つめていた。きっと、香織たちが来る前から、そこにいたのだろう。香織もさゆりも、手前の後輩グループのほうに、完全に気を取られていただけで。 その生徒の横顔を確認し、香織は、ああ、あの子か、と思った。やっぱり来ていたのか……。 香織とさゆりは、そちらに歩いていった。もう、半分はしゃいでいるような後輩グループの後ろを通り、近づいていく。 さゆりが、その生徒の肩を、いきなり、どんっと押した。驚いてこちらを向き、目をぱちくりさせる彼女。 香織よりも小柄な体。おそらく身長は、百五十センチもないだろう。肩まで伸びた、真っ直ぐすぎるストレートヘアからは、髪の毛一本のうねりさえ許せない、という頑なな思いが伝わってくる。うるうるとしたような、まん丸に近い大きな目の、なんとも子供っぽいこと。おまけに、常にぷーっと頬を膨らませている感じの、ふっくらとした顔のラインや口もとも合わさって、もはや、どことなくアニメチックな雰囲気を漂わせている。 南涼子にファンレターを手渡したことのある一年生、足立舞だった。(第七章に登場) ガキ……。この子は、本当に、中学を卒業しているのだろうか。もしかすると、小学校を出た後、残りの義務教育の三年間を素っ飛ばして、この高校に入ってきてしまったのではないか。彼女の容姿を見ると、毎回、本気でそんなことを思ってしまうのだった。香織は、その彼女に言う。 「ね? あたしたちの教えたとおりでしょ? 今日の夕方、ここに来れば、南センパイのセクシーな姿が見られるって」 セクシーな姿……。 舞の、シミひとつない白い頬が、ほんのりと赤らむ。 昨日の放課後も、舞は、南涼子を目当てに、この場所に立っていた。香織たちは、その舞を捕まえて、今日のこの出来事をそれとなく予告しておいたのだ。 香織は、意地悪く尋ねる。 「どうどう? 正直、あの南センパイの姿は……。ほれぼれしちゃう?」 舞は、恥ずかしそうに、もじもじするばかりだ。 面白いので、さらに、からかってみる。 「南センパイったら、すっごい格好してるよねえ? だってさ……、あれ、おしりどころか、やばいものまで、はみ出しちゃってんの、見えるでしょう?」 舞は、首を小さくふりふりしながら下を向いてしまう。あたし、南先輩のそんなところ、見てません、と言いたいのか。この子には、少々、刺激が強かったのかもしれない。 続いて、さゆりが訊く。 「もしかして、ウゲェーッ、オエェーッ、って思っちゃった?」 涼子については、何も言えないらしく、舞の唇は、ぴたりと閉じられている。 これ以上、あれこれと尋ねても無駄だろう。香織は、とっておきの話を語り始める。 「実はね……、南センパイのセクシーショーは、これで終わりじゃないんだよね。今回は、まあ、『第一部』みたいなもん。近いうち、別の場所で、『第二部』があるの」 もちろん、その『第二部』とは、香織たちのみで行う、秘密の宴のことだ。 舞は、おもむろに顔を上げた。続きを聞きたそうな様子である。 香織は、にやりとした。 「第二部では、あの南センパイ、なんと……、もっと過激な姿を見せてくれるんだよ」 舞は、小さく息をのむ。 「……もっと過激な姿?」 これまた小さな子供のような声で聞き返してくる。 「そう」 多くは語ってやらない。どんな姿かは、自分の頭で想像すればいいのだ。 「……もっと過激」 舞は、もう一度、その言葉をつぶやき、大きな目をしばたたく。脳裏に、何か思い描いているような表情である。そして、その視線が、斜め下に落ちる。どこか後ろめたそうに。 香織は、ささやくように問う。 「どう? その第二部のほうも、見に行きたいと思わない?」 舞は、にわかにうろたえ始めた。 少し考える時間を与える。舞の幼い顔に浮かんだ、迷いの思い。 やがて、舞は、ためらいがちに口を開いた。 「あの……」 「見に行きたいよねえ?」 香織は、舞の言葉をさえぎる。 舞の表情が固まった。否定しない。それだけで、もう充分だろう。 「よし、第二部の、日時と場所、教えてあげる。ただ、極秘情報だから、こんなところで話すっていうのも、ちょっとね……」 香織は、さゆりのほうを向く。 「これから、駅前の、どっか適当な店に行って、そこで打ち合わせしよっか?」 「そうですねっ。乾杯がてら」 「決まった」 舞の肩に手を置き、無理やり歩かせようとした。 「えっ、え……」 強引すぎたらしく、さすがの舞も、踏み留まるようにして、微力な抵抗を示す。 香織は、そんな舞の頭の中に、一言一句、染み込ませるように口にする。 「南センパイの……、何もかもを……、知りたいでしょ?」 舞は、こちらをじっと見返す。体の抵抗が、徐々に弱まっていく。 その舞の腕を、さゆりが、ぐいっと引っ張って言う。 「なんでも、おごってあげるからっ。なにが食べたい? ドーナツ? それともケーキ?」 二人の先輩には逆らえないと観念したのが半分、好奇心に負けたのが半分という感じで、舞は、おずおずと歩き始める。 幸いにも、横にいる後輩グループは、涼子を撮影したのであろうスマートフォンに熱中していて、香織たち三人のことは、気にも留めていないらしかった。 香織とさゆりは、見るからに無力な一年生を、その場から連れ去っていく。 こんなガキ、一度、ふところに誘い込めば、後は、どうにでも操れる……。香織の胸の内には、その確固たる自信があったのだ。 階段を下り、一階の通路を進む。玄関の前で、さゆりと舞を待たせることにし、香織は、フロアの出入り口へと向かった。秋菜に、一言伝えておくために。明日香には、バレー部の練習が終わったら、香織たちのいる店に来てもらうつもりだった。 フロアの出入り口のところにも、制服姿の後輩が数人、固まっている。驚くことに、その彼女たちにまで、二階のギャラリーにいた後輩グループと同様の、心理的変化が起こったらしい。口もとを押さえたり、互いに頭をくっつけ合うようにしたりして、くすくすと笑い声を立てているのだ。まだ帰らないのは、憧れだった涼子の見せる別人のような狂態が、この上なく愉快なショーに思えてきたからに違いない。 まったく、どいつもこいつも、と香織も苦笑させられる。この学校に、本当に善良と呼べる生徒が、果たして何人いるのだろう。もしかすると、砂山から砂金を見つけ出すようなものかもしれない。その貴重な貴重な一粒の光である南涼子が今、他の生徒たちの笑い物になっているのだ。そんな世も末のような状況を、自分が作り出してしまったと考えると、罪悪感めいたものが芽生えそうになるが、すぐに、どうでもよくなる。 フロアの出入り口の少し手前で、香織は足を止めていた。香織と秋菜が一緒にいるのを、涼子に見られるのは、都合が悪いからだ。変貌した後輩たちの横にいる、秋菜を呼ぶ。 「滝沢さん」 秋菜は、香織の姿を見ると、上機嫌な様子でやって来る。 香織は、話し始めた。 「たった今さ、この前、言ってた、あの……」 足立舞については、涼子にファンレターを手渡した一年生として、すでに簡単に話してあった。その舞を誘い出すのに成功したこと。これから、駅前の喫茶店にでも移動し、そこで舞を『落とす』つもりであること。その二点を伝える。 すると秋菜も、興味を持ったらしく、一緒に来ると言った。 香織は、秋菜と共に玄関に向かう。 歩き始めると、秋菜は、なにやら勢い込んで言い始める。 「ねーねー、吉永さん。聞いてよ、もう……。さっき、南さんがさ、わたしの目の前で、コートのサイドラインの、外に出そうになったボールを拾おうと、こっちに向かって身を投げ出してね、そんで、思いっ切り、どだんって倒れ込んだの。ほんと、わたしの、二、三メートル前で。その、這いつくばってる南さんと、目が合ったわけよ。だから、わたし、南さんの顔を、じーっと見下ろしてやったの。じーっとね。そうしたら、南さんったら……」 秋菜は、言葉を切り、冷然と整った顔を、一瞬の間、激怒したように歪めた。眉間にしわを寄せ、歯茎をむき出しにする。 「こーんな顔で、わたしのこと、にらみ上げてきたの。なんていうか、地獄の鬼って感じの、ものすごい形相で」 その二人の図を想像してみる。 「えー。なにそれ、なにそれ……。滝沢さんに向かって、『見世物じゃないわよお!』って言うように?」 涼子が、秋菜に対して、憤激を露わにしたというのか。 「いや、そういう怒りっていうより……、あれは、わたしに対する、憎しみね」 秋菜は、ときめきを覚えているような仕草をする。 「憎しみ?」 「そう。あの南さんの顔は、わたしに、こう言いたげだった。『あんたのことも、絶対、地獄に引きずり込んでやるから』って」 本当に、あの涼子が、そんな怨念めいた形相を秋菜に向けたのだろうか。 秋菜は、うわごとのように言う。 「あー、あの、憎悪に歪んだ南さんの顔、写真に撮って、保存したかったーん」 背筋が、むずむずとする。秋菜の悪意に接していると、時々、香織でさえ嫌悪感を覚えることがある。 玄関のところで、舞は、さゆりと一緒にちゃんと待っていた。 その二人と合流すると、秋菜は、しげしげと舞のことを観察した。 「ふーん。この子が……」 「そうなの」 舞のほうは、どうしていいかわからず、まごつくばかりである。 秋菜は、その舞に優しく笑いかけ、さらりと口にする。 「わたしも、南涼子さんの大ファンなの。ファン同士、よろしくね」 舞は、えっ、と意外そうに秋菜の顔を見つめる。 なるほど、と秋菜の意図を察する。まず、舞の警戒心を解こうということか。それには、たしかに、同じ涼子のファンを称するのが、もっとも効果的だろう。 香織からも舞に言う。 「そういうわけだから、この先輩とも、仲良くしてあげてね」 舞は、曖昧にうなずく。 香織は、舞の背中を、ぽんっと叩いた。 「じゃ、行こっか」 それぞれ、上履きから革靴に履き替え始める。一番遅れて、舞も同様に。 もたつく舞を待ち、四人は、そろって玄関を出る。 ふと、香織は、夕刻の空を見上げた。 頭上には、重苦しい黒雲が垂れ込めていた。まるで、今、体育館内にいる誰かの、恐ろしい未来を暗示するかのように。 夜は、しんしんと深まる。 吉永香織は、勉強机に向かって、沈思黙考していた。机の上に、教科書やノートの類など、はなっから広げていない。むろん、頭の中を占めているのは、南涼子のことだった。 バレー部の練習場という衆人環視の場で、涼子を、徹底的に辱めてから、丸二日が経っている。 二日前のあの日、涼子が、最後まで自分の脚で立っていられるかどうかを、見届けることなく、香織たちは、学校を出た。その一時間半ほど後に、バレー部の練習を終えた竹内明日香から、電話があった。香織は、まず、涼子の安否を尋ねた。涼子は、無事だった。ゲームの終了まで、一、バレーボール選手として、コート上で踏ん張りきったという。しかも、涼子の粘り強い奮闘のおかげもあって、明日香の言いつけどおり、三年生チームは、二年生側には屈せず、一セット目、二セット目と、続けて勝利を収めたらしい。香織は、その報告を受け、心底ほっとすると同時に、涼子の精神と肉体の屈強さを、拍手で褒め称えたい気分になった。南さん、あんたは、やっぱりただ者じゃないね。あたしみたいな平凡な女の子とは、次元の違う生き物って感じ。かっこいい。サイコー! 香織は、そして感謝した。ありがとう、南さん。……これで、まだまだ、あんたをオモチャにして遊べる。 しかし、その翌日、つまり昨日、学校に行き、事態の深刻さを悟ったのだ。 涼子は、言うなれば、香織たちによって、見えない首輪を付けられた状態で、高校生活を送っているようなものである。にもかかわらず、これまで、クラスメイトたちの前では、決して苦悩の影を見せず、気丈にも、一点の曇りもない笑顔を振りまき続けてきたのだ。それこそが、ある意味、涼子の一番すごいところだと、香織は感じていた。だが、そんな涼子の明るさも、とうとう、大きく陰り始めたのだった。 鈍感なクラスメイトたちでさえ、涼子の異変に気づいていた。休み時間、昼食時、移動教室など、様々な場面で、涼子に向けられたこんな言葉が、香織の耳にも入ってきた。 「りょーこー。今日、朝からずっと、テンション低すぎぃ。なにか、訳あり?」 「またまた、孤独な世界に入り込んじゃってるっ! いくら最後の大会が近いからってさあ、教室でまで、精神修行に励むなんて、やめてよねー」 「南さーん。おーい、おーい、起きてるー? 具合でも悪いのー?」 「ふさぎ込んでる涼子の姿なんて、ほんと、新鮮だねえ。で、なになに? 悩み事は……。もしかして、男? まさかね。涼子に男関係はないよね。涼子だもんね」 「ちょっとちょっと、あんた、目、死んでるよ。本当に、だいじょうぶなの?」 「うわぁ。しんどそぉ……。立ってるのもつらいくらいなら、早退したほうがよくない?」 そういった言葉をかけられるたび、涼子は、精一杯の笑顔を作って、その場をやり過ごしていた。だが、友人たちが離れたとたん、その顔には、反動のように、前よりさらに沈んだ表情が浮かぶ。 前日、バレーコート上で繰り広げられていた、非現実的なまでに凄惨な光景。その被害者たる涼子に関して言うなら、こう表現しても大げさでないかもしれない。涼子は、気力も体力も、持てる力を最後の一滴まで出し尽くし、あの地獄から『生還』したのだ。そのことに対しては、心からの賛辞を送りたい。だが、どうやら、その苛烈を極めた体験ゆえに、涼子の心身には、回復不能なダメージが残ってしまったらしかった。なんのことはない。結局のところ涼子も、一介の女子高生に過ぎなかったということだ。 そして、その涼子を一層、追い詰めるような事態が生じていた。 前日、バレー部の練習場で起こった出来事は、噂となって、ひそやかに、だが確実に、クラスメイトたちの間に浸透しつつあったのだ。 少々、驚いたことに、香織が、クラス内で便宜的に付き合っている、冴えない友人までもが、その噂を、どこからか聞き及んでいた。その友人は、何か、悪だくみでも打ち明けるかのように、こう切り出した。 「ねえ、香織ちゃん、香織ちゃん、知ってる? 南さんのこと……」 超小さい水着みたいなもの、あり得ない最悪の格好、あそこの毛、怪物的な大声の絶叫、といった言葉を用い、友人が、前代未聞の珍事件のあらましを語る。その内容に、これといって事実に反する事柄は含まれていなかった。 むろん、それを聞いた香織は、信じらんない、と驚愕してみせ、さらには、南涼子への嫌悪感を、ぞんぶんに示しておいた。 そういうクラスの状況を踏まえ、涼子と、その周囲に集まる生徒たちを観察していると、ある現象が起きていることに気づいた。各自が、噂を耳にしたのだろう、くしの歯が欠けるように、一人、また一人と、涼子のそばから離れていっているのだ。涼子に話しかける生徒の数も、帰りのホームルームが近づく頃には、普段の、三分の一以下に激減してしまっている感じだった。 涼子は、もちろん馬鹿ではないし、また、鈍感でもないはずだ。クラスメイトたちに、そうして距離を置かれ始めていることは、誰よりも涼子自身が、一番わかっているに違いない。机に頬杖をつき、自分の席で暗く沈み込んでいるのは、その、いたたまれない思いに、ただただ耐えている姿、というふうにも見受けられる。 その光景の残酷さに、香織は、いささか困惑を覚えていた。たかが噂ぐらいで、クラスの太陽のような存在だった涼子のことを、あからさまに忌避し始めたクラスメイトたち。なんと薄情な連中だろうかと、香織でさえ呆れ返ってしまう。あるいは、涼子の交友関係の実態は、まさに広く浅くで、本当に友達といえる友達など、ごく一握りだったことが、はからずも証明されてしまったというほうが正確かもしれない。なんにせよ、涼子を取り巻く環境が、こうも悪くなってしまうなんて、香織にとっても想定外だった。 しかし、思い出すべきだろう。その噂は、単なる噂では終わらないかもしれないのだ。 香織の脳裏には、前日の、ある出来事が思い浮かんでいた。 体育館の二階のギャラリーで、涼子の恥辱の舞台を見物する、香織たちの横に、後輩が、四、五人、固まって立っていた。その後輩グループの取った行動が、とてつもない問題をはらんでいるのだ。彼女たちのうち、選ばれたひとりが、スマートフォンを使って、眼下の光景を、というより、涼子のその、陰毛をはみ出させたままプレーする醜悪な姿を、動画として撮影していたのだから。さらに、別の誰かは、その映像を校内に広めるとか、そんなことを匂わせる発言をしていたはずである。 このご時世だ。あの後輩たちが、本気で、くだんの映像を、学校中の生徒に視聴させようと企んだのなら。そのもくろみが達成されるのにかかる時間は、ほとんど一瞬だという気がした。つまり今、流れている涼子についての『噂』が、そっくりそのまま、決定的な場面を捉えた『映像』に、置き換えられてしまうのだ。 香織は、今一度、クラスの状況を見つめ直した。 噂の段階で、すでに、涼子を中心とした人間模様は、亀裂だらけの様相を呈しているのだ。それが、実際の映像という、比較にならないくらいの破壊力を持つ代物に変わったとしたら……。想像するだけで、背筋に寒いものを感じてしまう。もし、実際にそうなった場合、涼子には、災厄にも等しい逆境が襲いかかるに違いない。そこで、さらに問題となるのが、涼子の健康状態である。ただでさえ、心身ともに衰弱している涼子が、果たして、そんな逆境に耐えられるだろうか……? 耐えられなくなる可能性も、充分にある。そんな気がした。それはつまり、どういうことを意味するのか。下手をすると、涼子は、この学校からドロップアウトしてしまうかも……。 香織は、目の前が暗くなる気分を味わった。香織にとっても、それは、最悪の事態といえた。なにしろ、もう二度と、涼子に会えなくなってしまうのだから。涼子に対して、やりたいことは、まだまだたくさん残っているのに、それらすべてを、諦めさせられることになるのだ。 だが、あの涼子である。香織や、そこいらの生徒たちとは違って、人生の設計図というものを、ひしと胸に抱えているはずなのだ。それを、そう簡単に捨て去ることはできまい。香織は、自分に言い聞かせる。だいじょうぶ。涼子なら、今後、たとえ身を切るような逆風に煽られようとも、土俵際で踏み留まってくれるに決まっている。そう。学校という境界線の、ぎりぎりところで。 香織は、そうして、なんとか不安を抑え込んだのだった。 しかし、さらにその翌日、つまり今日、香織のそんな希望的観測を打ち砕く、決定的な出来事が起こった。 古文の授業中のことだ。 教壇に立っているのは、山辺という名の、五十代後半と思われる女の教師だった。小柄で、丸眼鏡をかけており、いつも柔和な表情を浮かべている、いかにも人のいいおばさん、という感じの人物である。 その山辺教諭が、いきなり驚いた声を上げた。 「あっらぁ……。南さんっ、南さんっ」 それを聞いた香織は、斜め前方の、涼子の席に目を向けた。 涼子の背中が、はっと我に返ったように見えた。 「珍しいわねえ、あなたが、居眠りするなんて……。でも、駄目よお。部活で大変なのはわかるけど、勉強のほうを、おろそかにするようになっちゃ……。なんていったって、三年生なんだから。ねっ?」 山辺教諭は、優しくさとす。 涼子のほうは、後ろからでも見て取れるくらい、周章狼狽していた。 「あっ……。すいませんっ! 気づいたら、うとうとしちゃってて……。わたしっ、気合い、入れますんでっ」 そう口にすると、両手で、自分の頬を二度、強く打ったのだった。ばちんばちん、という乾いた音が、小気味よいくらい教室に響いた。 山辺教諭は、そんな涼子の体育会系っぷりに、あらあらと、半ば呆れたような顔をする。が、すぐに慈悲深い微笑みを見せ、授業を再開した。 実のところ、香織は、その時点ですでに衝撃を受けていた。なにしろ、香織の知っている涼子は……。ほかの誰より真剣に、また積極的に、授業に臨む生徒だった。挙手しての質問や回答といった、授業中の発言回数の多さにおいては、クラスで頭ひとつ抜けているだろう。もしかすると、教師たちの、涼子に対する好感度の高さは、生徒会長と同等か、あるいはそれ以上かもしれない。その涼子が、あろうことか、授業中に居眠りだと……? 青天のへきれきといっていい。 ところが、それだけでは終わらなかったのだ。 それから、十五分ほど過ぎた時である。 山辺教諭は、突然、嘘みたいな大声を発した。 「ちょっと! 南さんっ!」 香織は、きもを潰した。クラス全体に、緊張が走った。 一拍遅れて、涼子の背中が、びくりと跳ねた。どうやら、また眠っていたらしい。 教諭の顔には、先ほどと違って、強い怒気が表れていた。つり上がった目じりと、ぴくぴくとけいれんを起こしている頬。普段の柔和な表情からすると、その顔もまた、冗談のように見えてならなかった。彼女は、絞り出すような声で言う。 「もういいですよっ。わたしは、二度と、あなたのことを信用しませんからねっ。そんなに眠くて仕方ないなら、どうぞ、好きなだけ、そうやって寝ていなさいっ!」 のけぞった涼子の背中が、なんとも痛々しい。今や、狼狽を通り越して、ほとんどパニックに陥りかけているように思われた。涼子は、勢いよく椅子から立ち上がった。 「すっ、すいませんっ! わ、わたしっ、廊下で、立ってます!」 言い終わるが早いか、自分の椅子も机も弾き飛ばすようにして駆け出し、ばたばたと教室から出て行く。 山辺教諭は、その後もしばらく、わなわなと肩を震わせながら、放心したように口を利けないでいた。 どう考えても、山辺教諭の憤りぶりは、尋常ではなかった。そもそも、この古文の授業で、居眠りをする生徒など、これまでにいくらでもいたのだ。だが、たいていの場合、それらの生徒たちは見過ごされてきた。それが、今回は大きく違った。南涼子だから、だ。可愛い教え子である涼子だからこそ、山辺教諭は、上空から落とされるような失望を味わったのだろう。そのことによる激しい怒りが、彼女を鬼に変えてしまったのだ。 しかし、香織は、それ以上、山辺教諭について思いを巡らすことはなかった。次の瞬間には、もう、廊下に飛び出した涼子のほうに、意識が完全に移っていたからである。 南涼子を南涼子たらしめている、最大の要素。それは、愚直なまでの真面目さ、にほかならない。その涼子が、授業中に居眠りをする。しかも、二度も。衝撃的というより、もはや、自然の摂理に反することが起こったような、そんな印象を受ける。 おそらく涼子は、夜、布団に入っても、ろくに睡眠の取れない体になっているのだろう。極度のストレスによって、自律神経とか、そういう機能が、完全に狂っている状態なのだ。だから逆に、日中でも、体が睡眠モードに切り替わりうるし、もし、そうなると、溜まりに溜まった眠気が猛然と襲ってくる。ほとんど体力の残っていない今の涼子にとって、その睡魔に打ち勝つことは、崖をよじ登るよりも難しい。その結果、眠るというより、半ば気絶するように意識が暗転してしまう。きっと、そんなところだろう。 とにかく、今の涼子が、生きるしかばねのごとき健康状態にあることだけは、確実といえる。そうでなければ、あの涼子と、授業中の居眠りという行為が、結びつくわけがないのだ。まさか、何者かが、涼子に睡眠薬を盛ったとか、そんなことはあるまい。 その時、香織は、はっきりと悟ったのだった。現時点ですでに、涼子は、学校という境界線の、ぎりぎりのところまで追い込まれている状態なのだ、と。つまり、これ以上、その身を外へと押し出す力が働けば、もう、学校には留まっていられなくなる可能性が高い、ということ。それを思うと、否が応でも、ひとつの懸念が脳裏に浮かぶ。あの、よこしまな後輩たちが、どう出るか。もし、くだんの映像を端緒にした、涼子への逆風が、学校中で吹き荒れるようなことになったとしたら……。 おそらく、涼子は、その時……、学校を飛び出してしまうに違いない……。そう確信するに至り、香織は、茫然自失の状態に陥った。 気づけば、思考という思考が停止し、感情が麻痺し、そればかりか身体感覚までもが失われていた。 自分の内側の世界が、空洞と化していることを感じる。 が、間もなく、のどをかきむしりたくなるような感覚を抱いた。その感覚の正体が、激しい焦燥感であることに気づく。 意識の中心から急速に膨らんでくる、烈々たる一念。 涼子が学校を去る、その前に、先手を打たなくては……。 香織の脳裏では、早くも、結論めいたものが、ぼんやりと形成されつつあった。 明日だ……。明日、涼子をどこかに呼び出す。そして、涼子との関係に、自分の納得のいく形で、決着をつける。それしかない……。 今。 夜の静けさが耳につく。 香織は、勉強机から上体を起こした。椅子の背もたれに背中を預け、まぶたを閉じる。 考えれば考えるほど、結論は、揺るぎないものになっていく。 近い将来、涼子が、学校からドロップアウトするという事態が、現実味を帯びてきた以上、それに備えるのは当然のことである。つまり、涼子との今生の別れが、すぐそこまで迫っている、という前提で、行動を起こさなくてはならない。計画の大幅な変更だ。もはや、涼子に対して、次はこんなことをする、その次はこんなこと、そのまた次は……、などと悠長に考えている場合ではないのだ。次が、最後の機会。そう見るべきだろう。 だとすれば、選択の余地はない。 日時は、明日の放課後だ。涼子を連れ込む場所は、体育倉庫の地下をおいてほかにない。そこで、涼子との関係に、自分の納得のいく形で、ピリオドを打つ。簡単にいえば、思い残しのないよう、涼子を、なぶり尽くすのだ。 むろん、今の涼子の健康状態を考えれば、それが、いかに無茶なことであるかは、充分、承知している。まず間違いなく、涼子は、心身ともに壊れ、人間らしさを完全に失い、いわば人の形をした、ただの物体と化すだろう。そして、そうなった時点で、涼子の残りの高校生活は、幻のものとなる。その翌日から涼子を待っているのは、鬱々たる病床の生活である。それが、どのくらいの期間にわたるかは、誰にもわからない。最悪、涼子が、健康的な暮らしを取り戻す日は、二度とやって来ないかもしれない。そんな涼子の運命を思うと、いささか良心の呵責を感じることも、また事実だ。けれど……。 もう、やむを得ないのだ。なんといっても、自分にとっては、そうすることが、残された唯一の道なのだから。もしも、未練を残したまま、涼子と離れ離れになったら、こちらの気がおかしくなってしまう。相手のことより、自分のことを考える。そんなのは、人間ならば、当たり前の話である。 やはり、結論は、ただひとつ。 明日、涼子との物語に、自らの手で幕を引く。悲劇のヒロインたる南涼子には、空前絶後のバッドエンディングを迎えさせた後に。 香織は、ふうっと息を吐いた。 それにしても、明日で最後だと思うと、なんとも寂しい限りである。 今、振り返ってみれば、涼子を辱める舞台を、バレー部の練習場という、衆人環視の場に移したことが、そもそもの間違いだった。現場に居合わせる人間の数が多ければ多いほど、不測の事態も発生しやすくなる。自分は、どうして、そのリスクに、ちゃんと目を向けなかったのだろう。その自分の愚かさのせいで、涼子を好きにできる虹色の日々は、残すところ、あと一日となってしまったのだ。 だが、悪いことばかりかというと、そうでもない。 明日の、最後の舞台を前に、しっかりと役者を揃えられたのだから。 ラストステージでは、五人で協力し合って、どでかい花火を打ち上げてやる。 五人で……。 あれは、一週間ほど前のことだ。体育の授業中、香織は、滝沢秋菜に働きかけ、彼女と手を結ぶことに成功した。そして、その後すぐ、こう思った。もう一人くらい、仲間に引き入れたい、と。涼子に対して、絶望という名の外壁を、もう一枚、築くように。問題は、その人選だった。そこで、香織は、涼子の視点に立って考えた。涼子にとって、恥ずかしい姿を見られる相手として、最悪の部類に入るのは、どんな生徒だろうか……? とりあえず思い浮かんだのは、バレー部の後輩のうち、涼子自身が、とりわけ可愛がっている部員、という人物像だった。なかなか、いい線を行っている気がした。また、それにぴったりの人物も、きっといるはずだと直感した。しかし、バレー部の部員を、仲間に誘うことの意味を考えると、気持ちにブレーキがかかった。バレー部というのは、立派な一つの組織である。その一員に、キャプテンを裏切るよう、裏工作を仕掛けるのは、組織の結束に、亀裂を生じさせようとする行為にほかならないのだ。一歩間違えれば、バレー部全体を敵に回すことになりかねない。そんな危ない橋は、渡るべきではないと判断した。そうして、バレー部の部員は、対象から外すことにし、ふたたび、ターゲットを絞り込む作業に没入した。だが、その作業は、難航を極めた。そのため、香織は、人選について、石野さゆりと竹内明日香の二人に相談することに決めた。そして、その日の放課後、校舎内で落ち合った、石野さゆりと、まず、話し合いの場を持った。香織としては、さゆりが、本領発揮とばかりに、悪知恵を働かせてくれることを期待していた。しかし、後輩は、いきなり、そんなことを言われても、と繰り返すばかりで、ちっとも役に立たなかったのである。その展開に、香織は、大きく落胆させられた。残るは、竹内明日香だったが、彼女のほうは、なにしろ、あの、ちゃらんぽらんな性格なので、相談相手としては、あまり期待が持てなかった。だが、それでも一応、さゆりを引き連れて、明日香のいる体育館へと向かった。体育館に着いた時、バレー部の本格的な練習は、まだ始まっていなかったこともあり、明日香は、簡単につかまった。香織は、明日香に、ダメもとで意見を聞いた。 ところが。 明日香の口からは、予想に反して、目からうろこが落ちるような回答が返ってきたのである。 涼子のファン……。なかでも、ファンレターを手渡すくらい、熱烈な……。 どうして、自分は、その発想に行き着かなかったのだろう。そんな茫漠たる思いが浮かんで、消えた、その直後のことだった。血の沸騰するような感覚を覚えた。同時に、明日香の背後には、後光が射してさえ見えた。ワンダフル。ファンタスティック。マーベラス。とにかく、素晴らしい、という意味の英単語を、思いつく限り、明日香に対して浴びせてやりたい気分になったが、人目のある場所だったので、それは控えておいた。その代わり、明日香の両手を、ぎゅっと握り締めようとした。が、そこで、まだ大きな課題が残っていることに思い至った。明日香が示した、その人物像に当てはまる生徒を、どうやって探し出すか。涼子のファン、というだけなら、放課後、体育館に来れば、それらしき生徒たちの姿が、嫌でも目に入ってくる。だが、求めているのは、涼子に、ファンレターを手渡すなど、直接的な行動を起こすくらい、本気度の高いファンなのだ。そうした生徒の、顔や名前といった情報を、香織は、何一つとして持ち合わせてはいなかった。だから、そのことを口にした。 すると、明日香は、ふふふっと笑って、こう言った。 ひとりだけ、知ってるんだよね……。 そうして、明日香の口から、ある生徒のエピソードが語られ始めた。 明日香が、バレー部のマネージャーの任に就く形で、部内にもぐり込んでから、十日ほどが過ぎた頃のことだという。 午後六時前後。同じく体育館を練習場としている、バスケット部も、卓球部も、その日の練習を切り上げた。だが、強豪校としての伝統を誇るバレー部だけは、例外的に練習時間が長い。 バレー部の練習が終了したのは、普段と同様、午後七時を回った頃だった。 それから、十数分後。 体育館フロアに残っているのは、一年生の部員たちと、それに、駆け出しのマネージャーである明日香だけだった。 一年生の部員たちが、フロアのぞうきんがけや、器具の後片づけなどで、せかせかと動き回っている。明日香は、そんな彼女たちの様子を横目に見ながら、練習日誌に、その日の記録をつけていた。 その時、フロアの出入り口の外、館内通路から、二、三年生の部員たちの、奇妙なざわめきが聞こえてきた。 「あれえっ? あの子、なに……?」 「ホントだ……。何部の子だろ……?」 「みんなに、置いていかれちゃったのかな」 「ねえっ、きみ。どうしたのー? うちの部活の誰かを、待ってんのー?」 「なんか、可愛いんだけど」 それらの言葉が、何とはなしに気になって、明日香は、館内通路に出て行った。 そして、そのまま、声のするほうに、足を向けた。 目の前に、すでに制服への着替えを終えた、二、三年生の部員たちが、十人ばかり立っている。彼女たちが、一様に、向こう側、玄関のほうを向いているので、明日香も、そちらに目をやった。すると、七、八メートルほど前方に、小柄な生徒の姿が見えた。どこからか迷い込んできた、近所の子供のよう。それが、その生徒の第一印象だった。とても高校生には見えないほど、外見が、とにかく幼いのだ。おそらくは、一年生だと思われた。その生徒が、なにやら、遠慮がちにこちらをうかがっている。 明日香も、ほかの部員たちと同じく、怪訝の念を抱いた。この時間、体育館に残っているのは、バレー部の部員だけのはずである。それ以外の生徒が、いったい、そんなところで、何をしているのか。 そう思っていると、その生徒が、出し抜けに、こちらに向かって駆けてきた。 そして、部員たちの前で、ぴたっと立ち止まった。 いや、というより、彼女は、あるひとりの部員の前で、足を止めたのだ。その部員とは、ほかならぬキャプテンの南涼子だった。 一同の視線が、その二人に集中する。 その小柄な生徒の様子は、明らかにおかしかった。じっと何かに耐えているような、悲壮感の漂う顔つき。それに、彼女の柔らかそうな頬は、いかにも乙女じみた桜色に染まっている。 一方、涼子のほうは、戸惑うように、自身の横にいる部員と、視線を交わし合う。だが、そこは、やはりキャプテンらしく、おおらかに対応した。おしりを後ろに突き出すようにして、大きな身をかがめ、その小柄な生徒と、目線の高さを合わせる。それから尋ねた。 「どうしたの・か・なっ?」 こちらからだと、涼子の表情は確認できないが、あの、透明感あふれる笑顔を向けているのが、目に浮かぶようである。 間もなく、その小柄な生徒は、バッグのポケットから、何かを取り出した。 それは、薄いピンク色の封筒だった。 「先輩……。これ、受け取ってほしいんです……」 消え入りそうな声で言い、彼女は、両手に持った封筒を、こわごわとした手つきで涼子のほうに差し出す。 突然の出来事に、涼子も面食らったようで、一刹那の間だったが、その体が固まった。 「えっ。これ、わたし個人に……?」 愚問だろう。 その小柄な生徒は、こくんとうなずく。不安でたまらないらしく、彼女の顔は、泣きべそをかいたように歪んでいる。もし、ここで、涼子に冷たくあしらわれたら、たちまち泣き出してしまいそうに思われた。 涼子は、困惑から立ち直った。 「わかった。それじゃあ、家に帰ったら、ちゃんと読ませてもらうねっ」 そう明るく答え、封筒を受け取る。 その小柄な生徒の顔に、ぱっと安堵の表情が浮かんだ。そのうえ、ほっとしすぎたのか、彼女の大きな瞳が、じんわりと潤み始める。 涼子は、小さな子供をあやすように、その彼女の頭を、ぽんぽんした。涼子にとっては、何気ない行為だったはずだ。が、涼子から、そんなふうにされたことで、彼女は、心臓の乱調をきたしてしまったらしい。ただでさえ、桜色だった彼女の頬が、ぶわっと赤みを増し、またたく間に、顔全体が、ゆで上がったように真っ赤になった。 彼女は、血がのぼった顔を隠すように、慌てて身をひるがえす。そして、脱兎のごとく逃げ出した。 一同は、走り去る彼女の後ろ姿を、黙って見送る。 つかの間、意味深な沈黙が流れる。 しかし、彼女が玄関の外に出た、そのとたん、部員のひとりが、嬌声を発した。 「きゃああああああ」 それが呼び水となって、部員たちは、にわかに色めき立った。 「見っせろっ! 見っせろっ!」 「先輩っ。ちょっと読ませて下さいよっ」 何人かの部員が、涼子の体に飛びつく。 だが、涼子は、首を横に振る。 「だめ。こういうのは、ほかの人が見るもんじゃないのっ」 きっぱりと言い、貰った封筒を、自分のバッグにしまい始める。 「ええー、いいじゃないですかあ……。なに書いてあんのか、めっちゃ気になるぅ」 二年生の部員が、なおも食い下がる。 「ちっともよくないっ。わたし、家に帰るまでは、この封筒、絶対に開けないから」 涼子の意思は固い。 部員たちも、封筒の中身を見るのは、無理だと悟ったようだった。とはいえ、それで、騒ぎが沈静化するはずもない。三年生の部員が、涼子に、冷やかしの言葉を浴びせる。それに合わせて、部員たちは、口々に、涼子を、はやし立て始めたのである。 渦中の涼子は、やれやれ、という仕草をしてみせる。 明日香は、その光景を、後ろから、ただ眺めていた。それから、ほどなくして、フロアの出入り口へと引き返した。フロア内に戻ると、ある予感を抱いた。この出来事は、いつかきっと、何らかの形で役に立つ……。自然と微笑みが湧いてきた。 ……香織は、そのエピソードを聞きながら、激しい胸の高鳴りを覚えていた。 明日香は、すこぶる得意げに言う。 「りょーちんが、あの子から貰った手紙にはねえ、ぜーったい、ぜーったい、『先輩のことが、大好きです』とかぁ、『あたしと、付き合ってください』とかぁ、そういう言葉が、書かれてたの」 おそらく、実際にそうだったのだろうと、香織も確信する。ファンレターというより、ラブレターなのだ。その子の、涼子に対する思いは、憧憬というより、恋心と呼ぶほうがふさわしいに違いない。だが、あえて疑問を呈してみる。 「でも……、でもだよお? 女同士じゃん? そんな告白みたいなこと、書くかなあ?」 すると、明日香は、ぽかんとした顔になった。その後、ふっと鼻を鳴らして笑う。 「だって、あたしだってぇ、今までに……」 そう口にしながら、なにやら、右手の指を折り始める。右手では数えきれず、左手の指に移った。 「……もう、八回、いや九回かな。この学校の生徒からぁ、そういう告白の手紙、貰ったもん」 香織は、ぐっと言葉に詰まった。 「だからぁ、まあ、言っちゃえば……、よくある話、なんじゃなぁい?」 そうなのだ。南涼子も、また、目の前にいる竹内明日香も、同性である女子生徒からもモテてしまう、という点では共通しているのだ。香織にとっては、まるで、別世界の話のようであるが。ただ、今は、そのような事柄に対して、羨望めいた感情を抱いていても、仕方がないだろう。 「そっか、そっか。明日香が、経験則から言うなら、間違いないね。その子が、南さんに渡した手紙には、告白の言葉が書かれていた、と。……となると、あとは、どうやって、その子に会うか、だよね」 香織は、気を取り直して言う。 「ああ、それなら、簡単だよぉ。その子、毎日のようにぃ、放課後、体育館に来てるからさ。きっと、りょーちんのことが、好きすぎるんだろーねー」 明日香は、事も無げに答える。 「えっ、そうなの!?」 つい、声が大きくなる。 香織は、明日香から、その生徒の外見的特徴を詳しく聞き出した。そして、今度こそ、明日香の両手を、ぎゅっと握り締めた。 その翌日の放課後。 香織とさゆりは、体育館の二階のギャラリーで、その生徒を発見した。一目でわかった。その場で、彼女と接触した。彼女は、足立舞という名前だった。 今。 スマートフォンの画面には、午後、十時半過ぎの時刻が表示されている。 香織は、勉強机の上で、両手の指を組んだ。 時々、思うことがある。 明日香は、ああ見えて、意外と、思慮深い人間なのではないか、と。たとえば、涼子を辱めている時。一見、気まぐれに振る舞っているように見える明日香だが、その実、自身の言動が、涼子の心理に、というよりは、同い年の女の子の心理に、どういう影響を与えるかを、きちんと計算しているようなフシがある。こういう言葉を浴びせられたら、さぞかしプライドが傷つくことだろう。あるいは、体のこの部分に触れられたら、羞恥心と同時に、強烈な劣等感をも抱くに違いない。そのような、悪意に満ちた計算である。つまりは、相手の身になって物事を考える、という思考法を、それなりに得意としているような気がするのだ。そんな明日香だからこそ、五人目の仲間候補の絞り込みに際しては、涼子にとっての、最悪の人選として、足立舞の存在を思い浮かべることができた。香織は、そう推量する。 ひょうきんなようでいて、時に、ぞっとするほどの冷徹さをかいま見せる。それが、竹内明日香という女だ。どうにも、つかみどころのない、不思議な友人である。よくよく考えれば、自分は、彼女のことを、ほとんど何も知らない、という気がしてくる。……そもそも、である。なぜ、彼女は、香織たちの仲間に加わろうと思ったのか……? 刺激に飢えていたわけでもあるまい。なにしろ、歓楽街を歩けば、男たちが、引きも切らず声をかけてくるような、美貌の持ち主なのだ。面白おかしいことなど、学校の外に、山ほど転がっているはずである。にもかかわらず、南涼子を罠にかけて服従させるなどという、香織の、おどろおどろしい計画に、参加の意向を示した。しかも、そればかりか、涼子に付け入る材料を探すために、バレー部のマネージャーとして、日々、部員たちと行動を共にするという、途方もなく大変な役回りを、あっさりと引き受けてくれたのだ。 彼女を、そこまで突き動かした、根本的な動機は、なんだったのか……? 今までずっと、胸の奥底にわだかまっていた疑問である。だが、それについて、本人に尋ねる気にはなれない。なんとなく、その話をすると、気まずいことになりそうな予感がするからだ。お互い、相手に深入りするのは避ける。そうして、ほどよく距離感を保ってきたからこそ、自分と彼女は、それなりにうまく付き合ってこられた。今となっては、そう思う。 何はともあれ、その明日香が推薦してくれた足立舞のことだが、彼女は、結果からいうと『落ちた』のだ。いや、正確には、まだ、そうと決まったわけではないのだけれど、あれは、落ちたも同然だった。 二日前、つまり、バレー部の練習場で、涼子を、徹底的に辱めた、あの日。 太陽もだいぶ西に傾いた頃、香織とさゆり、それに秋菜と舞を加えた四人で、学校を出た。その後の出来事である。 四人は、バスで学校の最寄り駅に移動した。それから間もなく、駅のすぐ近くにある、喫茶店に入った。 テーブル席に腰を落ち着けてから、舞を除いた三人は、本性を露わにし始めたのである。まず、バレーコート上における涼子の痴態は、香織たちの強要によるものだったことを、舞に、それとなく明かした。それにより、いくら頭の弱そうな一年生といえども、自分の置かれている状況を理解したようだった。あろうことか、憧れの南涼子を虐げる者たちと、自分は、仲良くテーブルを囲んでいるのだ、と。しかし、舞は、怒って席を立つでもなく、戸惑いの様子を見せながらも、三人の話を聞き続けた。 ほどなくして、話題は、次、どういう方法で、涼子を辱めるか、という計画のことに移った。ただし、三人とも、性的な内容に関しては、暗にほのめかすような表現にとどめた。むしろ、そのほうが、舞の好奇心をかき立てるのには、効果的だろうと判断したからだ。 そうして、店に入ってから、一時間も過ぎた頃である。 舞は、とうとう、甘えるように言い始めた。 「教えてください。先輩たちは、南先輩に、どんなことしようとしてるんですかぁ? 教えてくださいよぉ」 何か恐ろしい答えを期待しているような、彼女の顔。 香織は、それを見て、舞が落ちたことを確信し、その上でなお、さあ、どんなことしよっかあ、とあやふやに返したのだった。さゆりと秋菜も、手応えを感じているかのように、にたにたと笑っていた。 そして、その店で、舞と連絡先を交換した。 あれから、二日。 香織は、窓の外の暗闇を、何気なく眺めた。 時間的には、舞も、まだ起きているはずだ。明日のことは、すでに、舞に伝えてある。放課後、体育倉庫の地下で、涼子の過激な姿を鑑賞できる、一般非公開のイベントを行う予定である、と。こちらとしては、今夜のうちに、舞から、なんらかの返事を貰いたいところなのだが……。 その時、勉強机の上のスマートフォンが振動した。メールの着信だ。 画面を確認してみる。 送信者は、足立舞。 本文には、こう書かれていた。 『明日、ちょっぴり怖いかもだけど、イベント楽しみにしてますo(≧▽≦)o』 香織は、その画面を、じっと見つめた。しばらく、そうしていた。 徐々に、腹がひくひくとし始める。ははっ、はっ、はははっ、と笑いが漏れた。 南さん……。あんたって人は、本当に、ツイてないねえ……。 腹を抱えて、椅子に座ったまま、両足で床を踏み鳴らす。 涼子の運のなさが、おかしくてたまらなかった。滝沢秋菜が、香織たちの側に付いた、それだけでも、涼子の不運ぶりは、相当なものである。ところが、それでは終わらず、今度は、足立舞までもが、涼子の敵と化してしまったのだ。南涼子……。まるで、不運が服を着て歩いているかのような女。なんと哀れな。今や、涼子の存在そのものが、何かのジョークのように思えてくる。 それにしても、舞は、明日、体育倉庫の地下で行われるイベントが、どれだけ陰惨なものになるか、ちゃんと想像できているのだろうか。……いや、充分、わかっているに決まっている。わかっていながら、それに参加したいという意思を示したのだ。あのエロガキめ。 確定した。 明日、南涼子は、五人に取り囲まれることになる。むろん、着ているものを、すべて脱がされたうえで……。その恥辱は、並大抵のものではあるまい。それに耐える涼子の様子を、香織は、脳裏に思い浮かべてみた。いかにも極限状況に置かれた人間らしい、がちがちにこわばった表情。どことなく焦点の合わない眼差しが、何もない宙に向けられている。その場の誰とも視線を絡ませたくない、という気持ちの表れなのだ。憎き香織たちを睨みつけようという気概など、かけらも湧いてこないらしい。情けない限りである。そして、全裸にさせられた時の、お決まりのポーズを取っている。乳首を隠すことは諦め、両の手のひらを、恥部に、というより、陰毛の茂る範囲に、ぴたりと押し当てた、あの、乙女心を全開にしたポーズである。長い手脚は、小刻みに震えており、それに合わせて、乳房やおしりの肉がぶるぶる揺れている。かつてないほどの精神的苦痛に神経を蝕まれているせいで、体中の毛穴から、あぶら汗が噴き出しており、きつくなった体臭が、むんむんと立ち上っているかのようだ。その姿の惨めさ、下品さ、いやらしさ……。 あっ、と思った。 香織は、右手を、パンツの中に突っ込んだ。軽くまさぐってみる。早くも、体から滲み出したもので、パンツが濡れていた。 いけない、いけない。ここ最近は、涼子を辱めることを想像しだすと、すぐに体が反応を起こしてしまう。 勉強机の椅子から立ち上がり、部屋の反対側に移動した。タンスの引き出しから、バスタオルを取り出し、それを、ベッドのシーツの上に広げる。それから、クローゼットの扉を開けた。暗がりの奥から、ある衣類の入った、チャック付きの大きなビニール袋を引っ張り出す。それに入っているものは……、滝沢秋菜の体操着のシャツだった。もちろん、家に持ち帰ってから、一度も洗濯はしていない。 香織は、そのビニール袋を両手に持った。 これから行おうとしていること。それは、ある種の一線を越えている。そんなことは、百も承知だ。しかし、気が変わりはしない。そもそも、自分は、すでに、この体操着を何回も『使って』いるのだ。 それを抱えて、ベッドに戻る。 たった今、敷いたばかりのバスタオルの上に、腰を落とした。 パジャマの上着のボタンを外し、ブラジャーをたくし上げる。パジャマのズボンとパンツは、脚から抜き去ってしまう。 これで態勢は整った。 香織は、ビニール袋のチャックを開けた。 その瞬間、むっとする臭気が鼻を突いた。部屋中に、臭いが充満しそうである。その臭いに包まれているだけで、もう、頭がくらくらとしてくる。 ビニール袋の中から、体操着のシャツを取り出した。 赤く縁取りされた丸首の部分は、そこに染み込んだもので、白く、がびがびになっている。 香織は、躊躇することなく、その部分に鼻を押しつけた。思いっ切り息を吸い込む。鼻腔を突き抜ける、猛烈な腐臭。嗅覚への刺激が強すぎたせいか、まるで、脳細胞がとろけるような感覚を味わう。興奮のあまり、自分の口から、世にも下品なうなり声が出た。涼子の怒号を、よく、獣じみていると思うが、それより何倍も女らしからぬ声音だった。 一度、体操着を鼻から離し、その生地をぴんと張った。片方の肩口のところに、三センチほどの、黄土色の線が確認できる。香織は、うふふっと笑いながら、その部分に頬ずりした。こんな汚れですら、愛おしいと思える。 それから、ごろりと横になった。 ふたたび、体操着の赤い丸首の部分で鼻を覆う。鼻がねじ曲がるほどの悪臭だというのに、それでいて、なぜか、安心感を与えてくれる、その臭い。ただ、ひとつ、問題があった。この体操着は、体育の時間、滝沢秋菜が身に着けていたものだということ。それを考えると、なんだか、あの、いけ好かない滝沢秋菜の体臭まで混じっているようで、気持ちが悪くなってくる。だが、そのことは、なるべく意識しないようにし、今、自分が嗅いでいるのは、純然たる涼子の臭いなのだと、自分自身に言い聞かせる。そうして、その臭気を貪るように嗅ぎ続けた。 誰にも言えない。滝沢秋菜の体操着を、こんなふうに使っていることは……。 香織は、すっかり火照った性器に、右手を当てた。そこは、もはや、お漏らしをしたかのように濡れていた。我ながら、浅ましい体だなと思う。だが、押し寄せる興奮の嵐の前では、どうでもいいことだった。大陰唇の全体をこね回すようにして、性器への愛撫を開始する。直接、クリ○リスに触れることはしない。少しずつ快感を高めていくのが、香織のやり方なのだ。 しんしんとした夜の静けさに、香織の切なげな声が滲む。滝沢秋菜の体操着は、口もとを覆う役割をも果たしていた。 ねえ、南さん……。あたしと、さゆりと、明日香。あなたにとって、この三人は、どんな存在? ヘドロの塊みたいな、醜すぎる生き物? うん、うん、わかる、わかる。じゃあ、そんな腐りきった三人の前で、素っ裸になるって、どんな気分だった? 思い出すだけで、気が狂いそう? うん、うん、それも、よーくわかる。でも、ごめん……。明日は、もう二人、こっちに加わるからね。それも、ただの二人じゃないよ。 滝沢秋菜。 涼子が、苦手意識を抱いている生徒である。 明日の宴では、秋菜を、どう活用するかが、最大のキーポイントとなるだろう。 そういえば、その秋菜は、この前、足立舞を連れて入った喫茶店で、こんなことを言っていた。 涼子と同等の立場に堕ちた、芝居を打つ……。 「吉永さんたちは、次に、わたしを標的として狙ってる。南さんは、そう思い込んでるんでしょう。だったら、わたしも、堕ちたことにしようよ。つまり、吉永さんたちの前で、わたしと、南さんは、哀れな者同士、寄り添い合うっていうシチュエーションになるね。南さんだって、人間。自分ひとり、恥ずかしい目に遭わされるより、誰かと一緒のほうがいいって、絶対に思うんだから。でも……、結局、服を脱ぐことになるのは、南さんだけ。そうなると、南さんの頭の中は、『なんで、自分だけなの?』って思いでいっぱいになる。その思いが爆発したら、南さん、とんでもない醜態をさらしてくれそうで、わたし、それが見たくてたまんないのお」 秋菜は、そう熱っぽく語り、とろんとした三白眼の目をするのだった。その顔の、怖ろしかったこと。絶対、敵に回したくない。心の底から、そう思わされる女の顔が、そこにはあった。 その一場面を思い出し、香織は苦笑した。秋菜の底無しの悪意には、身震いすら覚える。だが、それでこそ、自分の見込んだ人物。 それと、もうひとり。 足立舞。 涼子に、告白の手紙を手渡したと思われる生徒である。 明日、香織たちの手引きにより、涼子と舞は、『感動の』対面を果たすのだ。先輩と後輩。堂々たる体格を有するバレー部のキャプテンと、小動物のように小柄な生徒。好かれている側と、好いている側。そんなパワーバランスは、徐々に逆転していく。涼子の衣類が、一枚一枚、はぎ取られていくにつれて……。 全裸になり、文字通り、手も足も出ない涼子と、その涼子に対して、恋心を抱く舞。その二つをくっつけ合わせたら、いったい、どんな化学反応が起こるのかと、香織は、わくわくしている。 滝沢秋菜と足立舞という、涼子にとって、赤裸々な姿をさらす相手としては、もっとも嫌な部類に入るであろう二人の生徒を、仲間に加えてやった。 吉永香織。石野さゆり。竹内明日香。その腐りきった三人に加え、滝沢秋菜と足立舞。涼子に恥辱を与えることにおいて、その五人の組み合わせは、まさに天の配剤だという気がする。明日は、その五人の手が、触手のように伸びて、涼子の肉体に絡みつくのだ。それを思うと、興奮と快感は、一段と高いところへ押し上げられた。 せわしなく性器を愛撫する右手の動きに合わせて、熟し切った果実が潰れるような、卑猥な音が鳴り続けている。 明日は、涼子に、どんなことをしよう。 家畜以下。涼子を、そういう存在に貶めたいのだ。 とりあえず、恒例となっている、体毛の生え具合のチェックは欠かせない。滝沢秋菜と足立舞も、その場にいることから、涼子が、これまで以上に激しい拒絶反応を示すのは、火を見るより明らかだ。だからこそ、やりがいがある。 それが終わった後は、涼子に、この世の地獄と呼ぶにふさわしい責め苦を味わわせるつもりだ。 香織には見える。 涼子が、万力で頭蓋骨を締め上げられているような、そんな凄絶を極めた形相で、恥辱に身悶えているところが。 いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ! 明日は、涼子のあの、耳をつんざくような絶叫が、陰鬱な体育倉庫の地下に、幾度、響き渡るだろうか。 そうして最終的に、涼子は、地面に崩れ落ちて動かなくなり、ただの汚らしい肉塊と化すのだ。それが、涼子の高校生活、最後の姿である。 ああ、愉快、愉快。 香織は、けたけたと笑う。 しかし、次の瞬間、ぽつりと思った。 なんで、こんなことになったんだろう……。 性器を愛撫する右手を、ふと止めた。 どうして、自分と涼子の関係は、こんなことになっちゃったんだろう……。 その答えが、自分でも不思議なくらい判然としなかった。 涼子に夢中になり始めた頃、自分は、どんな思いで日々を過ごしていたのだったか。 高校を卒業するまでに、何がなんでも、涼子と仲良くなりたい。進路よりも何よりも、そのことが大事だった。まだ、あと一年ある。しかし、あと一年しかないともいえた。今日も、涼子と話すことができなかった。一日一日が、そうして削られていく、そんな焦燥感を覚えていた。めでたく、涼子と仲良くなるのに成功したら、どうしよう。土曜、日曜も、涼子は、部活で忙しいのだろうか。自分の理想は、休みの日に、涼子と二人きりで遊ぶことだった。邪魔者は、みな消えればいい。涼子が、自分を、どこかに誘ってくれたなら、友達との旅行をキャンセルしてでも、必ず駆けつける。涼子と、ショッピングに行きたい。涼子の服を、自分が選んであげたい。涼子には、きっと、グリーンのスキニーパンツが似合う。なぜか、日頃から、そんな印象を抱いていたのだ。また、逆に、自分の服を、涼子に選んでもらいたい。買い物が終わったら、テラスのあるカフェに寄りたい。適当な飲み物と、それから、お互い違うパフェを注文し、テラス席に着く。涼子は、パフェを一口食べた後、とびっきりの笑顔で、『おいぃっしいっ!』と言うのだろう。その笑顔を見られるだけで、自分は、もう、ほかに何もいらないくらい、幸せな気分に浸れたはずだ。 本当は……、そういうのを、望んでいたのに……。 目から、涙があふれ出る。 自分は、それほどまでに、涼子のことを想っていた。けれども、待てど暮らせど、涼子は、自分にアプローチしてくれなかったのである。 ひどいよ、南さん……。 香織は、しゃくり上げる。 そういえば、ずっと前に一度だけ、涼子と、親密になれるチャンスがあったのを思い出す。 いつもより、だいぶ早く学校に着いてしまった、ある朝のことだ。自分の教室のある三階の廊下で、涼子と、ばったり出くわした。互いに、『おはよう』の挨拶を交わした。そのこと自体が、奇跡のように感じられた。その後、香織だけ先に、教室に入った。教室には、なんと、誰もいなかった。そして、もうすぐ、涼子がやって来るのは、確実なことだった。涼子と、二人きり……。その状況を想像し、気が動転した。気まずい、恥ずかしい、耐えられない。そんなふうに思った。それゆえ、香織は、教室を飛び出して、トイレに逃げ込んでしまったのだった。 あの時、自分に、もう少し勇気があったなら……。 いや、そんなことは関係ない。 問題は、涼子の側にある。 涼子は、社交的な性格の人間だが、香織は、残念ながら、そうではない。そのため、二人が親密な関係を築けるかどうかは、涼子の行動にかかっていた。涼子のほうから、香織に、がんがん声をかけてくるべきだったのだ。こちらが、ちょっと、うっとうしいなと感じるくらいに。現に、涼子は、滝沢秋菜に対しては、それを行っていたのだから。しかし、香織に対しては、それをしようとはしなかった。なぜか。香織のことを、取るに足らない存在だと見なしていたからに違いない。 悔しさと怒りで、体が熱くなる。 許せない……! 香織は、今一度、滝沢秋菜の体操着をつかみ直し、赤い丸首の部分に、鼻をごしごしとこすり付けるようにして、涼子の臭気を、めいっぱい嗅ぎ取った。それから、性器への愛撫を再開した。先ほどまでより、激しい手つきで。 今になって、ようやく、わかったことがある。 なぜ、自分は、涼子のことを、できる限り苦しめたいなどと思うのか。その最大の理由を、今さらながら理解した。 自分の心の根底には、涼子に対する被害者意識が根付いているのだ。 実際、自分は、被害者というべきだろう。 本来ならば、高校三年生という、青春、真っ盛りの一年間を、涼子と共に過ごせるはずだった。自分には、その権利があったと確信している。けれども、涼子は、その幸せな時間を、自分に与えてくれなかった。すなわち、自分は、涼子によって、かけがえのない幸福を、不当に『奪われた』のだ。 考えれば考えるほど、はらわたが煮えくり返ってくる。 もし、自分が、どこかの国の王女だったらと、香織は夢想した。王女たる自分を蔑ろにした、涼子の罪は重い。涼子には、自らの手で、厳しい処罰を加える。具体的に、何をするか。まだ、純潔を守っている涼子の、女の穴に、指を突っ込み、その場で鮮血を流させてやるのだ。そうすることができたら、どれだけ気分がすっとするだろう。 しかし……、現実世界において、香織は、王女でも権力者でもなく、ただの女子高生に過ぎない。もし、涼子の処女膜を傷つけたら、後々、犯罪者として断罪されるハメになることくらい、香織の頭でも、容易に想像がつく。(すでに、いくつもの犯罪行為に手を染めている気もするが、そのことは、あえて無視する。)明日を境に、涼子の人生は、大きく狂うことになるだろうが、自分は、その後も、真っ当な道を歩んでいきたいのだ。進学もしたい。いずれは、結婚もしたい。高い山がなくとも、深い谷がなければいい。ささやかながらも、幸せな人生。それを望んでいる。だから、涼子への復讐のせいで、一生を棒に振るなど、まっぴらごめんである。 だったら、後ろの穴なら、いいのだろうか……? 香織は、はっとした。 涼子の後ろの穴を、陵辱することなら、許されるのだろうか……? それを真剣に考えたことはなかった。 香織は、想像をたくましくする。 場所は、体育倉庫の地下だ。 その場にいるのは、香織たち五人と、饗宴の生贄たる涼子である。 涼子は、一糸まとわぬ全裸で立っている。香織は、その涼子の背後に陣取り、そこにしゃがみ込んでいる状態だ。 香織の視界を占める、涼子のド迫力の生尻。 まず、やるべきは、涼子の身動きを封じることだ。さゆりが、涼子の右腕を、明日香が、左腕を、がっちりとつかんだ。香織は、涼子に釘を刺す。何があっても、暴れたりしちゃダメだよ、と。 おそらく、涼子の口から、恐怖と絶望に満ちた声が漏れることだろう。 香織は、涼子のおしりの割れ目に、両手の親指を差し込み、その汗ばんだ肉塊を、左右にぐいっと押し広げた。その奥に覗く光景は、以前、目にしたことがあるので、網膜に焼きついている。だから、毛の生え具合も、また、穴の色さえも、鮮烈に思い起こせるのだった。密生林のごとく生えた、おびただしい量の縮れ毛。だいぶ色素の沈着が進んだ感のある、ねずみ色の肛門。いい機会なので、涼子のその、不浄の穴を、じっくりと観察する。しわは、何本くらい刻まれているだろう。ひくひくと収縮する様が、おぞましいまでに淫猥だ。直接、そこに触れたことはない。試しに、人差し指で、軽くつついてみる。案の定、べたべたとした感触だ。多少、汚いと感じるが、涼子のものなら許せる。香織が、構わないのだったら、涼子の意思など無視していいのだ。その窄まった穴に、人差し指をぴたりと当てた。そのまま、ゆっくりと中に押し込む。強い抵抗を感じるものの、なんとか、第一関節まで入った。 その時点で、きっと、涼子は、化鳥のような絶叫を発するに違いない。 だが、香織は、それで止めようとは思わない。もっと奥に……。人差し指の第二関節まで、穴に埋まった。直腸の壁が、指を、強烈に締めつけてきそうだ。指が痛いくらいかもしれない。それでも、気合いを込めて、さらに奥へと指をねじ込んでいく。 そのうち、涼子の身に、異変が生じ始めるものと予想される。全身のけいれんとか、そういう類のものだ。しかし、こちらは、すでに開き直っている。涼子が、意識を失って崩れ落ちるなら、それはそれでいい、と。そのため、怖いものは何もないのだ。 とうとう、人差し指の付け根の付近まで、涼子の体内に入った。 すると、どうだろう。その指は、塊にぶち当たるのではないか。時間が経てば、涼子の体から排泄される予定の塊である。もし、指先に、その感触があるなら、どうしてやろう……。 恐ろしく不道徳な考えが、頭に浮かぶ。 香織は、爪で引っかけるようにして、その塊の一部を削り取り、指をずずっと後退させた。その指を、涼子の穴から引き抜く。見ると、爪の間に、黒っぽいものが詰まっている。今や、生きるしかばねのごとく、健康状態が悪くなっている涼子のことだから、腸内環境も最悪に違いない。なので、香織のかき出した涼子の便は、すさまじい悪臭を放つことだろう。 香織は、四人の仲間たちにも、その臭いを確かめさせる。そして、最後に、汚辱に震える涼子の顔に、その黒っぽいカスをこすり付けてやるのだ。 そういう行為に及んでも、許されるのか。それとも、許されないのか。 また、仲間の目も気になる。たとえば、滝沢秋菜などは、香織のその行為を見て、どう思うだろう。なんという大胆さだと、感服の念を抱くか。それとも、この子は変態だと、どん引きするか。 明日は、その辺りの判断さえできなくなり、涼子に対して、暴走してしまいそうな気がしてならない。そんな自分自身が、正直なところ怖くもあった。 激しく性器を愛撫する、右手の動き。 いよいよ、絶頂が近づいてきた。膨張したクリ○リスが、大陰唇の上から、間断なく圧迫を受けており、その悶えるような快感に、腰が浮き上がっていく。もはや、体中の細胞が、獣のような本能に翻弄されている状態だった。 夜の静寂に響く、香織の淫らなあえぎ声。 明日は、覚悟してね、南さん……。あんた、骨の髄まで辱めてやるんだから……! わかっている。もう、自分の感情をごまかすのは、やめにしよう。自分の感情に、素直になろう。そうしたほうが、ずっと気持ちよくなれるはずだ。 絶頂に昇り詰める、その時、香織は、口もとを押さえる体操着越しに、くぐもった声を発した。 「ビダビジァン、ダビジュギィィィィィ」 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.