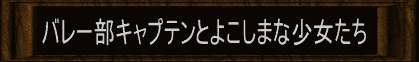
第二十一章〜邪悪な罠
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
過酷な状況だ……。南涼子は、そう強く感じていた。 予想外の形で、地獄の底に引きずり戻されてしまった。これから、裸にさせられ、悪魔たちの享楽の、生贄となる……。その暗黒に包まれた現実が、もう、眼前に迫っている。だが、まだ、諦めてはいない。とにかく、滝沢秋菜の呪縛を断ち切ればいいのだ。それを可能にする妙案をひねり出すために、今、頭の中では、思考がフル回転している状態だった。たとえ、どれだけ追い詰められても、最後まで、つまり、着ているものをはぎ取られるまでは、希望を捨てないと心に決めている。それと、決して忘れてはならないのが、いかなる時でも冷静さを失わないこと。吉永香織は、どのような策謀を張り巡らせているかわからない。この先は、きっと、ほんの小さな判断ミスを犯しただけで、邪悪な罠にからめ取られ、自分の立場は、最悪なものになる。そういう不吉な予感を、漠然と感じるのだ。そのため、何があっても、激情に駆られるままに行動を起こすような、早まったことだけはするまいと、自分自身に言い聞かせる。 ふと、涼子は、横にいる滝沢秋菜の顔を見た。 秋菜は、目が合うと、不快そうな視線を返してきた。おそらく、涼子だけが助かるのは、絶対に許せないが、それと同時に、涼子の仲間という境遇に置かれていることも、我慢のならない思いなのだろう。 吉永香織が、浮かれた声で言う。 「はいっ! 南さんも、引き返してきたことで、これから、めでたく、南さんと滝沢さんの共演による、世界一、過激なセクシーショーが開催されまーす。ぱちぱちぱちぱちぱちぃ」 自分で口にしながら、手を叩き始める。 竹内明日香と石野さゆりも、嫌味たっぷりに拍手を合わせた。 足立舞は、まるで、頼りになる大人たちを見るように、その三人の先輩に視線を向ける。 涼子と秋菜は、完全に、惨めなさらし者になっていた。 「さて、南さん。もう、いい加減、諦めは、ついたでしょ? すぐに、脱ぎ始めて。いつまでも、往生際悪く、服を着てると、裸になった時に、よけい恥ずかしい思いをするだけだからね。逆に、ぱっぱっぱっと脱いじゃって、堂々と裸を見せれば、全然、格好悪くなんてないの。そうして、南さんが、立派にお手本を示せば、滝沢さんも、緊張が取れて、脱ぎやすくなるのよ。滝沢さんのほうは、初脱ぎなんだから、やっぱり、ここは、『場慣れ』してる南さんが、先に、裸になってあげなさいよ」 香織は、すでに、自分たちが、完全に主導権を掌握したと確信しているようだ。 涼子は、スパッツに覆われた、両脚の太ももの外側を、ぎゅっと押さえた。 秋菜と一緒に、一糸まとわぬ姿をさらしている光景も、想像するだけで、全身に悪寒が走るくらい、気持ち悪く感じられる。だが、秋菜を含めた、この場にいる五人の注目を浴びながら、自分ひとり、着ているものを脱いでいき、全裸になるというのは、それ以上に、耐え難い状況だという気がした。 自分に残された時間は、あと、どれくらいなのだろう……? 我が身の自由を得るための、妙案が思い浮かぶまで、なんとかして、時間稼ぎをする必要がある。 「あっ。それとも、滝沢さんに、先に、脱いでもらうことにしようかなあ……。滝沢さんが、脱いだら、いくらなんでも、南さんのほうも、覚悟が決まるだろうし……。ねえ、滝沢さん、ここで、いい子であることを、行動で示してくれたら、あたしたち、あんたには、優しくしてあげないでもないよ? だから、思い切ってやってみない? あんたが先に、着てるものを全部、もちろん、ブラもパンツも脱いで、その、堂々とした立派な姿を、情けない南さんに、見せつけてやるの」 香織は、今度、秋菜のことを試し始めた。 秋菜は、即座に、頭を激しく横に振った。 「やだやだやだ……。どうして、わたしが、先に脱がなくっちゃならないの……? 吉永さん、そんな、ひどいこと言わないで」 いかにも、か弱い少女のような声で言いながら、すでに、裸にされてしまったみたいに、左腕で、胸のところを、右手で、恥部の辺りを押さえる。 秋菜も、涼子と同様、自分ひとり、脱衣して全裸になるという状況は、これ以上ない屈辱だと感じるのだろう。 それにしても、秋菜の嫌がりようは、涼子に比べると露骨すぎる。プライドの高さゆえだろう、辱めには耐えられないという情念が、非常に強く、それが、彼女の言動に、如実に表れている感じだ。そんな秋菜が、この場で、下着まで脱がされ、あまつさえ、体を触られるようなことになったら、金切り声を発して泣き叫ぶのではないだろうか。希代の加虐趣味者である香織が、秋菜のその狂乱した姿を見て、強い悦びを露わにしている光景まで、今から目に浮かぶようだった。 「そっかそっか……。滝沢さんも、先に脱ぐのは、無理っていうわけね。でも、だからったって、二人同時に脱ぎ始めるっていうのは、ショーとしての面白味が、半減しちゃう気がするんだよね。やっぱり、ストリップは、南さんなら南さんの時間、滝沢さんなら滝沢さんの時間って、じっくりと、一人ずつ愉しませてもらいたいし。どうしよう。どっちが先に脱ぐか、どうやって決めようかな……」 香織は、真剣に頭を悩ませている様子だった。 そこで、さゆりが、口を挟んだ。 「あたしたちで、ジャンケンして決めるっていうのは、どうですか。あたしが勝ったら、南せんぱいが先、香織先輩が勝ったら、滝沢せんぱいが先、みたいに」 「うーん。待って……。これは、大事なことだから、もっと、ちゃんとした形で決めたい気がしてきた。そのために、南さんと滝沢さんで、なにか、勝負をするっていうか、そういうのを、セクシーショーの前座として取り入れるのも、面白いかなって思って」 香織は、にらむように地面を見つめながら、さらに考え込む。それからまもなく、ぽんっと手を打った。 「いいこと思いついた。『おしくらまんじゅう』で勝負してもらう」 「おしくらまんじゅうっ?」 さゆりが、馬鹿にするように笑って聞き返す。 「そう……。南さんと滝沢さんで、体の正面からぶつかり合うの。負けたほうは、問答無用で、先に脱いでもらう。ただ、パワーでいうと、圧倒的に、南さんのほうが強くて、普通にやったら、勝負にならないだろうから、禁止事項を設ける。相手に、体当たりしたり、相手の体を、突き飛ばしたり、そういった暴力的行為は、一切、禁止。もし、それを破ったら、その時点で、負けにする。まあ、簡単に言えば、お互いに、体と体を密着させ合って、その状態に、どっちが長く耐えられるかを競う、って感じ。先に、耐えられなくなって逃げ出したほうが、負け。このルールなら、公平だし、なかなか、面白い前座になりそう」 香織は、右手の甲を、下唇に当て、よだれを拭くような仕草をした。 涼子は、その『勝負』の光景を思い浮かべたとたん、血の気の引くような感覚を覚えた。 体と体の密着……。なんという悪趣味な発想だろう。やはり、香織は、涼子と秋菜に、同性愛的な行為を強要するつもりなのだ。 秋菜も、落ち着きを失っていた。 「ねえ、お願い、吉永さん……。考え直して。わたし、そんな勝負、無理……。この人の、こんな、汗まみれの体と、くっつき合うなんて、考えただけで、鳥肌が立ってくる」 なぜ、秋菜は、いちいち涼子を侮辱しないと気が済まないのかと、腹立たしくて仕方ない。それに、涼子のほうだって、秋菜などと体を密着させるのは、最低最悪のことだと思っているのだ。 「だったら、滝沢さん、南さんと勝負するのを、やめる……? その場合、あなたの不戦敗ってことになるけどね。つまり、問答無用で、滝沢さんから先に、脱いでもらうよ。それでも、あなたが、脱がなかったら、あたし、南さんに、命令する。滝沢さんの服を、力ずくで、全部、脱がして、って。南さんの腕力を持ってすれば、滝沢さんの体から、服を、はぎ取っていくなんて、きっと、薄っぺらい紙を引きちぎるくらい、簡単なことだろうね」 香織は、あごを反らし、不敵な笑いを見せる。 秋菜は、顔をくしゃくしゃにしていた。今にも、その目から、涙がこぼれ落ちそうである。 「あっ。それとも、南さん……。先に脱ぐ決意が、固まったかな? それなら、おしくらまんじゅうの勝負は、取りやめにするけど」 香織が、最後に、涼子の意思を尋ねてきた。 秋菜が、さっと涼子のほうに顔を向け、怒りに満ちた罵声を浴びせてくる。 「そうしなさいよっ! さっきから、あんたが、いさぎよく脱がないせいで、わたしが、どれだけ迷惑してると思ってんのよ!? わたしが、今、こんな状態におちいってるのは、何もかも、あんたのせいじゃないっ! 少しでも、わたしに、申し訳ないって思うなら、せめて、今すぐ、素っ裸になりなさいよ!」 それを聞くともなく聞きながら、涼子は、ゆっくりと首を横に振る動作を繰り返した。脱がない。その意思表示だった。 秋菜と体を密着させるのは、想像もしたくないくらい嫌なことだ。しかし、服を脱ぎ始めてしまったら、その時点で、自分の運命は、闇に閉ざされる。なんとしてでも、時間を稼がなくては。この、自己保身の塊であるクラスメイト、滝沢秋菜の呪縛を、一刀両断に断ち切ることのできる、秘策を編み出すために。 「はいっ。南さんも、先に脱ぐ気は、なし、と。これで、おしくらまんじゅうの勝負を行うことが、決定、と」 香織は、上機嫌な口調で言った。 秋菜が、聞こえよがしに舌打ちし、眉間と鼻の周りに、しわを寄せた、忌ま忌ましげな表情で、涼子のことを見てくる。 涼子は、その視線を無視した。 「さゆりっ。おしくらまんじゅう始めるから、手伝って。あたしたちが、あの二人の背中を後ろから押して、お互いに、くっつき合うようにしてやるの」 「はーい」 香織とさゆりは、バッグを地面に置き、涼子たちのほうに歩いてくる。 双方の距離が、三、四メートルほどになったところで、さゆりが、ぴたっと足を止めた。 「うえっ……。臭ってきた、臭ってきた。この辺、一帯に、ものすごい漂ってる。南せんぱいの、汗の臭いが……」 苦笑しながら、鼻を押さえる。 案の定、という感じだった。涼子の体臭について、あからさまに指摘してくるだろうことは、事前に予想がついていたのだ。だが、それでも、涼子は、またもや女の子としての誇りを穢された思いで、自分の身を大事にするように両肩を抱いた。 「ホントだぁ……。南さんのことを、汗臭いって思ったことは、これまでに、何度もあったけど、今日の、この臭いは、今までとは、段違いって感じ。たしかに、滝沢さんの、言ったとおりだわ……」 香織は、そう言いながら、さらに涼子に近づいてくる。 「でしょう!?」 秋菜が、なにか嬉しそうに同調する。 香織は、涼子のすぐ目の前、体に触れられる距離まで来て立ち止まった。そうして、涼子の胸の辺りに、顔を突き出すようにし、すんすんと鼻を鳴らす。 涼子は、後ろに下がりたい衝動に襲われた。だが、涼子が、そうやって嫌がれば嫌がるほど、香織の嗜虐欲を満たすだけなのだ。だから、両肩を抱いたまま、身動きせずに、じっと耐えていた。 香織は、あああっ、と切なげな声を漏らした。 「ねえ、南さん……。この汗の臭い、どう考えても、やばいよ。もしかして、どこか、体の悪いところがあるんじゃないの? あたし、南さんの体が、心配になってきちゃったあ……」 秋菜が、それに追従した。 「きっと、食生活の問題よ。この人、バレーのことしか頭にないからさ、筋肉量を増やしたくて、毎日毎日、肉ばっかり食べてんのよ。わたしたちから見れば、女っていうより、獣みたいな生き物。いくら女子校通いだからって、そこまで女を捨てたら、本当に、おしまいね」 どうやら、秋菜は、この期に及んで、まだ、香織たちと一緒に、涼子を侮辱し続けることで、自分の助かる道を見いだそうと考えているようだ。 「たしかに、南さんの、この体臭は、食生活も関係してるかもしれない。ただ、あたし、気になるのは……」 香織は、涼子の体に、両手を伸ばしてきた。 涼子は、左右の脇腹に、ぺたりと触れられ、上半身の筋肉全体が、ぐっとこわばるのを感じた。 「この、半端じゃない汗の量……。シャツが、びしょびしょだもん。この格好で、プールにでも入ったのかって思っちゃう……。南さん、どうして、こんなに汗っかきになったの? もしかして、あたしたちのせい? あたしたちに、苦しめられるストレスのせいで、健康な体じゃ、なくなっちゃったの? もし、そうだったら、ごめんねえ」 おそらく、香織にしてみれば、自分たちの行いによって、涼子が、健康を失うことすら、悦びの一つなのだろう。 涼子は、きつく奥歯を噛み締めていた。 じりじりと迫り来る絶望、それに、恐怖、屈辱……。そういった感情に精神が蝕まれているうえ、さらに自律神経の狂いも影響して、体中の毛穴から、あぶら汗が、止めどなく噴き出してくる感覚がある。そのため、涼子の身に着けているTシャツとスパッツは、乾くどころか、むしろ、より濡れそぼっていくような状態だった。 香織は、涼子のTシャツの濡れ具合を、両の手のひらで熱心に確かめている。やがて、つと、その手を止めると、上目遣いに涼子の顔を見た。それから、左手を、やや下に動かし、Tシャツのすそに手をかけた。涼子の不安を煽るかのように、一秒、二秒、と間を置く。次の瞬間、ぺろりとTシャツをめくり上げた。無駄な贅肉の付いていない、涼子の腹部が露わになる。 涼子は、驚愕に目を見開いた。 香織は、涼子の顔を見ながら、にやりと笑う。ほどなくして、右の手のひらを、露わになった、涼子の腹部に、べたりと張りつけてきた。 耐えられない不快感が、全身に走った。 「やめてっ! 触らないでっ!」 涼子は、思わず叫び、身をよじるようにして逃れた。 すると、香織の顔に、不満の色が表れた。香織は、秋菜のほうに首を巡らせた。 「ちょっと、滝沢さん。あたしは、南さんの体の状態を、調べておきたいの。それなのに、南さんに、抵抗されちゃった。滝沢さんが、仲間として責任を持って、南さんを、大人しくさせて。それができないっていうなら、滝沢さんにも、重い罰を与えるよ。場合によっては、退学もありうるからね」 その脅しを受けて、秋菜は、かしこまったような表情をする。それから、射るような視線を涼子に向けてきた。 「あんた、なに、吉永さんに逆らってんのよ!? どうして、いつまでも、自分の立場をわきまえられないわけ? 言っておくけど、あんたの命運は、わたしが握ってるんだからね。それを、忘れてないでしょうね? わたしは、あんたに命じる。吉永さんには、絶対服従して。あんたが、吉永さんに、反抗的な態度を取ったせいで、わたしの立場が危うくなったら、わたし、あんたのことを許さない。本気で、学校から、あんたを抹殺してやるから」 涼子は、秋菜の脅し文句を聞いて、絶望に囚われかけた。 香織が秋菜を脅迫し、それに怯えた秋菜が、涼子を脅迫する、という構図だった。例えるなら、こういうことだ。涼子は、見えない首輪で拘束されており、その鎖の先を握っているのが、秋菜である。そして、その秋菜もまた、見えない首輪を付けられていて、その鎖の先は、香織が、がっちりと握っている。要するに、香織は、涼子と秋菜の二人を、思いのままにできるということだ。涼子にしてみれば、香織の支配下に置かれているという状況は、以前までと、まったく変わっていない。 香織は、涼子の身動きを封じることに成功したという、確信の笑みを浮かべる。 「あたしに、肌を触られるのが、そんなに嫌なの……? でも、我慢するしかないよねえ? だって、ここで、学校を辞めることになったら、南さんの人生、大変なことになっちゃうだろうしぃ」 ふたたび、香織の左手が伸びてきて、涼子のTシャツをめくり上げた。そして、反対の右手が、もったいを付けるようにゆっくりと、露わになった、涼子の腹部に伸びてくる。 涼子は、両肩を抱いたまま、腹の底に力を入れるようにして、全身を駆け巡るであろう不快感に備えた。 へそのところに、香織の右の手のひらが張りつく。 香織は、円を描くような手つきで、涼子のへその周辺を撫で回し始めた。ひとしきり、それを繰り返した後、今度は、涼子の体を抱くようにして、背中の側へと手を回した。 香織の鼻息が荒い。 「なにこれ……。肌が、べたべたじゃない……。普通の汗って感じじゃないねえ。あぶら汗? 南さん、これから、自分は、どうなっちゃうんだろうって、怖くてしょうがない思いで、体中から、あぶら汗が出てるの?」 涼子は、この世でもっとも気色悪いと感じる女の手で、肌をまさぐられる苦痛に、あえぐような息を吐いた。 香織は、そんな涼子の反応を見て、満足感を得た様子だった。右手を引っ込め、Tシャツを握っている左手を離す。しかし、それでは終わらなかった。その後、おもむろにしゃがみ込むと、涼子の下半身に、じいっと視線を注いだ。まもなく、香織の両手が伸びてきて、涼子の両脚の太ももを、がしっと横からつかんできた。スパッツ越しに、鍛え抜かれた太ももの肉を、ぐいぐいと揉み込むようにする。 「うっわ、すごい……。スパッツも、びちゃびちゃ……。さゆりっ、ちょっと、これ見て。こうして触ってると、汗が、生地から滲み出てくるの。下半身も、ここまで汗だくになるって、どう考えても異常だと思わない?」 「げえ……。しかも、汗の色が、なんか濁ってるように見えるんですけど。汚らしーい」 さゆりは、気分悪そうに口もとを手で押さえる。 自分の体は、香織たちのせいで、壊れかけている。それを思うと、涼子は、叫びだしたくなるほど悔しくてならなかった。 やがて、涼子の両脚の太ももを揉んでいた、香織の両手が、ずずずっと後方に滑っていった。そのまま、おしりを触ってくる。次の瞬間、おしりの肉を、むぎゅっとつかまれた。 涼子は、びくっとしてしまった。 香織は、は虫類のように目を輝かせる。 「どうなってんの……? おしりまで、汗で、ぐっしょり濡れてる。これは、さすがに引くなあ……。南さんもさあ、いちおう、女の子でしょう? こんなところの毛穴まで、開きっぱなしの状態で、どうすんのよ? これじゃあ、おしりの肌が、どんどん荒れていくよ。あんたのおしり、ただでさえ汚い印象を与えるのに、さらに肌荒れが進んだら、もう、見るに堪えない見た目になっちゃうよ」 涼子は、震えるような屈辱と戦いながら、懸命に自分を鼓舞していた。希望を捨てたら、だめ。この地獄から抜け出す方法は、まだ残されているはず。それを、絶対に見つけだしてやる。とにかく、考え続けるんだ……。 香織は、涼子のおしりから、両手を離すと、よっこらしょ、というふうに立ち上がった。それから、両の手のひらを、しげしげと眺める。手のひらの表面は、涼子の汗で、てらてらと濡れている。ほどなくして、その両手で、自分の鼻を覆った。 「おあっ……」 香織は、うめき声のようなものを発した。そして、企みに満ちた笑い顔になり、涼子の顔を見上げた。香織の両手が、涼子の顔面に伸びてくる。 「はいっ。化粧水を塗ってあげるから、じっとして」 その両手が、ぴしゃりと頬を包み込んできた。手のひらに付着している汗を、頬に塗りたくってくる。それに続き、右の手のひらが、涼子の鼻と唇に押し当てられ、何度も執拗にこすり付けられる。 まがまがしいまでに強烈な臭気。 涼子は、香織のその行為に対する怒りも、さることながら、自分の体は、壊れかけているというより、腐ってきている、と表現したほうが正確なのではないかと思われ、烈々たる悲しみを抱いていた。ちゃんと自分の汗の臭いを嗅ぎなさいよ、という手つきで、香織に、鼻を押し曲げられながら、えうっ、とおえつをこぼしてしまう。 「どう? 南さん。たぶん、あんた自身も、自分が、汗臭い体をしてることは、自覚してたんだろうけど、認識が甘かったって、気づいたかな? 今、あんたが嗅いでる臭いが、あんたの体が発してる、正真正銘の臭いなの。あたしたちが、別に、あんたを傷つけようとして、くさい、って言ってんじゃないって、よくわかったでしょう? 思ったことを、そのまま口にしてるだけなの……。それが理解できたら、お願いだから、もうちょっと、女の子らしく、自分の体臭の問題と、きちんと向き合ってくれる?」 香織は、ねちねちと涼子を言葉責めし、その両手を下げた。 顔中に付着した汗の臭いが、間断なく鼻腔に流れ込んでくるため、頭痛を起こしそうだった。今すぐ顔を洗いたい。それに、このままだと、汗の汚れが皮膚に染み込み、そのうち、顔中が、かゆくなるような気がする。 「あっ。そうだ。あたし、思い出しちゃった……。さっき、あたし、誰かさんから、とんでもない暴言を浴びせられたんだった。あたしの脳みそは、どろどろに腐ってて、たくさん、虫が湧いてるとか、言われた気がするんだけど、誰に言われたんだっけなあ……?」 香織は、ふてぶてしい表情を見せる。 涼子は、斜めに視線を落とした。 「たしか……」 香織は、右手を、涼子の口もとに伸ばした。 その手が、涼子の上唇を、ぎゅっとつまみ、上にめくり上げてきた。 「この口じゃなかったかなあ……? この、いけないお口が、あたしに、暴言を吐いてきた気がするんだけどなあ」 上唇を、右へ左へと動かされる。 今、自分は、ひどく見苦しい顔をさらしているはずだ。 香織は、さらに調子づいた。右手の親指を、涼子の唇の中に押し入れてきたのだ。歯の前を通り過ぎ、その指が、左頬に達する。そうして、涼子の左頬を、親指と中指で挟み、外側に、ぐいっと限界まで引っ張った。 「そうだよねえ、南さん? 言ってくれたよねえ……? 聞きたいんだけどさ、あんた、あの時、どんな心理状態だったの? あたしたちに、勝った気分でいたわけ? だから、もう、あたしに、遠慮する必要はないって思ったの? そうなんでしょ? でも……、今じゃ、残念ながら、このザマ。ねえ、あの暴言について、あたしに、何か言うことがあるんじゃないのお?」 謝れということか。 涼子は、顔を醜く歪められながら、葛藤を覚えていた。喉まで出かかっている、謝罪の言葉。だが、それを口にしてしまえば、その時点で、自分の完全な負けを認めることになるのだ。 そこで、秋菜が、苛立った声を出した。 「あんた、吉永さんに、早く謝りなさいよっ! 吉永さんには、絶対服従だって、言っておいたでしょっ!」 涼子のことを、見えない首輪で拘束している、秋菜からの命令だ。 それにより、涼子は、ぽっきりと心が折れるのを感じた。 「……ご、めぇんなしゃいっ」 舌を動かしにくかったが、涼子は、もごもごと口にした。敗北感で胸が一杯になる。 香織は、ふんっ、と笑うと、涼子の口から、親指を抜いた。指に付着した唾液を、涼子の首筋にこすり付け、手を下ろす。 「まあ、謝ったくらいじゃあ、許さないけどね。これから、たっぷりとお仕置きをさせてもらう。あたしに、暴言を吐いたことを、あんたが、一生、後悔するような思いをさせてやるから、覚悟しておくんだね。あんたは、きっと、泣き叫ぶことになる。『吉永さん。お願いですから、それだけは、やめてください!』ってね。あんたの、その姿を見るのが、今から愉しみでしょうがない」 香織は、一国の女王にでもなったかのような、大きな優越感に浸っている様子を見せる。 涼子は、自分自身に問いかけた。 もう、わたしは、諦めるしかないの……? しかし、すぐに、心の内で、激しくかぶりを振った。 着ているものをはぎ取られるまでは、希望を捨てないと、心に決めていたではないか。考え続けろ。どうしたら、自分を拘束している、この見えない首輪を外せるのか。その鎖の先を握っているのは、吉永香織ではなく、滝沢秋菜だ。だから、滝沢秋菜に対して、なんらかの形で対抗する必要があるだろう。 対抗……。 それだったら、いっそのこと、こちらも、秋菜に、見えない首輪をはめてやればいいのではないか……? 涼子は、はっとした。 見えない首輪。それは、むろん、脅迫のことである。秋菜は、涼子のことを脅迫しているのだ。それと同じことを、やり返して、いったい、何が悪いというのか。 非情になれ。この地獄から、抜け出すために。 秋菜を脅迫するのに使えるネタなら、今、香織のバッグの中に入っているはずだ。秋菜が、覚醒剤を使用している証拠の写真。もし、それが、手に入ったなら……。 秘策の形が見えてきた。もうちょっとで、その完成形を、頭の中に思い描ける気がする。そのための、時間がほしい。 「さてさて。じゃあ、おしくらまんじゅうを始めたいんだけど、ちょっと、問題あり、かもね。南さんの、この、汗まみれの体と、猛烈な汗の臭い。滝沢さんは、密着状態で、それに耐えないといけないから、かなり苦しいっていうか、不利だね」 香織は、涼子と秋菜を見比べた。 「そうよっ! どう考えても、わたしのほうが、不利じゃないっ。それに、この変態女、わたしのことを、性的対象として見てるのよ? わたしと密着したら、これ幸いとばかりに、わたしの体に、何か変なことをしてくるかもしれない。わたし、そんなの、我慢できない! ねえ、吉永さん。だから、おしくらまんじゅうの勝負は、中止にして。それで……、さっき、吉永さん、こう言ってたよね? この女が、あの、一年生の子の、すぐ目の前で、裸になるなら、わたしは、脱がなくてもいい、って。もう一度、そのチャンスをくれない? わたし、この女に、今度こそ、それを、必ずやらせてみせる!」 秋菜は、そうまくし立てると、恐ろしく険しい表情で、こちらを向いた。 「わたしから、あんたへの命令。今すぐ、あの、一年生の子の前に移動して、着てるものを脱ぎ始めて。従わないっていうなら、学校から、あんたを、抹殺するわよ」 涼子は、目の前が、真っ白になるような心地がした。 もう、ここで、わたしの運命は、闇に閉ざされるの……? 「待ちなよ、滝沢さん」 香織が、横から口を入れた。 「勝手に話を進めないで。さっき、あたしが言ったのは、南さんが、自分の意思で、滝沢さんを守るために、自己犠牲の精神を見せられるかどうか、ってことなのよ。でも、南さんは、それをしなかった。滝沢さん、あなたが、南さんに、無理やり、同じことをやらせても、それじゃあ、美しい自己犠牲とは認められない。もう、あなたたち二人とも、脱ぐことは、決定してるの。滝沢さんも、いい加減、往生際が悪いね。あなたが、今、できることは、ただ一つ。南さんとの、おしくらまんじゅうの勝負に勝って、脱ぐ順番が、あとになるよう、頑張ることだけ。あなたが、不利なのは、あたしも、理解してる。だけど、不利は不利でも、どうしたら勝てるのか、その、優秀な頭で、なんとか考えなさい……。いい? わかった?」 秋菜は、両手の十本の指で、脳を刺激するかのように頭部を押さえた。何かに取り憑かれたような目つきをしている。おそらく、希望を失いかけているが、着ているものを脱ぐなど、決して受け入れられないという、彼女のプライドが、絶望の底に沈むことを許さないのだろう。 涼子は、そんな秋菜の様子を見て、強く確信した。きっと、秋菜は、これから先も、まだまだ、自己保身の本能に突き動かされるままに、涼子のことを、口汚く侮辱し続けるに違いない。 「滝沢さんっ。おしくらまんじゅうを始めるから、バッグを下に置いて……。あと、さゆりっ、あんたは、南さんの後ろに回って」 香織は、秋菜とさゆりに指示した。 秋菜は、観念したようにバッグを地面に置く。 だが、さゆりは、難色を示した。 「えっ……。あたしが、南せんぱいの側ですか? あたし、その、汗まみれの体に触るの、すごい抵抗があるんですけど」 本当に抵抗を感じているらしく、顔全体をしかめている。 「いいから、南さんの後ろに回って。だって、あんた、滝沢さんに対しては、遠慮しちゃいそうだし」 香織は、涼子のほうに、あごをしゃくった。 「あっ、はあ……」 さゆりは、しぶしぶとした様子で、こちらに歩いてきて、涼子の背後に回った。その直後、涼子の背中に顔を近づけ、露骨に体臭を嗅いでくる。 「うっ……。くっせぇ」 吐き捨てるように言う。 それから、涼子の肩甲骨のあたりに、ぺたぺたと触れてきた。 「なに、この汗……。あたしが、もし、こんな体になったら、もう、生きていけなくなりそう」 思えば、石野さゆりという後輩は、涼子の、これまでの常識を、根底から覆すような存在だった。誰しもが、遅くとも中学に入学したら、先輩に対しては、最低限の礼儀を守って接するようになる。そういうものだと考えてきた。ところが、それを平気で無視する人格の持ち主が、こんな身近なところにもいることを、涼子は、身をもって思い知らされたのである。 さゆりは、涼子の両肩をつかむと、信じられないくらい、荒っぽい手つきで、秋菜のほうに、体の向きを変えさせてきた。 反対側では、香織が、秋菜の背中に手を回し、涼子のほうを向かせる。 涼子と秋菜は、二、三メートルほどの距離で向かい合う形となった。これ以上、一歩たりとも相手に近寄りたくない。お互いが、そう感じているのだ。自分の体の大量の汗を、相手に付着させる涼子と、その汗を体に付着させられる秋菜。自分でも閉口する汗の臭いを、密着状態で嗅がれる涼子と、その臭気に苦しめられる秋菜。いったい、どちらのほうが、精神的な苦痛が大きいか。お互い、はち切れんばかりに恥じらいを抱えた、思春期の女の子なのだ。どう考えても、わたしのほうが、絶対につらい。涼子には、そう思えてならなかった。 また、この『勝負』が、いかに馬鹿げたものであるかは、充分にわかっている。どちらが勝つにしても、いずれは、涼子も秋菜も、着ているものを、すべて脱がなくてはならないという既定なのだから。しかし、涼子は、秘策を練るための、時間稼ぎがしたかった。一方、秋菜のほうは、涼子を攻撃する姿勢を見せ続けることで、あわよくば、香織の手下のような存在になれたらいいと、そんなふうに考えているのだろう。つまり、お互いが、自分だけは助かるのではないか、という希望を抱いているがゆえに、これから、香織の考えた悪趣味極まりない『勝負』を始めようとしているのだ。 ふと、涼子は、竹内明日香と並んで立っている、一年生の足立舞のほうに、視線を飛ばした。 うきうきしているような舞の表情が、目に入る。が、舞は、目が合ったとたん、気まずい思いがしたのだろう、さっと視線を地面に落とした。南涼子と滝沢秋菜。その三年生同士の、醜い戦いを見られるのが、それほど嬉しいのか。 「あのさあ、きみ……。一言だけ、言わせてもらうんだけど、きみって、嫌な趣味してるよねっ」 涼子としては、これだけでも言ってやらないと、どうしても気が済まない思いだったのだ。 しかし、舞は、とっくに、涼子には嫌われていると開き直っているのか、悲しげな顔を見せるわけではなかった。そればかりか、すねたように唇を曲げている。 そこで、涼子は、いきなり後頭部を、ぱんっとはたかれた。 「うっせえんだよ、おめーは」とさゆり。 一年生には舐められ、二年生からは手を出される。いったい、どこの高校に、これほど情けない最上級生がいるだろうか。そんな暗澹たる気持ちになり、涼子は、震えるため息を吐き出した。 「それじゃあ、おしくらまんじゅう、開始するよっ!」 香織が、その言葉と共に、秋菜の背中を押す。 続いて、涼子も、さゆりに、どんっと肩を邪険に突かれ、前に進み始めた。 二人の距離が、一メートルを切ろうかというところで、秋菜は、後ろに身を引くようにして足を止めた。 「うっわっ、くっさーいっ! ちょっと、ちょっと待って、吉永さんっ。この人の汗の臭い、わたし、耐えられそうにない!」 涼子のほうも、背筋の引きつるような羞恥感情から、思わず立ち止まった。 「先に脱ぐのが嫌だったら、ごちゃごちゃ言ってないで、ほらっ、早く行って」 香織は、秋菜の身を、さらに、こちらへと押しやる。 涼子も、さゆりに、ぐいぐいと肩を押され、一歩、二歩、と脚を前に動かす。 いよいよ、お互いの体が密着し合う瞬間だった。 涼子は、ガードを固めるように両腕を上げて、体全体で秋菜と密着するのを防ごうとした。 秋菜のほうも、涼子と同様に構えた。 二人の腕と腕がぶつかる。 身長は、涼子のほうが、四、五センチ高いくらいだ。そのため、もし、二人とも腕を下ろしたら、お互いの唇が、相手の顔にくっついてしまいそうである。そんな最悪の事態だけは、絶対にあってはならないという思いから、涼子と秋菜は、両腕で押し合いをしている状態だった。 「おっしくらまんじゅうっ、押されて、泣くなっ」 香織が、愉快そうに、かけ声を出す。 「おしくらまんじゅう、押されて、泣くな」 さゆりも、涼子の体を、もっと秋菜に密着させようと、後ろから圧力を加えながら、香織に声を合わせる。 玉のように汗が浮いている涼子の腕にこすられ、秋菜の前腕も、すっかり濡れ光っていた。涼子の汗が潤滑油となり、二人の腕と腕が、ぬるぬると滑る。 「やだ! この汗、気持ち悪いっ! もうっ! どうして、わたしが、こんな目に遭わないといけないのよ!」 秋菜は、いかにも、自分が一方的な被害者だとでもいうように、大声でわめき散らす。 涼子は、この、苦痛に満ちた状況下で、懸命に頭を働かせていた。 秘策。その道筋を立てるために。 滝沢秋菜の呪縛から逃れるには、こちらも、彼女に対抗することが必要である。秋菜は、涼子の変態行為を写した、例の三枚の写真と、それに、涼子の体液で汚れた体操着のシャツを、手中に収めている。そして、さらに、南涼子から、同性愛的な好意を寄せられていたという、嘘のストーリーを作り上げた。それらを複合させる形で、涼子のことを脅迫している。そのため、現在、涼子は、見えない首輪で拘束されており、この地獄から抜け出せないのと同時に、秋菜の命令には服従せざるを得ない。しかし、もし、こちら側も、秋菜を脅迫することが可能になったら。そう。秋菜が、覚醒剤を使用している証拠の写真を、手に入れることに、成功したなら……。 秋菜に向かって、こう言ってやることができる。 『わたしを、学校から、抹殺する? そう。それなら、そうすればいい。わたし、学校に通えないような状況に追い込まれたら、滝沢さん、あなたのことを、絶対に許さない……』 それから続ける言葉は、香織が、秋菜に対して言ったという脅し文句と、ほぼ同じである。 『……あなたが、覚醒剤を使った証拠である、この写真を、匿名で学校に届けて、あなたが、退学になるようにしてやるから』 こちらも、秋菜に、見えない首輪をはめるのだ。その首輪で、秋菜の首を、ぎりぎりと締めつけてやる。秋菜が、その苦しみから解放されたいという一心で、涼子を拘束している、この首輪を外すまで。 しかし、一番の問題は、どうしたら、秋菜の致命的な弱みである、その写真を、香織から入手できるか、という点である。 「ちょっと、南さんも滝沢さんも、その両腕を下ろして、ちゃんと体と体で密着し合いなさいよ」 香織は、今のままだと面白くないと思ったらしく、さらなる要求を突きつけてきた。 だが、涼子は、それに従う気になれなかった。 秋菜も、涼子と、体全体で密着するなど、とても耐えられないと感じるのだろう、両腕の前腕を、こちらに押しつけたままである。 「はいっ。いつまでも、そうやってると、負けにするよ。滝沢さん、腕を下ろしなさい。……さゆり、南さんの腕を、下ろさせて」 香織は、秋菜の両腕を後ろからつかんで、無理やり下げさせ、後輩に指示した。 さゆりは、涼子の前腕の部分を引っつかむと、まるで、犯罪者を逮捕するかのように、後ろ手にさせてきた。 それから、香織とさゆりは、それぞれ、目の前の背中を勢いよく押した。 涼子は、秋菜の顔面に、唇を押し当てることにならないよう、とっさに、顔を右側に向けた。 秋菜のほうも、涼子から見て左側に、思いっ切り顔をそらす。 最初に、お互いの胸と胸が当たった。続いて、肩同士がぶつかり合い、また、自分の腹部を、相手の上半身に押しつける形になる。涼子と秋菜は、文字通り、べったりとくっつき合ったのだった。二人とも、後ろから背中を押されるままに、体と体をこすり付け合う。 「いいよいいよ。おしくらまんじゅうらしくなってきた……。おっしくらまんじゅう、押っされて、泣くなっ」 香織は、これぞ求めていたものだと満足したらしく、ふたたび、かけ声を出した。 「おしくらまんじゅう、押されて泣くなっ」 さゆりも、笑い混じりに口にした。 密着している秋菜の体からは、ふんわりといい匂いがする。今の涼子とは対照的な、女の子らしい、綺麗で清潔な秋菜の体。だが、その秋菜のセーラー服も、涼子のTシャツに染み込んでいる汗が付着し、うっすらと濡れてきているのが見て取れる。まるで、うら若き少女の身を、ケダモノが穢しているかのよう。その思考に頭の中が占拠され、涼子は、羞恥心というより、劣等感と屈辱感が、どろどろに混じり合ったような感情を抱かされた。それにより、苦痛が増大し、思わず声を漏らしてしまう。 「あああ、いやあ……」 喉の焼けたような、がらがら声だった。 「なにが嫌よっ! あんたの、こんな汗まみれの体とくっつかされてる、わたしの身にもなってみなさいよ! わたしのほうが、あんたの何十倍も苦痛なんだから!」 秋菜が、涼子の耳もとで、憤慨したように怒鳴った。 そのやかましさに、頭の神経がずきずきする。 「ねえ、南さん。あたし、知ってるの。南さんが、今まで、滝沢さんとの距離感に悩んでいたことを。滝沢さんと接近したいって、ずっと思ってたんでしょう? で……、どう? ようやく、滝沢さんと、こんなにくっつき合うことができた気分は。もう、すっかり親友の関係になった距離感じゃない。っていうか、この距離感は、親友なんて、完全に通り越して、滝沢さんと、まさに、恋人同士になったって感じだよね。嬉しい? 幸せ?」 香織は、秋菜の背後から顔を出し、こちらを見ながら、ひひひっ、と笑う。 滝沢秋菜との距離感に悩んでいた……。それは、否定しようのない事実だ。今日に至るまでの高校生活のなかで、滝沢秋菜に、距離を置かれている、と感じさせられたことが、どれだけあっただろうか。涼子が、話の輪に加わると、その場にいた秋菜は、すっと離れていく。それが、判で押したように繰り返されてきたのだ。そのたびに、涼子は、やるせない気持ちで胸が苦しくなった。 あるいはまた、しばしば、こんな場面を経験した。 教室前の廊下で、涼子は、六、七人のクラスメイトたちとお喋りをしていた。その輪の中には、滝沢秋菜の姿もある。秋菜は、積極的に会話に加わっているわけではないが、涼子がいるからといって、すぐに立ち去る気もないようだった。これは、秋菜との距離を縮めるチャンスだ。涼子は、そう思った。秋菜とコミュニケーションを試みるのは、少しばかり勇気がいることだった。けれど、思い切って、秋菜に話を振ってみた。と同時に、とびっきりの笑顔を浮かべてみせる。だが、秋菜からは、気のない返事しか返ってこなかった。涼子は、失意を感じながら、気まずさをごまかすように、曖昧な言葉を口にし、もじもじと指をいじる……。 そうした出来事の後、たいてい、秋菜との距離感に対する思いが、胸中に渦巻くのだった。もしかしたら、滝沢さんに、嫌われてるのかな……。だとしたら、きっと、わたしが悪い。わたしの、生意気な性格が、原因なんだろうな……。でも、できれば、滝沢さんと親しくなりたい。下の名前で呼び合えたらいい。『涼子、秋菜』って。滝沢さん、お願いだから、もっと、あなたに近づかせて……。 まさか、その滝沢秋菜の体を、こうして、自分の体液で汚す日が来るなんて、想像だにしなかった。目くるめく非現実感に、身も心も押し潰されそうである。悪夢のようだった。 「滝沢さん、南さんの、体臭責めは、どう? きつい? もう限界?」 香織が、今度は、秋菜に尋ねる。 「とっくに限界を超えてるわよ! この臭い、鼻がおかしくなるどころか、もう、気が狂いそう!」 秋菜は、苦しさを訴えるというより、涼子を罵るように叫んだ。 今の言葉が、あの、滝沢秋菜の口から、自分の体のことに対して発せられたものだと思うと、より一層、この現実が信じられなくなってくる。 耳もとで聞こえる、秋菜の苦しげな呼吸の音。だが、涼子の息づかいは、それよりずっと荒かった。マラソンを走っている最中のように、はあっ、はあっ、と息を吐いている。秋菜にとっては、さぞかし耳障りに違いない。 そして、こうして体と体をこすり付け合っていて、とにかく嫌なのは、衣類越しとはいえ、自分の乳房が、秋菜の胸のふくらみに圧迫され、むにゃりと押し潰されている、この感覚だった。また同時に、自分の胸の圧迫で、秋菜の乳房が、柔らかく潰れている感触も、はっきりと伝わってくる。あまり考えたくないことだが、これは、まさに、女同士で肉体的な快楽を求め合っている、という状況だろう。 「ねえ! あんたさあ……、よく、恥ずかしげもなく、わたしの体に、くっついていられるわね。あんた、自分の体が、どれだけ不潔な状態なのか、自分でわかってないの? わたしのほうは、拷問を受けてる気分よ! いい加減、わたしに、とんでもない迷惑をかけてるってこと、自覚して。それが自覚できたら、お願いだから、わたしの体から、離れてよ! 勝負から降りて!」 秋菜は、きんきん響く声でわめき立てる。 むろん、涼子は、秋菜の要求を無視した。ここで、自ら、秋菜の体から離れたら、時を移さずして、着ているものを脱ぐことになるはずだ。だから、なるべく、この『勝負』を長引かせ、その間に、秘策を練り上げなくてはならない。絶対に、自分だけは、この地獄から抜け出してやる……。 「うーん。南さんも、滝沢さんも、なかなか頑張るじゃない。これだと、一向に終わらなさそうだから、次の段階に進もうか。ねえ、南さん……。あたしが、禁止にしたのは、暴力的行為だけなんだよ? つまり、それ以外なら、何をやってもいいの」 香織は、意味ありげに言う。 それから、少し間を置き、言葉を続けた。 「南さん、滝沢さんのことが、大好きだったんでしょ? 滝沢さんに、チューとかしてみたかったんでしょ? ねえ、今の状況は、千載一遇のチャンスだと思わない? 勝負ってことを名目に、欲望のままに行動していいんだよ。思い切って、チューしちゃいなさいよ。それで、滝沢さんが、嫌がって逃げたりすれば、南さんは、その時点で、勝ちになるの。欲望を満足させることができて、さらに、勝負に勝てるなんて、一石二鳥じゃない。ほらっ、そんなに顔を背けてないでさ、滝沢さんのほうを向いて、唇を突き出して」 聞いているだけで、涼子は、身の毛のよだつような気分になった。 今の香織の話に触発されたようで、背中を押している、さゆりが、手を伸ばし、涼子のあごをつかんできた。無理やり、秋菜のほうに顔を向けさせようとしてくる。 涼子は、低いうなり声を漏らしながら、荒っぽく頭を振り、さゆりの手から逃れた。 「あっ、南さん。それとも、滝沢さんの体に、やらしいことがしたい? いいんだよ、やったって。たとえば、滝沢さんの、制服の中に、手を入れて、おっぱいを、もみもみするとか」 香織は、秋菜のセーラー服のすそを握り、少しばかりめくり上げる。 密着している秋菜の体がこわばったのを、涼子は感じ取った。 「あるいは……、もう、いっそのこと、下のほうを攻めちゃう? スカートの中に、手を入れて、滝沢さんの、あそこを、パンツの上からまさぐったって、これは、勝負なんだから、許されるんだよ」 香織は、続いて、秋菜のスカートをつまみ、その生地を、ふわりと浮かせた。 涼子の耳もとで、秋菜が、凍えるような嘆息を吐き出した。おそらく、プライドの高さゆえに、早くも、屈辱感に耐えられなくなってきたのだろう。 「あんた、もし、わたしの体に、何か変なことしてきたら、殺すわよ」 秋菜は、涼子に対して、脅すような声で言う。 心外だった。 「変なことなんて、するわけないでしょっ……」 涼子は、腹立ちを露わに言い返した。 なぜ、秋菜は、香織の行為に対する怒りの感情を、八つ当たり的に、涼子にぶつけてくるのか。その心理が、まったくもって理解できない。もう、滝沢秋菜など、どうなってもいい、どんなひどい目に遭わされてもいい……。涼子の胸の内で、その思いが募っていく。 「ほらっ。滝沢さんも、意地を張ってないで、南さんの愛を、受け止めてあげなさいよ。それに……、滝沢さんだって、南さんの、汗まみれの体と、こんなずっと、くっつき合っていられるなんて、本当は、まんざらでもないんじゃないの? 嫌がってるフリしているけど、内心は、南さんのフェロモンの臭いを、吸い込んでるうちに、興奮してきちゃったんじゃないの? 滝沢さんが、その気になるのを、南さんは、ずっと待ってるんだよ? これ以上、南さんのことを焦らすのは、やめたらどう? もう、この際だから、ひと思いに、二人で、愛し合いなさいよ。その時は、もちろん、服なんて必要ないよね。お互い、裸になって抱き合うの。女同士のエッチを、女子高生のうちに、一度、経験しておくのも、悪くないんじゃないかな?」 香織は、秋菜が、どんな拒絶反応を示すのか、それを試すように喋る。 「こんな、何もかも気持ち悪い女に、抱かれるくらいだったら、家畜に犯されたほうが、よっぽどマシよっ」 秋菜は、涼子の耳もとで、そう言葉を吐き捨てた。 その発言には、さすがの涼子も、かちんときて、思わず口を開いた。 「あんたのことは、見捨ててやるから……。わたしだけが、助かっても、恨んだりしないでね……」 すっかり、いがみ合う者同士の関係になったことを、身に染みて実感する。そんな両者の内面を反映するように、お互いの息づかいが、一段と荒くなった。 涼子は、秋菜の、乳房の柔らかさや体温などが、体に伝わってくることに、吐き気を催すほどの不快感を覚えながらも、宙を見上げるようにして、必死に考えを巡らせていた。 秋菜の致命的な弱みである写真を、いかにして、香織から入手するか。 涼子が、その写真を、滝沢秋菜の呪縛を断ち切るための、つまり、この地獄から抜け出すための、武器にしようとしていることが、香織に見抜かれてしまったら、そこで、万事休すである。涼子の手に、その写真が渡っても、香織の、支配者としての立場は、少しも変わることはない。香織に、そう思わせられるかどうかが、最大の勝負所であることは間違いない。涼子が、その写真を、手に取ることさえできたなら、もはや、それで勝ったも同然である。涼子は、ただちに秋菜を脅迫し返す。そうすることで、秋菜に、涼子に対する脅迫の意思を引っ込めさせてやる。その瞬間、香織は、涼子に、まんまとやられたことを悟るだろう。そして、当然、涼子に、その写真を返すよう、要求してくるはずだ。しかし、涼子は、その時点で、すでに我が身の自由を得ているのだから、そんな要求は、突っぱねてしまえばいい。また、香織たちが、力ずくで写真を取り返そうと、襲いかかってくることも、充分に予想される。吉永香織。竹内明日香。石野さゆり。それに、滝沢秋菜も加勢するだろうか。だが、しょせんは、肉体の鍛錬とは無縁な、涼子からしたら貧弱な生徒たちである。涼子が、本気で大暴れしたら、その圧倒的なパワーの前に、四人とも、腰を抜かすようにして戦意喪失するに違いない。その後、涼子は、香織から入手した写真を握りしめ、地上への階段に向かえばいいのだ。 幸いにも、香織は、涼子のことを、青く澄み渡った空のような、純真な心の持ち主だと思っているフシがある。まさか、そんな涼子が、秋菜を脅迫し返すなどとは、想像もしないはず……。そう信じたかったし、そこを狙い目にするしかなかった。 これは、一発勝負だ。 どんなふうに話を持ちかければ、香織は、疑念を抱くことなく、その写真を、涼子に手渡してくれるだろうか。 そのセリフを、頭の中で思い浮かべてみる。 『滝沢さんは、本当に、覚醒剤を使ったの……? わたしには、ちょっと信じられないな……。本当だっていうなら、その証拠の写真を、わたしにも見せてよ……』 いくらなんでも不自然か。却下だ。 『わたしと滝沢さんは、仲間同士なんでしょ……? だったら、対等の立場じゃないとおかしいじゃない……。だから……』 その時だった。 突然、股間に衝撃を感じ、涼子は、びくんと跳ね上がった。恥部をわしづかみにされているのだとわかる。愕然として目をむき、自分の下半身を見下ろした。 秋菜の右手が、その部分に伸びていた。 性感帯を強く圧迫される感覚。ありうべからざる状況だった。 「やっ! やめてっ! なにすんの! 離してぇっ!」 涼子は、悲鳴混じりに叫びながら、秋菜の手を押しのけようとした。 だが、秋菜は、手を離さないどころか、より力を込めてきた。 秋菜の指が、スパッツに覆われた涼子の恥部に、めりめりと食い込み、その黒い生地から、湧き水のように汗が滲み出てくる。 涼子は、自分の身に起きていることが信じがたい思いで、その異常な行為を仕掛けてきている、秋菜の顔を見た。 秋菜は、やめてやるものか、とでもいうような鬼気迫る表情を浮かべていた。 この子、おかしい……! 頭の中で、閃光がまばゆく弾け飛んだ。 涼子は、怒りに任せて、秋菜の胸もとを、両手で、どんっと突いた。 秋菜の身は突き飛ばされ、その背中が、香織に直撃する。二人は、よろめきながら、一メートルほど後退した。 奇妙な空気が流れる。 さゆりも、もう、涼子の背中を押してこない。 涼子は、自分の恥部を、手で軽くこすった。秋菜の手の感触を、ぬぐい去るように。それから、憤怒の目で、秋菜のことをねめつけた。 「なに考えてんのよ、あんた……」 しかし、秋菜に、悪びれた様子はない。 「あっ、わたし、暴力を振るわれた……。暴力は、反則でしょう? 今の勝負、わたしの勝ちよねえ?」 秋菜の顔には、むしろ、喜びの思いが表れている。 「やっちゃったねえ、南さん……。暴力的行為は、禁止だって言っておいたのに。だめじゃない、そのルールを破ったら。はい、これで、南さんは、反則負け。だから、南さんから先に脱ぐことが、決定」 香織は、にたにたと笑いながら、そう告げてきた。 そういうことか……。 涼子は、秋菜の狙いが、なんだったのかを、ようやく理解した。秋菜の今の、異常な行為は、涼子が、自ら逃げ出すか、あるいは、腕力を用いる形で抵抗するよう、仕向けるためのものだったのだ。 秋菜は、右の手のひらを、顔の高さまで上げる。 「っていうか……、あんたさあ、なんで、『そんなところ』にまで、ぐっしょり汗をかいてんのよ……? やっだあ。わたし、この人の、最悪に不潔な汗で、手を汚されちゃった」 そう文句を口にして、侮蔑の眼差しで、涼子の顔を見返してくる。それから、なにやら、地面に置いてある、自分のバッグのところに行き、腰を落とした。バッグのチャックを開け、その中から、制汗スプレーの缶を取り出す。缶を何度か振ってから、右の手のひらにスプレーした。念入りに吹きつけている。どうやら、気休めでも手のひらの除菌をしておかないと、右手を使えないと思ったようだ。その後、今度は、バッグの中から汗拭きシートを取り出した。シートで、右の手のひらを、ごしごしとこすると、続いて、涼子の汗で濡れた、腕を拭き始める。しっかりと拭いておかないと、肌荒れを起こしてしまう、とでもいうように。 秋菜は、それを終えると、制汗スプレーの缶と汗拭きシートをバッグにしまい、おもむろに立ち上がった。香織のほうを向く。 「吉永さん。わたしの体、くさくない? だって……、わたしのこの制服、見てよ。だいぶ湿ってるでしょう? これ全部、この人の、汗なのよ? なんていうか、もう、体を穢された気分よ」 おそらくは、その発言も、涼子への攻撃姿勢を、香織に示そうという意図によるものだろう。 涼子は、秋菜に対して、胸ぐらをつかんでやりたくなるほどの憤りを覚えていた。 体と体を密着させ合っている時、秋菜は、涼子に言った。もし、自分の体に、変なことをしたら、絶対に許さない、という趣旨のことを。にもかかわらず、自分自身は、『勝負』に勝つために、涼子の体の性的な部分に、容赦なく手をかけてきたのである。それも、女の子にとっては、一番、触れられたくないところに、だ。秋菜のその、身勝手さ、冷酷さ、卑劣さは、どれも非人間的な域に達していると感じる。 それに何より、あの、滝沢秋菜に、スパッツの上からとはいえ、恥部をわしづかみにされたという事実を、涼子は、どうしても受け入れられない気持ちだった。嘘のようだ。だが、秋菜の指が、恥丘から肛門の近くにかけて、大陰唇に深く食い込んでいた感触は、まだ、生々しく残っている。自分は、秋菜から、言葉で侮辱されるだけではなく、とうとう、性的な辱めまで受けたのだ。そう思ったとたん、激流のような屈辱感が、体中を駆け巡った。 「では、勝負に負けた南さん、もう、猶予は与えないよ。ただちに、脱ぎ始めて。今から、一分以内に、脱ぎ始めないなら、滝沢さんに、あなたの服を脱がすよう、命じることになるからね。はい、スタート!」 香織は、最後通告を突きつけてきた。 涼子は、すっかり狼狽した。 秋菜との『勝負』が、もう少し、長引いていれば、秘策を、完璧に練り上げることができたかもしれない。だが、秋菜の暴挙のせいで、それは、中断されてしまったのだ。秋菜の致命的な弱みである写真を、手に入れるには、香織に、どんなふうに話を持ちかけたらいいのか。まだ、その肝心の部分が、頭の中でまとまっていない。しかし、それでも、ここで、いちかばちかの賭けに出るしかないだろう。 涼子は、覚悟を決めて切り出した。 「あの……、待って。脱ぐ前に、わたしから、吉永さんに、お願いがあるの……」 一瞬、場がしんとなった。 「お願いって、なあにぃ?」 香織は、こちらに顔を突き出すようにした。 涼子は、ごくりと生つばを飲み込み、そして話し始めた。 「わたしと、滝沢さんって……、その、あの、仲間、なんだよね? でも、わたしは、滝沢さんから、一方的に攻撃されてる。散々、変態女とか、気持ち悪いとか、ひどい体臭とか、侮辱されまくって、おまけに……、体の、絶対に触られたくないところを、不意打ちで、つかまれることまでされた。そこまでされても、わたしは、反撃することができないの。こうなってる、一番の原因は、滝沢さんが、わたしの、恥ずかしい姿を写した、写真を持っていて……、その、つまり、わたしの秘密を握っているから。それは、間違いないでしょ? わたし……、今のこの状況は、どうしても、納得できない」 秋菜は、凶暴な肉食獣のような目を、涼子に向けてくる。 涼子は、気が遠くなるほどの緊張感に襲われていた。 「はっきり言うと、わたし……、滝沢さんのことが、許せないの。わたしも、滝沢さんに、反撃してやりたい。だから……、滝沢さんが、わたしの秘密を握ってるように、わたしにも……、滝沢さんの、秘密を、握らせて。あの……、滝沢さんが、覚醒剤を使った証拠の写真、吉永さんは、今、持ってるんでしょ? わたしに、その写真を、渡してくれる?」 まるで、一世一代の大舞台でスピーチをしているかのように、声が震えるのを抑えられなかった。 「なに、ふざけたこと言ってんのよ! わたしに反撃するために、わたしの秘密を握りたい!? あんたって女は、体も汚ければ、心も同じくらい汚いのね! 恥ってもんを知りなさいよ!」 秋菜は、予想していたとおり激高した。 だが、涼子は、秋菜には構わず、香織の顔を、真っ直ぐに見つめていた。 香織は、両目を細め、左手の人差し指を、頬に当てた。 「……南さん、なにか、よからぬことを考えてない?」 そのとたん、寒風に体を煽られた気がした。 ひょっとして、こちらの意図は、見抜かれているのか……? 心の秩序は、土台から揺らぎ始めていた。 涼子は、香織の言葉を否定するために、ぶんぶんと頭を振った。 「いやっ、べつに、わたしは、ただ……、今のこの状況は、どう考えても、不公平だから、それを、どうにかしてほしいだけっ。わたしは、滝沢さんと、その……、対等な立場に立ちたいの。だからっ、吉永さん、お願い。わたしにも、滝沢さんの、秘密を、握らせてっ」 しどろもどろになりながらも、最後まで諦めるものかと訴える。 「あんた、言わせておけば……。なんで、わたしが、あんたみたいな惨めな女と、対等な立場にならないといけないのよ! 冗談じゃないわよ! よくもまあ、わたしのことを、侮辱してくれたわねえ。あんた、今すぐ、その場で土下座して、わたしに謝りなさいよ!」 秋菜は、狂ったように叫んだ。 「……わかった、いいよ、南さん。滝沢さんが、覚醒剤を使った証拠の写真、あなたにあげる……。ただし、条件」 香織は、静かな口調で言った。 涼子は、期待と、それをはるかに上回る不安で、心臓が破裂しそうなくらい鼓動を打っているのを感じながら、香織の言葉の続きを待った。 「南さんが、ちゃんと……、セクシーショーを演じたなら、ね」 香織の顔に、涼子の心を見透かすような笑みが浮かぶ。 目の前の光景が……、闇に覆われた。 涼子は、茫然と立ち尽くす。きょろきょろと、周りに目を向けた。どこかに、希望の光は見えないか、というような気分で。しかし、目に映るのは、涼子が脱ぐのを待っている、四人の生徒と、それに、今や敵対関係にあるともいうべき滝沢秋菜の姿だけだった。 五人の見ている前で、着ているものを、脱ぐ……? そのことを想像すると、呼吸困難を起こしたように、息をするのが苦しくなった。Tシャツの胸もとの部分を、強く握りしめる。 「やっ……。いやあ……。お願いだから、先に、その写真を、渡してぇ……」 涼子は、命がかかっているかのような、余裕のかけらもない声で懇願した。 「だから、言ったでしょう? 順番が逆なの。南さんが、セクシーショーを頑張って演じたら、その、ご褒美に、写真をあげる。ほらっ、みんな待ってんの。早く、脱ぎ始めなさいよ」 香織の声が、涼子の耳に冷たく響く。 「いやあ……」 涼子は、首を横に振り続けた。 香織は、嘲笑するように唇を歪める。 「やっぱり、自分の意思で脱ぐっていうのは、無理ってわけね。それじゃあ、しょうがない……。滝沢さん、あなたが、責任を持って、南さんの服を脱がせて。まずは……、Tシャツから」 その命令を受けた秋菜は、軽いため息をついた。そして、すぐに動き始めた。気だるげな足取りで、こちらに歩いてくる。 涼子は、後ずさりするように身構えた。 秋菜は、涼子の目の前で立ち止まり、手を伸ばしてきた。 Tシャツの左肩の部分を、ぞんざいにつかまれる。 「やめて! わたしに触らないで!」 涼子は、堪らず声を上げ、秋菜の手を払いのけた。 すると、秋菜は、妙に大人びた仕草で髪の毛をかき上げた。 「自分のことだけ考えてんじゃないわよ。これは、吉永さんの命令なの。あんたの服を脱がさないと、わたしの立場が危険にさらされるの……。次、抵抗したら、遠慮なく、あんたの顔、殴らせてもらうわ。痛い思いをするのは、嫌でしょ? まあ……、あんたが、あくまでも抵抗し続けるつもりなら、好きにすればいい。だけど、その代償は、とっても大きいわよ。わたしが、あんたのことを、学校から、それこそ、虫けらみたいに抹殺してあげる。忘れたら、ダメよ。わたしは、あんたの人生そのものを奪えるの……。いい? あんたは、この場を、自分の家の風呂場だと思って、大人しく脱がされればいいの。それが、あんたにとって、一番、賢明な選択よ」 秋菜の口から発せられる、一言一言に、魂を侵食されていくような感覚だった。 その感覚は、やがて、かつて経験したことのない絶望感へと変わる。 涼子は、意識を失いそうになっていた。足もとがふらつく。 秋菜は、そんな涼子のTシャツの両脇に、両手をかけた。 Tシャツのすそが、するっと引き上げられる。腹部と背中が外気にさらされ、まもなく、涼子の身に着けている、白いブラジャーが露わになった。 嘘でしょう……!? 涼子は、胸の内で絶叫していた。 秋菜は、涼子の体から、Tシャツを力任せに脱がそうとする。だが、涼子が、それに協力する体勢を取っていないため、手間取っている様子だった。 「あんた、さっさと、シャツを脱がさせなさいよ! あんたが、こんな、くっさぁいシャツ着てるせいで、みんな、迷惑してんのよ!」 苛立ちに満ちた怒声を、涼子に浴びせてくる。 ほどなくして、Tシャツは、涼子の頭と両腕から、乱暴に抜き取られた。 涼子は、その後、ただちに、両腕を胸の前で交差させた。 とうとう、着ているものを脱がされ始めたのだ……。その受け入れがたい現実を、脳が認識し、もはや、生きた心地がしなくなる。 「滝沢さん、そのシャツ、こっちに、よこして」 香織が、秋菜に向かって、手を伸ばす。 秋菜は、涼子の白いTシャツを、香織の手のひらに載せた。 「すっごい……。生地に含まれてる汗のせいで、ずっしりくる。このシャツ、二、三キロ、重さがあるんじゃないのっ」 香織は、感嘆したような顔をする。それから、洗濯したての衣類の香りを確かめるように、汗まみれの涼子のTシャツに鼻を寄せた。胸を上下させている。どうやら、涼子の汗の臭気を、肺いっぱいに吸い込んでいるらしい。 そして、先ほどと同じく、ああああっ、と切なげな声を出した。 吉永香織。どう考えても、普通の女子高生ではない。完全に変態だ。こんな変態女に、自分は、これから、好き勝手にもてあそばれるのかと思うと、涼子は、怖気をふるうような気分になった。 「それじゃあ、滝沢さん。次は……、南さんの、スパッツを脱がせて」 香織は、気の昂ぶった様子で、秋菜に命じた。 秋菜は、まったく躊躇のない態度で、ふたたび、涼子の前にやって来た。すーっとかがみ込む。 やだ……。 恐怖と絶望が、果てしなく膨らんでいく。その時、強烈に意識させられたのは、自分に、告白の手紙を手渡した、一年生の足立舞も、離れたところから見ているということ。 涼子は、スパッツの上縁をつかみ、秋菜に脱がされないようにしたうえで、さっと舞のほうに顔を向けた。 「足立さんっ! さっきは、きつく言い過ぎちゃって、ごめんねっ。そのことは、心から謝る。ただ……、わたしにだって、プライドがある……。正直に言って、わたし、あなたには、これ以上、恥ずかしい姿を見られたくないの! この、わたしの気持ちを、ほんのちょっとでも理解してくれるなら、もう、あなただけは、お願いだから、帰って!」 ほとんど涙声で叫んでいた。二つ下の後輩に向かって、哀願する姿は、とてつもなく格好悪い。そんなことは、百も承知だったが、訴えずにはいられなかったのだ。 だが、舞は、迷うような素振りすら示さず、隣にいる明日香の顔を見上げた。まるで、明日香が、涼子に言い返してくれるのを期待しているかのように。 明日香は、涼子が、舞の存在を嫌がれば嫌がるほど愉悦を覚えるのだろう、実に嬉しそうな含み笑いの表情で、こちらを見ている。 涼子は、胸の底から言葉を絞り出すようにして、舞に問いかける。 「ねえ、そんなに、わたしが脱がされるところが見たい? 無理やり、人前で、裸にさせられるってことが、どれほど苦痛か、あなただって、わたしと同じ女なんだから、想像できるでしょ? それでも、わたしが、そういう目に遭うところを、見てみたいって思うわけ!?」 しかし、舞は、ごまかすように、というより、なぜ、自分だけ、涼子から詰問されないといけないのかと、不満を表すように、ゆらゆらと上半身を左右に揺らしている。 涼子の足もとにかがみ込んでいる、秋菜が、刺々しい声で言う。 「あの子に言いたいことは、それだけ? 気が済んだなら、とっとと、その手をどかしなさいよ」 秋菜の両手が伸びてきて、涼子のスパッツの上縁に指がかかった。 そこで、香織が、注意を与えた。 「滝沢さん、勢い余って、南さんのパンツまで下ろしちゃ、ダメだよ。一枚一枚、じっくりとね」 「はい、了解です」 秋菜は、従順に返事をする。 それからまもなく、秋菜の両手が、涼子のスパッツを下に引き始めた。秋菜から脅迫を受けている涼子には、脱がされないよう、その力に抗うことはできないのだった。涼子のスパッツは、無情にも、ずるずると引きずり下ろされていく。そうして、白いブラジャーとセットの、白い綿のパンツが、五人の視線にさらされることとなった。 陰毛は、はみ出ていないだろうか……? その心配が、まず、涼子の脳裏をよぎる。 涼子は、恥部を両手で覆うようにし、その情けない姿勢で、童話の絵本の主人公みたいな、幼い容姿の一年生に、目で問いかけ続けた。 服を脱がされるって、こういうことなんだよ……? あなたは、わたしの、こんな姿を見たかったわけ……? しかし、舞と目は合わなかった。舞の視線は、肌の露出していく涼子の下半身に、真っ直ぐ向けられていたのだ。 スパッツの上縁が、涼子の太ももまで下がったところで、秋菜が、首を絞められたかのように、うえっ、と声を出した。 「もんのすごい激臭が、立ち上ってくる……。この臭い、本当に、悶絶しそうっ!」 泳いだ後の水着のように汗で濡れそぼった、涼子のスパッツ。誰にも嗅がれたくない、その臭気を、今、よりにもよって、滝沢秋菜に嗅がれているのだ。涼子は、恥ずかしさのあまり、頬が、ぼっと紅潮していくのを自覚した。 スパッツが、涼子の足首まで下げられ、丸まって止まる。 秋菜は、香織のほうを向いた。 「吉永さん。裸にさせるってことは、このシューズやソックスも、脱がしたほうがいいのかな?」 まるで、彼女自身は、裸になることとは無関係のような口ぶりである。 「そう。南さんには、何も着けさせないで。裸足にさせて」 香織は、腕を組んだ、尊大な態度で答える。 秋菜は、二度、軽くうなずいた。それから、涼子のランニングシューズをつかんだ。 「脚、自分で上げなさいよ。いちいち、イライラさせないで」 まさに、涼子のことなど、人間扱いしないで構わない、という命令の仕方だった。 涼子は、秋菜の手の動きに合わせて、自ら片脚ずつ上げていく。 ランニングシューズを脱がされ、続いて、黒のスパッツを、両脚から抜き取られる。最後に、バレーソックスも脱がされた。 涼子は、裸足で地面に立った。 コンクリートのひんやりとした感触を、足の裏に、嫌というほど感じる。それにより、自分は、もはや下着しか身に着けていない、という事実が、心の芯まで染み込んでくる。いよいよ、本格的に、泣きたい気持ちが湧き上がってきた。 「もう、このパンツも、今すぐ脱がしてあげようか?」 秋菜は、そう口にし、涼子の身に着けている、白いパンツの左サイドの部分を、いきなり指でつまむと、嫌がらせみたいに、ぱちんと弾いた。 その瞬間、恥部を露出させられる、という極度の恐怖に襲われた。 「やめてぇぇぇぇ!」 涼子は、思わず叫び声を発し、両手でパンツをきつく押さえた。 秋菜は、おもむろに立ち上がると、ふっ、と苦笑しながら、涼子の下着姿を眺める。 「なんなのよ、その、白いブラに、白いパンツの組み合わせは。見てると、寒気がしてくるんだけど……。うちの学校に、下着は白、みたいな校則、あったっけ? それとも、優等生は、そうあるべきとか、あんた、自分で、そう思ってるわけ?」 ブラジャーの色は、部活の練習のことを考えると、仕方がないのだが、今日という日に限って、セットの白いパンツをはいてきてしまったことは、涼子自身、猛烈に後悔していた。むろん、汚れが目立つからだ。 それにしても、秋菜が、涼子の下着姿を前にして、まるで他人事のように振る舞っているのは、どうにも解せない。涼子の次は、秋菜が脱ぐ番なのだ。今の涼子の姿は、近い未来の自分自身の姿だという不安を、秋菜は抱かないのだろうか。 「滝沢さん、その、脱がせたものを全部、こっちに、よこして」 香織は、カモンカモンというふうに手招きする。 秋菜は、その指示に従い、汚物にまみれた衣類でも触るような手つきで、汗で濡れそぼった涼子のスパッツをつまみ上げ、さらに、ソックスとシューズを持って、香織のところに行った。それらが、香織の手に渡る。 香織は、さながら宝物でも手に入れたかのように、涼子の身からはぎ取ったもの一式を、感慨深げに見つめる。だが、ソックスとシューズは、地面に置いた。その後、涼子のスパッツの上縁を両手で持ち、顔の高さに掲げた。スパッツの前が、香織の顔のほうに向いている。しばし、そうして眺めていたが、なにか意を決したように、スパッツに顔を近づけた。涼子の位置からは、死角になっていたが、香織が、スパッツの、ちょうど恥部に当たる部分に、鼻を寄せたのは、どう見ても明らかだった。 涼子は、香織のその行為に、胃液が込み上げてきそうな気分になり、まぶたを閉じて顔をそらした。 「うっひゃっ!」 香織は、悲鳴みたいな甲高い声を発する。 「ちょっとちょっと……、さゆりも、この、南さんの、ま○こ汗の臭い、嗅いでごらんよっ」 涼子は、薄目を開け、性悪の後輩の姿を、視界の隅に入れた。 さゆりも、好奇心を抱いたらしく、下卑た笑いを顔に張りつけ、香織のところに近寄った。香織がぶら下げている、涼子のスパッツに、顔を寄せる。 それ以上は、もう見ていたくなくて、涼子は、ふたたび瞑目した。 「ぐえ! この臭い……、なんていうか、いかにも、毒素が、この股の部分に染み込んでるって感じですねえ」 香織とさゆりは、下品な笑い声を立てる。 いったい、この女たちの精神構造は、どうなっているのかと、涼子としては、不思議でならなかった。同性である女が着用していた衣類の、恥部が当たる部分の臭いを確かめる。どう考えても、常軌を逸した変態行為としか思えないが、それが、この場では、堂々とまかり通っているのだ。ここは、学校などではなく、自分は、それこそ、別世界にでも紛れ込んでいるのではないかと、そんな錯覚すら覚え始める。 「あっ、いいこと思いついちゃった……」 香織は、そうつぶやくと、地面に置いてある、涼子のソックスとシューズを拾い上げた。そうして、竹内明日香と足立舞の立っているほうに歩いていった。 さゆりも、香織の後を追う。 「ねえ、舞ちゃん……。舞ちゃんの好きな、南せんぱいが、今日、部活の練習の時、使ってたものなんだけど……」 香織は、舞の足もとの地面に、白いTシャツと黒のスパッツ、それにバレーソックス、ランニングシューズを並べた。 舞は、さり気なく鼻を押さえる。おそらく、涼子の衣類から発せられる、強烈な汗の臭気を、鼻腔に感じ取ったのだろう。 「あああっ、舞ちゃん……。もしかして、くさかった? 今、息、止めてない? だいじょうぶ?」 香織が、面白がって訊く。 舞は、泣き笑いのような表情で、口をつぐんでいる。 「はい、舞ちゃんにプレゼント。今日の、南せんぱいの、セクシーショーの記念品として、これ全部、舞ちゃんにあげる。欲しいでしょ? おうちに持って帰っちゃえ」 香織は、地面に並べた四点を指差す。 その勝手ぶりに、涼子は、唖然とさせられた。 舞は、ためらいがちに視線を落とす。涼子の身に着けていたものを、品定めするように観察している。それから、香織に尋ねた。 「えっ、でもでも、いいんですか……?」 「いいのいいの。舞ちゃんが欲しいって言うなら、南せんぱいだって、喜んで、これ全部、くれるに決まってんじゃない」 香織は、横目で涼子を見ながら、皮肉たっぷりに答える。 「あの、先輩、いいんですか……?」 今度は、聞き取れないくらいの小声だった。舞の、まん丸に近い大きな目が、こちらに向けられる。どうやら、涼子に訊いているようだ。 涼子は、信じられない思いで、舞の瞳を見返した。言葉が出なかった。本気で、欲しいと願っているのだろうか。涼子の汗で濡れそぼった、Tシャツやスパッツなどを。だとしたら、それは、もはや変態的な趣味としか言い様がない。足立舞に対して、肌のあわ立つほどの嫌悪感を抱く。それと同時に、自分は、この一年生に、とことん舐められていると痛感し、腹の底から怒りが込み上げてきた。 「あのさあ、あなた……、いいわけないでしょ? そこにあるものは、わたしが、部活で使うものなの。それ全部、あなたが持って帰ったら、わたし、これから先、どんな格好で、部活の練習に出ればいいっていうの? そもそも……、わたしのTシャツやスパッツとか、そんなものを持って帰って、どうするつもり? はっきり言って、人の汗で汚れたものを、欲しがるなんて、すっごい気持ち悪い」 涼子は、左手で、右腕の上腕をさすった。 叱られたことで、舞は、しょんぼりとした顔つきになった。 「南さん、バレー部のキャプテンのくせに、ずいぶん器が狭いんだね……。まあいいや。その代わり、あんた、自分のその体で、舞ちゃんを、ちゃんと愉しませてあげなさいね……。滝沢さん、次は、いよいよ、南さんのブラを取って」 香織は、目をぎらりと光らせ、秋菜に命じた。 「はーい」 秋菜は、淡泊に返事をし、涼子のところへ歩いてくる。荷物を取りにくるような、どこまでも平然とした態度で。 涼子は、そんな秋菜の顔を、憎しみを込めて、きっ、とにらんだ。しかし、それが、秋菜に対して、今の自分ができる精一杯のことだと思うと、よけい惨めな気持ちになった。 「なによ、その目は……。吉永さんの命令なんだから、仕方がないって、何度、言わせるつもりなのよ。ほらっ、ブラのホック、外すから、後ろを向いて!」 秋菜は、右手で、涼子の肩を乱暴につかんできた。 その手に、無理やり、九十度ほど体の向きを変えさせられる。 涼子の背後に、秋菜は回った。 ブラジャーのホックに、秋菜の指がかかる。 数秒後、ホックが外された。 続けざまに、両肩の肩ひもが、するすると落とされていく。 涼子は、ほとんど無意識のうちに、両腕で乳房を覆っていた。 秋菜は、涼子の前に戻り、手を突き出してくる。 「それ、大人しく、よこしなさいよ」 まるで、涼子が、ブラジャーを身に着けているのは、不当なことであるとでも言うような口調だった。冷酷な少女。というより、もはや、香織の命令を遂行するためだけに動く、血の通っていない、ロボットか何かのような感じである。 膠着状態に入った。 いくら息を吸っても、酸素を取り込めないように苦しい。乳房を押さえている両腕は、完全に硬直していた。 すると、秋菜は、うんざりしたように三白眼の目つきをした。 なんという怖ろしい顔なんだろう……。その瞬間、涼子は、心の底からそう思った。 「聞こえなかったの!? よこしなさいって言ってんのよ!」 秋菜は、金切り声で怒鳴り、涼子の胸に右手を伸ばしてきた。 胸の膨らみ。そこは、女の子にとって性的な部分であり、同性とはいえ、むやみに触れるべきではない、という当たり前の観念すら欠落しているのか、わしづかみにするような勢いで、涼子の左の乳房に、秋菜の指がめり込む。 涼子は、ひゅっと、喉から空気の漏れるような声を出してしまった。ブラジャーを引っつかまれたことで、反射的に、両腕をさらに乳房に押しつける。 しかし、秋菜は、引きちぎるつもりなのかという手つきで、涼子の体から、ブラジャーをはぎ取っていった。 当然、涼子としては、乳首を隠し、なるべく乳房全体の輪郭が表に出ないように、両肩を抱くポーズを取るしかなくなる。そうして、極寒の地に立たされているかのように、身を縮こまらせる。初めて、香織にブラジャーを奪い取られた時も、その指が、乳房の肉に深く食い込んだことで、強いショックを受けたのを憶えている。そして、今度は、滝沢秋菜の手によって、同じ感触を体に味わわされたのだ。この心の傷は、しばらく癒えそうにない気がした。 秋菜は、そんな涼子の気持ちなど、一顧だにしない態度で、白いブラジャーを手にぶら下げ、香織たち四人のところに歩いていく。涼子の身に着けていたものは、すべて香織に渡す。そのことを、すでに理解しているのだ。 香織は、秋菜から、涼子のブラジャーを受け取った。 その時、そちらからの、熱っぽい視線に気づく。 舞は、ほんのりと赤らんだ頬を、両手で包み込み、とろんとした目で、涼子の姿を凝視していた。涼子の半裸に、すっかり目を奪われている様子だ。もはや、涼子に対する遠慮の念など、忘却の彼方なのだろう。乳房の曲線、いよいよ露わになった、ボディライン、それと、まだパンツに覆われている部分……。それらを、穴のあくほど観察されているのが、嫌でもわかる。 しかし、もはや、舞に向かって、敵対的な視線を飛ばす気力も湧かなかった。 そのため、涼子は、舞と目を合わせるのを拒むように、コンクリートの地面を見つめながら、ただただ、自分の悲惨な運命を呪っていた。 秋菜が、涼子のほうに戻ってくる。 それが、何を意味するのか。 わかっているようで、わかっていないような気分だった。 「吉永さーん、もう、この人のパンツも、脱がせちゃって、いいわけ?」 秋菜は、能天気な調子で言った。 涼子は、肉体はおろか、心臓まで硬直するような感覚に襲われた。 「やあぁぁ……」 唐突に喉がけいれんして、勝手に声が出ていた。 「待ちなよ、滝沢さん」 香織は、しかし意外な言葉を発した。 「あなたさあ……、自分も、南さんの『仲間』だっていう自覚、ある? なんか、見てると、ずいぶんと澄ました態度で、南さんの服を、脱がしてるけど、そんなんで、大丈夫なの? 次は、あなたが脱ぐ番だってこと、忘れてないでしょうね?」 涼子は、秋菜の反応に注目した。 「えっ……。あの、待って、吉永さん……。やっぱり、それは、なし、っていうか、計画を、変更して、この女の、一人舞台ってことに、できないかな……?」 秋菜の顔色が、急変している。頬が、ぴくぴくと引きつっている様まで、目で確認できる。 「なに、寝ぼけたこと言ってんの、あなた……。自分は、南さんのことを、パンツ一枚の格好にさせたんでしょうが。それでいて、自分だけは、脱ぎたくない? いくらなんでも、虫がよすぎるよねえ?」 それについては、涼子も、香織の発言に同感だった。 「でも……、でもだよ? わたしは……、おしくらまんじゅうで勝ったんだし。そう。こーんな、汗臭い、獣みたいな女と、体をくっつけ合って、気が狂うような思いをしながらも、ちゃんと勝ったの。そのことを、もっと評価してほしい。あと……、そうだ。とにかく、この女を、素っ裸にして、ショーを演じさせようよ。それで、あの、一年生の子が、満足してくれたら、もう、それだけで充分じゃないっ。あっ、わたし、すぐに、もう今すぐ、この女の、パンツを脱がしてやるから、ちょっとだけ待ってて」 秋菜は、自己保身に満ちた主張をし、即座に、こちらに駆け寄ってきた。 「いやあぁ!」 涼子は、死神に迫られるような恐怖に見舞われ、思わず走って逃げ出した。 「逃げてんじゃないわよお! 学校から、抹殺されたくなかったらっ、じっとしてなさいよお!」 秋菜は、吹き荒れるような怒号を浴びせてきた。 「滝沢さん、あなたに、そんなことを決定する権利は、ないの」 香織が、再度、待ったをかけた。 秋菜は、ぴたっと足を止める。涼子も、それを見て、逃げるのをやめた。 「それに……、さすがに、冷酷すぎない? ちょっとくらい、『仲間』である、南さんの気持ちも、考えてあげたらどうなのよ? 南さんだって、あたしたちと同じ、年頃の女の子なんだよ? 年頃の女の子が、人前で、パンツを脱がされるのが、どれだけ恥ずかしいことか、それくらいは、あなただって、想像できるでしょう?」 どういう風の吹き回しか、香織が、まともなことを言い始めた。 「あっ、えっと、それは……」 秋菜は、右手の人差し指を頬に当て、斜めに視線を落とす。 「あたし、だんだん、南さんが、可哀想になってきちゃった。いくら、おしくらまんじゅうで負けたからって、一気に、パンツまで脱がせるのも、どうかってところだし……。だから、次は、滝沢さん、あなたが、今の南さんと、同じ格好になりなさい。パンツ一枚の格好にね。もし、自分で脱げないっていうなら、今度は、南さんに、滝沢さんの服を脱がすよう、あたしが、命じるから」 香織は、秋菜の全身を眺めながら話す。 今度は、滝沢秋菜の服を、自分が、脱がす……? そのことを思うと、涼子は、今までに感じたことのないような複雑な感情を抱いた。 秋菜は、中分けのストレートヘアを振り乱し、何度も頭を横に振った。 「いやよっ! わたしには、プライドってものがあるの! たしかに、この女は、吉永さんたちの前では、素っ裸でいるのが、お似合いだと思う。うん、わたしも、心から、そう思う。でも、わたしは、普通の女子高生なの! わたしと、こんな、救いようのないほど惨めな女を、一緒にしないで! わたし……、こんなふうにだけは……、絶対に、なりたくないっ」 驚き呆れるくらい、涼子のことは、好き放題に言ってくれる。秋菜の発言は、涼子にとって、到底、許せるものではなかった。 復讐心……。涼子の胸の内に、その感情が芽生え始めた。 涼子は、秋菜の着ているセーラー服を、ぼんやりと見つめる。 秋菜は、何か思いついたように、さらに続けた。 「あっ、そうだ……。わたしに、この女の、調教を任せてくれない? 言っちゃえば、この女なんて、吉永さんたちの、奴隷みたいなものでしょう? この女が、吉永さんたちの、従順な奴隷になるよう、わたしが、徹底的に躾けてやるから。ねっ? いい案でしょう?」 もはや、積極的に、加害者側に荷担しようとし始めた。 涼子は、怒りに歯噛みする。もし、秋菜から一方的に脅迫を受けている身でなかったら、自分は、彼女の頬を、平手で張っていたかもしれない。 香織も、呆れたように苦笑いした。 「滝沢さんって、面白い人だね……。ある意味、南さんが脱ぐよりも、面白いかもしれない。ますます、滝沢さんが、セクシーショーを演じるところが、見たくなってきちゃった。あたしたち、期待してるよ……。さっ、覚醒剤の件で、退学になりたくなかったら、今すぐ脱ぎ始めて」 わかり切った答えが、香織の口から返ってきた。 秋菜の瞳に、絶望の色が表れる。 きっと、彼女は、涼子が、そうなったように、闇に覆われた光景を、今、目の当たりにしているに違いない。 時が、静かに刻まれていく。 秋菜は、心神喪失したのか、焦点の合わぬ目で、空中を見つめているだけだった。 「やっぱり、滝沢さんも、自分じゃあ、脱げないみたいだねえ……。それじゃあ、仕方ないなあ。南さん、出番だよ。あたしからの、命令。滝沢さんの服を、脱がし始めて。まずは、制服の上からね。もし、滝沢さんが抵抗するようなら、バレー部で鍛えた、その腕っぷしでねじ伏せて、強引に脱がせて」 香織は、むしろ、悦ばしい展開だとでもいうように、涼子に命じてきた。 命令か……、と思う。 しかしながら、涼子を拘束している、見えない首輪から伸びた鎖を握っているのは、秋菜なのだ。香織ではない。そのため、香織と秋菜の意思が、対立するような場合、涼子は、香織に服従する必要はないのだった。だが、今は、このまま流されるように、自分の二本の脚は、秋菜のところへと向かっていきそうな感じがする。 今や、涼子にとって、滝沢秋菜など、どうなってもいい存在なのだから……。いや、少し違う。 これまでの、秋菜の、涼子に対する言動を思う。口汚い言葉で、涼子を、これでもかというほど侮辱し続けた。涼子の恥部を、いきなりわしづかみにしてきた。涼子の身に着けているものを、一つ一つ、容赦なくはぎ取っていった。しかも、挙げ句には、自ら進んで、涼子のパンツまでも脱がそうとしてきたのである。 それらを思えば思うほど、胸の内で、復讐してやりたいという気持ちが強まっていく。 わたしの敵だ。滝沢秋菜は……。 「どうしたの? 南さん。考え込んでるみたいだけど。いいんだよ、あたしの命令なんだから、遠慮しないで……。だいいち、滝沢さんの手で、無理やり、Tシャツもスパッツもソックスもシューズも、それにブラまで脱がされて、パンツ一枚の格好にされたっていうのに、ちっとも、悔しくないわけ? 滝沢さんに、同じことを、やり返してやりたいって、そう思わないの? ……今度は、南さんが、滝沢さんの服を、脱がす番だよっ」 香織は、不気味な微笑みを、涼子に向けてくる。 悔しいかどうか……? 当然、そりゃあ悔しい。悔しくてたまらない。秋菜に対しては、はらわたが煮えくり返っている。いや、そればかりか、憎悪の念すら禁じ得ない。 魂が抜けたように突っ立っている、秋菜の姿を、涼子は、ぎろりと見すえた。 なんで、わたしは、こんな格好をしてるのに、あんたは、きっちりと服を着たままなのよ……!? 理不尽極まりない状況だという怒りから、一歩、二歩と、そちらに脚が進む。 秋菜は、涼子が動きだしたのを察知し、はっとして、警戒する様子を見せた。 「やだっ! やめてっ! とにかく、あんた、そのパンツを早く脱ぎなさいよ! あんたが、あの一年生の子を、満足させてあげれば、それで、ショーは、終わりになるかもしれないじゃない! わたしだけでも助かるよう、最大限の努力をして! こっちに来ないでっ!」 そのヒステリックさが、よけい、かんに障る。 血も涙もない態度で、涼子の身に着けているものを、次々と脱がしていったくせに、今度、それを、自分自身が受ける番となると、半狂乱にわめき叫ぶ。まさに身勝手の極致である。怒りの炎に、油を注がれている気分だった。 パンツ一枚の格好で、両腕で乳首を覆ったまま、そろそろと秋菜に迫っていく。今の自分の姿は、香織たちの目には、さぞかし滑稽に映っているに違いない。しかし、今や、そんなことなど、どうでもいいと思う。涼子は、嵐のような感情に突き動かされ、着実に、秋菜のところに前進し続けていた。 一方、秋菜のほうは、金縛りに遭っているように動かない。 憎らしい秋菜との距離は、二、三メートルほどにまで縮まった。 このまま進み、秋菜の制服に、手をかけてやる……。 だが、ふと、その時、本能からの警告のようなものが、脳裏をよぎった。 今、自分は、冷静さを失っている。それは、とても危険なことだ。今一度、頭を冷やしたほうがいいのではないか。よく思い出せ。先ほど、何があっても、早まったことだけはするまいと、自分自身に言い聞かせていたはずだ。そもそも、今この瞬間、なにか、見えない力に操られるままに、自分は、行動を取っているような気もするのだが……。 それに、と思う。 いくら、秋菜に、やられたことをやり返すのだとはいえ、女の子の服を、無理やり脱がせるという、恥ずべき行為に、手を染めてしまっていいのだろうか……? 涼子は、秋菜のすぐ目の前で、わずかに逡巡した。 しかし……、秋菜を許す気にはなれなかった。むしろ、秋菜の顔を見れば見るほど、復讐心は、無限大に増幅していくような感じがする。そして、涼子と秋菜が、『仲間』同士であることを考えれば、現在の状況は、いかにも不公平だった。涼子ひとりが、パンツ一枚という惨めな格好をしているのに対して、秋菜のほうは、依然として、完全なる着衣の状態なのだ。秋菜にも、体の肌の大部分を露出させ、屈辱感を味わわせないと、とても気が済まない。その情念にも、背中を押された。 涼子は、最後の一歩を踏み出した。 秋菜は、恐怖に青ざめた顔で、涼子の目を見返してくる。 「やっ……。やめて……。お願いだから……」 銃口を突きつけられているかのような、哀訴の声。 それを聞いて、涼子は、ほとばしる憤怒の念に、目のくらむような感覚を覚えた。 脱がせてやる……。 その直後、頭に浮かんだのは、秋菜の衣類に手をかけるなら、乳首を覆っている両腕を、胴体から離さないといけないという思いだった。秋菜の至近距離で、それに、舞の視線もある。しかし、今となっては、その恥ずかしさすら、忘れそうな境地に至っていた。 秋菜のセーラー服に、目線を固定する。 涼子は、ついに行動に移した。青色のスカーフに、迷わず両手を伸ばし、その生地を握る。その瞬間、それまで、涼子の腕で覆われていた部分、紫がかった赤い色の乳首が、寒々しく露出する。秋菜に、間近で乳首を見られるのは、もはや防ぎようがないが、なるべく、舞の位置からは、乳房の中心部が死角に入るよう意識しながら、腕を動かした。そうして、ぞんざいな手つきで、スカーフを襟から抜き取った。 続いて、フロントのホックを外しにかかる。ほかの子のセーラー服を脱がすなど、むろん、生まれて初めての経験であり、その妙な緊張感から、かすかに手が震える。 秋菜は、今、自分の身に起こっていることが、まるで理解できていないような、そんな顔つきをしていた。 涼子は、それから、やや身をかがめ、セーラー服のサイドファスナーを上げた。 身を起こすと、秋菜の虚ろな眼差しと、また目が合った。秋菜の口が、わずかに動く。 「脱がさないで……」 今までとは別人のような、消え入りそうな小声だった。 うるさい。 「あなたも、わたしと同じ気持ちを、味わってみなさいよっ!」 涼子は、心の底でくすぶっていた感情を、秋菜にぶつけ、セーラー服のすそを、両手でつかんだ。秋菜に、そうされたように、涼子も、強引に生地をめくり上げる。その下の、薄い色のキャミソールが露わになった。 しかし、その時、突然、香織が声を発した。 「はい、ストーップ……。ストップ」 涼子は、手を止め、怪訝に感じながら、香織のほうに顔を向ける。 ストップ……? 意味がわからない。 とにかく、一刻も早く、秋菜のセーラー服を、脱がさなくては……。 ふたたび、秋菜の体に向き直り、両手に握っている生地のすそを、勢いよく引き上げた。すその部分が、秋菜の胸もとまで上がる。 ところが、再度、香織から声が飛んできた。 「だから、ストップって言ってるでしょ、南さん」 涼子は、水を差された気分で、手を止めた。だが、秋菜のセーラー服のすそは、手に握ったままでいた。その状態で、香織のほうを向く。 どういうこと……? 香織に、目で問いかける。 香織の顔が、薄笑いの表情に変わる。 「……やっぱり、いい。……滝沢さんは、脱がなくて、いい」 涼子の両手は、宙ぶらりんのまま固まった。 しきりとまばたきを繰り返しながら、香織を凝視する。 秋菜が、生気を取り戻したように、明るい声を出す。 「えっ……? わたしは、脱がなくていいの!?」 香織の顔に、より、はっきりとした笑みが浮かぶ。 「うん。まあ、そういうことかな……」 すると、秋菜は、ぱっと、涼子の顔に視線を移した。そして、涼子の手から、自分の青色のスカーフを奪い返す。 「あんた、わたしから離れなさいよ!」 秋菜の両手に、どんっと胸もとを突かれ、涼子は、よろめくように後退した。すぐさま、両腕で乳首を覆い隠す。 「なっ、なんで……。どっ、どうゆうこと……?」 思わず、そうつぶやき、きょときょとと、香織と秋菜を交互に見る。 香織に命じられたから、秋菜のセーラー服を脱がせるという、倫理にもとる行為に及んだのに、それを、いきなり中断させられてしまったのだ。恐ろしく決まりが悪かった。 次の瞬間、香織が、涼子を指差し、ぎゃはははははははっ、と盛大に笑い声を響かせた。 「最低! あいつ、滝沢さんの服、脱がせようとしたあぁぁ!」 それが呼び水となって、さゆりと明日香も、嬌声を発して大笑いし始める。 頭の中が、混乱の極みに達する。 なに、なに……!? どういうことなの……!? あんたが、滝沢さんの服を、脱がせろって、命令してきたんじゃない……!? もしかして、なにかの、罠だった……!? わたしの立場は、どうなるわけ……!? なんで、わたしだけが、恥ずかしい目に遭わないといけないのよ……!? 涼子は、この十七年間の人生で経験してきたもの、すべてが、一気に弾け飛んだかのような恐慌に襲われた。 「や、や、や、や、や、やだやだやだ、な、な、なんで、わたしだけ、こんな格好でいないといけないのよっ、だったら、わたしも、もう、服、着るからっ」 脱がされたものは、香織たちの後ろに捨て置かれている。その場所に、一目散に向かおうとした。だが、精神の均衡が、すっかり崩れており、その影響により、身体機能まで狂っている感じで、脚が、もつれにもつれ、うまく前に進めない。 しかも、石野さゆりが、瞬時に反応し、涼子の身からはぎ取ったものを、一つ残らず拾い上げ、鬼ごっこをするように逃げ始めた。 「おっ、おっ、おかしいじゃないっ! どうして、滝沢さんは、脱がないでいいのに、わたしは、こんな、パンツだけの格好をしてないといけないのよおぉぉ! わたしの服を、返してえぇぇぇ! こんなの、いやぁぁぁぁ!」 涼子は、声の限りに叫んだ。両腕で乳首を覆ったまま、泥酔状態のような覚束ない足取りで、性悪の後輩を、どたどたと追っていく。まるで、小屋が炎に包まれ、あっちへこっちへと逃げ回っている、ニワトリのような、そんな無様な姿だった。 吉永香織と竹内明日香は、まさに抱腹絶倒していた。 つと、視界の端に、同じ『仲間』であるはずの、滝沢秋菜の姿を捉える。 滝沢秋菜は、完全に傍観者の風情だった。いや、そればかりか、涼子の激烈な醜態ぶりを、冷笑的に眺めている感すらある。 そして……、怖ろしいことに、涼子に告白の手紙を手渡した、一年生の足立舞までもが、手を叩くようにしてはしゃいでいた。 「いやあああああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」 陰鬱な地下の空間に、涼子の悲痛な絶叫が響き渡る。 六月の蒸し暑いある日の夕刻、学校の体育倉庫の地下で、純朴を絵に描いたような生徒、南涼子を生贄とした、よこしまな少女たちによる地獄の饗宴が、ずるずると幕を開けたのだった。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.