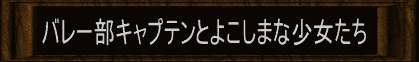
第二十五章〜もどかしい距離感
同性残酷記ご案内へ
小説のタイトル一覧へ
目次へ
子供から大人の女性へと成長していく過程における、もろもろの身体的変化に関しては、ともすると、ネガティブに受け止められがちだ。 とりわけ、陰部の発毛に限っては、ひょっとすると、世の大多数の女の子が、言葉にならないショックを受け、友達にも、また親にも、このことを知られたくない、自分の胸の内に秘めておきたいと、そんなふうに考えるのかもしれない。 もちろん、十七歳の今となっては、すでに、遠い過去の話である。 しかしながら、誰にも見せられない、という思いだけは、第二次性徴期を迎えた当初から変わらぬままだった。その最大の理由は、陰部の毛深さに、強烈なコンプレックスを抱えていることにある。 自分とは、極めて微妙な関係にある、二人の生徒も見ている前で、そんな部分をさらけ出さねばならない状況に追い詰められた身としては、とにもかくにも、プライドを、綺麗さっぱり捨て去らなければならなかった。また、その前段階として必要なのが、徹底的な自己否定だった。 セーラー服姿の生徒たちの前で、ただひとり、全裸姿をさらしている、今のわたし。この地獄絵のごとき惨状こそ、わたしと、彼女たちの力関係を、端的に物語っている。わたしは、見えない首輪に身を拘束されており、言ってしまえば、彼女たちの奴隷なのだ。奴隷であるがゆえに、身に着けていた衣類はおろか、人間にとって大切なものを、ほぼ全部、奪い取られたというわけだ。 そう……。 わたしに残されているものといえば、この裸の体だけ。それも、健全な状態の体ではない。全身の毛穴という毛穴から、止めどなく噴き出してくる、あぶら汗により、髪の毛は、頭皮にべったりと張りつき、腋から、乳房から、おしりから、汗のしずくが、ぽたぽたと、地面にしたたり落ち続けているような有様である。また、その汗の量に正比例するように、自分の体が、猛烈な臭気を放っていることも、嫌というほど認識している。そんなわけだから、自分のことながら、思春期の少女らしさとは、恐ろしくかけ離れた、まさしく恥まみれの体だなと、つくづく感じさせられる。 あと、残されているものを、しいて挙げるとすれば、醜く歪んだ、この心。 どうして、わたしだけ、こんな悲惨な目に遭わないといけないのよ……!? この世の中、不条理にもほどがある。許せない。正直なところ、今この瞬間、幸福な時間を過ごしている人たちが、世間には大勢いると思うだけで、気が狂いそう……。 これでは、自ら認めざるをえない。 今のわたしは、生きとし生けるものすべてを憎む、怨念の塊と化してしまっている。 体は不潔この上なく、おまけに、心までも腐りきった、毛むくじゃらのケダモノみたいな生き物の、わたし、南涼子……。うっわぁ、サイアク……。 ここで、百八十度、考え方を変えてみればいい。 だけども……、こんな女を、支配者側の立場である彼女たちは、奴隷として、つまりは、ひとりの人間として扱ってくれようとしているのだ。それならば、わたしとしては、むしろ、感謝すべきことなのではないだろうか……? よし、わたしは、もう、すっかり心を入れ替えた。これからは、彼女たちによる、いかなる命令にも、喜んで服従しよう。そうすれば、彼女たちは、わたしの態度を評価してくれるかもしれない。もしも、彼女たちから、ちょっとでも優しい言葉をかけてもらえたら……、わたし、とっても嬉しいなっ。 あっ、なんだか、胸の中にあった、ドロドロした感情が、霧みたいに消え去っている気がする。よかったあ。せめて、心くらいは、清らかでありたいもの。 ハハハッ……。 そして、今現在、岩礁に着生した藻のように陰毛の茂った、自分のそのVゾーンを、完全にさらけ出した格好で立っているのだった。 すでに、覚悟はできていたはずだ。 だが、目の前に立つ、彼女たちの顔つきを見ると、みな、揃いも揃って、同性とは思えぬほど、背徳的な好奇心を丸出しにしているような印象を受け、そのため、だんだんと、戸惑いの念が、胸いっぱいに広がっていく。 やっぱし……、わたしの、下の毛、尋常じゃないほど濃い、ってことだよね……? 南涼子は、ぎこちなく笑いの表情を作ったまま、顔全体の筋肉が引きつるのを自覚した。 「ねえねえ、教えて、南さん。どう? 今の気分は……」 吉永香織が、ねっとりとした口調で尋ねてくる。 今の、気分……? 涼子は、つかの間、言葉を失っていたが、ここは、なんらかの返事をしなければ、埒が明かない空気であることを悟る。 「あっ、ええっと……、率直なところ……、かなり……、気まずいっていうか、は、恥ずかしいかなあ、なんて思ったりしてっ」 そう口に出すと、その言葉どおり、より一層、いたたまれなくなり、それこそ、穴があったら今すぐにでも逃げ込みたい気持ちになる。だが、それでも、なるべく自然なスマイルを心がけた。 「かなり、気まずい……? あたしたち、女の子同士なんだから、なにも、ことさら気まずく感じる必要は、ないんだよ? それともなに? やっぱり、南さん的には、滝沢さんと、舞ちゃんの目が、気になって気になってしょうがないってわけ? まるで、男子に、自分の大事なところを、見られてるような気分なのかな?」 香織は、つり上がり気味の目に、ほの暗い愉悦の光を湛える。 「あっ! いやいやいや、もう、ぜーんぜんっ、ぜーんぜんっ、そ、そんなことなくってっ! 別に、誰かを、特別、意識してるとかじゃなくって! ただ、あの、なんていうかっ……」 涼子の声は、悲鳴みたいに上ずっていた。 「あらあら……。そこまで躍起になって、否定するところを見ると、どうも、図星だったみたいだね……。もう、バレバレだよ……? まったく、南さんってば、本当に、わかりやすい女なんだから。一言で言うなら、乙女そのもの」 香織は、女性心理学の権威のごとき風情である。 涼子は、好きな人の名前を、ずばり言い当てられた女の子みたいに、へどもどしてしまった。そして、香織が名前を出した、『二人』のほうには、絶対に目を向けられないと感じる。 「でも、だけど……、まん毛の検査を受けるのは、南さんの、最低限の義務だから、なんとか頑張り抜いてちょうだい。まあ……、あたしからアドバイスするとしたら、滝沢さんに見られてるから、舞ちゃんに見られてるから、恥ずかしい、恥ずかしいって思ってると、何十倍も恥ずかしくなってくるし、逆に、なんでもないって思っていれば、なんでもないことで終わるのよ? いい? わかった? 理解した?」 やたらと上から目線の香織の物言いに、内心、かちんときている自分がいた。しかし、フラットな心で、香織の言葉を解釈すれば、涼子のためを思って言ってくれていることだけは、確かであるという気がした。 「はいっ! わかりました! ありがとうございまぁーっすっ!」 涼子は、元気いっぱいの小学生さながら、はつらつと答えた。 香織は、すこぶる満足げに、にんまりと笑う。 「うん、いいお返事ね。そういう素直な子は、あたし、大好きよ」 それを聞いて、涼子も、ほっとし、誠実な思いを込めた眼差しで、香織の顔を見つめ返す。 「あれれ……、南せんぱいったら、今までの反抗的な態度が嘘みたく、まさに、優等生っぽくなっちゃって。あたしたちに、気に入られたほうが、得策だと判断したのかな。でも、なんか、必死感が、ものすごい伝わってきて、痛々しいし、果たして、いつまで、いい子を続けられるか、見ものっちゃあ見ものですねえ……」 後輩の石野さゆりが、香織に向かって、ぼそぼそと、しかし、聞こえよがしに言う。 聞き捨てならない。 涼子は、その後輩の姿を、横目で眺めた。 さゆりは、いつもの薄笑いを浮かべながら、セミロングの髪を撫でつけている。その、人を舐めきったような顔つきといい、いかにも軽薄そうな仕草といい、一目見た時から、生理的に合わない、という印象を持ったことを思い出す。だが、その吐き気にも似た不快感を、腹の底に、ぐっと押し込める。 「あの、石野さん、だったよね……? ううん、わたし、ちーっとも必死なんかじゃないの! わたしなんて、要するに、吉永さんや石野さんたちの、奴隷でしょ? それなのに、同じクラスメイト同士なんだから、対等でありたいとか、年下の子には、先輩と後輩の上下関係くらい、わきまえてほしいとか、わたし、そういうことに、こだわり続けて、くだらないプライドを守りたがってた、って感じ。そのこと、本当に、反省してます。今まで、生意気にしてて、ごめんねっ? だから、うん、また、わたしが、間違ったことしたら、遠慮せず、どんどん指摘してねっ」 涼子は、さゆりのほうに、左手を突き出し、ひらひらと振ってみせる。 だが、さゆりは、涼子の健気さに感心するどころか、むしろ、小馬鹿にするように、ひひひっ、と笑い声をこぼした。 これ以上、あの後輩の顔は、視界に入れていたくない……。 その思いから、涼子は、目を背けるように視線を外した。 そして、その視線を、バレー部のマネージャーであり、目の前に立つ生徒たちのなかで、涼子にとっては、もっとも縁の深い、竹内明日香のほうに、さり気なく向けた。 目が合うと、明日香は、ほんの少しだけ首を傾け、こちらに、やんわりと微笑みかけてきた。 そんな明日香の仕草が、妙に色っぽく見えたがために、涼子は、不覚にも、たじろいでしまい、自分のべたついた髪の毛の右サイド部分を、軽く耳にかけた。あの子は、存在自体が反則だ、という感慨を抱く。今さらだが、彼女の美貌たるや、なんら変哲のない、この高校に通っている生徒であることが、ある種の奇跡にすら思えるほどである。それほどの美少女から、意味ありげに見つめられると、同性としても、気後れして落ち着かない心地にさせられる。それをごまかすように、涼子も、明日香に向かって、てへへっ、と無理して笑い返してみせた。 その後も、しばし、涼子と明日香は、じっと目と目を見合わせていた。そうしていると、不思議なことに、支配者と奴隷という主従関係を超えて、明日香とは、だんだんと、心が通じ合っている感じすらしてきた。まるで、バレー部の部員同士、毎日、苦楽を共にしてきた仲であることを、互いに確かめ合うかのように。 しかし、ふと、違和感を覚える。 トップモデルにも勝るとも劣らぬ美少女である、明日香のその顔に浮かんだ、魅惑的な微笑。一見、涼子に対する親愛の情の表れと捉えられるが、見れば見るほど、彼女の口もとは、なにか、そこはかとない悪意に歪んでいるような、そんな印象をも受けるのだった。 ひょっとしたら、明日香は、今、心の中で、涼子のことを、ひたすら嘲り笑っているのではないか……? そう考えたとたん、涼子は、ぞわりと寒気に襲われた。 セーラー服姿の生徒たちの前で、ただひとり、全裸姿をさらし、恥部を隠すことすら許されない立場である、奴隷、南涼子。支配者側である彼女たちが、今この瞬間、涼子のコンプレックスである、陰毛の生え具合に、強い好奇心を寄せているであろうことは、ほぼ間違いない。屈辱……。これは、まごうことなき性暴力である。だというのに、涼子は、女として、また、人間として持つべき最低限のプライドまで捨て、香織たちのご機嫌を取るために、滑稽なくらい従順に振る舞い始めたのだ。きっと、明日香の目には、そんな涼子の見せる、一挙一動が、笑いの種として映っているに決まっている……。 もはや、涼子にとって、今、目を合わせている相手は、茶目っ気あふれる美少女などではなく、魔性の女と化していた。 うーん? 明日香のあの、人を挑発するような声が、今にも聞こえてきそうな気がする。 そう……。 忘れられるはずがない。 竹内明日香は、肩を並べる者はいない美貌を武器に、マネージャーとしてバレー部のなかに溶け込み、そして……、キャプテンである涼子のことを、罠にハメた。 もしも……、彼女のことを、信じさえしなければ、わたしは、今こうして、陰惨な性暴力の被害者という、息もできないような立場に立たされることはなかったのだ。 わたしを、地獄に引きずり込んだ、どれだけ憎んでも憎み足りない女……。 いや、そればかりではない。 先ほど、あの女は、このわたしに何をしてきたのか……。 涼子の裸出したVゾーンに、べたりと押し当てられた、蝋のように白い両手。もっさりと茂った陰毛を引っ張ったり、Iゾーンにまで指を這わせたりしながら、恥部を執拗にまさぐり続けるという、明らかに一線を越えた行為。あまつさえ、洗ってもいない、涼子のおしりの、その割れ目に、鼻を寄せ、便の残滓の臭気をも吸い込んできたこと。それらを思い起こしたとたん、耐え難い屈辱感に、体の芯が、かっと熱くなった。 この、性的異常者……! この、変態サディスト……! 涼子は、明日香に向ける自分の眼差しが、瞳に火が灯ったかのごとく険しくなっていくのを感じ始めた。 しかし、すぐさま、ぶんぶんと頭を横に振り、自分自身に強く言い聞かせる。 わたしは、プライドのかけらを持つことすらおこがましい、奴隷なのよ……! 奴隷。奴隷。奴隷……。 ほどなくして、燃え上がった憎悪の炎が、徐々に鎮静化していった。 よく胸に刻み込んでおこうと思う。 もし、感情が荒ぶり、精神の均衡が崩れそうになった時は、こうして、心の中で魔法の呪文を唱えればいいのだ。 それから、改めて、明日香の顔に目をやった。 純真な心を取り戻し、目と目を見合わせていると、やはり、明日香は、フランス人形に生命が宿ったのではないかと、そう真剣に思いたくなるほどの美少女だった。 同性として、正常な範囲の軽い嫉妬心が、自然と芽生える。 涼子は、あえて目を潤ませるよう意識し、拗ねるように、きゅっと唇を突き出した。 チェッ……。明日香っちは、ホント、可愛くていいよなあ……。わたし、生まれ変わったら、明日香っちみたいな女の子になりたいよ……。その体からは、とってもいい匂いが伝わってきそうだし、こんなケダモノみたいな体のわたしとは、本当に大違い。そもそも、奴隷のわたしなんかと、比べる時点で、申し訳ない話だよね……。 そうして無言で語りかけている最中、誰がどう見ても見苦しいと感じるであろう、毛深い陰毛までさらけ出した状態で、同じ学校の生徒に対して、媚びた表情を作っている自分自身は、彼女たちの目に、どれほど浅ましく映っていることだろうか、という思いが、脳裏に浮かんだ。が、次の瞬間には、その思考を打ち消した。 でも、でも……、明日香っち……。わたしは、明日香っちたちの奴隷だけども、これでも、いちおう、生物学上は、女の子なんだよ? だから、わたしのこと、汚いとか、くさいとか、あんまり言わないでね? わたし、明日香っちみたいな可愛い女の子に、そんな言葉を浴びせられると、何倍も惨めな気持ちになっちゃうよ……。 その時、滝沢秋菜の声が、耳に入ってきた。 「これはこれは……、今のご時世では、天然記念物ものの、すさまじい毛の量ねえ……。まるで、野生児みたいじゃないの。南さん、正直に答えてほしいんだけど、その、下の毛、いつから生え始めたのお?」 秋菜は、涼子のVゾーンを、ぶしつけな目で見下ろしながら、苦笑いを浮かべている。 デリカシーのかけらもない、秋菜のその発言に、涼子は、愕然たる思いを禁じ得なかった。 滝沢さん……。 なんなの、あなたは……? 下の毛が、いつから生え始めたのか、って……。そんなこと、なんで知りたがるわけ……? 悪趣味すぎるでしょ……! しかも、すさまじい毛の量って。野生児みたいって。言われたこっちは、すごい傷つくんだけど……! というより……。 どうして、わたしは、誰にも見せられないはずのVゾーンを、よりにもよって、苦手意識を抱いている相手、滝沢秋菜に直視されている状況下でありながら、平然と立っていられるのだろう……? 涼子は、その疑問を抱いたとたん、頭の中で、何かが爆ぜたような感覚に襲われ、脊髄反射的に、自分の陰毛部の前で、両手を重ねた。一拍遅れて、心の奥底から突き上がってきたのは、錯乱におちいりそうな、猛然たる羞恥感情だった。 やだやだやだ、恥ずかしい……! 滝沢さん、やめて……! わたしの変なところ、じろじろと見てこないでよ……! しかし、その時、支配者側のリーダー格である、香織が、いかにも、がっかりした、とばかりに舌打ちした。 涼子は、それを耳にして、すぐに、しまった、と思った。慌てて両手をどかし、それから、ふうーっと、上空に向かって息を吐き出す。 奴隷の身である、わたしの体を、滝沢秋菜『様』が、隅々まで観察しようとするのは、当たり前の話じゃないの……。落ち着け、落ち着け、わたし……。 その後、秋菜からの嫌な質問にも、ちゃんと答えるべく、ポーカーフェイスを装いつつ、軽く首を傾けた。ちょっとばかり考え込むように、右手の人差し指を、頬に当てる。 「うーん……。毛が生えてきたのは……、しょ、小五くらい……、かな?」 真摯な姿勢とは裏腹に、いい加減な答えを口にしてしまう。 「出ましたあー。当たり障りのない、模範的な回答!」 秋菜が、すかさず突っ込んでくる。 「うそうそ」と、石野さゆり。 二人の反応に、涼子は、困惑を覚える。 「南さーん。正直に答えてって、わたし、言ったじゃなーい。本当のところ……、南さんは、小二の頃か、もっと早ければ、小一の時点で、もう、生え始めてたんでしょう? それくらい、早熟じゃなかったら、とても、そこまでの状態には、ならないわよお……。ねえ?」 秋菜は、賛同を求めるように、ほかの四人のほうに顔を向ける。 香織とさゆりは、涼子を見ながら、にたにたと笑っている。 もちろん、涼子自身、陰毛の量のおびただしさを、やゆされていることくらい、十二分に理解しており、胸が張り裂けそうほど悲しくて、涙を堪える時、人が、よくそうなるように、目もとの筋肉が、ぴくぴくと引きつれを起こし始めた。しかし、そんな自分を懸命に鼓舞し、明るく声を張り上げる。 「あっ! でもさ、でもさ……、こういう、毛って、知らないうちに、気づいたら生えちゃってた、って感じじゃない!? みんなも、そうでしょ!? だから、正直、わたしも、自分の体のことだけど、生えてきた時期って、よく憶えてないんだよねー。あ、だけども、滝沢さんの言うとおり、小五っていうのは、テキトーすぎたかもしれないっ。ごめんごめん!」 涼子は、まるで、自分も、目の前に立つ彼女たちの、輪に入っているかのごとく、フレンドリーな空気を作ろうとしていた。自分は、陰惨な性暴力の被害者などではなく、たとえば、温泉で、仲のいい友人たちに、裸を見られているようなものなのだ……。そのように脳を錯覚させたいという、自己防衛の本能が、かつてないほど働いている状態なのかもしれない。しかし、その一方で、支配者側である彼女たちに対し、これほどまでに卑屈に振る舞っている自分は、いったい、何者なのだろうという情けない思いも、胸の内で延々と渦巻き続けている。 「舞ちゃん、舞ちゃん……。どう? どう? 南せんぱいの、大人の女の、まん毛は……」 香織が、おどけたような低い声で、隣の生徒に尋ねる。 涼子は、息を呑む思いで、そちらに目をやった。 支配者側である彼女たちのうち、ひとりだけ、異様な雰囲気を放っている生徒がいることは、だいぶ前から感じ取っていた。しかし、自分は、意図的に、その彼女の存在を無視していた気がする。 セーラー服を着込んだ小学生にすら見える、一年生の足立舞は、身を乗り出すような姿勢で、涼子の恥部を、まばたきもせず凝視している。まるで、覚醒剤でも打たれたかのように散大した瞳孔。荒い息遣いのせいだろう、絶えず上下している肩。もはや、興奮は、最高潮に達しているという様子である。 そう……。 わたしが、全裸にさせられた最大の理由は、同性愛的な傾向のある、あの子に、性的な悦びを与えてあげるため。 一瞬、身悶えしそうな生理的嫌悪感が、全身を駆け巡ったものの、すぐに、奉仕の気持ちに立ち返る。 そうして、左斜め前に立っている舞に、自分の陰毛部を、より見えやすくするべく、涼子は、彼女と正対するように、ゆっくりと体の向きを変えた。 「あ、あの、ホント言うと……、さっき、南先輩の裸の写真、見た時、あたし、え? なにこれ? 嘘でしょ? みたいに、カルチャーショックな感じで、だから、ずっと生で見てみたい、って思ってたんですけど、まさか、本当に、こんな毛深い体してたなんて……。なんだか、高校生の女の子じゃないみたい……」 舞は、涼子のVゾーンから、目を逸らそうともせず、今の心情を熱っぽく吐露する。その夢中っぷりからは、なにか、涼子の陰毛、一本一本の縮れ具合まで、網膜に焼きつけたがっているかのような、鬼気迫る執念が、ひしひしと伝わってくる。 涼子は、そんな舞に対して、怒りを表すことはせず、逆に、慈悲深い表情を意識し、小さく微笑んでいた。しかし、その口もとの笑みとは裏腹に、左右の太ももの外側をつかんでいる、両手の指先には、ぎりぎりと力が入りっぱなしだった。太ももの肉に、深く爪が食い込んでおり、早くも、血が滲み出てきている感じがする。女としての本能が、その痛みに意識を向けることで、精神的苦痛を紛らわせよと、自分の肉体に、指令を送っているのかもしれない。 「あ、でもでも、そう言う舞ちゃんだって、高校三年生の半ば頃になったら、南せんぱいみたいに、まん毛が、びっしりと生え揃ってるかもしれないよお? どうする? こんなふうになっちゃったら」 香織が、冗談めかして訊く。 「あっ、あたしは、絶対、こんなふうにならないと思う……。だって、あたし、この、十分の一も、生えてないですもぉん……」 舞は、茫然とつぶやくような口調で、そう答える。 「ええ! うそっ! ってことは、舞ちゃんって、もう、下のお毛ヶ、生えてたの!?」 香織は、わざとらしくのけぞり、仰天した素振りを示す。 その時になって、舞は、ようやく、涼子のVゾーンから視線を外し、慌てふためいた様子で、香織のほうに顔を向けた。 間を置かず、秋菜も、驚きの声を上げる。 「わたしも、びっくりよお! あなたみたいな、可憐な女の子は、あそこも、まだ、つるつるのすべすべ状態だと思ってたのに……。まさかまさか、大人の女と同様に、まん毛なんてものが、生え始めてたとはねえ……。お姉さん、かるーいショックだわーん」 二人の先輩から、性的なからかいの言葉を浴びせられ、舞の乙女心は、爆発的に燃え上がったらしい。それこそ、秋菜の言う、『すべすべ』のほっぺたが、血しぶきを浴びたかのごとく真っ赤に染まっている。 「いやいやいやぁ……。やめてくださいっ。そういう、毛の話とかぁ、あたし、恥ずかちぃですっ」 舞は、紅潮した顔を見られたくない、というふうに両手で頬を包み込むと、ふるふると身を横に振った。 第二次性徴期を迎えたばかりのように、外見も精神年齢も幼すぎる、一年生の生徒にとっては、自分自身の体のこととなると、陰部の発毛について言及されるだけでも、悲鳴ものの恥ずかしさらしい。だというのに、そのVゾーンを、実際に、さらけ出す格好で立っている、涼子の立場のことには、まったくの無頓着という、あきれ返るしかない身勝手ぶりである。 「うーん、舞ちゃんたら、可愛いんだからぁ。ごめんねえ、あたしたち、舞ちゃんに、意地悪なこと言っちゃって」 香織は、舞の頭を、ぽんぽんと軽く叩く。 だが、舞は、ぷいっとこちらを向く形で、ふたたび、涼子の陰毛部に視線を注いできた。不機嫌そうに、唇を曲げている。 「そんなに怒らないでえ、舞ちゃーん。もう、仕方ないなあ。お詫びのしるしに、いいものあげる……。あのさっ、さっきは、舞ちゃんに、南せんぱいの腋毛を、記念品として、プレゼントしたでしょ? で、今度はぁ……、せっかくだし、記念品を、もっとエロエロなものにグレードアップしてぇ……、南せんぱいの、あの、ボーボー状態の……、ね? これ以上は、あたしが言わなくても、なんのことを指してるか、わかるでしょ?」 香織は、涼子の顔をうかがいながら、舞に対して語りかける。 舞は、やや真剣な顔になり、目をしばたたいた。 「えっ、えっ……。まさか……。え、もしかして、南先輩の……、ま……」 最後まで口にすることには、ためらいがあるらしく、言葉を切る。 「そそっ。その、まさか、よ。もし、舞ちゃんが、記念品として欲しいと思うんだったら、自分のお手々で、抜いて取ってきな。南せんぱいに、くーだーさいっ、てお願いして」 涼子は、香織の話を聞きながら、半ば、無我の境地に至っていた。 「ええっ……、でも、なんかなんか、もじゃもじゃの毛が、汗? で、べたべたしてるように見えて、ばっちい感じがするし……、顔を近づけたら、すごい臭いがして、ウゲッ、てなりそう」 まるで、たった今、二人の先輩から恥をかかされた、その憤りの矛先を、舞は、無力な涼子に向けるかのように、歯に衣着せぬ物言いをした。 涼子は、その発言で傷ついたという意思を示すべく、舞に向かって、軽くにらむ目つきをし、ちょっとだけ頬を膨らませてみせた。 「あ、言っちゃったね、舞ちゃん。すごい臭いがして、ウゲッ、てなりそう、だなんて。あたしたちでさえ、南さんの気持ちを考えて、そのことだけは、言わなかったのに」 香織は、つり上がり気味の目を、ぎょろっと見開く。 「だってぇ、だってぇ、本当に、そう思っちゃうんだしぃ……」 舞は、悪びれもせず、言い訳っぽく口にする。 「だけどね、舞ちゃん。大好きな人の臭いなら、たとえ、どんな激臭でも、全然、気にならないはずだよ。恋って、そういうものでしょう? だから、取りあえずは、試しに、南せんぱいの、あそこの臭いを、近くまで行って、くーんくんっ、て嗅いでごらん。それで、どうしても無理、触りたくないって思ったら、そのまま、回れ右して戻ってくればいいの。はい、何事も、やってみることが大事。ささっ、ゴーゴー、レッツゴーッ」 香織は、アニメの萌えキャラクターみたいな調子で、舞を促す。 やがて、舞の表情が、デレデレと崩れていった。 「じゃあ……、ちょっとだけ……。いいんですよね? 先輩っ」 涼子の立場など一顧だにせず、舞は、香織にだけ確認を取る。 「もちろんよ」 香織は、勝手に快諾する。 涼子は、その場に立ち尽くしたまま、心の中で、取り憑かれたように呪文を唱え続けていた。 わたしは、奴隷なのよ……。 高校三年生であり、バレー部のキャプテンを努めてもいる、わたしと、まだ、中学を卒業したばかりの一年生であり、か弱さを絵に描いたような体つきの、彼女という、先輩後輩の上下関係、あるいは、フィジカル面での強弱など、今は、考えるにも値しない事柄だ。また、かつては、女同士でありながらも、彼女が、ゆでだこのように赤面しながら、わたしに、ラブレターを手渡してきた、あの過去の記憶も、忘却の彼方へと消し去るべきだろう。 要するに、わたしと、彼女の力関係は、もはや、完全に逆転しており、その落差は、天と地ほどもあるということ。 だから、支配者側に付いている、彼女が、奴隷である、わたしの体の、性的な部分の臭いを確かめたいのなら、それを、黙って受け入れるべきなのだ。その結果、もしも、彼女が、満足感を示すのなら、わたしは、感謝の念を持てばいいし、逆に、彼女が、『くさい』と不快感を露わにしたなら、わたしは、ごめんなさい、と頭を下げればいい。 ただ、それだけのことよ……。 怖くなんかない……。 悲しくなんかない……。 屈辱なんかじゃない……。 しかしながら、涼子は、足立舞の顔つきを、改めて目にし、思考途絶するほど唖然とした。今や、舞は、よだれを垂らさんばかりに、だらしなく口を半開きにし、支配者側の者というより、正反対に、女子高生の身分でありながら、この世の底辺まで、堕落しきった人間のごとき風情を漂わせていた。 その舞が、一歩、二歩と、こちらに向かって足を踏み出した。 まもなく、舞の足取りが、とととっ、と早まったのを見た直後、涼子の脳裏に、めくるめく閃光が走った。その光の中に映し出された、卒倒しそうになる情景。全裸で立つ自分の足もとに、幼い妖魔じみた女子が、ちょこんとしゃがみ込む。自分としては、堪らず腰を引きたいところだったが、感情を殺して直立し続ける。すると、その女子は、さらに、すーっと、こちらに顔を寄せてきた。それこそ、陰毛に、鼻先が触れるか触れないかという、超至近距離まで。そして、彼女は、ある種のエクスタシーに浸りきっているかのような、とろんとした眼差しで、鼻をひくつかせ始め……。 次の刹那、涼子は、弾かれたように、後方に飛び退き、さらに、左手で、さり気なくVゾーンを半分ほど隠す。 「え、え、えええ、えっ……。ちょっ、ちょっと待って。ごめん……。これって、いくらなんでも、おかしく、ない……?」 なるべく、落ち着いて対応したかったが、出る声が、一オクターブほど高くなっていた。 その場に、時間が止まったかのような空気が流れる。 「どうしたの? 南さん……。早くも、いい子を、続けられなくなっちゃったの?」 香織が、皮肉な口調で言う。 「ううんっ! 違う、違う! わたしのほうは、別にいいんだけど、この子に、ショックを与えるのは、可哀相かなぁー、なんて、思ってさ! だって、わたしの、『ここ』、めちゃめちゃ蒸れてたから、絶対、気絶しちゃうほど、くさいだろうし……。だから、やめておきなっ? ねっ?」 涼子は、目の前にいる舞に対して、幼児をあやすように笑いかけた。かろうじて、おおらかな態度を取り繕ったものの、心臓が乱調を来たし、ばくばくと音を立てていた。 舞は、呆気に取られた様子で、ぱちぱちとまばたきをする。それから、香織のほうに、何かを訴えるような視線を向けた。 「舞ちゃん、舞ちゃん……。南せんぱいったら、どうも、舞ちゃんに幻滅されるのが、怖くて怖くてしょうがないみたい。舞ちゃんには、いつまでも、かっこいい女だと思われていたいみたい。どうする? そんな南せんぱいの女心を傷つけないよう、ここは、引いてあげる?」 香織は、しんみりと舞に訊く。 すると、舞は、しゅんとなった。その姿は、彼女が、涼子の肉体に関することに対して、およそ正常ではない程度の好奇心を抱いている、という事実を、如実に現していた。 涼子は、なんともいえぬ忌まわしさを覚える。 「南さんさあ、あなた、自分の口から、『わたしは、奴隷だ』って言ったよね? だから、南さんは、ようやく、自分の立場を自覚したんだなって、あたし、嬉しくなってたんだけど……、やっぱり、あなた、プライドを捨てきれてないっぽいねえ……。あたしとしては、お互いに、気持ちよくセクシーショーを始めたいから、あなたには、正々堂々と、まん毛の検査を受けてもらいたいんだけど、ダメ? 無理? 苦痛すぎる?」 香織の機嫌が、だんだんと悪くなっていくのを感じる。 「いえ! ごめんなさいっ! あの、わたし、南涼子は! 奴隷として、正々堂々と、まん毛の検査を受けることを誓います! どうぞ、よろしくお願いしまーっす!」 涼子は、生徒会長然とした語気で宣誓したが、むろん、その覚悟が決まっているわけではなかった。 「そう……。立派な心意気ね。安心した。じゃあ、南さんの、まん毛の検査は……、『仲間』である、滝沢さんに、お願いしようかな……。ちょっと待っててね」 香織は、そう言い残すと、きびすを返して移動する。自分のバッグの置いてあるところに行くと、チャックを開け、その中を漁り始めた。やがて、一枚の写真を取り出し、こちらに戻ってくる。その写真が、秋菜に手渡された。 目を凝らして見ると、秋菜が手にしたのは、彼女の保健の教科書に貼り付けられた写真と、同一のものだった。つまり、一糸まとわぬ全裸姿の涼子が、両手を頭の後ろで組み、服従のポーズを取っているところで、その全身が写っている。何より目を引くのは、むろん、逆三角状に燃え盛ったような、陰毛の黒い茂みである。あの写真は、たしか、一週間半ほど前に、ここ体育倉庫の地下で撮られたのだった。 「この写真と見比べて、南さんが、まん毛の処理をしてないか、よーく確かめて。よーく、ね」 香織が、秋菜に念を押す。 「はい。承知しました。わたしが、責任を持って、あの女が、吉永さんの命令を遵守してるかどうか、もう、それこそ、徹底的な検査を行いますので、お任せください」 秋菜は、大企業の重役に仕える、敏腕の秘書のように答える。 そうして、すぐさま、こちらに歩き始めた。 涼子は、ごくりと生つばを飲み込んだ。 秋菜は、取り澄ました態度で、つかつかと近寄ってくる。 冷ややかな印象を放つ目つき。中分けのストレートヘアを、胸もとで内側にハネさせた、エレガントな髪型。夏場でも汗ひとつ掻かなそうな、いかにも涼しげなオーラ。しっとりとした声質。そして……、普段の高校生活において、涼子が、どんなに熱烈にアプローチし続けても、よそよそしい反応しか示してくれなかったクラスメイトであること。 やっぱし……、わたし、この子が、ものすごい苦手……。 涼子は、今さらのごとく、滝沢秋菜という生徒に対しては、どうしてもアレルギーが生じてしまうことを自覚した。 しかも、嫌なのは、今、こちらに向かってくる秋菜の顔には、見るからに底意地の悪そうな冷笑が浮かんでいることである。まるで、全裸の奴隷である涼子のことを、ことさら挑発するかのように。 その秋菜の顔つきを見ているうちに、涼子の胸の内では、消えていたはずの対抗心が、にわかに燻り始めた。 この子にだけは、下に見られたくない……。 いかなる状況下であろうと、対等な関係でありたい……。 わたしが、奴隷だということを、今さら否定しても仕方がないだろう。でも、でも、それならば、同じ『仲間』である、滝沢さんだって、奴隷のはずじゃないの!? もちろん、恐ろしく次元の低い話であることは、百も承知だけれど……。なのに、パンツまで脱がされて、最低限の尊厳さえも奪われている、わたしと、しれっと制服を着たまま、普通の女子高生を気取っている、滝沢さんの、このアンバランスさは、なんなの!? こんなの、不公平じゃないの! 理不尽じゃないの! さらには、その滝沢さんに、わたしは、下の毛の生え具合まで、一方的に調べられるなんて……、悪い冗談でしょう!? 信じられないことに、すでに、その秋菜との距離は、二メートルを切っているように思われた。 涼子は、パニックにおちいり、無自覚のうちに、どたどたと後退していた。そうして、Vゾーンを正面から見られたくない、という意識が働き、秋菜に対して、斜めに構える体勢になる。 「ねえねえ、ねえっ! 待って! そこまで近づいてこなくても、よくない!? だって……、だってさ、滝沢さん、その、持ってる写真と、見比べて……、わたしが、ここ、この、まん毛? 剃ったりしてないことが、わかればいいんでしょ? だったら……、もう、この距離で、充分、確認できるよね?」 角が立たないよう、限りなく穏やかな口調で、ささやかな抗議をした。 しかし、秋菜は、耳を傾ける素振りすら見せず、なおも、こちらに進んでくる。 「やっ、やっ、やぁ……。お願いだから、待ってぇ……。それ以上、こないでぇ……」 スリラー映画のシーンでよくある、殺人鬼に迫られている者のごとく、涼子は、不可抗力的に後ずさりし続ける。 まもなく、秋菜は、苛立ちを露わに舌打ちすると、いきなり早歩きになり、一気に距離を詰めてきた。 「いちいち、逃げるんじゃないわよっ!」 左の二の腕を、秋菜に引っつかまれ、涼子は、乱暴に身を引っ張られた。そのまま、秋菜の体に激突しそうになり、後ろに重心をかけて急停止する。 身長差は、五センチあるかないかで、涼子のほうは、裸足なのに対し、秋菜は、革靴を履いている。そのため、もはや、互いの息遣いが聞こえるような距離で、涼子と秋菜は、顔と顔を突き合わせる形となった。 目の前の、冷然と整った目鼻立ちをした少女は、ほどなくして、勝ち誇ったように、ふんっ、と笑い声を漏らし、それから口にする。 「念のために言っておくけど、今から始めるのは、純然たる検査だからね? わたしとしては、心底、嫌なんだけど……、多少、『触診』もすることになるの。だからといって、あんた、変な気を起こさないでよ? もしも、検査の途中で、『濡らして』ることがわかったら、あんた、わたしに対する侮辱と見なして、半殺しにするわよ」 涼子の耳に、秋菜の発言は、ほとんど意味不明な言語にしか聞こえなかった。しかしながら、動物としての本能が、肉体に警告を発しているせいか、自分の呼吸が、獣のように荒々しくなっていることに気づく。 そこで、今さらながら、滝沢秋菜との距離が、異様に近いことを痛感した。 やだっ……。わたしったら、滝沢さんの顔に、めちゃくちゃ息を吐きかけてる……。はしたないっ……。これじゃあ、まず間違いなく、口臭だって伝わってるよね……? 不安を抱いたのも、つかの間、秋菜は、ゆるゆると身をかがめ始めた。 涼子の目には、その秋菜の動作が、スローモーションのように映っていた。 ふと、頭の片隅に、奇妙な疑問の念が生じる。 この感情は、なんなんだろう……? あと数秒後には、自分が、人間でもなければ、生き物ですらない何か、そう、ただの肉塊に変わっているかのような、漠然とした予感……。 ああ、これは、恐怖だ。わたしは、怖がってるんだ。具体的に、何を怖がってるのかは……、考えたくもない。けれど、おぼろげには理解してる。しいて言葉で表現するとしたら、滝沢さんとの、あってはならない距離感……。 秋菜は、涼子の足もとにしゃがみ込むと、持っていた写真を地面に置き、左右の手を伸ばしてきた。 その両手に、涼子は、両脚の太ももの裏側を、むんずと押さえられる。 ついつい、下に目を落としてしまった。網膜に飛び込んできたのは、これまでの十七年間の人生で目にしてきた、どんなものよりも、非現実的かつ怖ろしい光景だった。 岩礁に着生した藻のように陰毛の生い茂った、自分のVゾーンと、苦手意識を抱いている相手、滝沢秋菜の顔の、言語に絶する近接ぶり。自分の陰毛の毛先から、秋菜の鼻先までは、あろうことか、親指と人差し指で測れるほどしか、間隔が開いていなかったのである。 そして、その直後、言葉の雷鳴ともいうべきものが、耳朶を打った。 「なによ、この臭い……! あんたの体のことだから、鼻がひん曲がるような激臭を嗅がされるのは、覚悟してたけど、これは、想像以上ねえ! なんかもう、ウンコとゲロとヘドロを混ぜて、ぐつぐつ煮てみました、みたいなレベルの、最低最悪な臭いがするわ!」 秋菜は、ハハハハハハハハハッ、と天井を突き抜けるような高笑いを響かせた。 とうとう、涼子のなかで、理性を司る大事な糸が、ぶつんと切れた。 「うわわあああいやああああああぁぁっ!」 涼子は、爆発した感情を吐き出し、秋菜の両手の力に逆らって、勢いよく後退しようとした。 だが、秋菜は、そうはさせまいと、なんと、今度は、ひとかけらの躊躇もなく、涼子のおしりを、ぐっと両手で押さえてきたのだった。 むき出しの、それも、あぶら汗にまみれた、おしりの肉を、秋菜に、わしづかみされたことに対する、激烈な拒絶反応が起こり、涼子の肉体は、びくんびくんとけいれんした。 「暴れるんじゃないわよ! じっとしてないと、また、手加減なしに、顔を、ぶん殴るわよお? ほらっ、ちゃんとこっちに、腰を突き出しなさいよ!」 強引に腰を引き寄せられるがままに、直立、というより、秋菜の顔の前へと、恥部をせり出すような体勢を取らされる。いや、そればかりか、全力で足を踏ん張っていなければ、次の瞬間にも、自分の、おびただしい量の陰毛が、秋菜の鼻に覆い被さりそうで、涼子は、まるで、この世と冥界の狭間を漂っているような心地だった。 たとえ、気心を知り尽くした友人同士だとしても、もちろん、これほどまでに距離感を狭められる事態に至ることはない。 そもそも……、自分と、滝沢秋菜の関係は、どのようなものだったか……。 涼子の脳裏に、つい一ヶ月ほど前の、青春のほろ苦い思い出となった、ある情景が、ぼんやりと映し出される。 その日、バレー部の三年生部員たちは、練習時間の前半を、トレーニングルームでのマシントレーニングに当てていた。 息苦しいまでに充満する熱気。競い合うように体を動かす部員たち。 キャプテンの南涼子は、まず、スタミナの一層の向上のために、有酸素運動として、エアロバイクのペダルを漕ぎ始めた。たっぷり四十分ほど、それを続け、ほどよく汗を流す。続いて、本格的な筋力トレーニングである、ベンチプレスのマシンに移った。その一番の目的は、大胸筋を主として、上腕三頭筋や腹筋など、上半身全体の筋力強化だった。 午後五時頃になると、三年生部員たちも、適当なところで切り上げては、三々五々、退出し始め、バレー部の練習場である体育館へと向かっていく。 しかし、涼子は、自らに課したトレーニングメニューを、最後までこなすべく、バーベルを両肩に担いでのスクワットを続けていた。 バーベルスクワットは、バレーボーラーにとっては、命でもある、下半身の筋肉の肥大化に、極めて有効なトレーニングである。とくに、ゆっくりと腰を落とし、おしりを、ぐぐっと後ろに突き出す際、下半身に意識を集中すると、大臀筋から大腿筋にかけての筋肉が、限界までパンプアップしている感覚を得られる。 やっとのことで、そのメニューを終えた時には、もう、練習着であるTシャツもスパッツも、水を浴びたように、汗でぐっしょりの状態になっていた。 室内を見回すと、案の定、残っているのは、涼子ひとりだ。 そのため、涼子は、トレーニングルームを出ると、ドアを施錠し、鍵を返却するべく、職員室に向かった。 心のしこりとなる出来事は、その後に起こったのだった。 職員室へと続く廊下の角を曲がったところで、涼子は、はっと目を見開いた。 まさに今、職員室のドアが開き、クラスメイトであり、また、涼子としては、どうも、相性のしっくりこない相手である、滝沢秋菜が出てきたのである。 あ、滝沢さんだ……。 部活に所属していない秋菜が、どうして、この時間まで学校に残っているのか、という疑問を抱く。しかし、なんにせよ、秋菜と打ち解けて話すには、絶好の機会であると思い、涼子は、胸躍る気分になった。 これって、ラッキーじゃん……。 「滝沢さーんっ!」 涼子は、思わず名前を呼び、まるで、アイドルに握手を求める女性ファンのように、きゃぴきゃぴと秋菜のもとに突き進んだ。が、五、六メートルまで迫ったところで、ぴたっとストップした。今、自分の身に着けている、Tシャツとスパッツは、二時間以上に及ぶ、激しいトレーニングで掻いた汗を吸い、びしょ濡れの状態なのだ。これ以上、近寄ったら、秋菜に、汗臭い、と思われてしまうに違いない。 「南さん……」 秋菜の、その冷ややかな印象を放つ目つきには、かすかながら戸惑いの色が表れている。 「あっ、滝沢さん、どうしたの!? こんな時間まで」 涼子は、やや不自然かもしれないが、とびっきりの笑顔を作ってみせた。 「ちょっと……、英語の補習を受けてて……。そのせいで、遅くなっちゃった」 秋菜は、例によって、しっとりとした声で答える。 そういえば……、と思い出す。滝沢秋菜は、難関大学の受験に向け、自ら望んで、しばしば個人的な補習を受けていると、クラスメイトから聞いたことがある。 「そっかそっかぁ、偉いなあ……。わたしもさ、この夏で、部活引退だから、そのあとは、滝沢さんみたいに、勉強一筋で、頑張らないといけないなって思ってる……。あの、あの、わたし……、自分では、どうしても解けない問題とかあったら、もしかすると、滝沢さんに、教えを請うかもしれない。その時は、ぜひ、よろしくね?」 涼子にとっては、勇気を振り絞った発言であり、我知らず、もじもじと両手の指をいじっていた。そして、遅まきながら、こんな時に、秋菜にアプローチしてしまったことを、徐々に後悔し始める。対照的な二人。いかにも涼しげなオーラをまとった秋菜と、全身、汗だくの自分が、こうして相対しているという、このシチュエーション、それ自体に、ひとりの女の子として、なんとなく、言い様のない決まりの悪さを感じてしまう。 「南さんの、バレー部のほうは……、たしか、この夏に、三年生にとって最後の、大事な大会が控えてるんだったよね? そのせいもあるのか……、なんか、見るからに大変そうだね……」 バレー部のことについて、秋菜が、少しでも知っていてくれたのが嬉しくて、涼子は、うん、うん、とテンション高めにうなずく。だが、その語尾の意味を考えると、どきっとした。 見るからに大変そう……? 秋菜の顔を、まじまじと見返す。 今、秋菜の視線が、これまでより下方、つまりは、涼子の胸もとあたりに注がれていることに気づく。 涼子は、慌てて自分のTシャツに目を落とした。ブラジャーが透けて見えるほど、汗で濡れそぼった白い生地。 間違いない。涼子が、尋常ではないくらい、汗を掻いていることに、秋菜は着目しているのだ。 たちまち、胸の内が、不安でいっぱいになる。 もしかして、わたしの汗の臭い、滝沢さんの鼻に届いてる……!? そのことを考えたとたん、血の気の引く思いがした。 さらに、そこで、自分の下半身に意識を向けると、スパッツの生地が、まるで水着のように、汗で肌に張りついているのを、改めて感じる。下手をすると、Tシャツだけではなく、スパッツのほうも、かなり臭気を放っているかもしれない。 やだ、やだ、恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい……。 「あ、あの、わたし……、今まで、二時間以上、トレーニングルームに籠もって、マシントレーニング続けてたから、その……、だいぶ、ね……。あっ、ごめんねえ、なんかぁ!」 涼子は、つい、気まずい思いをした時のクセで、サイドの髪を両耳にかけていた。 その時になって、ようやく、一刻も早く、秋菜とのやり取りを切り上げ、職員室に駆け込むべきだという危機感を抱く。だが、ちょうどドアのところに、秋菜が立っているのだ。もし、その横を通り過ぎたら、今度こそ、秋菜に、鼻を摘ままれてしまいそうで、怖くて動くに動けない。 秋菜は、不思議そうな表情で、そんな涼子の様子を眺めている。 どうしたらいい……? 一瞬の逡巡の後、判断を下した。 「わたし、何しにここに来たんだっけ? そうだ、トレーニングルームの鍵、返しに来たんだ……。でも、そういえば……、その鍵、ほかの子に預けたんだった。ここに来た意味、ねえぇぇぇぇぇっ! それじゃあ、体育館で、ずっと部員たちを待たせてるから、そろそろ行くね! じゃっねえ、滝沢さん」 涼子は、秋菜のほうに、左の手のひらを突き出す。 秋菜は、ぽかんとしている。 そんな秋菜に背を向け、涼子は、競歩のような足取りで引き返していく。 別棟まで来ると、廊下の壁に背中をもたせかけ、はあーっ、と溜め息を吐いた。 あっちゃあ……。絶対、滝沢さんに、変に思われちゃったよ……。 たった今の自分の行動を、脳内で繰り返し再生すると、まるで、好きな人に対する、ナイーブな少女みたいな反応だと思い、赤面しそうな感情が湧き上がってくる。しかし、今一度、自分の肩に鼻を寄せ、Tシャツの臭いを確かめると、あのまま、職員室に向かわなくてよかった、という心持ちになる。 あの子にだけは、下に見られたくない……。そのような対抗心のせいだろうが、滝沢秋菜の前だと、どうしても、女の子としての品位を保ちたいという心理が、同性同士にもかかわらず、強く働いてしまうことを、否が応でも自覚させられる。 滝沢さん……。 涼子は、彼女の名を、心の中でつぶやいた。 要するに、自分と滝沢秋菜は、互いの気持ちを探り合う男女にも似た、もどかしい距離感で接する関係だったのだ。 だというのに……、まさか、その滝沢秋菜に、自分の、洗ってもいない恥部の臭いを嗅がれ、あまつさえ、汗まみれの生尻をつかまれる時が来るなどとは、それこそ、夢想だにしていなかった。 「あんた、いい加減、じっとしなさいよ。っていうか……、この、脚の震えは、なんなの? 震える原因は、なに……? ひょっとして、屈辱? これは、屈辱の震えなの? だとしたら、生意気ねえ……。いい? あんたは、わたしたちの、奴隷なのよ? 奴隷の分際で、一丁前に、プライドだけは高い女なんて、もう、セクハラオヤジ並に、目障りな生き物だわ。それとも、なに? わたしのせいで、プライドを捨てきれない、奴隷になりきれない、とでも言うわけ? わたしから、性的な恥をかかされることだけは、耐えられなくて発狂しそうになる? たとえば、こうして……」 秋菜は、そう言い終えると、ずずずずずっ、と盛大に鼻をすする音を立て、涼子の恥部の臭気を、思いっ切り露骨に吸い込んできた。 「やめてえええええええええええええぇぇぇっ!」 涼子は、ふたたび、感情がほとばしるままに絶叫し、体を激しく左右に揺らした。 「やめて? なに言ってんのよ、あんた。違うでしょ……? 滝沢秋菜様、わたしの、不潔極まりないま○この臭いで、不快な思いをさせてしまって、申し訳ありませんが、どうか、まん毛の検査を、よろしくお願いしますって、わたしに、頭を下げるのが、礼儀ってものよ? それが、わからないって言うのなら、体で覚えてもらうしかないわね。わたしが、奴隷としての心得ってものを、あんたの、この体に、みっちりと叩き込んでやるわよ!」 秋菜は、決意を込めるかのごとく、涼子のおしりの肉に、十本の指を、めりめりと食い込ませてきた。 涼子は、その指の圧力に反発するように、自分のおしりに、意思とは関係なく力が入っていくのを感じる。 向こうにいる香織が、おもむろに口を開いた。 「どうしたのかなあ、南さん……。あなた、正々堂々と、まん毛の検査を受けますって、元気よく宣誓したばっかりじゃないの。それなのに、どうして……? どうして、急に人が変わったように、反抗的な態度を、取り始めちゃったのお……?」 空々しいことこの上ない口振りだ。 「あっ。もしかして……、検査官が、滝沢さんだから? 部活の練習で、たくさん汗を掻いた後、シャワーを浴びてもいない状態で、自分のま〇この臭いを、大好きな片思いの人に嗅がれるのは、年頃の女の子にとって、たしかに、超絶、ショッキングな出来事だよねえ。そのせいで、神経回路がショートしたみたいに、奴隷であることも忘れて、ひとりの乙女として、乱れ狂っちゃってるって感じぃ? あたし、南さんの、まん毛の検査を、滝沢さんに依頼するなんて、とっても罪なことしたかなあ?」 香織のつり上がり気味の目は、ガラスが太陽光を反射するかのごとく、ぎらぎらと光っている。なんだかんだと言いながら、香織は、結局のところ、涼子が、苦痛の叫びを上げる姿をこそ見たいのだ。 「あら、びっくりだわ……。おしりの肉が、岩みたいに、かちこちに硬くなってる。なになに? 強豪校って言われる、バレー部のキャプテンともなると、こんなところの筋肉まで、鍛え上げる必要があるってこと? それなら、実に壮絶な話ねえ。すんばらすぃ……。あ、もしかして、わたしが、筋肉フェチだって言ったから、今、めいっぱいの力で、おしりを引き締めて、自慢の筋肉を誇示してるのかな? それで、わたしの気を、ちょっとでも引こうとしてるわけ? あんたって、筋金入りのレズビアンだもんねえ。っていうことは……、こんなふうにされたら、あんたは、悦んじゃうのかな?」 秋菜は、爪を立てるように十本の指を動かし、あぶら汗にまみれた、涼子のおしりの肉を、ぐにぐにと揉んできた。十七歳で、まだ、性体験のない涼子としても、その手つきは、淫らな欲求を満たす目的で、女性の肉体の感触を堪能しようとする者の、それを連想せずにはいられなかった。 今この瞬間、自分の体の性的な部分、それも、裸出した臀部を、手でもてあそんでいるのは、あの、滝沢秋菜である……。その事実が心に染み入ってくると、涼子は、かつて経験したことのない恥辱に神経を蝕まれ、体の限界まで伸び上がった格好で、のたうつように身悶えした。 「あっらーん。たいへーん。脚の震えが、ひときわ激しくなったわーん! まるで、素っ裸で、北極の氷の上に立たされて、寒さに震えています、みたいな、普通じゃない震え方ねえ! そのうち、あんたの体、壊れるんじゃないの……!? この女! 奴隷の分際で、屈辱に打ち震えてるわ! おっかしい!」 秋菜は、キャハハハハハハハハハッ、と狂ったようにけたたましい嬌声を響かせた。その様子は、まさに、中世の世界各地に存在したとされる、精神的あるいは肉体的苦痛を、下賎の者に与えることで、サディスティックな快楽に耽溺した、貴族の婦人が、現世の、高校という場によみがえったかのようだった。 涼子は、自分の運命を、と共に神を呪う思いで、天井をにらみすえた。 気づけば、先ほどまで、精神の均衡を保つ役割をしていた、自己否定という名の薄皮は、滝沢秋菜の所業により、上から下まで引き剥がされていた。 わたしは……、断じて、奴隷なんかじゃない……! 毎日、高校に通い、学んで、笑って、時には、ちょっとしたことで怒ったりもする、世間の同年代の女の子たちと同じ、ひとりの女子高生よ……! いや、それだけじゃない。強豪校としての伝統を誇る、バレー部のキャプテンを努めている、という自負心だって持っている! そのわたしが、なんで、なんで、なんで、こんな群れていないと何もできないような、貧弱な女たちから、性暴力を受けないといけないのよ……! 「さて……、まん毛の量が減ってないか、あとは、怪しい剃り跡がないか、これから、司法解剖並の、徹底的な検査を始めるわよ」 秋菜は、そのように宣告すると、左手で涼子のおしりを押さえたまま、右手を、そこから離した。地面に置いた写真を、その手で拾い上げる。写真の中の光景を、目に焼きつけるようにした後、今度は、今現在、自身の眼前に迫っている、涼子の陰毛の茂みを、じいっと凝視する。そうして、何度も何度も、双方を交互に見比べる。なにやら、涼子のVゾーンの陰毛部、その面積や密度は、むろんのこと、生え際の角度や、一本一本の縮れ具合に至るまで、子細に照合しているような、そんな印象を禁じ得ない。 やがて、秋菜の右手から、はらりと写真が落ちた。 その右手が、すーっとこちらに迫ってきて、涼子のへその下、というより、陰毛の生え際に、ぴたりとあてがわれた。何かの間違いだと思いたいことだが、秋菜の、人差し指から小指にかけての、四本の指が、すでに、涼子の陰毛に触れているのだ。 秋菜は、一拍置いて、右手を動かし始めた。 逆三角状に広く茂った、涼子の陰毛の領域、その上の辺に当てた、四本の指で、デリケートゾーンの柔肌を、引き下げては戻し、引き下げては戻しと執拗に繰り返す。剃り跡の有無を調べるという話だったが、しかし、その手つきからは、明らかに別の、それも、邪念に満ちた意図が感じられてならない。 そして、いよいよ、滝沢秋菜が、一線を越えてくることを確信した。 秋菜の右手の指先は、涼子の陰毛を撫でつけながら、ずりずりと下に移動し始めたのである。二、三秒後、その下降が止まった。そこは、涼子のVゾーンの陰毛部における、ちょうど中心に当たる位置だった。涼子自身、自分の体のことだから、今、秋菜に、どこを触れられているのか、よくわかっている。肉が、丘のように盛り上がっている部分だ。秋菜のほうも、そこを覆い隠す陰毛越しに、こんもりとした、その触感を指先に感じ取ったのだろう、四本の指を、ずずっと押し込んでくる。 涼子は、そんな秋菜と、決して目を合わさないつもりだった。だが、下から伝わってくる気配からして、秋菜が、今、悪霊の取り憑いた猫のような目つきで、涼子の反応を眺めているであろうことは、容易に想像が付いた。 秋菜は、それだけに飽き足らなくなったらしく、およそ同じ女子高生とは思えぬ、なにか、人体実験を行ってみたいという願望を抱く、サイコパスのごとき加虐性を露わにした。あるまじきことに、涼子の恥丘部の肉を抓むと、毛穴の密度までも確かめるかのように、むにむにとこすり始めたのである。 涼子は、その瞬間、奥歯が削れるほど強く歯ぎしりした。 苦手意識を抱いている相手だからこそ、また、本来ならば、同じ『仲間』同士、対等な関係であるはずだった、という思いがあるからこそ、滝沢秋菜に対する、どす黒い感情の炎は、暴風に吹かれているかのごとく、特段、烈々と燃え上がっている。今となっては、涼子にとって、滝沢秋菜は、香織よりも、明日香よりも、さゆりよりも、ある意味、憎悪を掻き立てられる存在であった。 この女にだけは、絶対に、絶対に、復讐してやる……! たとえ、どんなに卑劣な手段を用いてでも、高校在学中に、この女を、わたしの足もとにひれ伏させる! その後、どうするかは、もちろん決まっている。顔面に拳を叩き込んだくらいでは、到底、わたしの気は収まらない。だから、そう。身に着けているものを、すべて、引き裂くようにはぎ取り、全裸にさせるのだ。その上で、わたしが味わったのと同じ屈辱を、この女の身に与えてやる……! その激情の源泉は、まさしく、女としてのプライドそのものだった。 「うん。まん毛の量は減ってないし、怪しい剃り跡も見当たらない。っていうか……、上のほうの生え際なんて、むしろ、この写真より、位置が高くなってるようにも見えるわねえ! うっわぁ、これは、たまげたもんよぉ……。なに? あんたの体、こと体毛に関しては、まだまだ発育盛りってこと!? あんた、成人になる頃には、もう、へそのところにまで、まん毛が届いてるんじゃない? さすが、肉体強化に明け暮れて、女ながら、男性ホルモンの充満した体だわぁ」 秋菜は、吃驚した口調で言い立てる。 涼子は、自分のコンプレックスについて、これでもかというほど侮辱されながらも、秋菜の言葉を、右から左へと聞き流していた。 とにかく、気が済んだのなら、わたしのおしりから、もう片方の手も離して、とっとと、あっちへ行ってよ……! 涼子の胸中にあるのは、その一念だった。 「まあ、まん毛の処理は、していなかった、吉永さんの命令は、遵守していた、っていうお墨付きは与えてあげるわ。それはいいとして……、あんた、今の検査、混じり気のない気持ちで受けてたんでしょうね? 筋金入りのレズビアンであり、わたしに対して、並外れた性的欲望を抱いてる、あんたのことだから、わたしとしては、どうしても疑念が拭えないのよ。あんたが、わたしに触られる検査なのをいいことに、不純なことを考えてたんじゃないか、ってね……。だから、今から、その点が、白か黒か確かめさせてもらうわ」 もはや、秋菜の発言は、支離滅裂を通り越して、なにか、見知らぬ宇宙惑星について喋っているのではないかと思うほど、人智の及ばぬ内容だった。 まず、涼子が、レズビアンであり、秋菜のことを、性的対象として見ているという、その前提自体が、完全に狂っている。なので、その疑念とやらを晴らそうにも、どのような形で潔白を証明すればいいのか、まったくもって想像できない。そもそも、『検査』をいいことに、涼子の身を利用して、自身の下卑た好奇心を満たしていた、つまりは、不純な考えに基づいた行為に勤しんでいたのは、ほかでもない、滝沢秋菜のほうだろうと、涼子としては、思いっ切り突っ込みを入れたいところだった。 しかし、秋菜の口から、次の一言を聞いて、涼子の、そんな思考は、たちまち吹き飛ばされた。 「両脚を、肩幅まで開きなさい」 感情のかけらも感じられない、無機質な声である。 涼子は、眉をひそめて唖然としたものの、それも、つかの間のことだった。 まさか、まさか……、と直感が働き始める。 涼子自身、自分が、同年代の少女たちのなかで、鈍感な部類に入るとは思っていない。また、性体験がないとはいえ、十七歳という年齢相応に、性に関する知見は、しっかりと人並みに蓄えている。それゆえ、この段階に至って、秋菜の話の筋道らしきものを、本能的部分が感じ取ったのだ。 やがて、秋菜の真意を、脳細胞の言語中枢で、余すところなく理解すると、その直後、涼子は、思わず二の腕をさすりたくなるほどの、耐え難い悪寒に襲われた。そして、おもむろに、この身に染み込んだ冷気のようなものが、絶望感にほかならないことを悟る。しかし、体感的な寒さとは真逆に、なぜか、全身の毛穴という毛穴から、それまで以上に粘っこい汗が、一挙に噴き出してくるのを感じるのだった。 「聞こえなかったの? 股を、肩幅まで開きなさいって言ってんのよ」 秋菜が、もう一度、同じ内容の言葉を発する。その声には、強い苛立ちが滲んでいた。 今の今になって、涼子は、すでに、この場の全員に見られて久しい、両の乳首を隠すように、自分の両肩を抱いた。女子高生にしては、わりと大きめの乳房に腕が当たり、肌同士が、にゅるにゅると滑る。 もしも、肌の一部に火を点けられたら、またたく間に、全身が炎に包まれるに違いない、あぶら汗で濡れそぼった体。蛇口の水漏れみたいに、延々と垂れ続ける腋汗。腐った肉より強烈な刺激臭を放っていそうな、気が滅入るばかりの体臭。挙げ句には、秋菜の左手で押さえられている、おしりの、その割れ目の中にも、あぶら汗が、だいぶ溜まっており、深部の器官である肛門周りに、粗相をしたような、不快極まりない感触がある。 そうした事柄を意識すると、今ほど、自分の肉体が、不潔なものに感じられたことはない。 毛むくじゃらのケダモノみたいな生き物の、わたし、南涼子……。 そのイメージが浮かんだのは、つい先ほど、精神の均衡を保つために、徹底的に自己否定した時と同様だった。 しかしながら、あの時と決定的に異なるのは、今、涼子は、女としてのプライドを取り戻している、という点である。 たしかに、今のわたしは、恥まみれの体の持ち主だ。けれども、多感な時期を過ごしている、ひとりの女の子である、という事実は、誰にも変えられやしない。 今ここで、両脚を開いたなら、足もとにいる秋菜が、自分のこの体に、どのような行為を加えてくるのかは、もう、考えるのも馬鹿らしいくらい明白だ。 思春期の少女である、わたしが、どうして、そんな恥辱を受け入れられようか。 涼子の両脚は、裸足の足の裏から、コンクリートの地面に根を張ったかのごとく、ぴくりとも動かなかった。 だが、秋菜は、涼子のことを、同じ身分である女子高生などとは、これっぽっちも思っていないかのように、恐るべき冷血ぶりを示した。 「奴隷は奴隷らしく、命令を下されたら、即座に従いなさいよ!」 左脚の太ももの内側に、秋菜が、右手を押し当ててきた。その手になぎ払われるようにして、強引に左脚を横に移動させられる。続いて、右脚も、力ずくで開かされるに至った。 涼子は、無様にも、自分の肩幅よりも広く、両脚を開脚した格好で硬直した。間を置かず、股の間に、つまり、Iゾーンの部分に、秋菜の右手の指先が、べたりと密着したのを感じ、その飛び上がるような精神的衝撃に、ひゃあぁっあっ、と間の抜けた悲鳴を漏らしてしまう。 「あっらぁ……。びっちゃびちゃねえ、あんたの、ま〇こ……。だけど、あんたの場合、超絶な汗っかき体質だから、これは、汗と捉えていいのかしら? それなら、まだ許せるんだけど、まさか、淫らな快感に浸ってたことからくる、体液が混じってはいないでしょうねえ?」 秋菜は、人差し指から小指にかけての、四本の指で、小さな円を描くように、ねっとりと手を動かし、涼子の大陰唇を撫で始める。その行為は、たいてい、男性から女性に、セクシャリティによっては、女性から女性に、という形態になるのだろうが、とにかく、基本的には、肉体関係を結ぶ合意に至った者同士の、いわゆる前戯と呼ばれるものに当たることくらい、生娘である涼子の頭でも、明確に認識できる事柄だった。だが、涼子は、純粋なる異性愛者にもかかわらず、同性から、しかも、普段の高校生活においては、ちょっとしたスキンシップを交わし合うことすら、まずあり得ないという、極めて微妙な関係にあった、その相手から、女性器への愛撫を、一方的に受けているのだ。 その時、秋菜が、うっふーん、という声を出した。涼子の耳にも、その声音は、まさに、男性の欲情をいたずらに刺激しようとする、妖艶な女性を思わせるものとして届いた。滝沢秋菜という女は、怖ろしいことに、自身が、性暴力の加害行為に手を染めている状況でありながら、その被害者である涼子に対して、性的挑発まがいの言動を示したのである。 涼子は、発狂するほどのおぞましさに、視界が暗転する感覚を味わった。 心理的に、目の前が真っ暗になったのとは違う。眼球が、ひっくり返るほど上を向いているのだとわかる。 「うーん、やっぱり、どうも、判別が難しいわねえ……。ちょっと、中まで触るわよお?」 秋菜は、涼子の陰裂部に、中指を食い込ませてくる。 その指に、ぬるりと粘膜を撫でられ、涼子の魂は、これまでにない勢いで慟哭した。 「タアアアアアハッハッハッハッハアアアアアアァァァ!」 さながら、品性下劣な老婆が、他人の不幸を見て、大爆笑しているかのごとき大音声がとどろき渡る。 もしかりに……、その声を耳にした、正義感にあふれる人間が、なんらかの事件性を疑って、この現場に足を踏み入れたとしたら、果たして、何を思うだろうか……。 愕然とすることに、ひとりだけ、全裸姿の少女がいるのを目撃する。そこで、ひょっとすると、と考える。たった今、聞こえてきたのは、その少女が発した絶叫だったのかもしれない……。だとしたら、彼女は、血生臭いまでの凄惨な被害に遭った可能性が高い……。しかしながら、なんとも不可解なのは、レイプ魔らしき男や、凶器を持った不審者の姿は、どこにも見当たらないという点である。居合わせているのは、セーラー服姿の女子高生たちだけなのだ。 そう……。 陰鬱な地下の空間に、よこしまな少女たちは、まさしく、この世の地獄を現出させているのである。 「まあ、いいわ……。限りなく黒に近いように思えるけど、確証を得られたわけでもないから、不問にしてあげる。わたしって、奴隷である女にも、これほど寛大になれちゃうんだから、自分で言うのもなんだけど、性格がよすぎるわね」 秋菜は、しみじみとした口調で言う。 涼子は、開かされていた両脚を、そろそろと閉じていく。 どうして、今、わたしの目からは、一粒の涙も流れ落ちないのだろう……。 わたしは、いかなる時であろうと、人前では、決して泣けない性格の女の子だったっけ……。いや、そんなことはない。今日に至るまでの部活の練習を振り返ってみれば、悲しさや、悔しさのために、何度となく、めそめそと涙をこぼし、同学年の部員たちから慰められてきたし、また、大会の試合では、手も足も出ないまま惨敗を喫した直後、キャプテンとしての自分の不甲斐なさを痛感させられ、人目もはばからず、泣きながらコートを去ったこともある。 なのに、なぜ……。 こんな女たちにだけは、情けない泣き顔を見られたくないという、意地みたいなものは、むろん、ないわけではない。だが、どちらかというと、すでに、涙が涸れ果てるまで泣いた後のような、そういう状態に近い気がした。 「そういえば、あんたには、あと一つ、肛門のほうの検査を受ける義務も、残ってるんだったわね。その検査は、吉永さんたちが、担当してくれるみたいだけど……。でも、吉永さんたちの、手をわずらわせるのも、申し訳ないし……、もう、この際だから、いっそ、わたしが、あんたの、肛門周りの毛まで、調べてあげるわよ! ほらっ、今すぐ後ろを向きなさいっ!」 秋菜は、涼子の腰の両脇に、両手を当ててきた。 体の向きを、無理やり変えられそうになるが、反射的に足を踏ん張って抵抗する。 「やだ! やめてぇっ! それだけは、いや!」 涼子は、足もとにしゃがんでいる、秋菜に向かって、大声でわめいた。 目と目が合う。秋菜の顔を、何時間かぶりに見た思いである。 すると、秋菜は、気だるげな態度で立ち上がり、凄むように顔を近づけてきた。 「なんなの、あんた……。やっぱり、わたしにだけは、うんこの出る穴なんて、何があっても見せられないんだ? わたしに幻滅されるのが、死ぬほど怖い? あわよくば、高校卒業までに、一度くらい、わたしと、レズエッチできるかも、みたいに、まだ夢を見てるんでしょ? あんたってさ……、ホンット、とことん気色悪い女ね」 目の前の、冷然と整った目鼻立ちをした女が、口を動かすたび、無臭の呼気が、涼子の顔にかかってくる。 涼子としては、当然ながら、そんな秋菜のことが、憎くて憎くて堪らなかった。しかし、そうなると、もどかしい距離感で接していた頃よりも、一層、対抗心の火に油を注がれる。だから、秋菜に、不浄の穴まで見られるなど、まかり間違っても受け入れられないことだった。 秋菜は、身をひるがえすと、ようやく、涼子のそばを離れた。香織たちのところへ戻っていく。 「吉永さーん。この写真と見比べて、厳正に検査した結果、あの女は、いちおう、吉永さんの命令を遵守している、というのが、わたしの見解です。なので、まん毛の検査は、合格、でいいんじゃないかと」 「ご苦労だったね、滝沢さん」 香織は、写真を受け取り、秋菜をねぎらう。 「実際、苦労っていうか……、正直、かなり苦痛だったわぁ……。だって、あの女のケツなんて、汗で、どろっどろなのに、そこを、ずっと押さえてる必要があったし、最終的には、やらしい汁が混じってそうな、股の汗までもが、手に付着するのも、我慢しないといけなかったし……。しかもしかも、しゃがんでると、上から、あの女の、腋汗っぽいしずくが、わたしの、髪の毛や制服に、ぽたぽた垂れてきたのよ? 吉永さんに依頼された仕事とはいえ、検査してる途中、なんで、わたしは、こんな悲惨な目に遭わないといけないんだろうって、泣きたくなっちゃった……。もう、今日は、紛れもなく、人生最悪の日よぉーん」 秋菜は、香織の同情を買おうとしているのか、猫撫で声を出して嘆く。それから、方向を変えて、ふたたび歩きだした。自分のバッグの置いてあるところに行くと、チャックを開け、おもむろに制汗スプレーを取り出す。『仲間』同士、まだ、お互いに衣類を身に着けていた時、自己保身のために、涼子の恥部を、スパッツ越しにつかんできた後と、まったく同じ行動だった。殺菌効果を期待してのことらしく、自身の両の手のひらに、念入りにスプレーを吹きかけている。 香織が、その秋菜に向かって口にする。 「それはそうと、滝沢さん。あなた、まだ、南さんに、ちゃんとした返事をしてなかったよね?」 「返事……?」 秋菜は、制汗スプレーをバッグにしまい、やおら腰を上げる。 「そうだよ……。南さんは、あなたに、公然告白したじゃないの。それも、おそらくは、南さんにとっての初恋だよ。初恋の相手である、あなたと、結ばれたいって、強く願ってるのよ。まあ、南さんの場合は、純真な恋愛感情だけじゃなく、薄汚い下心も、相当、入り混じってるみたいだけどさ……。たとえば、滝沢さんの、裸を、隅から隅まで観察したいとか、体の柔らかいところを、揉んでみたいとか、あとは、舐めてみたいとか、ね……。でもだけど、なんにせよ、滝沢さんのことが、好きで好きで仕方がないことに、変わりはないの。そんな南さんを、いつまでも焦らし続けるのは、可哀相すぎない? そろそろ、南さんと、女同士だけど、本気で付き合ってもいいと思うのかどうか、返事をしてあげたらどうなのよ?」 香織は、賄賂を要求する政治家のごとき、恐ろしく卑しげな顔つきで話す。 一方、秋菜は、目をしばたたきながら、香織を見返している。が、その数秒後、諦めたように小さく笑うと、緩やかな動作で、涼子のほうに体を向けてきた。 意味深な沈黙が流れる。まるで、秋菜が、涼子の顔立ちや体つき、それに性的部分に至るまで、改めて品定めしているような、そんな空気である。 涼子は、両肩を抱いて縮こまっていたが、今さらながら、コンプレックスのあるVゾーンの陰毛部を、無性に手で隠したくなった。 「わたし……、女同士には抵抗がある、とか以前に、体臭がきつかったり、体毛が濃すぎたりする人って、生理的に無理なの……。だから、ごめんなさい」 秋菜は、しおらしい少女みたいに、体の前で両手を重ね合わせ、深々と頭を下げてみせた。 あたかも、本当に、告白を断られているかのようなシチュエーションであり、涼子としては、なおさら体面を汚された心持ちだった。 「ちょっとちょっと! 滝沢さんっ。あんたには、人の心ってものが、ないの!? 振るにしても、その物言いは、いくらなんでも、残酷にもほどがあるよ! 乙女の恋心が、いかにデリケートか、くらいは、あんただって、同じ女なんだから、わからないはずがないよね? さすがに、あたしとしても、今のは、看過できない発言だった。まったく、少しくらい、南さんの気持ちも、汲んであげなさいよ」 香織は、ひくひくと笑いを堪えながらも、いかにも義憤を覚えている者っぽく振る舞おうとする。 「……うーん、そうねえ」 秋菜は、左手を頬に当て、なにやら、幾分、自省しているような素振りを示した。 むろん、それは、単なるポーズに決まっている。むしろ、次は、どのような言葉で、涼子を侮辱してやろうかと、頭をひねっているところなのではと思われる。 そして、案の定、その予想は的中した。 「わかったわ。南さぁーん、あんた、後輩たちも見てる前で、素っ裸にさせられたうえ、体毛検査まで受けさせられるなんて、もう、人権も何もあったもんじゃないわねえ。そんな、救いようのないほど惨めな、あんたに、わたしが、情けをかけてあげる……。わたし、申し訳ないけど、どうしても、あんたとは付き合えない。だけどね、もし、あんたが、わたしの、体だけでも欲しいって望むのなら……、わたし、今この場で、おっぱいくらいなら、じかに触らせてあげても、いいわよぉ?」 秋菜は、セーラー服の胸もとを、わずかばかり、両手ではだけてみせ、こちらに顔を突き出した。 「え!? やったじゃーん、南さんっ。なんとなんと、滝沢さんの、生おっぱいだってよ? 滝沢さんの体に、エッチなことをする時が来るのを、ずーっと待ち焦がれてたんだもんね? ついに、その夢が叶うんだよ? もう、欲望を制御するなんて、不可能でしょ? ささっ、早く、滝沢さんのところに行って、心ゆくまで、おっぱいを揉み揉みしちゃいなよお!」 香織は、自分自身のほうこそ、性的に興奮しているような口振りで、涼子をせき立てる。 涼子は、眉を寄せて視線を落とし、顔をしかめた。 滝沢秋菜の乳房など、大金を積まれても触りたくない。 が……、いずれ、その時は訪れるはずだ、とも思っている。いや、信じている。 そう。復讐のために。 たとえ、悪魔に魂を売ってでも、今日この場において、自分が味わったのと同じ屈辱を、秋菜の身に与えてやるという、確固たる決意。いつの日か、それが成就した時、あの、やたらとプライドの高そうな滝沢秋菜は、金切り声を上げて泣き叫ぶに違いない。また、その声は、きっと、自分の耳に、心地よく響くことであろう。 とはいえ、秋菜の裸体に手をかける、その自分の姿を想像するのが難しいのも、また事実だった。 「どうしたの? 南さん……。あなた、すでに、滝沢さんから、恋人同士の関係にはなれないって、振られちゃってるの。そのこと、自覚してる? だったら、せめて、滝沢さんの体に、性欲をぶつけたいって、そう思わないわけ? あたし、断言できる。あなた、このチャンスを逃したら、大人になっても後悔し続けるよ。あの時、初恋の相手である、滝沢さんの、おっぱいの感触を、ちゃんと確かめておけばよかった……、ってね」 香織は、まるで、人生の大先輩のごとき風情である。 涼子は、それを聞き終えると、コンクリートの地面を、半目で眺めながら、一度、二度、三度と、静かに首を横に振った。 「はっ……。とんだヘタレ女だわ。バレー部のキャプテンが、聞いてあきれる。そんなんだから、滝沢さんのことを、振り向かせることができないのよ。それとも、まさかとは思うけど、ここで、下手に下心を見せなければ、いずれ、滝沢さんに、再アタックできる、とか勘違いしてるんじゃないでしょうね? 無駄だよ、無駄……。とにかく……、南さんの思い描いてた、滝沢さんとの恋物語は、見るも無惨な形で、終焉を迎えました。ちゃんちゃん」 香織は、突き放すように言った。 恋物語……。 涼子は、以前から抱いていた、茫漠たる違和感の正体に気づいた。 吉永香織という女の口からは、どうして、こうも、同性愛にまつわる発言が、ぽんぽんと飛び出してくるのだろう……。普通の女子高生だったら、そういった発想が、頭に浮かぶこと自体、めったにないものと思われる。ひょっとすると……、香織は、自己の内面に関することを、そのまま吐き出しているのでは……? そこまで思い至った直後、涼子の胸の内では、言葉で表現できない感情が渦巻いたのだった。 「さてさて……、それじゃあ、南さん、本題に戻ろうか。たった今、大失恋したばかりで、傷心の南さんに、追い打ちをかけるようで、あたしも、少々、胸が痛むんだけどさ、今から、ケツ毛の検査を受けてもらうよ。まあ、さっき、乙女心全開にして、滝沢さんと、舞ちゃんにだけは、おしりの穴、絶対に、見られたくありませーん、って叫んだんだもんね? あたしも、その点は、約束どおり、南さんの希望にそった形にするよ。だから、あたしと、さゆりと、明日香で、あなたの、ケツ毛の生え具合を調べる。それなら、もちろん、納得よね? 心の準備は、オッケー?」 香織は、愉快げに問うてくる。 胸の底に、悲しみのしずくが、ぽつりと落ちる。しかし、ただそれだけのことだった。恐怖や、悲嘆や、憎悪といった強い感情は、不思議なくらい隆起してこない。 涼子は、どちらかというと、虚無の闇と向き合っている境地だった。現在、自分の置かれている状況を鑑みれば、人間の心理状態として、極めて不自然であることは、自分自身でも、おぼろげながら認識している。もしかすると、自分は、魂の荒廃により、とっくに、廃人と化しつつあるのかもしれない。 しかし、自分を褒めたいことに、脳細胞のどこかでは、どう行動するのが、自分にとって最善なのかと、わりと冷静に、思考を働かせていた。 確実なこと。それは何かといえば、今の自分には、拒否権がない、ということだ。また、香織たちが、翻意する可能性は、万に一つもあり得ない。すなわち、これから、自分が、たった今、香織の言ったとおりのやり方で、辱めを受けることは、すでに確定しているのだ。だが、滝沢秋菜と足立舞の二人が、それに加わらないのであれば、その点だけは、正直、せめてもの救いである。考えようによっては、この辺りが手の打ち所、という見方もできる。それならば、受け入れる意思を、香織に示すべきなのではないか。 けれども、と思い留まる。 自分のおしりの割れ目が、おそらくは、香織の両手の指で、左右に押し広げられ、その奥の光景が、つまり、女の子にとっては、ともすると、恥部より見られたくないと感じる部分が、三人の、観察対象となるのだ。わかり切ったことだが、きっと、審美性は、最悪だろう。下手をすると、臭いまで……。 ああ、もう、考えないほうがいいな。 涼子は、そこで、ごく近い未来に関する思考を、頭から追い払った。それから、つと、香織のほうに視線を向けると、誠意ある態度を意識し、口を開いた。 「はぁい」 自分の耳にも、それは、とても柔和な声に聞こえ、我ながら意外の感に打たれる。 あれ、わたしの声って、こんなに女性らしかったっけ……? 「はぁぁい」と、後輩の石野さゆりが、面白がって涼子の口真似をする。 「うーん、とっても、いいお返事ね。どうやら、ケツ毛の検査を受けることに、ちゃんと、納得してくれてるみたいで、感心、感心……。よし、南さんは、そこ、動かないで……。さゆり、明日香、行くよっ」 香織に促され、三人が、揃って動き始めた。 彼女たちは、涼子に対する、優越感に満ちあふれた態度で、こちらに近寄ってくる。 そうして、香織とさゆりが、横を通り過ぎ、涼子の背後に回った。 が、竹内明日香だけは、涼子の目の前で、意味ありげに足を止めた。 涼子は、ちらりと、明日香の顔を見たが、その人間離れした美貌を前に、今回で何度目だろう、息を呑むような心地になり、色々な意味での劣等意識から、すぐに、おどおどと視線を落とした。自分は、ひとりだけ全裸姿という悲惨な状況下で、数奇な運命にも、テレビや映画で活躍する、トップモデルに遭遇してしまったのではないかと、そんな非日常的な錯覚すら覚える。 まもなく、自分の真後ろにいる、香織たちが、しゃがみ込んだのを、気配で悟った。 「毎度、毎度、思うんだけどさ……、相変わらず、きぃーったないおしりだねえ。なに? なんで、寒い季節でもないのに、いっつも、こんなに鳥肌が立って、うぶ毛が、全体的に、びっしりと逆立ってるわけ? 文字通り、鳥の肌を見てるようで、キモいんだけど。それにぃ、よくよく観察すると、毛穴の黒ずみも、けっこう、ぶつぶつと目立ってるし……。あたし、このおしり見ると、極太うんこのイメージで、頭の中が、いっぱいになっちゃうんだよね」 きっと、香織のほうも、涼子の女心を傷つける意図というより、むしろ、同性としての率直な意見を、忌憚なく述べているに過ぎないのだろう。 「わりと色黒の肌だし、風船が、二個、並んだような、デカケツだから、よけい不潔な感じに見えちゃうんでしょうね。それに、今日は、オイルを塗りたくったように、汗で、でらでらと濡れ光ってるせいで、一段と、ひどい有様ですよ。なんか、見るからに、ケツの表面にも、人体に有害な、ばい菌とか、寄生虫の卵とかが、一ミクロンの隙間もなく、こびり付いてそーう」 さゆりは、おどろおどろしい声で言う。 汚い。不潔。便のイメージ。ばい菌だらけ。侮辱され放題であるが、いよいよ、それらの極致ともいうべき部分を、香織たちの目に触れさせるのだ。ただ、よく思い返せば、香織も、さゆりも、明日香も、ほとんど一瞬かもしれないが、涼子のその排泄器官を、一度は目にしているはずである。考えたくもないことではあるが……。しかし、今度ばかりは、香織が、『検査』的な形式にこだわっているため、三人が、たっぷりと時間をかけて、毛の生え具合を筆頭に、視覚的特徴について子細に調べてくるのは、ほぼ間違いないと覚悟するべきだろう。 ああ、苦しい。惨めすぎて、わたし、やっぱり、ものすごい苦しい……。 涼子は、それまで向き合っていた、優しい虚無の闇が、残酷な神によって、しだいに取り払われていく境地におちいった。 その後、視界に浮かび上がった光景を主として、聞こえてくる物音や、全身の肌に伝わってくる感覚情報など、五感全体で感じ取ったのは、目のくらむほど怖ろしい現実だった。 気づけば、自分の体は、中枢神経系に異常を来したかのように、がたがたと震え始めていた。 明日香が、そんな涼子の様子を、好奇の眼差しで見つめているのは、その表情を確認するまでもなく明らかだった。 しかし、涼子は、あえて再度、明日香の顔に視線を向けた。 今から十数分前だろうか、プライドを捨て去り、明日香と、目と目を見合わせていた時と同様、そのフランス人形のような美少女の顔には、一見、親愛の情の表れとも捉えられる、魅惑的な微笑が浮かんでいる。だが、今は、確信できる。彼女の口もとは、底無しの悪意に歪んでいるのだ、と……。なにしろ、彼女は、死神のごとき、変態サディストなのだから。 そこで、これから開始される、『検査』のことを考えると、先ほど、自分の下半身に、この女が、背後から絡みついていた時の、あの出来事を、嫌でも想起してしまう。 そう……。 涼子のおしりの割れ目に、明日香は、鼻を寄せると、女の子にとっては、ある意味、もっとも嗅がれたくない臭いである、便の残滓の臭気を、あからさまに吸い込んできたのだった。その瞬間、自分は、それこそ、死の恐怖にも似た恥ずかしさに襲われ、自我を喪失しかけたことまで、ありありと思い起こされる。 しかし、今度は、なんといっても、おしりの深部を調べられるのだから、自分は、あの時以上の、はなはだしい恥辱を味わうことになると、そう考えざるを得ない。 わたし、本当に、壊れちゃうかも……。 見た目だけは人間である、肉塊。コンクリートの地面に転がっており、目は開いていても、何も見えておらず、耳に音が届いていても、何も聞こえておらず、口は付いていても、何も喋れないという、まさに、粗大ゴミのごとき物体と化した自分の姿が、脳裏に、白黒映像でちらつく。 すると、未知への恐怖、いわば、動物としての、本能的、原始的恐怖が、一気に増幅し、とうとう、自分の体は、頭部まで、とくに下あごが、小刻みに震え始めた。それを抑えたい思いで、歯を食いしばるも、奥歯が、かちかちと鳴り続ける。 「うーん?」 明日香は、いつものあの、人を挑発するような声を出した。もしかすると、怯えきった涼子の姿に、なおさら嗜虐心をくすぐられる気分なのかもしれない。 涼子は、あごを引いて上目遣いになり、拗ねるように、震える唇を、きゅっと突き出した。浅ましくも、またぞろ、明日香を相手に、媚びた表情を作ってみせたのである。まさしく、絶対的支配者を前にして、無力な奴隷が、必要以上に卑屈になる構図そのものだと、自分のことながら深く感じ入る。 明日香……、明日香も、これから、わたしの体の、その……、一番、汚いところの、『検査』に加わるつもりなんでしょ? 当たり前のことだけど、わたし、そこを見られるだけでも、胸の中を、むちゃくちゃにかき乱されるくらい、恥ずかしい。それなのに、もしも、あなたから、また、あの……、さっきみたいに、臭いまで確かめられるなんてされたら、わたし、屈辱感というか、劣等感というか、あるいは、絶望感というか、たぶん、そういうのが一緒くたになった、想像も付かない感情に襲われて、本当に、壊れちゃいそうなの。一生のお願いだから、わたしの、心を、体を、人生を、壊そうとしないで……。 そのように、目で語りかけているうち、明日香も、そろそろ飽きてきたとばかりに、すーっと移動し、涼子の背後に立った。それから口にする。 「りょーちんの体、すっごい震えてるぅ……。ケツ毛の検査されるのが、よっぽど怖いみたい。可哀相な、可哀相な……、りょおぉぉぉぉぉぉぉぉぉっ、ちぃんっ!」 最後のかけ声と同時に、明日香が、上から叩きつけるように勢いよく、涼子のおしりを、両手でつかんできた。 「どっひゃああぁぁぁぁっ!」 涼子は、驚愕に満ちた奇声を発し、文字通り跳ね上がった。ただでさえ、極限の恐怖にさらされ、精神面が、著しく脆弱になっているというのに、不意打ちで、無情の一撃を喰らった格好だった。 しかも、明日香は、すでに、腰を落としているらしく、そのまま、涼子のおしりの肉を、やわやわと両手で揉んでくる。まるで、涼子の心にまで、爪を立てるかのように。 その悪魔の所業により、涼子のメンタルは、破滅的影響をこうむった。 恐怖や悲嘆が、もはや、耐えうる限界を超え、それが引き金となって、感情を制御する機能が働かなくなる。 「んわああああああああぁぁぁぁぁん……」 涼子は、涙こそ出なかったものの、恥も外聞もなく泣き声を上げた。 「……ははあああはっはっははあはぁぁぁぁぁん」 今まで、負の感情が、溜まりに溜まっていたのだが、その防波堤が決壊したことで、身も心も、錯乱の渦に呑み込まれており、一向に声が止まらない。 一方、明日香は、それを聞きながら、涼子の耳には、不快な音として、すっかりこびり付いている、あの、笛の音のような笑い声を立て始めた。 人を疑うことを知らぬ、純朴なバレー部のキャプテンは、浅はかにも、密偵活動のために部内に潜り込んだマネージャーを、仲間として受け入れてしまったがゆえに、恐るべき奸計に絡め取られ、その結果、両者の関係は、行き着くところまで行き着いたということ。その冷厳たる現実を色濃く反映する、両者の対照的な声音の重なり合いが、まさしく、この世の地獄に似つかわしい不協和音となって、長いこと響き続けていた。 |
| 前章へ | 次章へ |
目次へ
小説のタイトル一覧へ
同性残酷記ご案内へ
Copyright (C) since 2008 同性残酷記 All Rights Reserved.